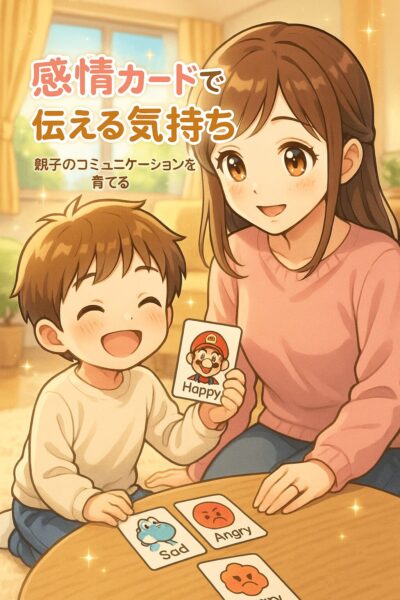はじめに
子どもの気持ち、ちゃんと伝わってる?
「泣く」「怒る」「黙り込む」――そんな時、子どもが本当はどんな気持ちなのか、戸惑ったことはありませんか?🌀
特に小さな子どもは、自分の感情を言葉で伝える力が未発達なことが多く、「どうして泣いてるの?」「言わなくちゃわからないよ」とつい大人が困ってしまう場面も…。
そんな時に役立つのが【感情カード】です💡
視覚的に気持ちを伝えられるカードは、子どもにとって心強いサポートツール。
この記事では、以下のポイントを中心に、感情カードの活用法をわかりやすくご紹介します👇
- 感情カードの使い方 5つのステップ
- 感情カードの効果的な使いどころ(活用シーン)
- 実体験から見えた変化とメリット
感情の言語化は、子どもの心の成長やかんしゃくの軽減、親子関係の改善にもつながる大切なステップです。
ぜひ最後まで読んで、今日から家庭に取り入れてみてくださいね✨
目次
- 感情カードの効果とは?感情表現・かんしゃく改善へのメリット
- 実体験エピソード
感情カードで息子の変化 - 感情カードの効果とは?
子どもの心を育てる3つのポイント - 子どもに合う感情カードの選び方|発達段階別のポイント
- 感情カードの使い方と活用シーン5選|日常で役立つ実例
- 感情カードの使い方|効果的な5ステップ
- 感情カード活用のコツ3つ💡
- よくある質問
- まとめ
1. 感情カードの効果とは?|感情表現・かんしゃく改善へのメリット✨
「怒ってるの?悲しいの?」――子どもの気持ち、わかりにくいときありませんか?
感情カードは、そんな時に子どもの気持ちを“見える化”してくれる知育ツールです🧠🖼️
イラストと言葉で感情を示すことで、まだ言葉で感情をうまく表現できない子にも、「これが今の気持ち!」と伝えやすくなります。
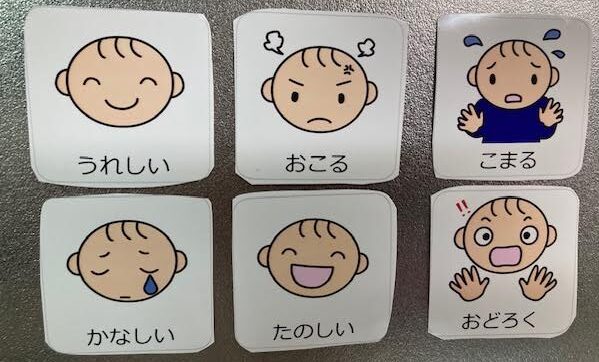
🌟感情カードの3つの効果
✅ 感情のコントロールをサポート
→ 「怒り」を自覚できることで、自分で落ち着く力が育つように。
✅ 自己表現の力を育む
→ 「悲しい」「悔しい」など、モヤモヤした気持ちの正体に気づける。
✅ かんしゃくや癇癪行動の軽減
→ 気持ちを伝えられることで、爆発せずに済む場面が増える。
💡特におすすめなのは、「気持ちをうまく言えない」「突然怒る・泣く」お子さんへの活用。
「伝えられた!」「わかってもらえた!」という経験が、子どもの安心感や自己肯定感の土台になります🌱
2. 【実体験】感情カードがかんしゃくを変えた!|4歳息子の変化
私の4歳の息子は、おしゃべりは大好きでよく話すのですが、気持ちを言葉で表すのがとても苦手でした。
質問しても「わからない」「どう言えばいいの?」という感じで、感情をうまく捉えられない様子…。
幼稚園でおもちゃを貸してもらえなかったり、友達に貸してほしいと言われたときに、つい「嫌だ!」と怒っておもちゃを奪い取ってしまうことがあり、お友達とのトラブルが絶えませんでした💦

そんな時に出会ったのが「感情カード」でした。
「どんな気持ち?」「これかな?」とカードを見せながら話すことで、少しずつ変化が…!
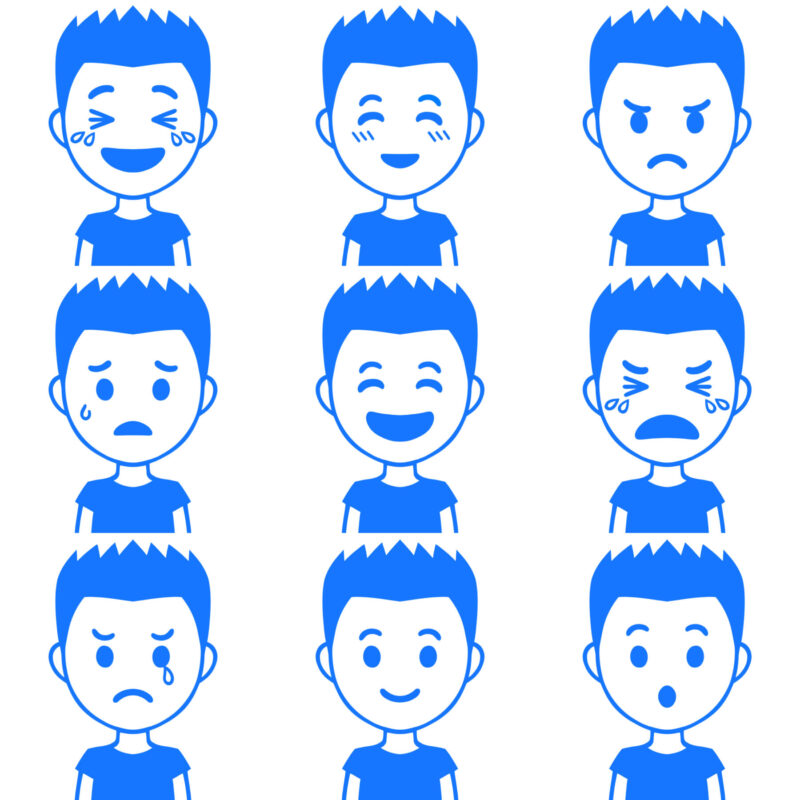
最初は黙っていた息子も、繰り返し使ううちに
👉「これ、悔しい!」
👉「悲しかった…」
👉「びっくりした」
と、自分の気持ちを伝えられるようになってきたんです✨
☘️その結果…
- かんしゃくの回数が明らかに減った!
- お友達とのトラブルも激減👫
- 「気持ちを伝える」習慣が自然に身についてきた
親としても、「どうしたの?」「何が嫌だったの?」と問い詰める場面が減り、お互いにストレスが少なくなったと感じています☺️
3. 感情カードの効果とは?子どもの心を育てる3つのメリット🌱
感情カードは、子どもの「気持ちを言葉で表現する力」を育てる知育ツールです。
言葉で伝えるのが苦手な子どもでも、視覚的に感情を理解しやすくなることで、かんしゃくの軽減や親子の関係改善にもつながります。
✅ ① 感情を「見える化」して伝えやすくする
イラスト付きのカードで「怒り」「悲しみ」「喜び」などを表すことで、まだ語彙の少ない子でも自分の気持ちを把握しやすくなります。
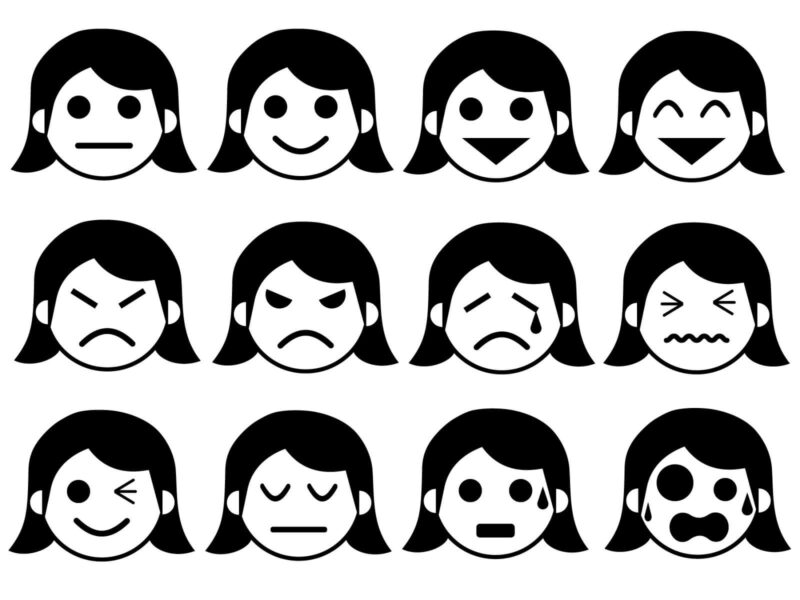
✅ ② 親子のコミュニケーションを促進
「今日の気持ちはどれかな?」とカードを見せながら会話するだけで、子どもとの対話が自然に増えます。
感情のやり取りが日常の中にあるだけで、子どもは安心感を得られます。

✅ ③ 感情コントロールの練習にも
気持ちを視覚化できることで、子どもは自分の感情に気づきやすくなり、落ち着くための方法を学べるようになります。

4. 子どもに合った感情カードの選び方🃏|年齢や発達に応じて選ぼう
感情カードは、市販・手作り問わず種類がたくさん!
子どもの年齢や発達段階に合わせて選ぶことで、より効果的に使えます。
📌選び方のポイント
- 年齢・理解度に合ったイラスト
→ シンプルで表情がわかりやすいものが◎ - 感情の種類が豊富
→「嬉しい」「怒り」だけでなく、「悔しい」「恥ずかしい」など細かな感情も含まれていると◎ - 視認性の高いデザイン
→ カラフルで感情ごとに色分けされていると、選びやすくなります

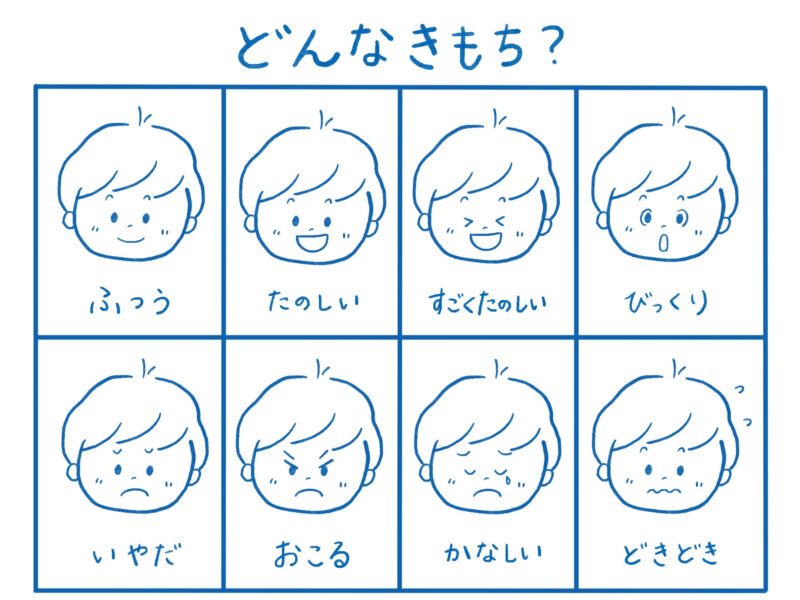
\身近な素材での手作りもおすすめ🎨/
お子さんの好きなキャラクターや色を取り入れると、より親しみやすくなります♪
市販のものから手作りまで、子どもに合ったものを選びましょう。
簡単なイラストや、色使いが鮮やかで視覚的にわかりやすいものが特に効果的です。
また、カードにはできるだけ多様な感情が含まれているものを選ぶと、子どもが自分の気持ちを細かく表現しやすくなります。
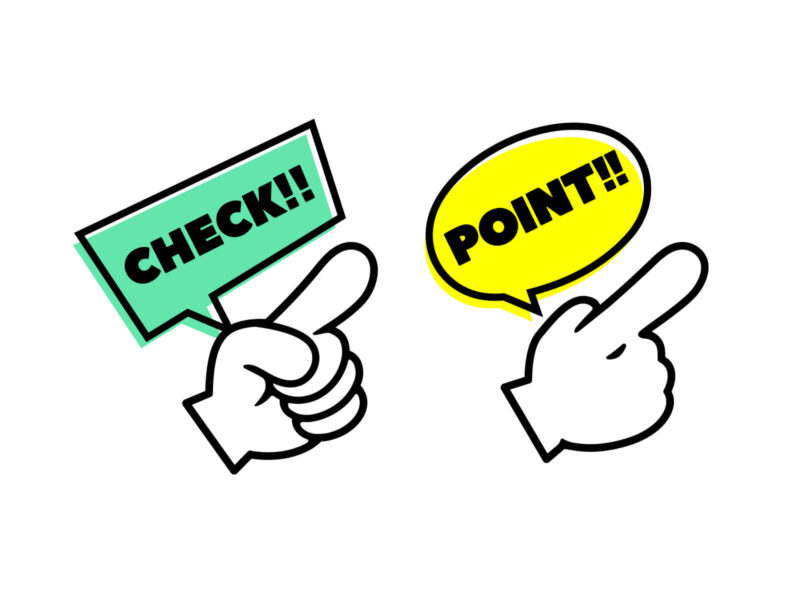
また、絵カード作りにおすすめの無料サイトもご紹介しておきます👇
【視覚支援に◎】絵カードが簡単に作れる!
▶︎ ザ・プロンプト!絵カードセンター(https://ecard.theprompt.jp/)
5. 感情カードの使い方5ステップ✨|かんしゃく・困りごとの予防にも
感情カードを活用するには、日常の中に「習慣化」することがポイントです。
ここでは、よくある5つのシーンと活用法をご紹介します。
① 朝の準備🕘
気分が乗らない時のサポート
「今日はどんな気持ち?」と聞きながらカードを見せると、子ども自身が気持ちを言葉にしやすくなります。
「眠い」「だるい」などの気持ちを表現できれば、無理なく支援する方法を考えることができます。
② 兄弟げんか👦👧
お互いの気持ちを理解する
兄弟げんかが起きたとき、「今、どんな気持ち?」と感情カードを使って伝え合うことで、自分の感情に気づき、相手の気持ちにも目を向けられます。
お互いの気持ちを知るきっかけになります。
→「怒った」「悲しい」と選ぶだけでも感情の整理になります。
③ 外遊びの後🌳
疲れやストレスを表現する
外遊びの後、子どもがイライラしたり、ぐずったりすることはありませんか?
そんなときも感情カードが役立ちます。
「今、どんな気分?」と問いかけながらカードを見せ、
遊び疲れや思い通りにならなかった気持ちを「疲れた」「もっと遊びたい」とカードで表現することで、イライラを言葉に変換できます。
④ 夜のふりかえり🌙
1日の気持ちを整理する
寝る前に「今日はどんな気持ちだった?」と振り返ることで、子どもが自分の感情を意識する習慣がつきます。
「楽しかった」「寂しかった」など、親子で感情を共有することで、安心感や親子の心のつながりも深まります。

⑤ トラブルの後🌀
感情の整理をサポートする
幼稚園や公園での出来事を、帰宅後に感情カードで整理。
自分の気持ちを知ることが、「次はこうしてみよう」という前向きな行動へとつながります。

🌼実体験エピソード|息子の「悔しい」が言えた日
先日、息子が児童発達支援のお友達と遊んでいるとき、ゲームに負けて悔しさのあまり喧嘩になってしまいました。
帰宅後、「どんな気持ちだった?」と感情カードを見せると、少し考えてから「悔しかった」と指差しました。
「悔しいとき、どうすればよかったかな?」と聞くと、「負けても大丈夫…」とぽつり。
完璧じゃなくても、「自分の気持ちを言葉で伝える」力が、少しずつ育っているのを感じた瞬間でした。
✅ポイント|感情カードを通じて「こころの土台」を育てよう
感情カードを活用することで、
- 気持ちの言語化
- かんしゃくの予防
- 親子の対話の習慣化
につながります。
日常のちょっとした時間に取り入れて、子どものこころを育てる習慣を一緒につくっていきましょう😊
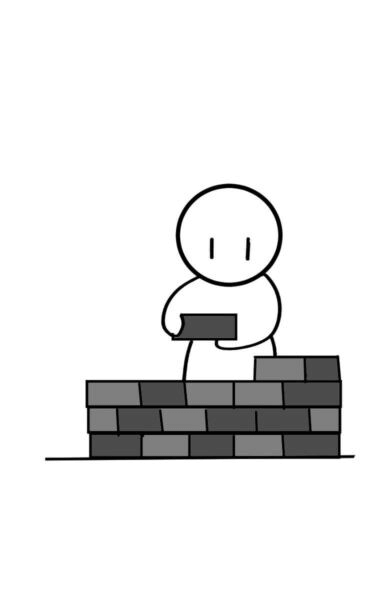
6. 感情カードの使い方|効果的な5ステップ 🌈

感情カードは「気持ちを言葉にする力」を育てる素晴らしいツールです。
以下の5ステップで、子どもとの関わりに取り入れてみましょう。
① 自分の気持ちをカードから選ぶ
「今日はどんな気持ち?」と声をかけ、子どもに今の感情に近いカードを選んでもらいましょう。
👉 選ぶことで「自分の気持ちに気づく力」が育ちます。

② 理由を聞いてみる
「どうしてその気持ちを選んだの?」と優しく問いかけましょう。
子どもが感情の理由を考え、言葉で説明する(感情と言葉をつなげる)練習になります。💬

③ 感情に共感する
選ばれた感情に寄り添う声かけが大切です。
「悲しかったんだね」「イライラしたんだね」と、まずはその気持ちを受け止めてあげてください ❤️

④ 対処法を一緒に考える
感情とどう向き合うかを親子で考えます。
例えば「怒ったときはどうすればいいかな?」と問いかけながら…
子どもに合った方法を一緒に見つけましょう。
- 🧘 深呼吸やリラックスタイムを取り入れる
一緒に深呼吸をしたり
落ち着ける方法を試してみる。 - 🧸 クールダウンの方法を決めておく
お気に入りのぬいぐるみを抱く
静かな場所に移動する
好きな音楽を聴くなど
自分に合った方法を見つける - 🌟 ポジティブな言葉を一緒に考える
「負けても大丈夫」「次はこうしてみよう」と、前向きな声かけを考える - 📚 感情がテーマの絵本や動画で感情を学ぶ
「悔しい」「悲しい」「怒り」などの感情を扱ったストーリーを読むことで、共感力を育む。
⑤ 感情を記録する
カードでやりとりした気持ちを、日記や記録シートに残す習慣もおすすめです 📝
繰り返すことで、感情のパターンや対処法が見えてきます。

7. 感情カード活用のコツ3つ💡
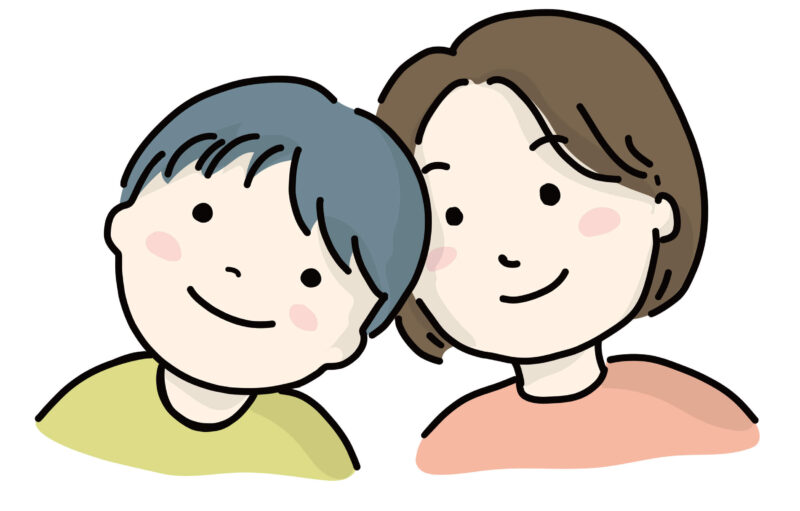
感情カードは、ちょっとした工夫で効果がぐっと高まります!
① 感情を押し付けない
「これは怒ってるでしょ?」と決めつけず、「どの気持ちが近いかな?」と子ども自身に選ばせましょう。
👉 自分の感情に自信を持つ練習になります。
② ポジティブな感情も大切にする
「嬉しい」「楽しい」「ありがとう」などのカードも活用して、前向きな気持ちの表現も増やしていきましょう 🌼
③ 家庭だけでなく園や療育でも共有
幼稚園や児童発達支援の先生にも相談し、統一した使い方をすると、より効果的です。
8. よくある質問
感情カードとは何ですか?
子どもの感情理解を助けるカードで、表情のイラストや感情の言葉が書かれています。
感情カードは何歳から使えますか?
2歳頃から使用可能ですが、3歳以降の方がより効果的です。
感情カードはどこで買えますか?
Amazonや楽天、知育玩具の専門店などで購入できます。
手作りの感情カードでも効果がありますか?
はい。親子で作ることで、より感情表現を学ぶ機会になります。
感情カードはどうやって使うのが効果的ですか?
子どもに選ばせ、理由を聞き、共感し、対処法を一緒に考えるのがポイントです。
感情カードは発達障害の子どもにも有効ですか?
はい。特にASD(自閉症スペクトラム)やADHDの子どもには有効です。
感情カード以外に感情を育む方法はありますか?
絵本の読み聞かせ、ロールプレイ、日記なども効果的です。
感情カードを使うタイミングは?
朝の準備時、兄弟げんかの後、外遊びの後など、気持ちを整理したい時がベスト
子どもが感情カードに興味を持たない時はどうすればいいですか?
無理に押し付けず、ゲーム感覚で楽しく取り入れると効果的です。
感情カードを使うことで子どもにどんな変化がありますか?
感情表現がスムーズになり、親子の会話が増え、自己コントロール力が向上します。
まとめ:感情カードで子どもの気持ちを育てよう!
【感情カード】は、子どもが「今の気持ち」を自分の言葉で伝える力を育ててくれる魔法のツール✨
✔️ 「悲しい」「イライラする」「うれしい」などを言葉にできるようになると、
→ かんしゃくが減る
→ 親子のコミュニケーションがスムーズに
→ 自己肯定感がアップ
実際に我が家でも、気持ちを言葉にできずにモヤモヤしていた息子が、少しずつ「伝えられた!」「わかってもらえた!」という安心感を感じられるようになりました🍀
もし、お子さんが
🔸 感情表現が苦手
🔸 かんしゃくを起こしやすい
🔸 気持ちをうまく伝えられず困っている
そんな悩みを抱えているなら、まずは感情カードから始めてみませんか?😊
毎日のちょっとした声かけや遊びの中で、子ども自身が「自分の気持ち」を理解し、表現できる力が育ちます✨
関連記事(内部リンクの追加)
🔜次回予告
\子どもがイライラ?泣き止まない?/
次回は【【保存版】子どものストレス対策7選|親ができる感情コントロール・自己調整サポート】をご紹介します🎈
お楽しみに♪