はじめに
発達に特性のある子どもを育てる親にとって、毎日の生活は小さな工夫の積み重ねですよね🍀。
NHKの教育番組「でこぼこポン」は、そんな親子に寄り添い、発達障害の子どもに役立つ番組として注目されています📺✨。
「おかあさんといっしょ」内のミニコーナーで放送されていて、
個性豊かなキャラクターたちが日常の「困った」を楽しく解決するストーリーが魅力です。
私自身、発達に特性がある息子の子育てに悩む中で、「でこぼこポン」の内容に何度も励まされてきました。
息子の苦手なシーンと重なるエピソードが多く、「うちと同じだ!」と親として共感しっぱなしです😌。
この記事では、私の実体験をもとに、
- 「でこぼこポン」が療育に取り入れやすいNHK番組である理由
- 親子での楽しみ方・活用のコツ
をわかりやすくご紹介していきます。
「発達に特性のある子の支援方法」を探している方に、少しでもヒントになりますように🌼。

目次
- 「でこぼこポン」が朝のルーティンに取り入れやすい理由
- 発達が気になる子の悩みを解決!でこぼこポンの魅力
- でこぼこポンで子どもと一緒に成長できる4つの理由
- 「でこぼこポン」を活用した子育てのヒント
- よくある質問
- まとめ
1. 「でこぼこポン」が朝のルーティンに取り入れやすい理由🌞
「でこぼこポン」は、発達障害の子どもに役立つ番組として、多くの家庭で朝のルーティンに取り入れられています✨。
朝の忙しい時間でも、子どもと楽しく学びながら過ごせるのが大きな魅力です。

⏰ 忙しい朝にフィットする短時間構成
- ⏰ 放送時間:約10分(7:20 または 8:25 ごろ)で、朝の支度中にも見やすい長さ。
- 「おかあさんといっしょ」内に組み込まれていて、子どもの生活リズムに自然と馴染みます。
🎭 子どもにとっての魅力ポイント
- 親しみやすいキャラクター × テンポの良いストーリー
- 難しいテーマもわかりやすく描かれており、楽しく「できること」が増える構成です。
🏠 親にとっての利便性も◎
- 「でこぼこポン」は、療育に取り入れやすいNHK番組として、親子の課題を一緒に見つめ直すきっかけになります。
- たとえば、「朝の着替えが苦手」「片付けがうまくいかない」といったテーマが、番組内でやさしく描かれています。
🏠 課題を楽しく共有&解決
番組をきっかけに子どもと「苦手なこと」や「こんなときどうする?」と話し合える時間を作ることで、
家庭での支援にもつながります💡番組を通してヒントを得られるのが魅力です✨。

2. 発達が気になる子の悩みを解決!「でこぼこポン」の魅力✨
「でこぼこポン」は、発達障害の子どもに役立つ番組として、日常でよくある「困りごと」をリアルに描いてくれます。
親子で観ていると、「うちの子と同じ!」「こういう場面あるある…!」と共感の連続で、安心感が生まれます😊
発達に特性がある子の支援方法を、楽しく・分かりやすく紹介してくれる番組なんです。
📺 物語の流れがわかりやすい!
発達に特性のあるキャラクター 「ぼこすけ」 が困りごとに直面し、天才発明家 「でこりん」 がユニークな発明品で解決を試みるストーリー。

「ぼこすけ」が悩み、考え、成長していく姿はとても親しみやすく、療育に取り入れやすいNHK番組としても人気です。
🔍 実際の課題×解決のヒントが満載!
番組では、子どもがよく直面する課題(日常でよくつまずく場面)をリアルに描きながら、
それを乗り越えるための方法をわかりやすく提示しています。
✅ 「怒り」とつきあう発明品
→ 怒りを冷静にする工夫を学ぶ
✅ 順番が「分かる」発明品
→ 順番を守る練習ができる
✅ 苦手を伝える発明品
→ 感覚過敏など自分の困りごとを周囲に伝える方法を知る
子どもが自分と似た悩みを抱えるキャラクターと共感することで「自分だけじゃない」と安心でき、自然と問題解決の力が育ちます!
👨👩👧👦 親にとってのメリット👪「気づき」がいっぱい!
「でこぼこポン」は、子どもだけでなく、親にとっても大きな学びがある番組です。
💡 子どもの気持ちを理解しやすくなる
💡 困りごとにどう向き合うか、親子で話し合うきっかけになる
例えば、わが家では「怒りのコントロール」の回を見たあと、
「ママもカッとなっちゃうことあるけど、ぼこすけみたいに深呼吸してみようかな?」と話すと、
息子も「じゃあ僕もやってみる!」と前向きにチャレンジしてくれました😊。
親子で同じ目線で考える時間ができ、信頼関係も深まりました。
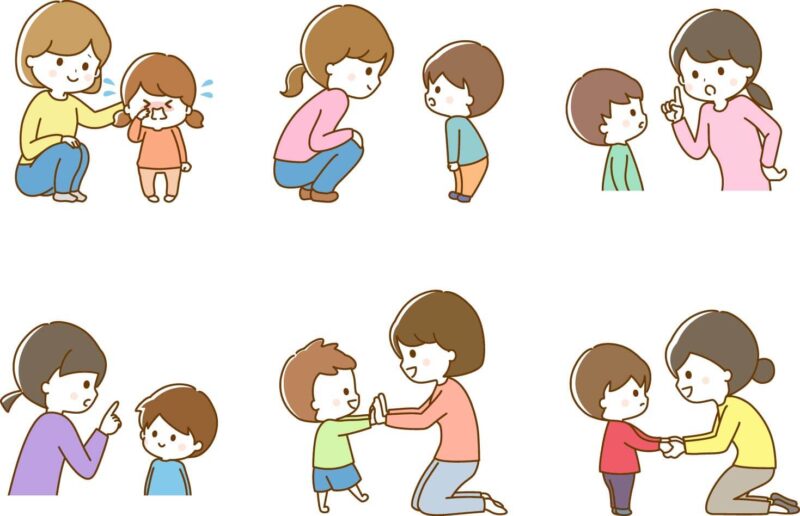
📢 エピソードタイトルの一部をご紹介
(公式サイトより)
「でこぼこポン」では、発達に特性のある子どもが直面しやすい課題をテーマにしたエピソードが豊富にそろっています。
🧠 たとえば「感覚過敏」や「こだわり」「順番を守ること」など、発達障害の子どもに役立つ番組として、リアルな悩みに寄り添った内容が多数!
発明家「でこりん」のユニークなアイデアで、子どもが楽しく学べるよう工夫されています。
療育に取り入れやすいNHK番組としても非常におすすめです😊
(公式サイトより抜粋)
- こだわりを調整する発明品
- 表情と気持ちを知る発明品
- 「やる気になる木」の発明品
- 怒りのコントロール発明品
- スマホを使いすぎないための発明品
- やることがたくさんあるときの発明品
- たくさんの人と話をする発明品
- 忘れ物をしないための発明品
- 時間を知る発明品
- 上手にねむるための発明品
- まちがいをくり返さない発明品
- 話が伝わる発明品
- 切りかえがうまくなる発明品
- なわとび忍者の発明品
- 苦手を伝える発明品 〜感覚過敏編〜
- 学校に行かないときの居場所の発明品
- 自信がもてる発明品
- 道に迷わないための発明品
- 「もしかして」とつきあう発明品
- 手をうまく使うための発明品
- 順番が「分かる」発明品
- 「心の声」を知る発明品
- 話しすぎない発明品
- 「苦手」を楽しくする発明品
- 「まちがい」とつきあう発明品
- おちつく場所の発明品
- スモールステップの発明品
- 「よい姿勢」の発明品
- 文字の書き方の発明品
- 自分の気持ちが分かる発明品
- おしゃべりを「見る」発明品
- 前向きになれる発明
- 「自分を研究する」発明
- 「やることを忘れない」発明品
- 力加減の発明品
- 集中する発明品
- 予定の変更とうまく付き合う発明品
- かたづけができる発明
- 相手の気持ちを知る発明
- ぶつからずに動く発明
✅ 親子で成長できる、優しい番組です🌈
「でこぼこポン」は、子どもが楽しく視聴しながら成長できるだけでなく、
発達に特性のある子の支援方法を親が自然に学べる、ありがたい番組です。
まずは1話だけ、一緒に観てみてください😊
「わかる!」「これ使える!」そんな発見がきっとあるはずです✨
✅ 見逃しても安心!公式サイトで配信中🎬
「でこぼこポン」は、親子で一緒に楽しみながら、発達に特性のある子の支援方法を学べる貴重な番組です。
エピソードのタイトルを見ただけでも、子どもの「苦手」をサポートするヒントが詰まっているのが伝わってきますよね✨

📱見逃した回も大丈夫!
NHKの公式サイトでは一部エピソードの見逃し配信が視聴可能です。
🔗 でこぼこポン|NHK公式ページ
まずは1話、ぜひ親子で観てみてくださいね😊
3. でこぼこポンで子どもと一緒に成長できる4つの理由
発達に特性のある子の支援方法を楽しく学べる!
「でこぼこポン」は、発達障害の子どもに役立つ番組として、子どもはもちろん、親にとっても多くの学びがある内容です。
私自身、息子と一緒に視聴しながら、日常生活に役立つヒントをたくさん得ることができました。
特に、以下の4つのポイントが印象に残っています。
①「困っているのは自分だけじゃない」と気づける安心感🫶
発達に特性がある子は、日常の中で戸惑いや失敗を経験しやすく、「どうしてできないの?」と悩むことが多いですよね。
私の息子も、友達との距離感がわからなかったり、順番を守れなかったりと、困りごとがたくさん。
そんなとき「でこぼこポン」で似たような悩みをもつキャラクターが登場し、解決していく様子を見ると、
子ども自身も「ぼくだけじゃないんだ」と安心できる様子でした。
②「やってみよう!」と思える挑戦のきっかけに🚀
番組では、困ったときの具体的な対処法が紹介されます。
「怒りのコントロール」「順番を守る」「気持ちを伝える」など、日常のシーンで使える工夫がたくさん!
発達に特性のある子が抱えやすい課題への具体的な支援方法が、わかりやすく紹介されます。
たとえば:
🔷 息子と一緒に見た「上手な借り方」の回では、
「貸す人の気持ちを考える」ことの大切さが、分かりやすく描かれていました。
息子も「どうやって頼めばいいかな?」と考えながら、おもちゃを借りる練習をしています✨
🔷 「相手の気持ちを知る」回では、
「仲良しでも、言われたらイヤな言葉がある」というポイントが、再現ドラマを通じて伝えられていました。
息子も「これ、言ったらイヤかな?」と考える場面が増え、少しずつコミュニケーションに変化が出てきました。
③ すぐ実生活に活かせる!分かりやすいストーリー📖
「でこぼこポン」の大きな魅力は、ただ正解を教えるのではなく、子ども自身が気づける構成になっていること。
たとえば:
🔷 「怒りのコントロール」の回では、
「怒り方には個人差がある」ことに触れ、いろいろな対処法が紹介されます。
わが家でも、「怒ったときの合図」を決めて、息子と一緒に「深呼吸をする練習」をスタート!
少しずつ癇癪が減ってきました。
🔷「文字の書き方」の発明品の回では、
でこりんが文字がはみ出してしまう理由が「視覚の特性」だったことに気づく描写がありました。
💡「なるほど、見え方の違いがあるんだ」
書きやすくなる工夫を試す場面では、
「こんな方法があるんだ!」と、親としても学びがありました。

療育に取り入れやすいNHK番組として、
日常に応用しやすい工夫、特性に合わせた工夫の仕方がとても参考になり、学びがたくさん詰まっています!
④「できた!」の経験が自己肯定感につながる🌱
番組のキャラクターが試行錯誤しながら成長する姿を見て、息子も「ぼくもやってみよう!」とやる気に✨
🔷「忘れ物をしない発明品」の回を見た後、一緒に「おでかけチェックリスト」を作成!
自分で確認できるようになり、「できた!」という成功体験につながりました😊
🔷また、縄跳びが飛べず諦めモードだった息子も、でこぼこポン「なわとび忍者の発明品」の回を活用!
キャラクターの真似をして、小さなステップから挑戦してみました。
①「髪を洗うイメージ」で腕を動かす練習
②「タオルを回す練習」
③「タオルとび」
④ そして、ついに「なわとび」へ!
この方法が息子にピッタリ合い、「あ、できそう!」と自信がついてきた様子✨
少しずつ練習を重ね、ついに数回ジャンプ成功!🎉

「無理!」が「できた!」に変わる、この成功体験が子どもの自信を育んでくれると実感しています。

🌟親子で成長できるヒントがつまった「でこぼこポン」📺
発達の凸凹がある子どもにとって、困りごとは日常的にたくさんあります。
でも、「でこぼこポン」を通して「こうすればいいんだ!」と気づくことで、少しずつ乗り越える力を育めます。
親も子も自然に学び、日常に取り入れやすい支援方法やヒントが詰まった番組です。
私自身も息子と一緒に視聴し、試せることを少しずつ取り入れながら成長中です。

💡 公式サイトでは一部エピソードの見逃し配信もあります!
親子で一緒に視聴して、楽しみながら学びを深めてみてくださいね😊

4. 「でこぼこポン」を活用した子育てのヒント🌱
「でこぼこポン」は、観るだけでなく日常に取り入れることで効果がぐんと高まる番組です✨。
ここでは、わが家でも実践している活用法をご紹介します!
📌 家庭で実践しよう!
番組で紹介された行動やセリフを、生活の中に取り入れてみましょう。
✅ 片付けのルールを一緒に練習
✅ 朝の支度をキャラクターと同じ順番で進めてみる
✅ 気持ちの切り替えが難しい場面で、番組の言葉を思い出す
👉 発達に特性のある子の支援方法として、無理なく家庭で始められるのが嬉しいポイントです。
🗣 親子で「ふりかえりタイム」を持つ
番組を観たあとに、
「今日のお話、どう思った?」
「こんなとき、どうしてる?」
と問いかけることで、子どもの感情や考えを引き出す時間になります😊
👀 子どもの視点を学べるチャンスに
- 「でこぼこポン」は、親が知らなかった子どもの思いや感じ方に気づけるきっかけになる番組です。
- 子どもの反応から、「こんなふうに見えていたんだ」と理解が深まることもあります。

💡親が寄り添い、子どもが自信を持って行動できる環境づくりに、「でこぼこポン」はとても心強いサポーターになります。
5. よくある質問
「でこぼこポン」は何歳向けの番組ですか?
主に 3歳〜小学生の子どもを対象にしています。
発達障害の診断がない子でも「でこぼこポン」は楽しめますか?
はい、すべての子どもに役立つ内容 です。
社会性や感情のコントロールなど、どの子にも大切なスキルを学べます。「でこぼこポン」の放送時間はいつですか?
「おかあさんといっしょ」内で7:20頃と8:25頃に放送 されています。(変更の可能性あり)
どこで「でこぼこポン」のエピソードを見ることができますか?
NHKのEテレの放送 や、NHKプラス(見逃し配信) で視聴可能です。
子どもの発達支援に「でこぼこポン」をどう活用できますか?
番組の内容を家庭のルールや日常生活に取り入れる と、子どもが学びやすくなります。
「でこぼこポン」のキャラクターはどんな役割を持っていますか?
「ぼこすけ」(困りごとを抱える子)と、「でこりん」(解決策を提案する発明家) が、親しみやすいストーリーを展開します。
「でこぼこポン」を見せることで子どもにどんな変化がありましたか?
実際に「順番を守る」「感情を言葉で伝える」などのスキルが身についたという声が多いです。
「でこぼこポン」の内容は療育に役立ちますか?
療育の専門家が監修しているため、家庭でも応用しやすい内容になっています。
「でこぼこポン」のグッズや関連書籍はありますか?
現時点では公式グッズはないが、NHKの子育て本に関連情報が載っていることがあります。
「でこぼこポン」はいつから始まった番組ですか?
2023年4月 からNHKで放送が開始されました。
6. まとめ🌱「でこぼこポン」で広がる子どもの可能性

「でこぼこポン」は、発達障害や発達に特性のある子どもが、楽しく学べるNHKの教育番組です。
親が子育てのヒントを得られるだけでなく、親子のコミュニケーションを深めるきっかけ作りにもなります✨。
たとえば――
- 朝の準備が苦手な子が、番組の流れをマネしてスムーズに動けるように
- 感情のコントロールが難しい子が、キャラクターのやりとりを参考に気持ちを整理できるように
- 親が「こう声をかければいいんだ」と気づけるように
…といった形で、家庭の中にすぐ取り入れやすい内容ばかりです。
📌 NHK公式サイトでは過去のエピソードが見られることもあるので、忙しい朝に見逃してしまっても安心です
(→公式サイトはこちら)。
「でこぼこポン」を活用して、子どもの「できた!」が増える毎日を一緒に作っていきましょう😊
まずは1話だけ、一緒に観てみてください📺💡






