はじめに
👶子どもの「発達」に関する悩みは、多くの親が一度は抱えるテーマではないでしょうか。
私自身も、初めて児童発達支援を利用すると決めたあの日のことを、今でも鮮明に覚えています。
迷いや不安、周囲との情報の違い――。
一歩を踏み出すまでに、たくさんの葛藤がありました。
この記事では、私がどのようにして児童発達支援の利用を決断したのか、
その背景や体験談を交えながら、
- 「児童発達支援とは?」
- 「どうやって事業所を選べばいいの?」
- 「利用料金や助成制度ってどうなってるの?」
といった疑問にお答えしていきます✨
「自分の子どもにも必要かも…」と感じている方が、一歩踏み出すヒントになりますように。

目次
- 勉強会での気づき:児童発達支援との初めての出会い
- 利用を決めるまで
- 児童発達支援の利用を決めたらまずすること
- 利用前に知っておきたいお金のこと
- 児童発達支援の料金はどう決まるの?
- 【学年別|児童発達支援の対象児童早見表(2025年度)】
- 児童発達支援の利用可能日数は?
- 助成制度はどう使うの?どこに聞けばいいの?
- 【見学のコツ】児童発達支援事業所の選び方
- 見学時にチェックしたポイント
- 児童発達支援と幼稚園の違い【比較と実体験】
- 児童発達支援と幼稚園の違い【比較表】
実体験と一覧でわかりやすく解説 - ポイント
- 児童発達支援と幼稚園の違い【比較表】
- よくある質問
- まとめ
1. 勉強会での気づき児童発達支援との初めての出会い
ある日、療育センターで開催された月1回の保護者向け勉強会に参加しました。
その日のテーマは「児童発達支援」📚
実は当時、私はこの言葉すらよく知らず、「なんとなく聞いたことがあるかも…」というレベル。
ですが、この日を境に私の考え方が大きく変わっていきました。
💬リアルな声との出会いが背中を押した
勉強会の後には、少人数グループでの座談会があり、市役所の方や実際に支援を利用している親御さんの話を聞くことができました。
🔸 週の半分を保育園、半分を児童発達支援で過ごすお子さんのお話
🔸 「専門家が見てくれるから、安心できる」というママの声
🔸 お子さんが「支援の日を楽しみにしている」と笑顔で語る姿
これらのエピソードが、心にスッと入り込んできました。
「うちの子にも、こんな居場所ができるのかな?」そんな希望が芽生えた瞬間です。
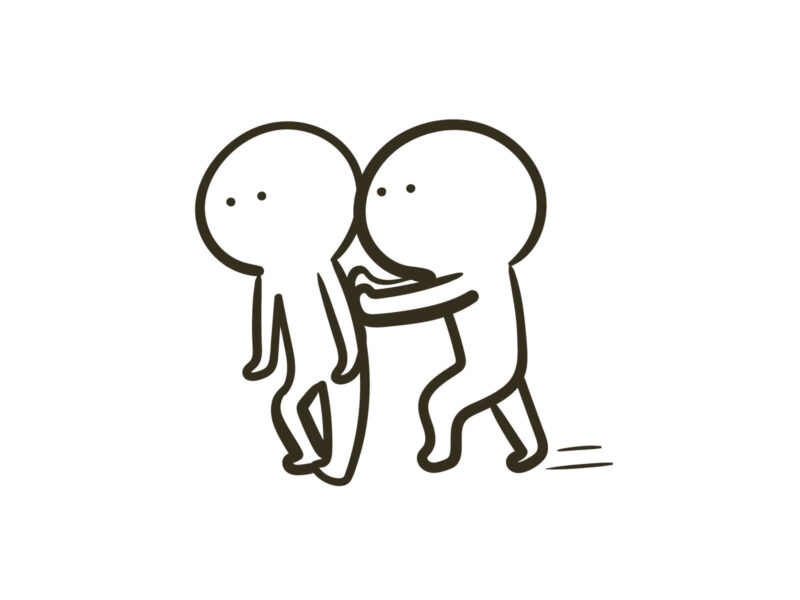
❓児童発達支援とは?
児童発達支援とは?
発達に特性を持つ未就学児を対象に、日常生活・社会性・コミュニケーションなどをサポートする福祉サービスです。
例えば、吃音やコミュニケーションの難しさ、身体の使い方の不器用さなど、子どもごとの課題に応じた支援が行われます。

- 対象:
0〜6歳の未就学児(発達の遅れや特性がある子ども) - 内容:
遊び・運動・言語など、子どもに合わせた個別・集団プログラム - 目的:
困りごとに応じた「できる」を増やし、子どもの自信と成長を促す - 費用:
自治体の助成制度により、3〜5歳は基本的に無償化の対象💡
この支援により、親子の不安はぐっと減り、日常に笑顔が増えていきます😊
🎂【2025年(令和7年)に児童発達支援を利用できるお子さんの誕生日】
対象となるのは、
2019年(平成31年/令和元年)4月2日〜2025年(令和7年)4月1日生まれのお子さんです。
📌さらに、以下のお子さんは「無償化」の対象になります
2019年(令和元年)4月2日〜2021年(令和3年)4月1日生まれ
※手続きの詳細や必要書類については、
お住まいの市区町村の障害福祉課(または福祉担当窓口)にご確認ください。
2. 利用を決めるまで私たち親子の決断のストーリー
勉強会をきっかけに、私は児童発達支援に強く惹かれるようになりました。
そこで、まずは信頼している療育センターのスタッフや、
吃音でお世話になっている言語聴覚士さんに相談してみることに。
「もっと支援の機会があれば、お子さんの力を伸ばせると思いますよ」と言われ、
私の中で「迷い」が「確信」に変わっていきました。

😢息子のつぶやきが決断の後押しに
ちょうどその頃、息子が幼稚園を嫌がる日が増えてきていて…。
ある朝、今まで聞いても教えてくれなかった答えが、
「ぼくだけできないことがあるから、行きたくない」とポツリ。
その一言に、胸が締め付けられるような思いがしました。
頑張っているのに、苦しさを感じている――
そんな息子に、楽しみながら「自信」を取り戻せる場所が必要だと痛感したのです。
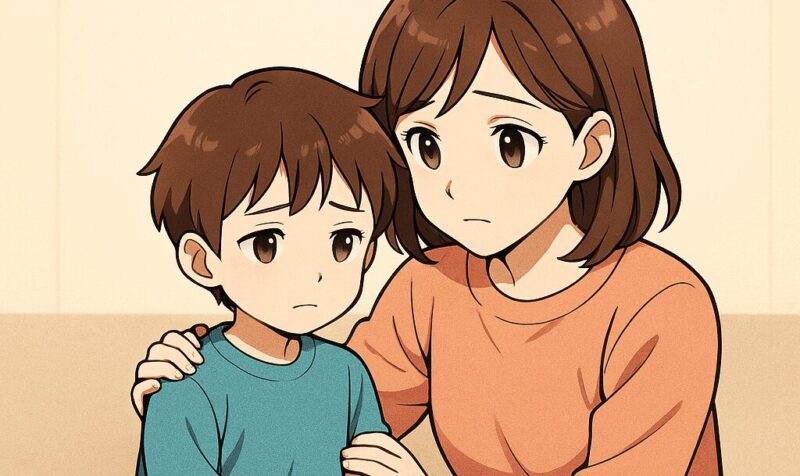
✅そして決意|児童発達支援を探し始める
その日から私は、地域の児童発達支援事業所を調べ、見学や面談を始めました。
「この子にとって、心地よく過ごせる環境を見つけたい」
そんな想いで動き始めたのが、私たちの新しいスタートでした🌈
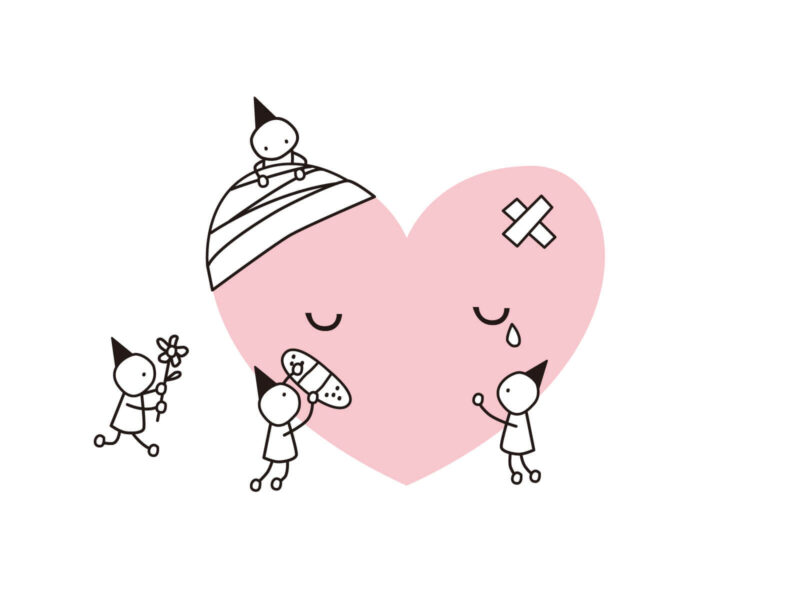
3. 児童発達支援の利用を決めたらまずすること【事業所選びと制度の確認】
- 料金や助成制度の確認
- 複数の事業所を見学・比較すること
事業所によって費用負担が異なることもあるため、
制度をしっかり理解したうえで見学を行うと安心です。
「どこがうちの子に合っていそうか?」を肌で感じながら比較することが、納得できる選択につながりました。
4.【最新版】児童発達支援の料金はいくら?【最新版】児童発達支援の利用料金と助成制度
料金や助成制度って複雑そう…
児童発達支援って高いの?うちも利用できる?
でも大丈夫!
そんな不安を持つ方に向けて、料金のしくみ・助成制度・無償化の範囲をわかりやすくまとめました😊

✅ 児童発達支援の料金はどう決まるの?
児童発達支援の自己負担額は、「所得に応じて段階的に決定される」仕組みです。
※ 利用日数や時間に関係なく、月額定額制(上限あり)です。
🌟負担額の目安(2024年度参考)
| 世帯の収入状況 | 月額上限負担額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 前年度の年間所得890万円までの世帯 | 4,600円 |
| 前年度の年間所得890万円以上の世帯 | 37,200円 |
🧸 3〜5歳のお子さんは原則、利用料が無償化されています!
※ ただし、食事代や送迎費は保護者負担となることが多いため、事前に確認しておくと安心です。
✅【学年別|児童発達支援の対象児童早見表(2025年度)】年齢・生年月日でわかる無償化と利用対象
| 生年月日 (西暦) | 生年月日 (和暦) | 年齢 (2025年4月時点) | 学年 | 児童発達支援 利用対象 | 無償化対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/4/2 〜 2023/4/1 | 令和4年4月2日 〜 令和5年4月1日 | 満2歳 | 年少々(3歳未満) | ✅ 対象 | ❌満3歳になった後の最初の4月1日からが対象 |
| 2021/4/2 〜 2022/4/1 | 令和3年4月2日 〜 令和4年4月1日 | 満3歳 | 年少 | ✅ 対象 | ✅ |
| 2020/4/2 〜 2021/4/1 | 令和2年4月2日 〜 令和3年4月1日 | 満4歳 | 年中 | ✅ 対象 | ✅ |
| 2019/4/2 〜 2020/4/1 | 平成31年4月2日 〜 令和2年4月1日 | 満5歳 | 年長 | ✅ 対象 | ✅ |
| 2018/4/2 〜 2019/4/1 | 平成30年4月2日 〜 平成31年4月1日 | 満6歳 | 小1 | ❌ 対象外 | ❌ |
🔍 例:令和4年4月25日生まれ
無償化開始は令和8年4月1日から。終了は令和11年3月31日まで。
✅ 児童発達支援の利用可能日数は?利用日数は決まってるの?
厚生労働省が提示している原則的な支給量の上限は月23日です。
これは月の日数から週2回の休養日(およそ8日)を引いた日数です。
| 月の日数 | 支給上限日数 |
|---|---|
| 31日 | 23日 |
| 30日 | 22日 |
📍 実際の利用日数は自治体によって違います。
例:大阪府八尾市では月15日が基本支給量。原則の日数より少なく設定されています。
👉 必ず、ご自身の自治体で事前確認を!
✅ 助成制度はどう使うの?どこに聞けばいいの?
- お住まいの市区町村の福祉課が窓口です。
- 児童発達支援の利用には料金がかかりますが、多くの自治体で助成制度が利用可能です。
- 実際に私も、市役所で丁寧に教えてもらい安心して利用開始できました📞
👉 詳細は、【厚生労働省公式サイト】にも掲載されています。
👉 🔗【児童発達支援・放課後等デイサービスについて】
5.【見学のコツ】児童発達支援事業所の選び方

料金や助成制度について調べた後、
私が次に取り組んだのは、複数の事業所の見学でした。
「児童発達支援」とひとことで言っても、
事業所によって ✨雰囲気・プログラム内容・スタッフの専門性✨ はまったく異なります。
つまり、児童発達支援事業所に「正解」はないということ。
だからこそ、実際に足を運び、雰囲気や対応を自分の目で確かめることがとても大切だと感じました。

🔍見学時にチェックしたポイント
- スタッフさんの対応や言葉がけ
- 子どもたちの様子や表情
- 支援の内容(個別?集団?どんな遊び?)
- 保護者へのフィードバックの有無
📚関連記事もぜひチェック👇
🔗「【完全ガイド】児童発達支援事業所の選び方」
🔗「児童発達支援事業所 見学時に確認すべきポイント」
🔗「【体験談】1時間(短時間集中型)の児童発達支援施設を選んだ理由」
🔗「【体験談】言語聴覚士・理学療法士の支援内容とは?」
🔗「【体験談】1日型の児童発達支援で見られたメリットと息子の変化」
6. 児童発達支援と幼稚園の違い【比較と実体験】
「幼稚園とどう違うの?」という疑問に、実際の体験からお答えします。
「幼稚園と児童発達支援ってどう違うの?」
私も最初はそう感じていました。
実際に両方を利用してみて、その違いは「子どもへの支援の深さと目的」にあると実感しました。

🧠児童発達支援と幼稚園の違い【比較表】
| 比較項目 | 児童発達支援 | 幼稚園 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 発達の遅れ・障害に特化した支援 | 一般的な幼児教育 |
| スタッフ | 言語聴覚士・作業療法士・心理士など専門家 | 幼児教育の有資格者 |
| 活動内容 | 個別支援・感覚統合・言語療法など | 集団遊び・お絵かき・体操など |
| スケジュール | 柔軟(週2~5、1~4時間など) | 固定(月~金 9:00~14:00など) |
| 利用対象 | 発達に特性のある子ども | 一般的な子ども(定型発達) |
📌実際に、息子は幼稚園では「みんなと同じにできない」と感じて苦しんでいたけれど、児童発達支援では「できた!」の経験を積み重ねることができました✨
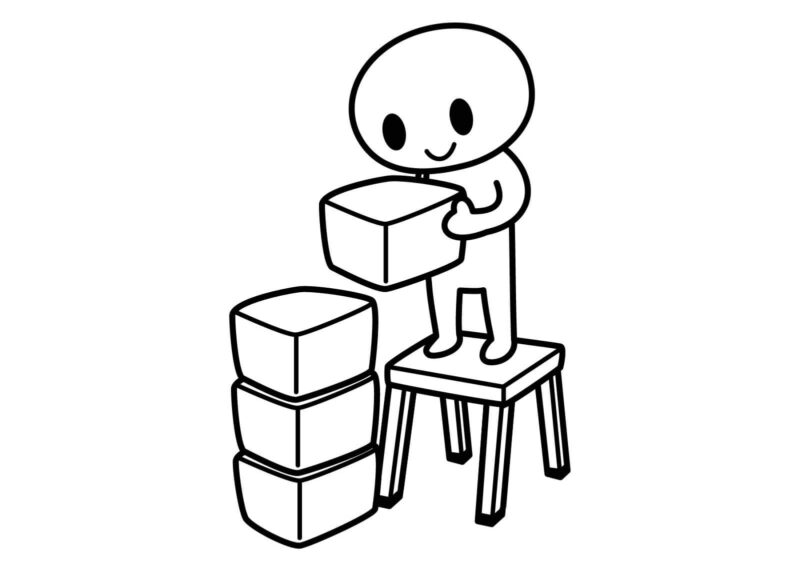
📝ポイント
✔事業所選びでは、見学と相性チェックが重要!
✔助成制度の活用で、無理なく続けられる✨
✔幼稚園と併用することで、子どもの笑顔と自信が戻ってくることもあります🌈
料金や助成制度は少し複雑に見えますが、正しい情報を知れば、安心して療育をスタートできます。
7. よくある質問
児童発達支援はどのような子どもが対象ですか?
発達に遅れや課題を持つ子どもが対象で、年齢や診断によって異なります。
利用には診断が必要ですか?
必要な場合もありますが、自治体や事業所によります。
児童発達支援を利用するにはどうすれば良いですか?
市役所や療育センターで相談し、手続きするのが一般的です。
助成制度はどのように申請しますか?
自治体の福祉課で申請手続きを行います。
助成制度は所得によって違いますか?
はい、所得区分に応じた上限額が設定されています。
児童発達支援と保育園や幼稚園は併用できますか?
併用可能ですが、スケジュール調整が必要です。
見学時にチェックすべきポイントは?
スタッフの対応、施設の雰囲気、支援内容が自分の子どもに合うかどうかを確認してください。
利用日数の上限を超えた場合はどうなりますか?
自費での利用になる場合があります。
どのような専門家がサポートしてくれますか?
言語聴覚士、作業療法士、心理士などが支援を行います。
児童発達支援の効果はどのくらいで実感できますか?
子どもによりますが、少しずつ行動や自信の変化が見られます。
児童発達支援を利用するメリットは何ですか?
専門的な支援を受けることで、子どもの発達を促進し、自信を持たせることができます。
また、親御さんの負担を軽減し、安心して子育てを続けることができます。児童発達支援の申し込み手続きはどのように行いますか?
申し込み手続きはお住まいの自治体の担当窓口で行います。
必要な書類や手続きの詳細は自治体のホームページや窓口で確認してください。児童発達支援と幼稚園の違いは何ですか?
児童発達支援は発達障害や遅れのある子どもを専門的にサポートするのに対し、幼稚園は一般的な教育と集団活動を提供します。
支援内容やスタッフの専門性にも違いがあります。
まとめ
🌱児童発達支援を利用し始めて、親子の毎日は少しずつ変わっていきました。
最初のきっかけは、勉強会で出会った他の保護者の方からのアドバイス。
「同じように悩んでいた保護者の方の体験談」を聞けたことで、私の心は少し軽くなりました。
息子の未来が見えず、不安で立ち止まりそうになった時期もありましたが、
専門的な支援を受けながら少しずつ成長していく姿に、私自身も勇気をもらいました。
特に助かったのが、3〜5歳の無償化制度や助成制度の存在💡
経済的な不安が減ることで、より安心してサポートに向き合えました。
さらに、3歳から5歳までの無償化制度があったことで、経済的な負担が軽減され、本当に助かりました。
こうしたサポートがあるおかげで、私たち親子も安心して次のステップに進むことができたと思います。
📌児童発達支援は、子どもの可能性を広げる大切な一歩。
この記事が、これから事業所を選ぶ方や制度を活用したい方のとな参考となれば嬉しいです。
🔜次回予告
次回は、
「【体験談】相談支援事業所と児童発達支援の選び方・申し込み手順をわかりやすく解説」についてお届けします!
お楽しみに!
🎁この記事が参考になった方は、ぜひ他の保護者の方にもシェアしてくださいね。
コメント欄でのご質問やご感想も大歓迎です📩






