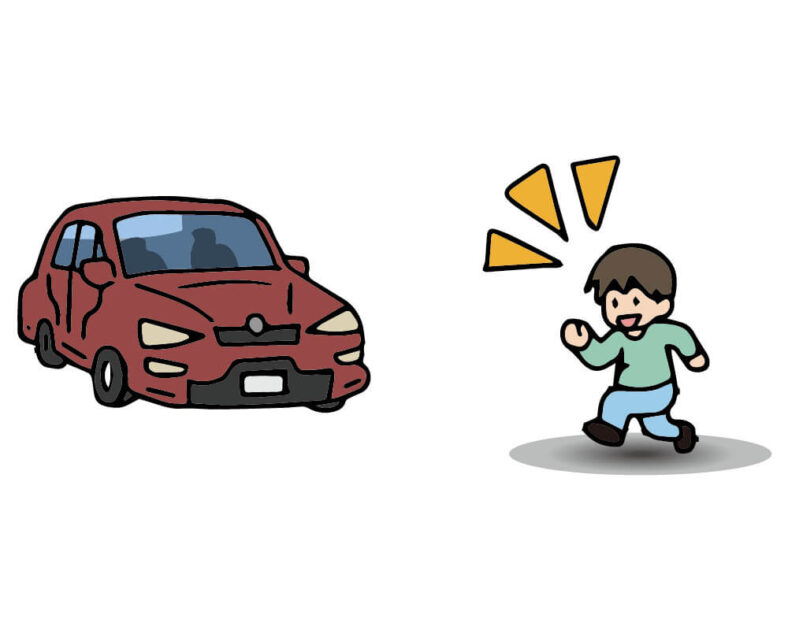はじめに
「狭いところでふざける」「砂を投げる」「道路に飛び出しそうになる」…。
もうすぐ6歳になる息子のヒヤッと行動が止まらなくて、毎日ハラハラしていませんか?

「なんでこんなことするの?」「危ないって言ってるのに!」
と、ついイライラしてしまうこともありますよね。
でも、子どもが危険を予測できないのは、発達の段階でゆっくり育っていく力の一つ。
本記事では、発達特性を踏まえた家庭での安全サポート方法と、ママが焦らず見守るコツをお伝えします。
📖 目次
- はじめに
- 第1章:危険予測ができない子とは?
- 第2章:背景にある発達的特性
- 第3章:家庭でできるサポート方法(実践編)
- 第4章:なぜ何回言ってもできないのか
- 第5章:ママが罪悪感を抱かないでほしい理由
- 第6章:成長と見通し — 危険予測力は必ず伸びる
- よくある質問と答え(FAQ)
- まとめ
🩵第1章:危険予測ができない子とは?
「危ない」が分からないのはなぜ?
- 危険を「想像」する力が未発達
- 経験から学びにくい
- 衝動のコントロールが難しい
- 注意の切り替えが苦手
こんな行動ありませんか?
- 狭い場所でふざける
- 砂を投げる/帽子の紐を目に当てる
- 道路に飛び出しそうになる
- 友達を突き飛ばす
👉 一見「わざと」「悪気がある」ように見える行動でも、
実は発達の特性が関係していることが多いのです。
🧠第2章:背景にある発達的特性
- 危険を想像する「見通し力」の未熟さ
- 行動を抑える「抑制機能」の弱さ
- ボディイメージや距離感のつかみにくさ
- 感覚の過敏さや鈍さ
- 注意の集中・分散の難しさ
※ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、発達性協調運動症(DCD)などの子に多く見られる傾向です。
🏠第3章:家庭でできるサポート方法(実践編)
① 危険を「具体的に」伝える
- 「危ないよ」ではなく、
「砂は投げないでね。目に入ると痛いよ」など具体的に。 - 行動のルールを明確にして、見通しを持たせる。
② 「見えるルール」で予防
- イラストや写真カードでOK/NGを可視化。
- 公園・家・道路など場所ごとにルールを掲示。
③ 行動の結果を一緒に振り返る
- 「砂を投げたら〇〇くんが痛そうだったね」
- 体験→結果→次への学びを結びつける。
④ 安全な「代替行動」を提案する
- 砂を投げたい → スコップで掘る/型抜きで遊ぶ
- 帽子の紐を触りたくなる → 紐なし帽子やセンサリートイに置き換え
- 道路に飛び出したい → 手をつなぐ/リード付きリュックで誘導
⑤ 「できた瞬間」を逃さず褒める
- 「危ないことしなかったね」「お約束守れたね!」
- 成功体験を可視化することで、自己コントロール力が育ちます。
⑥ 園や療育と連携する
- 危険行動が続く場合は、家庭だけで抱えず共有する。
- 環境調整や一貫したルール作りで学習効果が高まります。
🩵第4章:なぜ何回言ってもできないのか
① 理屈より体験で学ぶ
- 言葉だけより、実際に体験した方が学びやすい
- 「痛い」「怖い」「びっくり」といった感覚的な理解が鍵
② 危険のイメージが結びつかない
- 実際に車にぶつかった経験がないと、道路の危険は想像しづらい
- 「相手が痛い」という感情理解もまだ未発達
③ 衝動を止めるブレーキ機能が弱い
- 6歳前後では、思いついた行動をすぐやってしまう
- 「やってはいけない」と分かっていても、止める力(抑制機能)が未発達なのです。
🌟第5章:ママが罪悪感を抱かないでほしい理由
① 叱ってしまうのは愛情の証
- 「危ない!」と声を荒げるのは、命を守るための自然な反応。
- 叱ったあとにフォローすることで、子どもは安心して学べます。
② 怒ったあとに気持ちを伝える
🗣️「ママね、あなたがケガするかと思ってびっくりして怒っちゃったの。
本当は守りたかったの。」
- 怒りの根っこが「愛情」だと伝わると、子どもは心が落ち着きます
③ 叱ると教えるの使い分け
| シーン | 対応の仕方 |
|---|---|
| 命の危険がある | 真剣に短く止める(例:「ストップ!」) |
| 命の危険がない | 落ち着いて説明(例:「どうしたらよかったかな?」) |
④ 禁止より代替行動を教える
- 「砂投げたい → 砂でケーキを作ろう」
- 次にどうすればよいかを示すと、行動が変わりやすくなります。
⑤ ママ自身の心も守る
- 危険行動=しつけ不足ではない
- 脳が育つペースは子どもによって違う
- 焦らず見守ることが、子どもの「安全力」を育てます。
🌱第6章:成長と見通し — 危険予測力は必ず伸びる
① 脳の発達と危険予測
- 危険を想像する力や衝動を抑える力は前頭葉が関係
- 6歳前後では未発達だが、10歳前後にかけて徐々に安定
② 経験の積み重ねが力を育てる
- 「危なかった」「ケガした」「うまく止められた」などの経験が脳に蓄積される
- 小さな成功体験の積み重ねが、成長を後押しします。
③ 家庭でできる成長サポート
- 環境調整(紐なし帽子、手をつなぐ、広場で遊ぶ)
- 成功体験の可視化(シールやカレンダー)
- 代替行動の事前練習
- 園や療育とのルール連携
④ 焦らず安心して見守る
- 「まだできない=ママの教え方が悪い」ではない
- 小さな経験の積み重ねが、危険予測力を確実に育てていきます。
💬 よくある質問と答え(FAQ)
なぜうちの子は危ないことばかりするの?
危険を予測する「見通し力」や「抑制機能」が未発達だからです。
発達特性による脳の発達ペースの違いが関係しています。「危ない」と言っても何度も同じことをします。どうしたらいい?
言葉だけで理解するのが難しいため、体験や視覚的ルール(写真・カード)を使って伝えると効果的です。
叱ってもやめないのは、しつけが足りないからですか?
いいえ。発達段階による理解や制御の難しさが原因で、しつけの問題ではありません。
危険な行動をしたとき、厳しく叱ってもいい?
命に関わる危険のときだけ、短く強く止めてOKです。
その後はフォローの声かけを忘れずに。何歳くらいで危険予測ができるようになりますか?
一般的には10歳前後から安定しますが、経験の積み重ねで個人差があります。
危険行動が多いのは発達障害のサインですか?
一因である可能性はありますが、単独では判断できません。
心配な場合は発達相談や療育機関に相談を。家庭でできる一番のサポートは何ですか?
「具体的に伝える」「代替行動を用意する」「成功体験を褒める」の3つが基本です。
叱ったあとにどんなフォローをすればいい?
「びっくりして怒っちゃったけど、本当は守りたかったの」と愛情のメッセージを伝えると安心感が生まれます。
園や療育とどう連携すればいい?
危険行動の具体例を共有し、「どんな声かけをしているか」を統一することで、学習効果が高まります。
ママ自身が疲れてしまったときは?
完璧を目指さず、「今日も命を守れた」と思うだけで十分です。
支援センターや相談機関を頼ってOKです。
💬まとめ
- 危険予測が苦手な子は、発達段階での特性によるもの
- 家庭では「具体的に伝える」「見えるルール」「代替行動」「成功体験の可視化」が効果的
- 叱るのは命を守るときだけ、あとは“教える”を意識
- 成長と経験の積み重ねで、安全力は確実に伸びる
- ママは焦らず見守ることが、子どもにとって最高の安全基地
🌈 少しずつでも、子どもは“危険を予測できる力”を身につけていきます。
ママの愛情と工夫があれば、安心して成長を見守れます。
📢 次回予告 📢
「映画『ヒックとドラゴン』|「不器用でもいい」―違いを力に変える少年の成長物語」
どうぞお楽しみに♪