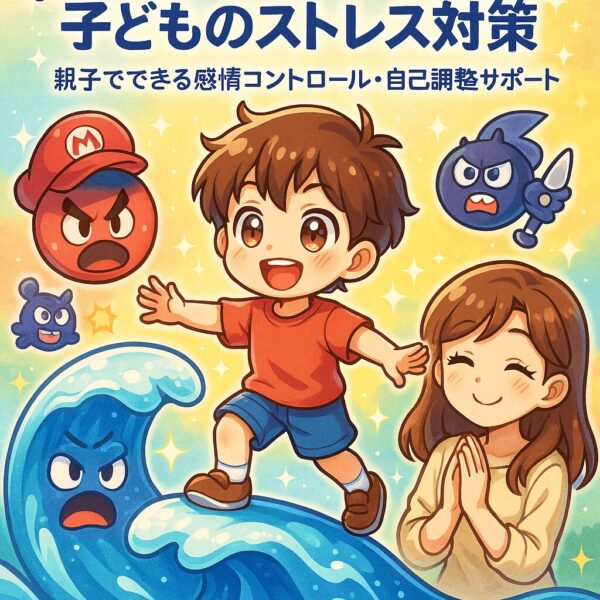はじめに子どものストレスや感情コントロールに悩んでいませんか?
子どもが日々の生活で感じるストレスや感情の波。
「すぐに怒る」「急に泣き出す」「パニックになる」…そんな場面に戸惑うこと、ありませんか?
特に発達障害や発達特性のある子どもは、音や光、予定変更などの刺激に敏感で、感情のコントロールが難しいことがあります。
親として、どう寄り添い、どうサポートすれば良いのか――これは多くの保護者が抱える共通の悩みです。
🌱私自身、4歳の発達障害の息子を育てる中で、感情調整の難しさと向き合ってきました。
些細なきっかけで大きく取り乱すことも多く、どう声をかけていいのか分からず、私も一緒に泣いた日もあります。
ですが、「感情を言葉にする練習」や「深呼吸」「気持ちカード」など、家庭でできる方法を少しずつ取り入れることで、息子に変化が見え始めました。
本記事では、以下のような方に向けて、感情調整力を育むための具体的なストレス対策方法を、私の実体験と共に紹介します。
✅「子どものストレスを軽減する方法を知りたい」
✅「発達障害の子どもへの感情コントロール支援に悩んでいる」
✅「親子でできる感情を言葉にする練習法を探している」
\家庭で今すぐ実践できるヒントが見つかります✨/
どうぞ最後までご覧ください😊
目次
- 感情調整とは?なぜ子どもに必要なのか
- 子どものストレス対策7選|家庭でできる感情調整の方法
- 深呼吸でストレスを和らげる
- マインドフルネスで集中とリラックスを
- リラクゼーション活動で気持ちを整える
- 感情の言語化をサポートする方法
- 感情日記をつけてみよう
- 体を使ったストレス解消法
- タイムアウトとリフレクション(振り返り)
- 【親の関わり方】感情の自己調整を育むためにできる4つのサポート
- モデリング(見本を示す)
- 感情調整できた瞬間を具体的に褒める
- 小さな成功体験を積み重ねる
- 柔軟なスケジュールで安心感を持たせる
- 感情の自己調整が子どもにもたらす3つのメリット
- ストレスに強くなる
- 人間関係が良くなる
- 学習や生活全体で力を発揮できる
- よくある質問
- まとめ
1. 感情調整とは?なぜ子どもに必要なのか 🧠✨
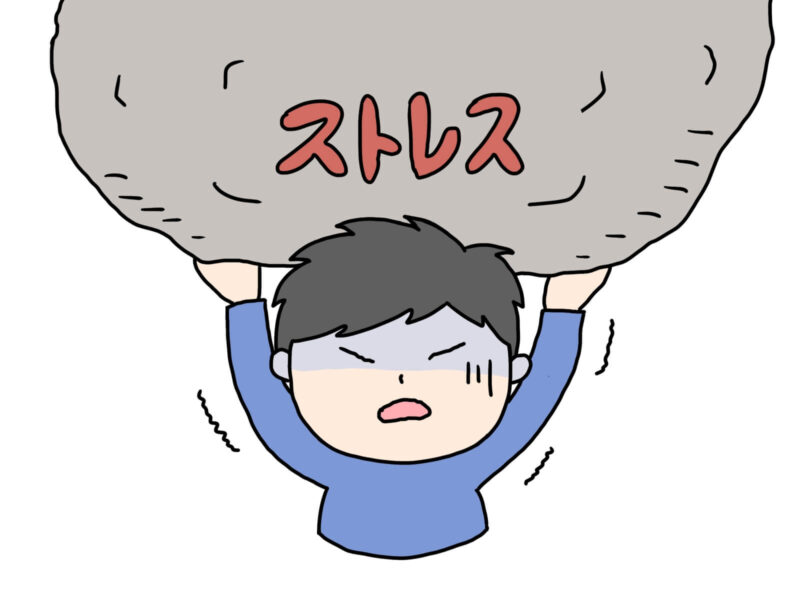
子どもが自分の感情を理解し、適切にコントロールする力——それが「感情調整」です。
この力が育つことで、怒りや悲しみといった強い感情に圧倒されず、ストレスを自分で軽減しながら行動できるようになります。
特に発達障害のある子どもは、環境の変化や刺激に敏感で、感情を言葉にするのが難しい場面もあります。
そんな時、親が少し手を差し伸べることで、子どもは安心し、自分で心を落ち着ける術を学び始めます。
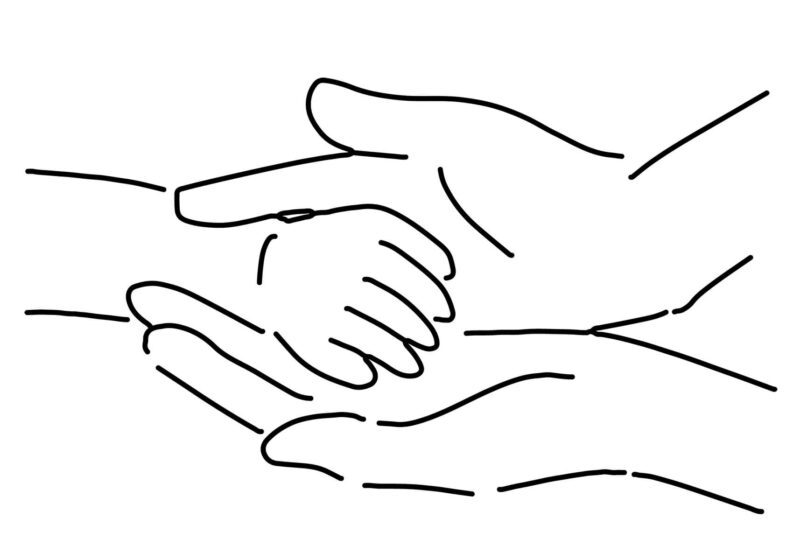
🌟わが家の実例
私の4歳の息子も、友達との距離感がつかめなかったり、衝動的な行動で、お友達とトラブルになることがしばしばありました。
けれど、日々の声かけやサポートを通して、こんなふうに言えるように:
👦「今、ちょっと怒ってるかも…」
👩🦰「そうだね。気持ちに気づけたの、すごいね!」
言葉で気持ちを表現できるようになったことで、衝動的な行動が減り、トラブルも減ってきました。
💡感情調整力は、社会性や学業の集中力にもつながる重要なスキル。
親の関わりが、子どもの未来を育てる土台になります。
2. 子どものストレス対策7選|家庭でできる感情調整の方法 😌🍀
ここでは、わが家でも実践して効果のあった方法を7つにまとめました。
まずは、基本の2つからご紹介します。
1. 深呼吸で気持ちを落ち着ける🫁
深呼吸の効果と具体的なやり方
深呼吸は、感情が高ぶった子どもを落ち着かせるシンプルで効果的な方法です。
呼吸を整えることで、自律神経が安定し、自然と心がリラックスしていきます。
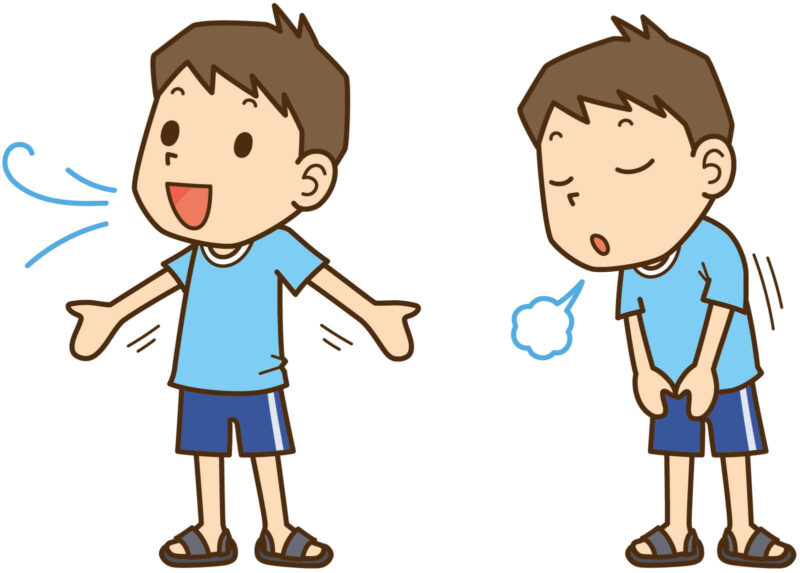
🎯おすすめのやり方:「4-4-4呼吸法」
- 4秒かけて息を吸う
- 4秒止める
- 4秒かけて吐く
これを親子で一緒に行いましょう。
👩🦰「じゃあ、一緒にお腹をふくらませて〜、1・2・3・4…」
👦「ふぅ〜、気持ちいい!」
💡 ぬいぐるみをお腹に乗せて「上下させよう!」と遊び感覚で取り組むのも効果的です。

📌【わが家の体験談】
感情が爆発すると泣き叫んでいた息子も、「ふーっ、ってやってみよう」と声をかけると、少しずつ深呼吸で気持ちを整えられるようになってきました。
2. マインドフルネスで集中とリラックスを ☁️🧘♀️
集中力向上やリラックス効果
マインドフルネスは、「今、この瞬間に意識を向ける」こと。
集中させることで、感情をコントロールしやすくなります。
静かな時間に、目を閉じて自分の呼吸や体の感覚に集中させる練習を行いましょう。
親子で一緒に取り組むことで、リラックスしながら心の落ち着きを体験することができ、集中力も高まります。

🎯おすすめのやり方
- 目を閉じて「どんな音が聞こえる?」と周りの音に意識を向ける。
- 「おててをおひざにして、5秒だけじっとしてみよう」と短時間の静かな時間を作る。
👩🦰「聞こえる?鳥の声…」
👦「うん、あと車の音も!」
📌【わが家の体験談】
食事中に落ち着きがなかった息子に「スプーンに集中してみて」と促すことで、気持ちが散らからず、最後まで座って食べられるようになってきました。
3. リラクゼーション活動で気持ちを整える🧘♀️
自然遊び・アート・読書でリラックスを習慣にしよう
子どもがストレスを感じたとき、感情を整える「リラクゼーション活動」が大きな助けになります。
特に発達障害のある子どもは刺激に敏感なため、落ち着ける時間が日常にあると安心感が生まれます。
自然の中での遊びはリラクゼーション効果が高く、ストレスを解消するのに効果的です。
自然の中でリラックスする遊び
公園や自然の中でのびのび過ごす時間は、気分をリセットするのにぴったりです。

- 川辺や森でのんびりお散歩
- 木の実や葉っぱを集める🍁
- ピクニックで空を見ながら休む
✅実体験
わが家では、ぐずりがひどかった日に、近所の公園を一緒に歩くだけで気持ちが穏やかになることが多くありました。
🎨アートで感情を表現
お絵描きや工作は、子どもが言葉にできない気持ちをアウトプットする手段です。
また、何かを「作る」ことに集中することで、気分が整いやすくなります。
- クレヨンで自由に描く🖍️
- 折り紙や紙粘土で創作
- 気持ちを色で塗ってみる
✅実体験
息子は触覚過敏があり、泥や粘土は苦手。
でも「紙に好きな色をぬってごらん」と声をかけると、気持ちが落ち着くようになりました。

📚読書で安心感を得る
親子での読み聞かせは、スキンシップと安心感を同時に得られる時間です。
お話の世界に浸ることで気持ちがリラックスし、安心感も得られます。
親が読み聞かせをするのもおすすめです。

- お気に入りの絵本を読む
- 感情の出てくるお話を選ぶ
- 読み終わった後に「この子はどんな気持ちだったかな?」と聞いてみる
4. 感情の言語化をサポートする方法🗣️
「今どんな気持ち?」と聞くことで、感情コントロール力が育つ
子どもが自分の気持ちを言葉にできる力は、ストレス対策や感情調整にとても重要です。
とくに発達障害のある子どもは、自分の感情を理解し、表現する力が育ちにくいことがあります。
例えば、「怒ってる?」や「悲しい気持ちになった?」と質問することで、子どもは自分の感情に気付き、それを表現できるようになります。
これにより、感情を抑え込まず適切に伝える力が身につきます。
🎭声かけの工夫で感情に気づかせる
- 「今、怒ってる?」「悲しい気持ちだった?」と感情の名前を添えて問いかける
- 泣いたり怒ったりしたときに、「悔しいんだね」「怖かったんだね」と気持ちを代弁する
✅ロールプレイ例
👩「今、怒ってる?」
👦「うん、だってオモチャとられた!」
👩「そうか、取られたら悔しいよね。どうしようか、一緒に考えようか」
📌【わが家の体験談】
以前、息子は怒ると泣き叫ぶだけでした。
そこで、「今、悔しいんだね」と声をかけると、「うん、くやしい」と言えるようになりました。
このように、子どもが自分の気持ちを理解し、伝えやすくなるよう手助けすることが大切です。
5. 感情日記をつけてみよう
感情を見える化することで、自分の気持ちに気付けるようになる
感情日記は、子どもが日々の気持ちを「見える化」し、自分自身と向き合うきっかけになります。
継続することで、感情のパターンに気づき、落ち着く方法を自分で見つけられるようになります。
📌続けやすい方法を選ぼう
- 顔マークシールで「今日の気分」を貼る😄😡😢
- お絵描きで「楽しかったこと」「イヤだったこと」を描く
- 短くてもOK!「○○が楽しかった」とひとこと書いてみる
✅ロールプレイ例
👩「今日はどんな気持ちだった?」
👦「うーん、にこにこ」
👩「じゃあこのシールにしようか」
👦「ぺったん!」
📌【わが家の体験談】
息子は「うれしい」「かなしい」の区別も難しかったのですが、感情シールを貼るようになってから少しずつ「今日は○○でうれしかった」と言える日が増えてきました。

6. 体を使ったストレス解消法 🏃♂️
運動でストレスをリセット!
ストレスを感じたときには、体を動かすことが効果的です。
運動をすると「ストレスホルモン(コルチゾール)」が減り、気分が前向きになりやすくなります。
特に子どもにとっては、感情をコントロールする力(自己調整力)を育てるうえで、「体を動かして発散すること」はとても重要です。
✅ 取り入れやすい方法
- シンプルな運動
縄跳び・ボール投げ・ダンスなど、おうちや公園で手軽にできる運動を。 - 親子で楽しく!
「一緒にジャンプしよう!」と声をかけると、遊びの延長で取り組みやすくなります。
📌【わが家の体験談】
息子は気持ちが高ぶると暴れてしまうことがありましたが、「ボール投げしよう!」と声をかけると、気持ちを切り替えることができました。
感情が爆発する前に運動を取り入れることで、落ち着くきっかけになっています。
7. タイムアウトとリフレクション 🧘♂️
タイムアウトは「休憩時間」🧘♂️感情を落ち着かせ、振り返る時間をつくろう!
「タイムアウト」とは、感情が高ぶったときにその場から一度離れ、落ち着くための時間のことです。
これは決して「罰」ではなく、気持ちを整える「休憩時間」であることを子どもに伝えることが大切です。

✅ タイムアウトを上手に使うには?
- 「ちょっとお休みしようね」「深呼吸してみようか」と声をかけて、静かな場所で一緒に気持ちを落ち着かせる
- タイムアウト後は、落ち着いたら、リフレクション(振り返り)の時間を設ける👇
💡リフレクションとは?
「リフレクション」とは、自分の感情や行動を振り返ることです。
なぜ怒ったのか?どうすればよかったのか?を一緒に考えることで、感情を言語化・整理する力が育っていきます。
自己理解が深まり、似た状況の時に、うまく対応する力が育ちます。

🎯 リフレクションを続けるメリット
- 自分の感情に気づけるようになる
- 同じような場面で冷静に対応できる
- 自己理解が深まり、感情のコントロール力が育つ
リフレクションを繰り返すことで、子どもは 感情をコントロールする力 を自然に身につけていきます。

✅ リフレクションの進め方
- 🟢 タイムアウトの時
「ちょっと休憩しよう」「一緒に深呼吸しようか」 - 🔵 気持ちを振り返る時
「どうしてあのとき怒っちゃったんだろう?」
「さっきのことでどんな気持ちだった?」 - 🟡 次の対応を一緒に考える
「次に同じことがあったら、どうしようか?」
「他にできる方法はあるかな?」
📌【わが家の体験談】
息子はおもちゃの貸し借りでトラブルになることが多かったのですが、タイムアウトの後に「どうしたらよかったと思う?」と一緒に話すことで、少しずつ振り返りができるようになりました。
今では「今度は順番で使う」と、自分から言えるようになってきました。
3. 【親の関わり方】感情の自己調整を育むためにできる4つのサポート
1. モデリング(親が見本を見せる)
親が日常の中で感情をうまく調整している姿を見せることは、子どもにとって最高の教材になります。
感情が高ぶったときの対処法を「実演」することで、子どもは自然とその方法を学んでいきます。
✅ 実践例
・「ママもイライラしたら、深呼吸してるよ」と声に出して行動する
・気持ちを整える方法(音楽・ストレッチなど)を子どもと共有(シェア)する
2. 感情調整できた瞬間を具体的に褒める
子どもが感情を調整できたときは、その努力をしっかりと認め、
「どう頑張ったのか」を具体的に褒めることが大切です。
✅ 声かけの例
・「今、怒らずに待てたね!かっこよかったよ」
・「ちゃんと深呼吸して落ち着こうとしたんだね、えらいね」
・「今日は泣かずにおもちゃ貸せたね!」
・「今日は『貸して』って言えたね!」
こうした声かけは、子どもが「感情をコントロールすることの大切さ」を実感するきっかけになります。
3. 小さな成功体験を積み重ねる
感情調整のスキルは、一朝一夕では身につきません。
日常の中で、小さな成功体験を積み重ねることで、自信をつけさせましょう。
日常の些細な行動を「できたね!」と認めていくことで、自信と意欲を育てていきましょう。
✅ 実践例
・「今日はちょっと待てたね!」など、些細なことでも成功を認める
・成功を絵やシールで記録し、成長を見える形にする

4. 柔軟なスケジュールで安心感を持たせる
子どもが感情的になる原因の一つに、予定の詰め込みすぎや、突然の変化があります。
安心できるスケジュールを整えることで、感情の安定につながります。
スケジュールに 「余白」 を持たせ、リラックスできる時間を確保しましょう。
✅ ポイント
・1日の中に「自由に遊ぶ時間」「ゆったり過ごす時間」を入れる
・スケジュールを絵やカードで見える化する
・予定変更がある場合は、事前に説明して不安を減らす
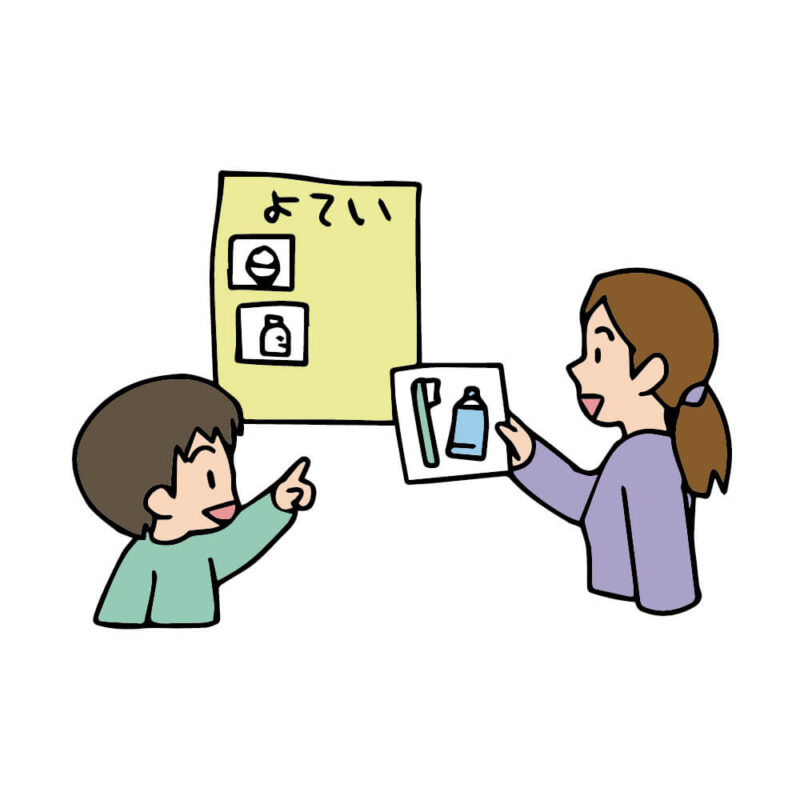
4. 感情の自己調整が子どもにもたらす3つのメリット
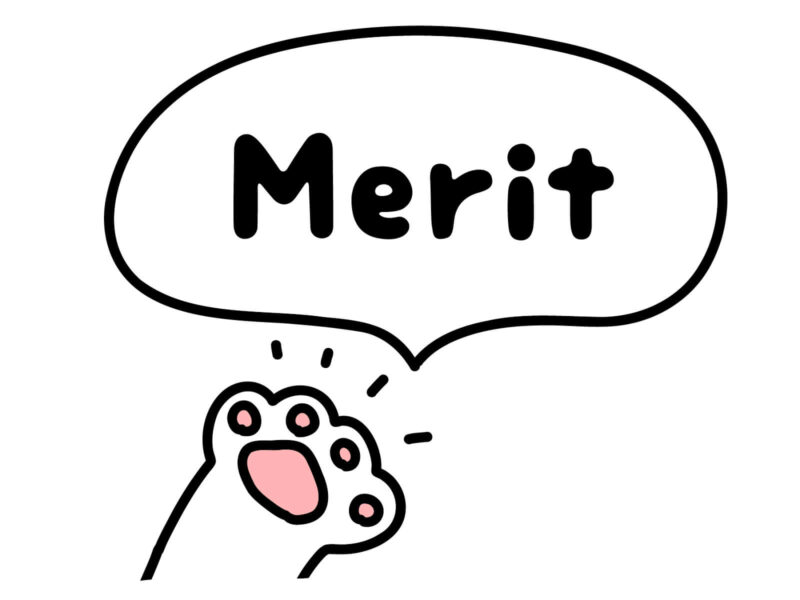
感情の自己調整力は、子どもにとって一生の財産となります。
ここでは、その力がもたらす主なメリットを紹介します。
1. ストレスに強くなる
感情を調整できる子どもは、ストレスに対してより強くなります。
感情をうまくコントロールできる子どもは、突然のトラブルや環境の変化にも柔軟に対応できます。
「どうすれば落ち着けるか」を知っていることで、困難な状況でも冷静に行動できるようになります。
2. 人間関係が良くなる
感情をコントロールできることで、友達や家族とのトラブルが少なくなります。
「言葉で気持ちを伝える力」が育ち、相手と対話を通じて上手にやり取りできるようになります。
3. 学習や生活全体で力を発揮できる
感情の安定は、集中力ややる気にも直結します。
感情をうまく調整できる子どもは、集中力が高まり、学習やスポーツなどで良い成果を出しやすくなります。
適切なストレス管理を習得することで、前向きな日々を送ることができます。
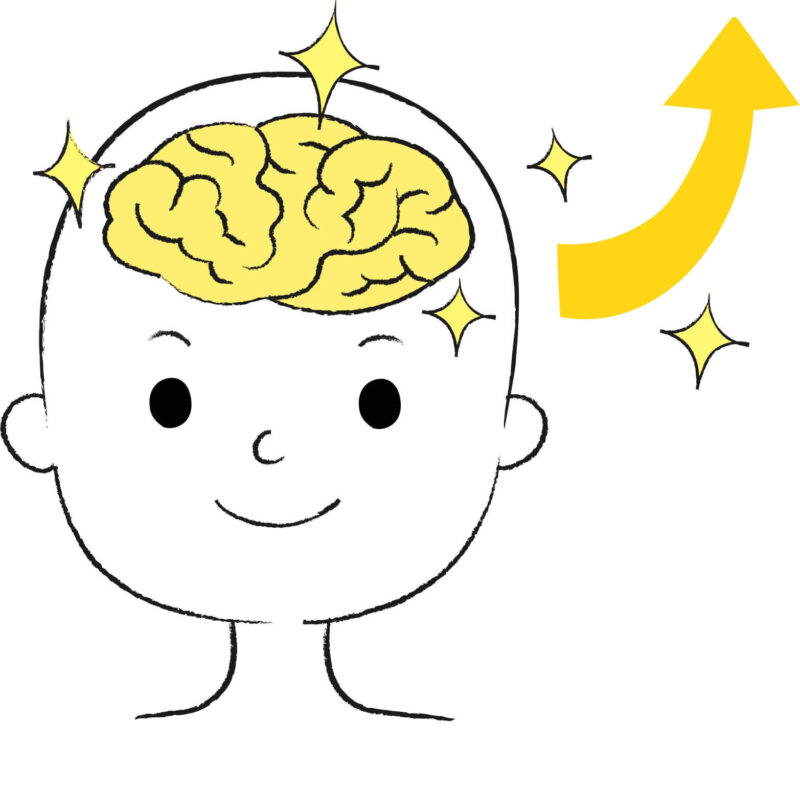
5. よくある質問
子どものストレスサインにはどんなものがある?
夜泣き、イライラ、食欲不振、かんしゃく、引っ込み思案など。
感情調整を教えるのに最適な年齢は?
2歳頃から少しずつ始めるのが理想。
子どもが怒りを爆発させたときの対処法は?
まず落ち着かせ、「どうしたの?」と感情を言葉にする手助けをする。
親が感情調整の見本を示すには?
自分がイライラしたときに「深呼吸するね」と口に出してみせる。
ストレス解消におすすめの遊びは?
外遊び、お絵描き、ぬいぐるみごっこ、ダンス、運動遊び。
感情日記は何歳から始めるとよい?
3~4歳から絵やシールで始めるのがおすすめ。
マインドフルネスは何分くらいが適切?
3~5分程度からスタートし、集中力に合わせて調整する。
感情の言語化がうまくできない子には?
絵カードや感情シールを使って「今どんな気持ち?」と聞く。
タイムアウトの適切な時間は?
1~2分が目安。年齢×1分が上限とされることが多い。
感情調整が苦手な子どもに追加でできることは?
絵本や動画を活用して「感情」の概念を学ぶ。
まとめ感情コントロールは一歩ずつ。親子で育む「こころの力」🌈
感情のコントロール力は、一夜にして身につくものではありません。
けれど、日々の小さな積み重ねが、やがて子どもの心の力として育まれていきます。

🌟例えば、
✅ 今日からできる6つのポイント
- 朝のルーティンに深呼吸を取り入れる
- 怒っているときはまず呼吸を整える声かけを
- イライラしたときは「気持ちカード」で伝える
- 感情を言葉にする練習を習慣に
- ママと一緒に「今日はどんな気持ちだった?」と振り返る
- リラクゼーション時間を意識的に取り入れる
子どもの心が落ち着くと、家庭も穏やかになります😊
まずは1つ、できることから始めてみませんか?
そんなシンプルな声かけや関わりが、子どもの「自己調整力」を伸ばすきっかけになります。
🔸 実践会話例(ロールプレイ)
👦子ども:「やだ!もうイヤだーーー!」
👩ママ:「うん、イヤだったんだね。どんな気持ちだった?悲しかった?怒ってた?」
👦子ども:「…怒ってた」
👩ママ:「怒ってたんだね。言ってくれてありがとう。じゃあ深呼吸してみようか、スーーーハーーーって😊」
🌱完璧じゃなくていいんです。
子どもも、親も、無理のないペースで感情を言葉にする練習を続けていくことが大切。
「今日はできなかった」そんな日も、自分を責めなくて大丈夫。
大切なのは、「親子で一緒に進む姿勢」です。
本記事は個人の体験に基づくものであり、全ての子どもに当てはまるものではありません。
📚 関連記事もあわせてどうぞ
🔹 発達障害の子どもの感情コントロールを育む方法
🔹 幼稚園でのストレス対策と親の関わり方
🔹 子どもの怒りと不安を和らげる5つの具体策:日常で使える23のアクティビティ付き
✨次回予告✨
「【発達障害の子向け】家庭でできる療育遊び6選|創造力・感情コントロールを育てる」
どうぞお楽しみに!😊