はじめに
太田ステージとは?ASDの発達段階をわかりやすく解説
わが子の発達に「どう関わればいいのか」迷ったことはありませんか?
自閉スペクトラム症(ASD)の子どもたちは、言葉の発達や社会的な関わり方などに個性があります。
そんな中、「今の子どもに合った支援」を考える上で参考になるのが 太田ステージです。
太田ステージは、ASDの子どもがどのような発達段階にいるのかを6つのステージで捉え、段階に応じた関わり方や支援のヒントを得られる評価法です。
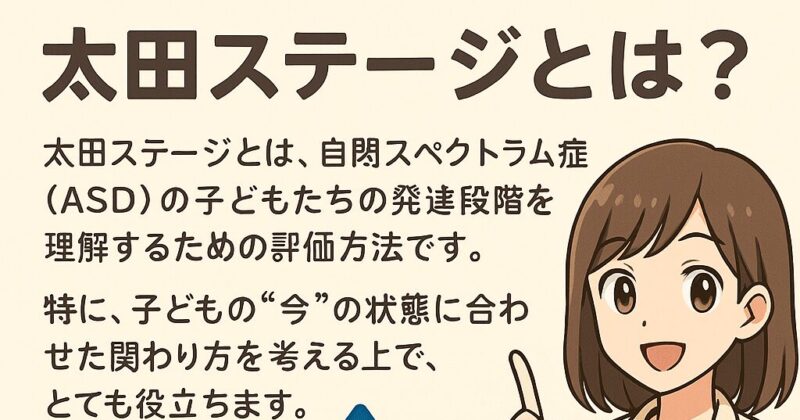
✅ この記事でわかること
- 太田ステージの6つの発達段階とその特徴
- 子どもの「今」に合わせた関わり方と支援のヒント
- 家庭で実際に取り組んでいる工夫や声かけの具体例
子どもの発達に悩む親御さんや支援者の方へ。
わが子の特性をどう理解し、どう支援していくか——。
そのヒントとして「太田ステージ」を、我が家での実践や工夫を交えて、わかりやすくお伝えします。
💡※本記事は医療的判断を目的としたものではありません。必要に応じて専門機関にご相談ください。
🧩\ここでステージ全体をパッと見れる!/
▼ 太田ステージの6段階をまとめたマトリクス図はこちら
▼図:発達段階を見える化!太田ステージ6段階のマトリクス発達段階
| ステージ | 主な特徴 | 子どもの行動の例 | 支援のヒント |
|---|---|---|---|
| ステージ1 | 覚醒の安定 | 目が合わない/刺激に反応しない | スキンシップや安心できる環境作り |
| ステージ2 | 情動共有の芽生え | 微笑む/人の顔をじっと見る | 一緒に楽しむ時間を増やす |
| ステージ3 | 感情のやり取り | 表情・声で気持ちを伝える | 模倣や共感を意識した関わり |
| ステージ4 | 意図の共有(共同注意のはじまり) | 指さし/相手の視線を追う | 興味を共有する遊びの提供 |
| ステージ5 | 意図の理解 | 要求のやりとり/簡単な言葉のやりとり | 言葉+ジェスチャーで対応する |
| ステージ6 | 社会的ルールの理解 | 順番を待つ/ごっこ遊び | ルールのある遊びを取り入れる |
目次
- 太田ステージとは?
- ASDの子どもたちに見られる特性と課題
- 太田ステージの評価方法と具体例
- 太田ステージの6つの段階
1️⃣Stage I (ステージ1) - 太田ステージの6つの段階
2️⃣Stage II (ステージ2) - 太田ステージの6つの段階
3️⃣Stage Ⅲ-1 (ステージ3-1) - 太田ステージの6つの段階
- 4️⃣Stage Ⅲ-2 (ステージ3-2)
- 太田ステージの6つの段階
5️⃣Stage Ⅳ (ステージ4) - 太田ステージの6つの段階
6️⃣Stage Ⅴ (ステージ5以上) - 太田ステージを活用した療育のメリット
- 太田ステージに基づく3つの療育目標
- 太田ステージを通じて得た気づき【ASD 子育て 成長記録】
- よくある質問
- まとめ
1. 太田ステージとは?
【ASDの発達段階を評価する方法】
太田ステージは、ASDの子どもの発達を段階的に捉え、最適な支援方法を見つけるための評価ツールです。
対象は0歳から7〜8歳が中心ですが、それ以降の子どもにも応用可能です。
6つのステージに発達段階を分類し、それぞれに合った支援プランを考えていきます。
教具や遊びを通して、子どもの意欲を引き出し、自然な学びを促すアプローチが特徴です。
2. ASDの子どもたちに見られる特性と課題
ASDの子どもには、高い記憶力や集中力を持つ子も多くいますが、一方で以下のような課題に直面することがあります。
💬 よく見られる特性と課題
- シンボル機能の困難
→ 目の前にないものを言葉や記号で表すのが難しい - 比較や空間認識の理解の難しさ
→ 大小、上下、前後などの関係性を理解するのが苦手
これらの特性が、人とのコミュニケーションや生活スキルに影響することもあります。
3. 太田ステージの評価方法と具体例
🧪 どうやって評価するの?
太田ステージでは、子どものシンボル機能の発達段階を把握するために、LDT-R(言語解読能力テスト改訂版)を用いて行われます。
太田ステージ評価は子どもにやさしい
🕒 評価時間:5〜10分ほど
🗒️内容:簡単な課題ややりとりを通して、言葉の理解力・使い方を確認
🎯 特長:遊びの中で自然に行える → 子どもへの負担が少ない
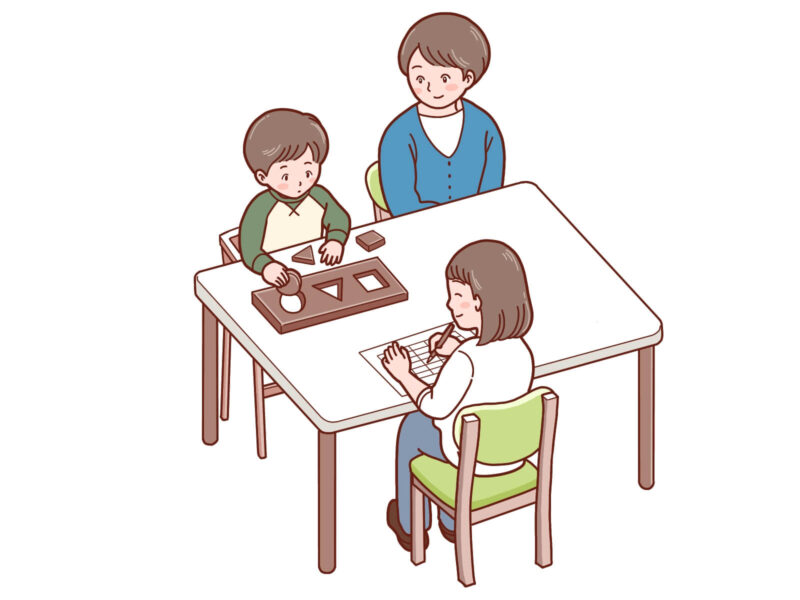
✅ 6つのステージを理解しよう(概要)
| ステージ | 特徴の例 |
|---|---|
| ステージ1 | 他者とのやりとりがほとんど見られない |
| ステージ2 | 目の前のものを使って簡単なやりとりができる |
| ステージ3 | モノに言葉や意味を持たせてやりとりができる |
| ステージ4 | 目に見えないもの(過去・未来など)も理解し始める |
| ステージ5 | 比喩や冗談、見立てが少しずつできる |
| ステージ6 | 状況や文脈に応じて言葉を柔軟に使い分けられる |
※後半のステージほど、抽象的・言語的な理解力が求められます。

次のセクションでは、それぞれのステージの詳しい特徴と支援方法の実例をご紹介します👇
4. 太田ステージの6つの段階
1️⃣Stage I (ステージ1)
モノに名前があることを理解できていない段階
(健常児では1歳半くらいまでの段階)
具体例:
- 評価内容:
「ワンワンはどれ?」と犬の絵を指さすように促しても、答えられない。 - 子どもの様子:
質問の意図が分からず、別の方向を見たり、指さしが的外れになる。 - 支援の例:
子どもが興味を持つおもちゃを使って、名前を繰り返し教える
(例:「これがワンワンだよ!」と犬のぬいぐるみを指す)。
ステージIの特徴と療育のねらい・課題
| 分類 | 状態像 | 療育のねらい | 具体的課題 |
|---|---|---|---|
| 認知・言語 | 言葉への反応が乏しく、有意味語はない | 物に名前があることを認識させる | - 絵本や写真を用い、物の名前を繰り返し教える - 指差しや身振りを添えて指示を出す (例:ドアを閉めて/~を持ってきて) |
| コミュニケーション | 指差しが少なく、クレーン現象が主な手段 | 要求を出す意欲を引き出す | - 要求があった際に指差しやサインを教える - サインを使った簡単な意思疎通を促す |
| 遊び | 感覚刺激的な遊びが多く、おもちゃの機能に沿って遊ばない | 物やおもちゃへの関心を高める | - おもちゃの特性に沿った遊び方を提案 - 感覚遊びを取り入れつつ、物の用途を理解させる |
| 対人 | 人への関心が乏しく、視線が合わない | 安定した対人関係を構築 | - スキンシップを伴う遊び (追いかけっこ、ボール遊び) - 手遊びや歌で楽しい模倣体験を提供 - 兄弟や家族との関わりを増やす |
| 異常行動 | 感覚過敏、睡眠障害、情緒不安定、物並べなどの行動が見られる | 生活のリズムをつける | - 規則正しい生活を心がけ、日々の生活の手順を繰り返す |
日常生活における適応行動の支援
| ねらい | 具体的課題 |
|---|---|
| 生活のリズムをつける | - 決まった時間に起床・就寝する - 生活の手順を一貫して繰り返す |
| 基本的な生活習慣の形成と身辺処理のスキル獲得 | - 言葉かけと介助で身辺処理を促し、徐々に自立を促す - 洋服や日用品を決まった場所に用意する |
| 初歩的な家事スキルの習得 | - 家事の手伝いに興味を持たせる (例:配膳、片付け、ゴミ捨て) |
| 親との安定した関係づくり | - スキンシップの多い遊びを通じて絆を深める (例:追いかけっこ、ボール遊び) - 手遊びや歌を一緒に楽しむ |
🌈太田ステージに基づく!我が家の発達支援エピソード
支援方法:
- 環境調整:
光や音を調整し、安心できる空間を作る。 - 予測可能な生活:
朝のスケジュールを視覚的に示す。 - 感覚遊び:
苦手な感覚を徐々に慣らすため、スライムや泥遊びを少量から試す。
【エピソード】服が汚れるのがイヤ!感覚過敏への対応
👕 課題:
服が汚れるとパニック&何度も着替え要求
🖌️ 工夫:
防水エプロン+筆を使った感覚遊びの導入
✨ 変化:
手形遊びを自ら楽しむように!
📊 図解:
| 課題 | 工夫 | 子どもの反応 |
|---|---|---|
| 服の汚れでパニック | 防水エプロン / 絵の具遊び | 少しずつ慣れて遊びを楽しめるように |
5. 太田ステージの6つの段階
2️⃣Stage II (ステージ2)
モノに名前があることを分かりかけている段階
(健常児では1歳半~2歳くらいまでの段階)
具体例:
- 評価内容:
「リンゴはどれ?」と尋ねると、リンゴの絵を指差して答えられるようになる。
たとえば、スーパーで「リンゴをカゴに入れてくれる?」とお願いしたとき、実物を探して持ってきてくれる場合もある。
ただし、「リンゴは赤い果物」という特性や用途の理解にはまだ至らない。 - 子どもの様子:
身の回りのモノ(例:犬、ボール、リンゴ)の名前は覚え始めるが、用途による区別は苦手。 - 支援の例:
絵本を使いながら、「ボールは投げるもの」「リンゴは食べるもの」といったシンプルな用途を教える。
Stage II(ステージ2)の特徴と療育のねらい・課題
| 分類 | 状態像 | 療育のねらい | 具体的課題 |
|---|---|---|---|
| 認知・言語 | 単語を使ったやりとりやオウム返しが見られる | 言葉と物の関連性を確実に理解させる | - 実物や絵本を使い、日常でよく目にする物の名前を教える - 絵カードを使って物の名前を反復して学ぶ |
| コミュニケーション | 指差しや身振り、単語など、複数の手段で要求を表現できる | 多様な表現手段を引き出し、要求を伝える力を伸ばす | - 要求時に指差しや単語を促す - 簡単なジェスチャーを繰り返し教える |
| 遊び | おもちゃを機能的に扱えるようになり、再現遊びやお気に入りの物での遊びが中心 | 遊びを通して興味の幅を広げ、学びを深める | - おもちゃの使い方を示しながら一緒に遊ぶ - 再現遊びに簡単なストーリー性を加える (例:人形にご飯を食べさせる) |
| 対人 | 特定の人とのパターン的な関係が強い | 親や家族以外の人との関わりを促し、対人スキルを育てる | - 要求時に父親や兄弟など、母親以外の人と関わるよう促す - 地域の行事に参加し、集団でのやりとりを経験させる |
| 異常行動 | 物の位置や手順に強いこだわりがあり、儀式的な行動やパニックが見られる | 柔軟性を養い、生活のリズムを安定させる | - 日課を明確にしてスムーズな切り替えを支援 - パニック時に安心できる環境を整える (例:お気に入りのアイテムを持たせる) |
言語・情緒・対人関係の支援
| ねらい | 具体的課題 |
|---|---|
| 物に名前があることの理解を深める | - 実物や絵本を使って多様な物の名前を教える - 簡単なイラストを描いて、模倣や興味を促す |
| 興味や遊びの幅を広げる | - 毎日のルーティンに絵本の読み聞かせを組み込む - 新しいおもちゃを取り入れ、楽しさを共有する |
| 言葉かけと行動を連動させる | - 簡単な指示を添えて行動を促す (例:「~持ってきて」「~を置いてきて」) - 身振りや指差しを加え、わかりやすく伝える |
| 家族や身近な人とのコミュニケーションを深める | - 家族間のやり取りを増やし、遊びや会話の場面をつくる - 母親以外の家族との役割を意識させる (例:外出時に父親と手をつなぐ) |
| 人との適切な関わり方を学ぶ | - 地域のイベントや友人家族との交流の機会を増やし、人間関係に気付かせる |
適応行動の支援
| ねらい | 具体的課題 |
|---|---|
| 生活のパターンを確立する | - 着替えや排泄、食事などの基本的な身辺処理を言葉かけで支援 - 嫌がる場合は歌やカウントダウンでリズムを作り、徐々に慣らす |
| 家事スキルを養う | - 配膳や洗濯物をたたむなど、簡単な家事を教え、成功体験を積ませる |
| 日常の自立を促す | - 日課を通じて、少しずつ自主性を引き出す (例:おもちゃを片付ける、自分で準備をする) |
🌈太田ステージに基づく!我が家の発達支援エピソード
支援方法:
- 視覚的な指示:
イラストや写真を使って状況を説明する。 - 小さな成功体験:
簡単な目標を設定し、達成したら褒める。 - 繰り返し練習:
同じ行動を何度も体験させて安心感を与える。
【エピソード】初めての場所で固まる息子に
🚫 困りごと:
「何をしたらいいのかわからない…」と動けない
👣 対応:
事前に写真や言葉で活動を説明+一緒に動いてサポート
📷 図解:
「初めての場所に行く流れ」
→ ①写真や動画でイメージ → ②行動を一緒に → ③成功体験を積む
6. 太田ステージの6つの段階
3️⃣Stage Ⅲ-1 (ステージ3-1)
モノの用途を理解できる段階
(健常児では2歳半くらいまでの段階)
具体例:
- 評価内容:
「ペンはどれ?」「ペンで何をする?」と聞くと、「これで絵を描く」と答えられるようになります。
たとえば、お絵かきの時間に「ペンを取って」と頼むと、正しい道具を選んで渡してくれます。
ただし、ペンの色や長さ、太さなどの比較をするのはまだ難しい段階です。 - 子どもの様子:
用途について質問されると、簡単な答えが出せる。 - 支援の例:
実際のモノを使った遊び(例:ペンと紙を渡して「絵を描いてみよう」と促す)で、用途を体感的に理解させる。
Stage III-1(ステージ3-1)の特徴と療育のねらい・課題
| 領域 | 特徴 |
|---|---|
| 認知・言語 | 単語や表現を覚える段階。 |
| コミュニケーション | 言葉の使用が限られており、会話としてのやりとりは成立しない。 |
| 遊び | 型通りの遊びや簡単なみたて遊びが中心。 |
| 対人 | 自分の興味を優先し、関わりは一方的でパターン的。 |
| 異常行動 | 日課や流れに強いこだわりを持つ。 興味が狭い範囲に限定され、変化があるとパニックになることがある。 |
| 前期・後期の違い | 複数の指示が理解・実行できるかどうかが目安となる。 |
言語・情緒・対人スキルの目標と課題
| ねらい | 課題 |
|---|---|
| ① 言葉の世界を豊かにする | - 身近な物の名前を正しく伝える。 |
| - 理解できる範囲で具体的な場面に合った言葉を教える。 | |
| ② 文字や数、比較概念の基礎をつくる | - トランプやひらがなカード、絵本など興味を引くツールを使いながら文字や数を学ぶ。 |
| - 日常生活で出会う物を利用して数や量、色などの基礎を教える (例: お菓子を数える、色分けする) | |
| - 絵と単語カードを対応させたり、壁に貼るなど視覚的な方法で文字や単語への理解を深める。 | |
| ③ 挨拶や簡単な2語文のやりとり | - 帰宅時や外出先で、簡単な質問をしながら会話を促進する。 |
| - 要求時には「~ちょうだい」などの2~3語文を使えるよう練習する。 | |
| ④ 行動の調整と納得を促す | - 翌日の予定や行動の流れを事前に説明し、不安を和らげる。 |
| ⑤ 対人関係を広げる | - 家族との団らんや外出を増やし、社会的な体験を積む機会を提供する。 |
| - 家族ぐるみで友達との関係を築き、地域行事に参加して社会性を広げる。 |
適応行動スキルの目標と課題
| ねらい | 課題 |
|---|---|
| ⑥ 自立的な行動を促進する | - 身の回りのことを自分でできるよう支援する (例: 着脱、食事の準備・後片付け) |
| - 食事のマナーや基本的なルールを教える。 | |
| ⑦ 初歩的な社会スキル・マナーを習得する | - 簡単な挨拶(「おはよう」「ありがとう」など)を覚える。 |
| - 家事の手伝いを取り入れる (例: 調理、配膳、食器拭き、洗濯物干し、布団の上げ下ろし) | |
| - スーパーで買い物を手伝う、また公園や公共施設で基本的なマナーを学ぶ機会を設ける。 |
具体的なアプローチ
- 視覚サポート:
絵カードやスケジュール表を使って、言葉や行動の理解を助ける。 - 日常生活を教材に:
買い物や家事を通じて、文字・数・色の認識や対人スキルを実践的に学ぶ。 - 楽しい体験を共有:
おもちゃやゲームを通じて遊びながら、言葉や社会的スキルの幅を広げる。
🌈太田ステージに基づく!我が家の発達支援エピソード
支援方法:
- 模倣遊び:
大人や友達の行動を真似する遊びを取り入れる。 - 簡単なルール:
「順番を守る」など簡単なルールを遊びの中で教える。 - 感情の言語化:
子どもの気持ちを代弁し、言葉で伝える練習をする。
【エピソード】おもちゃの取り合いトラブル
🧸 困りごと:
いきなり取ってしまう
📖 対応:
ぬいぐるみでやりとり練習+絵カードで順番を可視化
🌱 効果:
順番を守って行動できるように!
| 困りごと | 家庭での対応 | 子どもの変化 |
|---|---|---|
| 物の取り合い | 「貸して」「ありがとう」といったやりとりを、ぬいぐるみ と 絵カードで練習 | 順番を守れるように |
7. 太田ステージの6つの段階
4️⃣ Stage Ⅲ-2 (ステージ3-2)
比較(大小、長短など)ができる段階
(健常児では3~4歳くらいまでの段階)
具体例:
- 評価内容:
「どっちのボールが大きい?」「どの棒が一番長い?」といった質問に答えられるようになります。
たとえば、積み木遊びの中で「一番長い積み木を選んで」とお願いすると、正しく選べる場合もあります。
この段階では、大きさや長さの概念を徐々に理解し始めます。 - 子どもの様子:
「大きい」「小さい」の概念を理解し、簡単な比較ができるようになる。 - 支援の例:
積み木やブロックを使い、「この積み木は大きいね」「これは小さいね」と具体的に話す活動を行う。 - 特徴:
円の大小の比較ができるが、空間関係の理解が難しい段階
Stage III-2 (ステージ3-2) の特徴と療育のねらい・課題
領域 | 状態像 |
|---|---|
| 認知・言語 | 3語文以上の表現が可能。 文字どおりの解釈はできるが、文脈の理解がまだ不完全。 部分的に記憶力が優れている。 |
| コミュニケーション | 言葉を使ったやり取りが可能だが、会話の発展性が低い。 |
| 遊び | 象徴的な遊びができるが、役割を演じる「ごっこ遊び」は難しい。 |
| 対人関係 | 対人関係の希薄さは改善するが、協調性の不足が見られる。 |
| 異常行動 | 文字や数字への執着が強い。独特な質問を繰り返すことがある。 |
Stage III-2(ステージ3-2) の前期と後期
| フェーズ | 特徴 | 具体的な発展 |
|---|---|---|
| 前期 | 比較の概念に気づき始める | 意思表示が可能になる。 |
| 後期 | 頭の中で比較の理解が進む | 相対的な比較ができるようになり、選択を本人に任せられるようになる。 |
言語・情緒・対人関係
| ねらい | 具体的な課題 |
|---|---|
| ① 自分で考えて行動する力を育む | ・間接的な質問で考えさせる (例:「次に何をするの?」) |
| ・絵本や映像の内容を説明して理解を深める。 | |
| ・疑問詞(誰、何、どこなど)の理解を促進する。 | |
| ② 言葉や数の理解を日常に取り入れる | ・食事の場面で数や量を伝え、配分や順序の意識を持たせる。 |
| ③ 体験や情報を言葉で伝える力を育てる | ・学校や外出時の出来事を、質問や会話を通じて話す練習をする。 |
| ・連絡事項や質問への答えを文字で書く習慣をつける。 | |
| ④ 予定の理解と行動調整を促す | ・カレンダーやテレビ欄でスケジュール感を養う。 |
| ・行事前に具体的な説明をする。 | |
| ⑤ 子ども同士の交流を楽しめる環境作り | ・友人を家に招く、または一緒に外出する機会を増やす。 |
| ・地域の集まりや学童クラブに積極的に参加させる。 |
適応行動
| ねらい | 具体的な課題 |
|---|---|
| ⑥ 社会的な自覚と家族の一員としての役割 | ・家事を自主的に手伝う (例: 食器洗い、洗濯物干し、調理補助) |
| ・公共機関や買い物での基本的なマナーを教える。 | |
| ・家族内で感謝の気持ちを表現する場面を増やす。 | |
| ⑦ 自発性と意思決定力を養う | ・本人に選択の機会を与え、自分の意思を反映させる練習をする。 |
🌈太田ステージに基づく!我が家の発達支援エピソード
支援方法:
- 問題解決の練習:
トラブル時に解決策を一緒に考える。 - 役割分担:
家庭内で簡単な役割を与える。 - 絵本で学ぶ:
他者との違いや共感をテーマにした絵本を読む。 - 会話の練習:
給食の内容を質問する
【エピソード】お友達との距離感が近い、「一緒に遊ぼう」が言えない
👬 困りごと:
友達に近づきすぎてしまう、声かけができな
🎤 対応:
「何してるの?」「一緒に遊ぼう」と声をかける練習。
断られた時の気持ちの受け止めも支援。
気持ちに寄り添いながら、「じゃあ別の子に声かけてみようか」と励ましたり、代替の行動を一緒に考える。
🏃 効果:
療育先では積極的な姿も!
📌 図解:
「関わりのステップ表」
→ ①声の練習 → ②断られた時の支援 → ③次の行動を一緒に考える → ④徐々に成功体験
8. 太田ステージの6つの段階
5️⃣ Stage Ⅳ (ステージ4)
空間関係(上下・左右など)が理解できる段階
(健常児では7~8歳くらいまでの段階)
具体例:
- 評価内容:
「リンゴは箱の上にありますか?それとも中にありますか?」と尋ねると、正確に答えられるようになります。
たとえば、「おもちゃの車はどこにある?」と聞くと、「テーブルの下」と答えたり、実際にその場所を指し示したりします。
この段階では、空間認識や位置関係の理解が深まります。 - 子どもの様子:
自分の体や周囲のモノの位置関係を把握する力がつき、迷路遊びなどを楽しめるようになる。 - 支援の例:
絵本やパズルを使って「これはどこにある?」と上下や左右の位置関係を意識させる遊びをする。
🌈太田ステージに基づく!我が家の発達支援エピソード
支援方法:
- 自己評価の習慣:
簡単な振り返りを取り入れ、成功体験を増やす。 - 自立を促す:
自分で準備や片付けをする機会を与える。 - 地域参加:
地域のイベントや活動に参加して社会性を育む。
【エピソード】運動会のフォーメーションが覚えられない
📍 困りごと:
位置関係が覚えられず不安に
🖍️ 対応:
図やテープで“見える化”して家庭で練習
🏅 効果:
本番では自信を持って行動できた!
| 課題 | 工夫 | 効果 |
|---|---|---|
| 位置が覚えられない | 図解 / 床に印 | 理解が進み自信に |
【エピソード】できた!の達成感が自信に
✅ ポイント:
位置の“見える化”が理解のカギ
💡 工夫:
図+マスキングテープで動きを視覚的に練習
🌟 成果:
「自分でできた!」の達成感 → 自信アップ✨
📌図解:
「行動の見える化マップ」
→ スタート → 1→2→3…の順に印をつけた図で行動を整理
9. 太田ステージの6つの段階
6️⃣Stage Ⅴ (ステージ5)以上
太田ステージの枠を超えた発達段階
- 評価内容:
学校教育に必要な高度な認知スキルが求められる段階です。
たとえば、文章問題で「5本のペンのうち、3本は赤いペンです。残りは何色でしょう?」と問われたとき、文意を理解して答えを導き出せるようになります。
また、積み木や図形を使った課題では、物理的な関係性を考える力も発揮します。 - 子どもの様子:
太田ステージでは対応しきれない課題が増えてくるため、別の療育アプローチが必要となる。 - 支援の例:
学習支援や専門的なカウンセリングを取り入れ、個々の課題に応じた指導を行う。
我が家の今後の支援方法
支援方法:
- 継続的な挑戦:
新しい環境や活動にチャレンジさせる。 - 他者支援の体験:
年下の子を手伝うなど、役割モデルを与える。 - 多様な経験:
様々な人との交流や活動を通じて成長を促す。
10. 太田ステージを活用した療育のメリットとは?
【ASD 療育 実例あり】✨
太田ステージとは、発達障害(特にASD)のお子さんの“今”の発達段階を把握し、その子に合った支援方法を見つけるための評価法です。
家庭でも活用できるこの評価法には、次のようなメリットがあります👇
✅太田ステージを活用する5つのメリット
- 発達段階が明確にわかる
➡ シンボル機能や認知の発達段階を把握しやすくなります。 - 子どもの行動の意味を理解しやすくなる
➡ 理由がわからず戸惑っていた行動も、「なるほど」と納得できることが増えます。 - 支援方法の方向性が見えてくる
➡ どんな声かけ・遊び・課題が適しているかのヒントになります。 - 療育の効果を“見える化”できる
➡ ステージごとの成長変化を確認しながら支援の見直しができます。 - 短時間&低負担で評価が可能
➡ お子さんも保護者も無理なく取り組めるシンプルな方法です。

📌 注意点:この記事は、筆者の家庭での実践をもとにまとめたものです。
医学的なアドバイスではありません。必要に応じて専門家や医療機関にご相談ください。
11. 太田ステージに基づく3つの療育目標
【認知発達治療の視点】🎯
太田ステージを使った支援では、「認知」「生活」「行動」それぞれにアプローチする3次元の発達目標を重視します。
🔵 第1次元:認知・情緒の発達
- 目標:
感情や行動を自分でコントロールできる力を育てる - アプローチ:
楽しい体験や成功体験を通して、「やってみたい!」という気持ちを引き出します - 例:
ステージに合った遊びや課題を少しずつ提供することで、意欲や集中力がアップ!
🟢 第2次元:生活技能の向上
- 目標:
自立した生活に必要なスキル(身支度、片付け、食事など)を習得 - アプローチ:
お子さんの強みを活かしつつ、家庭や園でのさまざまなシーンに適応できるようサポート
🔴 第3次元:問題行動の改善
- 目標:
かんしゃく、こだわり、他児とのトラブルなどの頻度を減らす - アプローチ:
子どもと一緒にチャレンジ内容を考え、「できた!」を積み重ねていく - 支援のコツ:
断られた時の気持ちを受け止めたり、代替行動を一緒に探すことがカギ🔑
12. 太田ステージを通じて得た気づき【ASD 子育て 成長記録】🌱
太田ステージは、発達段階を可視化しながら、その子に合った支援を考える上でとても役立つ理論です。
私たち家族もこのステージを参考に、息子の特性に寄り添いながら、日々試行錯誤してきました。
その中で実感したのは——
🌟 どんなに小さなことでも「できた!」という体験が、子どもを確実に前へと進ませてくれるということ。
発達に特性のあるお子さんの歩みは、たしかにゆっくりかもしれません。
でも、その一歩一歩には確かな意味と成長があり、親としても「焦らなくて大丈夫」と思えるようになりました🍀
太田ステージは、親にとっても子どもとの向き合い方の「道しるべ」になります。
「今、ここにいるんだね」「次はこうしてみようか」と、共に歩む感覚を持てるのです。
これからも息子のペースを大切にしながら、
🌈 支援の方法を柔軟に見直し、親子で成長を喜び合える時間を増やしていきたいと思います。
11. よくある質問
療育を始めるタイミングってどう決めればいいの?
子どもの成長や日常生活での困りごとが増えたタイミングがきっかけになることが多いです。
我が家の場合は、3歳児検診や幼稚園で指摘されたことをきっかけに検討しました。
一人で悩まず、専門家や自治体の相談窓口を活用してみてください。療育ってどんなことをするの?
個別での発達支援や集団活動を通して、子どもの特性に応じたスキルを伸ばします。
例えば、遊びながら社会性やコミュニケーション能力を育む活動があります。
専門家から家庭での工夫を教わる機会もあります。親として何を準備すればいいの?
子どもの特性や日常の様子を記録しておくと、療育の場で役立ちます。
また、親自身も子どもの特性を理解するための知識を学ぶことが大切です。療育に通うと子どもはすぐに変わるの?
劇的な変化は期待せず、子どものペースで少しずつ成長していくのを見守ることが大切です。
私自身も、子どもだけでなく、自分の心構えが変わるのを実感しました。旦那や家族が療育に反対しています。どう説得すればいいですか?
具体的な例や専門家の意見を共有し、子どものためになることを話し合うのが効果的です。
我が家では、時間をかけて必要性を説明し、少しずつ理解を深めてもらいました。幼稚園に療育のことを伝えるべき?
子どものサポートを共有するために、最終的には信頼できる先生には伝えることをおすすめします。
我が家でも、先生との連携で息子の生活がスムーズになりました。子どもが集団行動を嫌がる場合、どう対応したらいい?
無理強いせず、少人数の場や個別での練習から始めるのが良いです。
専門家のアドバイスを受けて、子どもに合った方法を試してみてください。発達検査を受けるべきタイミングは?
日常生活や幼稚園で困りごとが増えた際に検討すると良いです。
検査結果は子どもの特性を理解し、適切な支援を受けるためのヒントになります。子どもが触覚過敏で着替えや遊びを嫌がります。どうすればいい?
子どもが快適に過ごせる素材や工夫を取り入れるのがおすすめです。
我が家では縫い目の少ない服や特定の素材を選ぶことで、息子が安心して過ごせるようになりました。親として孤立を感じるとき、どう乗り越えたらいい?
同じ経験を持つ親のコミュニティや療育センターの親向け勉強会に参加するのがおすすめです。
共感し合える仲間とつながることで、気持ちが軽くなります。太田ステージとは何ですか?
太田ステージは、自閉スペクトラム症(ASD)など発達障害の特性を段階的に評価するための方法です。
具体的には、社会性やコミュニケーション能力などの発達の進行状況を測定し、それに基づいて適切な支援策を検討します。太田ステージを利用するメリットは?
子どもの特性をより正確に理解できるため、療育や教育の方向性を明確にする手助けとなります。
また、進捗を可視化できるため、親や支援者にとっても安心材料となります。誰が利用できますか?
主に医療機関や療育センターで専門家が実施します。
保護者が直接活用するものではありませんが、評価結果を元に家庭でも役立つアドバイスが得られます。
🌟まとめ
太田ステージで「わが子の今」が見えてくる
太田ステージは、子どもの「今の発達段階」を把握し、それに合わせた支援を行うための有効な評価法です。
特性の強さではなく、「どこでつまずいているか」「どんな関わりが効果的か」を見極める視点を持つことで、
無理のないサポートが可能になります。
わが家でも、太田ステージを知ってから、「言葉が出ない理由」「集団が苦手な背景」が少しずつ理解できるようになり、
家庭での関わり方を見直すきっかけとなりました。
💡家庭でのちょっとした工夫の例
- イラスト付きのスケジュールで安心感をアップ
- 「できたね」「次はこれだよ」といった短くてシンプルな声かけ
- 苦手な場面では無理にやらせず、「待つこと」「環境を整えること」に注力
こうした取り組みが、子どもの安心感につながり、少しずつ行動にも変化が出てきています😊
「発達に不安があるけれど、何から始めればいいのかわからない」
そんな方にとって、この記事が最初の一歩になることを願っています。
次回予告
次回は、「子どもの不器用さが気になる?発達性協調運動症(DCD)の基礎知識」をご紹介します📚🎵
お楽しみに!
🔗 他の記事もチェック
- [【初心者向け】ASDの療育方法まとめ|ABA・TEACCH・感覚統合の選び方を解説]
- [療育って何から始めればいい?家庭でできること5選]
- [療育は必要?療育開始までの葛藤と乗り越え方:リアルな体験談]
ご意見・ご感想などありましたら、お気軽にコメント欄へどうぞ♪
この記事が少しでもお役に立ったら、ぜひシェアしていただけると嬉しいです✨






