はじめに
「小1の壁」――これは、働くママ・パパたちがよく耳にする言葉ですよね。

保育園や保育園での生活に慣れた年長さんが、4月からいよいよ小学生に。
楽しみな反面、
💭「学校ってどんな感じ?」
💭「仕事との両立はできるかな…」
と、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
私自身もまだ入学前の段階ですが、
先輩ママたちの体験談やアンケート結果を調べる中で、
「小1の壁」には事前に知っておくと安心できるポイントがたくさんあることが分かりました。
この記事では、
✅ 小学校生活を具体的にイメージできる
✅ 「自分だけじゃない」と安心できる
✅ 不安が少しずつ解消され、小学生ママライフが楽しみになる
ような内容をお届けします🌸
目次
- 小1の壁とは?
小1の壁の原因とよくある変化 - アンケートで分かる「小1の壁」のリアル
- 学童保育も「壁」のひとつ?
学童でのトラブルと対応
民間学童と公営学童の違い - 放課後等デイサービスという選択肢
- 子どもの安全を守る「魔の7歳」とは?
- 小1の壁を乗り越える7つのポイント
- 今からできる入学準備アクション
- よくある質問と答え(Q&A)
- まとめ|「小1の壁」を知ることが安心への第一歩
1. 小1の壁とは?
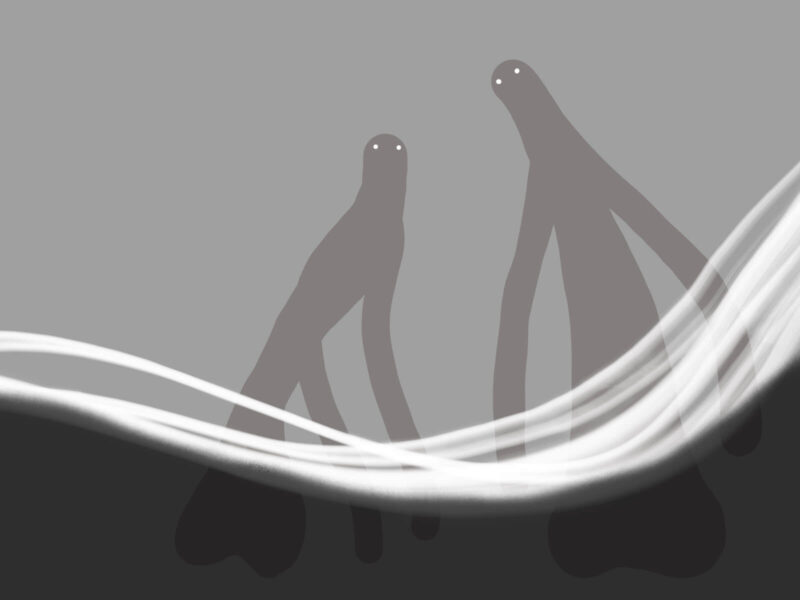
「小1の壁」とは、子どもが小学校に入学したタイミングで、
家庭や仕事の生活リズムが大きく変化し、
親が負担やストレスを感じやすくなることを指します。
よくある変化ポイント
- 学校の終わりが早く、保育園より預かり時間が短い
- 学童保育の定員・時間に制限がある
- 宿題や持ち物チェックなど、親のサポートが増える
- 長期休み(夏休み・冬休み)の過ごし方に悩む
つまり、子どもの生活環境の変化に、親の働き方やサポート体制が追いつかないことが「小1の壁」の正体なんです。

2. アンケートで分かる「小1の壁」のリアル
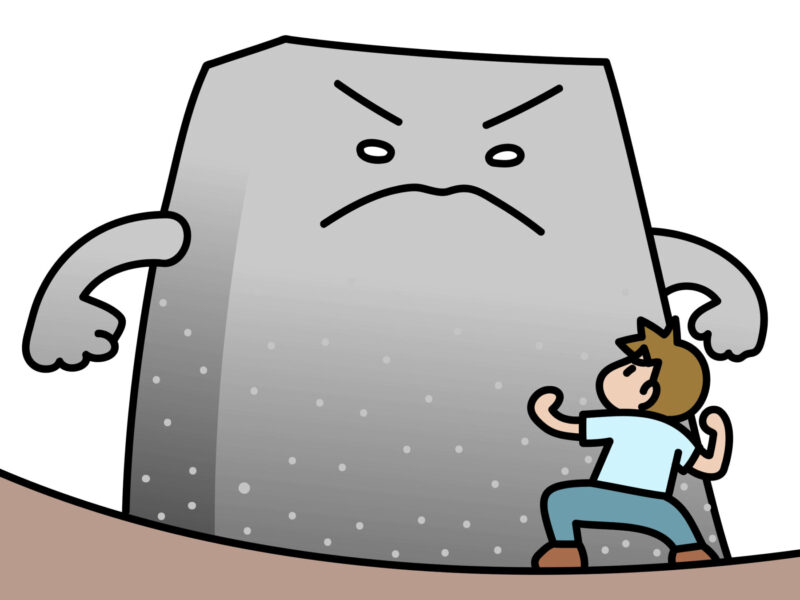
「小1の壁」について調べてみると、実際に小学生ママたちのアンケート結果から、
入学後のリアルな変化が見えてきました。
多くのママが感じているのは、「年長の頃より大変になった」という声。
実際の調査では、
- 68.5% が「年長の頃より大変になった」
- 15.8% が「同じくらい大変」
- 15.7% が「年長より楽になった」
という結果でした。
とくに負担に感じるポイントとして挙がっていたのが、親のサポートが増えること。
例えば、
✅ 間違えた問題を直すのも一苦労
✅ 時間割に合わせて教科書や持ち物をそろえる
✅ 学童の送迎や持ち物確認
など、毎日の小さなタスクが積み重なることで、思った以上に手がかかるようです。
3. 学童保育も「壁」の一つ?
働くママにとって欠かせないのが「学童保育」。
でも、ここにも小さなハードルが。
アンケート結果
- 4月1日からフル利用した:67.2%
- 最初の1〜2日は短縮:18.7%
- しばらく短縮して慣らした:14.1%
最初からフルで通う子も多い一方、
新しい環境や上級生に圧倒されて、最初は泣いてしまう子も。
「学童あるある」として、上級生との関わりに戸惑う声も多く聞かれます。
学童での「トラブル」経験も少なくない
調べてみると、「学童でのトラブルを経験したことがある」という声も少なくありません。
アンケート結果では、
- トラブル経験あり:44.9%
- 経験なし:55.1%
約半数の家庭が何らかのトラブルを経験しており、
たとえば「上級生との関わり」「持ち物の貸し借り」「遊び方の違い」など、
子ども同士の人間関係が壁になることもあるようです。
ただ、こうした経験を通して、社会性や自己表現の練習の場にもなっていくとの声も多く、
「最初は不安でも、少しずつ慣れていく」という意見が目立ちました。
民間学童を利用する家庭も増加中
最近では、民間学童サービスを利用する家庭も増えています。
公営の学童に比べて、
✅ 英語・プログラミング・アートなどコンテンツが充実している
✅ 少人数制で、個別のサポートが受けられる
といったメリットが魅力です。
一方で、やはり気になるのが料金面。
公営に比べると月額が高くなる傾向があり、
「料金の高さ」が最大のデメリットとして挙げられています。
そのため、
🧩 公営学童をベースにしつつ、週に数回だけ民間学童を利用する
🧩 長期休みや特定の曜日だけ併用する
など、学童+民間サービスの組み合わせを選ぶ家庭も増えています。
卒業のタイミングは小3の終わりが最多。
家庭のライフスタイルに合わせて、柔軟な選択が大切です。
4. 放課後等デイサービスという選択肢
「小1の壁」を感じやすいご家庭の中には、
放課後等デイサービス(放デイ)を利用する方もいます。
これは、発達に特性があるお子さんやサポートが必要なお子さんを対象に、
放課後や長期休みの時間に療育や学習支援、ソーシャルスキルトレーニングなどを行う福祉サービスです。
例えば、
- 宿題のサポート
- 生活スキルの練習
- 遊びや活動を通じたコミュニケーション力アップ
など、家庭や学校だけでは補いにくい部分を支援してくれます。
利用には市区町村への申請と受給者証の発行が必要ですが、
費用は所得に応じて上限があり、1日数百円程度で利用できるケースもあります。
💡もし「学童が合わない」「支援が必要そう」と感じたら、早めに地域の相談支援センターや自治体に相談してみましょう。
💡まとめ
調べてみると、「小1の壁」は単に「忙しくなる」というだけでなく、
環境の変化・人間関係・選択肢の多さなど、
さまざまな要素が関係していることが分かりました。
でも、あらかじめ情報を知っておくことで、
「どんな壁があるのか」「自分の家庭にはどんな形が合うのか」
をイメージでき、入学前から心の準備を整えられそうです🌸
5. 子どもの安全を守る「魔の7歳」とは?
「魔の7歳」とは、心理学や教育学でよく言われる、
子どもが自己主張や自立心を強め、親の指示やルールに反発することが増える時期を指します。
この時期は、好奇心や挑戦心が旺盛になる一方で、危険への認識がまだ十分ではないため、
思わぬ事故や怪我が起こりやすくなります。

魔の7歳の特徴
- 自分でやりたい気持ちが強くなる
→ 高いところに登る、走り回るなど、危険行動が増える。 - ルールより好奇心を優先
→ 道路や交通ルールを軽視しがち。 - 感情のコントロールが未熟
→ 怒ったり泣いたりする行動が急に出ることがある。 - 友達関係のトラブルが増える
→ ケンカや喧嘩、押したり叩いたりすることも。
保護者ができる安全対策
- 危険箇所の明確化と環境整備
- 家の中では階段やキッチンにゲートを設置。
- 公園では高すぎる遊具には注意。手すりや安全マットを活用。
- ルールの具体化と視覚化
- 「道路では手をつなぐ」「高いところに登るときは声をかける」など、ルールを絵や文字で示す。
- 安全行動を褒めることで学習を強化。
- 危険回避の体験を通して学ぶ
- 自転車や道路横断の練習など、体験を通じて危険を理解させる。
- 「どうしたら安全か」を一緒に考える機会を作る。
- 感情や行動の切り替えサポート
- 怒りや不安が出たときの落ち着き方を一緒に練習。
- 「深呼吸」「安全な場所で休む」など具体的な方法を提示。
💡 まとめ
「魔の7歳」は、子どもの好奇心と自立心が高まる素晴らしい成長期である一方、
危険に気づきにくい時期でもあります。
家庭や学校での安全対策と、体験を通した学びを組み合わせることで、安心して成長を見守ることができます。
6.「小1の壁」を乗り越える7つのポイント

① 小学校は楽しいところ!と伝える
子どもが安心して通えるように、
「楽しい絵本」や「入学準備のごっこ遊び」で前向きなイメージを。
② 保育園との違いを理解しておく
担任の先生が1人、給食時間・掃除・移動などすべて自分たちで行うなど、
自主性が求められるのが小学校生活です。
③ 「友達できた?」は聞かない
答えにくいことも。
代わりに「今日の給食、何だった?」など答えやすい質問をしましょう。
④ 家ではゆっくり休ませてあげよう
見た目は元気でも、学校では緊張の連続。
「毎日通えているだけで100点!」と、頑張りを認めてあげることが大切。
⑤ 先生の悪口は言わない
親の発言は、子どもの信頼関係に直結します。
気になることは、担任の先生に直接相談を。
⑥ 子どもの話を鵜呑みにしない
子どもの目線と大人の目線は違います。
話をしっかり共感しながら、全体像を確認する姿勢を持ちましょう。
⑦ 毎日の会話を大切にする
短い時間でもOK。「お風呂タイム」「寝る前」など、
リラックスした時間に本音が聞けることも。
7. 今からできる準備アクション
- 朝の支度・帰宅後の流れをシミュレーション
- 学童・民間サービスの情報収集
- 通学路の練習・交通ルールの確認
- 入学前に「できること」を少しずつ練習(ランドセル開け閉め、プリント提出など)
8. よくある質問と答え(Q&A)
「小1の壁」っていつから始まりますか?
多くは入学直後の4月〜5月に始まり、生活リズムが変化するタイミングで感じやすいです。
働くママが特に大変と感じるのはどんなこと?
学校が早く終わることによる送迎・宿題サポート・持ち物準備・行事対応などです。
小学校と保育園の違いは?
自主性が求められ、時間割や持ち物の管理、宿題、集団行動などが増えます。
学童に入れない場合はどうすればいい?
民間学童や放課後等デイサービスの利用、祖父母サポートなどを検討しましょう。
放課後等デイサービスとは?
発達に特性があるお子さんを対象に、放課後の支援や療育を行う福祉サービスです。
民間学童は高いけど利用価値はありますか?
英語・プログラミングなど多様な体験が可能で、送迎付きの安心感もあります。
宿題のサポートが大変です。どうしたら?
最初は一緒に習慣をつけ、できたら褒める。学童で宿題タイムがあるところもおすすめです。
子どもの友達トラブルが不安です。
まずは子どもの話を共感的に聞き、必要に応じて先生に相談を。
行事や役員仕事が多いときはどう乗り越える?
有給の計画取得、家族内の分担、ママ友との情報共有が助けになります。
小1の壁を少しでも軽くするために今できることは?
朝の支度・通学路練習・学童見学・生活リズムを小学校モードに整えておくことです。
まとめ|「小1の壁」を知ることが安心への第一歩
小1の壁は、誰にでも訪れる自然な変化です。
「自分だけじゃない」と知ることで、気持ちがずっと軽くなります。
焦らず、完璧を目指さず、
「今できること」をひとつずつ積み重ねていくことが、何よりの準備。
子どもも親も、新しい一歩を笑顔で踏み出せますように🌸
📢次回予告
お楽しみに!






