はじめに
お絵描きは、子どもの発達を支える大切な遊びのひとつです🎨✨
色や形を自由に描くことで、手先の器用さ・集中力・感覚統合など、さまざまな力が自然に育まれていきます。
でも…
🖍️「クレヨンのベタつきが苦手」
📄「紙の感触が気持ち悪い」
そんな触覚過敏や不器用さがある子どもにとっては、お絵描きがストレスになってしまうことも💦
この記事では、
✅ お絵描きが子どもの発達に与える具体的な効果
✅ 感覚過敏や不器用な子どもでも楽しめる工夫
✅ 発達をサポートする親の関わり方
✅ 子どもに優しいおすすめ画材の選び方
などを、実体験を交えながらわかりやすく解説します💡
「うちの子、お絵描きが苦手かも…」
そんなふうに感じたことがある方にも、今日から試せるヒントが見つかるはずです😊
ぜひ最後まで読んで、お子さんとのお絵描き時間をもっと楽しく、成長につながる時間にしてみてください!

目次
- お絵描きと発達の関係|子どもの成長にどう役立つ?
🧠 お絵描きが育む3つの発達スキル
└ 1️⃣ 手と目の協調性
└ 2️⃣ 集中力の向上
└ 3️⃣ 感覚統合の促進
📝ママの実体験|触覚過敏の息子とお絵描きの距離が近づいた - 年齢別に見る|お絵描きの発達段階と見守りのポイント🖍️
▶ 1歳半頃|初めて「線」を引き始める時期
▶ 2歳頃|「丸」を描けるようになる
▶ 3歳半頃|「顔らしき絵」を描きはじめる
▶ 4歳頃|「人物像」を描き始める
💡 発達には個人差があるから、焦らなくて大丈夫! - お絵描きを通じて子どもの発達をサポートする方法
お絵描きがもたらす4つの発達効果
└ 1️⃣ 手先の器用さを育てる
└ 2️⃣ 色彩感覚と視覚認識の向上
└ 3️⃣ 想像力と自己表現力の発達
└ 4️⃣ 集中力・忍耐力を育てる
親のサポートのコツ - 触覚過敏がある子どもへの対応とおすすめ画材
触覚過敏に配慮したおすすめの画材とツール
└ クレヨン
└ 色鉛筆
└ タッチペン(デジタル画材)
画材選びの注意ポイント
環境の工夫で安心感UP! - 子どもの発達を支える親の観察力と環境づくり
お絵描きを通じて見える発達のサイン
発達を促すお絵描き環境づくりのヒント - よくある質問(Q&A)
- まとめ
1. お絵描きと発達の関係|子どもの成長にどう役立つ?
お絵描きは、子どもの発達を自然に引き出す「成長スイッチ」ともいえる大切な遊びです🎨
自由に色や形を表現する中で、創造力・手先の器用さ・集中力・感覚統合など、さまざまな力が育まれます。
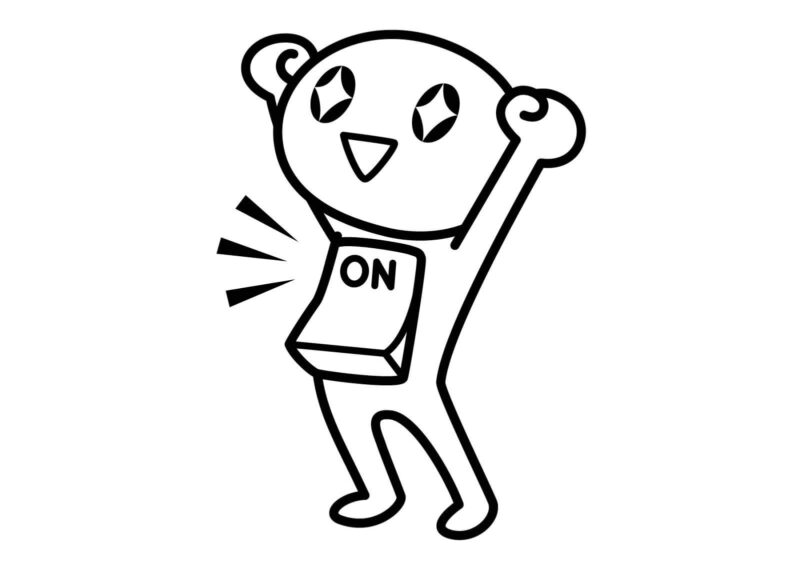
🧠 お絵描きが育む3つの発達スキル
✅ 手と目の協調性
→ 線や形を描くことで「手元をじっと見る力」が育ち、書く・切るなどの動作の基礎に!
✅ 集中力の向上
→ 好きな色や形を選び、描き込む工程が自然と集中力を鍛えてくれます🎯
✅ 感覚統合の促進
→ 手を使って描くことで、触覚や視覚の情報が脳で整理・統合されるようになります🧠✨
📝ママの実体験|触覚過敏の息子とお絵描きの距離が近づいた
私の息子は、2~3歳の頃は触覚過敏の影響でクレヨンのべたつきを嫌がり、お絵描きを楽しめませんでした💦
でも、以下のような工夫で、少しずつ「描くこと」へのハードルが下がっていきました。
🔸 タッチペンや手につきにくいクレヨンを試す
🔸 グリップ付きの鉛筆や滑らかなクレヨンを使用
🔸 ザラザラ感が苦手なため、ツルツルした紙に変更
さらに、指先のトレーニング(シール貼り・ひも通しなど)を毎日の遊びに取り入れたことで、
苦手だった「丸描き」もスムーズに描けるように🎯
以前は殴り書きだった塗り絵も、今では枠内に丁寧に塗るようになり、息子の成長を感じる場面が増えました✨
そして驚いたのは、お絵描きで育った集中力が、積み木・ハサミ・折り紙など他の活動にも広がっていったこと!
「お絵描きが苦手なんじゃなくて、合う道具や環境がなかっただけだったんだ」
そう気づいたことで、お絵描きは「苦手を克服するきっかけ」になり、
息子にとっても私にとっても前向きで楽しい時間になりました😊
2. 年齢別に見る|お絵描きの発達段階と見守りのポイント🖍️
お絵描きの力は、年齢ごとに大きく成長していきます。
「どのような絵を描くのか?」「どんな動作をしているか?」は、発達のサインを知るヒントになります。
ここでは、1歳〜4歳頃までのお絵描きの発達段階と、それぞれの時期に注意したい観察ポイントを紹介します👀✨
▶ 1歳半頃|初めて「線」を引き始める時期
🖌 特徴:
ギザギザとした線を描くようになり、ペンやクレヨンを持つことに興味を持ちはじめます。
🔍 観察ポイント:
- 👀 手元をじっと見ながら描いている?
→ 手と目の協調が育ち始めているサイン! - 😯 手元を見ずにただ動かしている?
→ 視覚・触覚の発達がまだ未熟な可能性も。
▶ 2歳頃|「丸」を描けるようになる
🖍 特徴:
円や楕円など、曲線を描く動きが見られるようになります。
形の認識が発達してきた証です。
🔍 観察ポイント:
- ✅ なめらかな丸が描けるか?
→ 記憶力・手先のコントロール力が育っているサイン! - ❌ 線がガタガタのまま?ギザギザのまま?
→ 発達のペースは個人差があります。
もし気になることがあれば保健師や専門家に相談すると安心です。
▶ 3歳半頃|「顔らしき絵」を描きはじめる
🎨 特徴:
顔や目・口などのパーツを描こうとする姿が見られ、色使いや構図にも個性が出てきます。
🔍 観察ポイント:
- 🔁 いつも同じ絵ばかり描いている?
→ 想像力を広げるサポート(テーマの提案など)をしてみて。 - ✋ クレヨンの感触を嫌がる?
→ 触覚過敏の可能性も。画材選びを工夫して。子どもに合った画材を選びましょう!
▶ 4歳頃|「人物像」を描き始める
🖼 特徴:
頭から直接手足が出ている絵を描き始め、人間の体への認識が育ちます。
人の体を「頭・手・足」などに分けて描きはじめ、全体のバランスを意識し始めます。
🔍 観察ポイント:
- 🚸 人物の絵をまったく描かない?
→ 自己認識や他者理解の発達に関係するケースも。
遊びの中でイメージを広げてあげましょう。

💡 発達には個人差があるから、焦らなくて大丈夫!
「うちの子、発達が遅れてるかも…」と感じることがあっても、子どもによってペースはそれぞれです。
大切なのは、子どもに合った環境・画材・声かけで、無理なく楽しめるようにすること。
私自身、息子の絵や色塗りの様子に不安を感じた時期がありましたが、
「他の子と比べず、その子の変化や小さな成長を大切にすること」の大切さを実感しています😊
お絵描きは、発達のサインがたくさん詰まった成長の時間。
ぜひ、お子さんのペースに合わせて見守ってあげてくださいね✨
🔗 関連ページ:
- 指先トレーニング9選|3歳から始める家庭での遊びで脳を育てる
- 【体験談あり】発達障害の兆候とは?3歳前に気づくサインと早期支援の大切さ
- 感覚統合とは?発達が変わる家庭でできる遊び&支援法
- 【感覚過敏の子ども向け】家庭でできる環境づくりとおすすめ支援グッズ
3. お絵描きを通じて子どもの発達をサポートする方法🎨
お絵描きは、子どもの発達を促すとても効果的な遊びです。
楽しめる環境を整え、自由に表現する時間を持つことで、子どもは自然とさまざまなスキルを身につけていきます。
ここでは、お絵描きがもたらす発達への効果と、親としてできる具体的なサポート方法をご紹介します🧒✨

🎯 お絵描きがもたらす4つの発達効果
1️⃣ 手先の器用さを育てる✋
線や形を描く動作は、指先の細かい動きや筆圧の調整力を育てます。
クレヨンで色を塗ったり、鉛筆で線を引くことが、手の発達に直結します。
2️⃣ 色彩感覚と視覚認識の向上🌈
いろいろな色を使うこと(組み合わせること)で、色彩センスや形の認識力が育まれます。
「何色にしよう?」と考える時間も、立派な学びの時間です✨
最初は簡単な色塗りや形の描写から始めて、徐々に色を組み合わせたり、複雑な絵に挑戦することが大切です。
3️⃣ 想像力と自己表現力の発達🧠
絵を描くことで「気持ち」「考え」「見たもの」をアウトプットでき、想像力と自己表現力、問題解決能力が育ちます。
「今日は〇〇を描こう」と自分で決める経験も、思考力や自信につながります。
4️⃣ 集中力・忍耐力を育てる💡
一つの作品を仕上げる過程では、じっくり取り組む集中力や粘り強さが必要です。
「最後までやりきる力」も自然と養われます。
また、色を塗る、線を引くなどの過程を通じて、注意深く取り組む力も身につきます。
👪 親のサポートのコツ
- ✅ 無理のない時間設定が大切⏳
最初は5分〜10分など短時間でOK。
少しずつ時間を伸ばして、飽きずに楽しめるリズムを作りましょう。
途中で休憩を入れることで、疲れやストレスも防げます◎ - ✅ ポジティブな声かけを心がける
例:「その色の組み合わせ、素敵だね!」「この形、よく描けたね!」
具体的に褒めることで、自信を育みます。 - ✅ 表現の自由を大切にする
うまく描けたかどうかではなく、「描く過程」を楽しむ雰囲気をつくるのが大切です。 - ✅ テーマを提示してみるのも◎
「今日は海の生き物を描いてみようか?」など、イメージを広げるサポートも効果的です。
お絵描きは、子ども自身の発達に合ったスキルを自然に身につけられる遊びです。
日々のちょっとした関わりが、子どもの成長を大きく支えることにつながります😊🌱
4. 触覚過敏がある子どもへの対応とおすすめ画材🖍️✨
触覚過敏がある子どもにとって、ベタつくクレヨンや紙の感触が「不快」であることも少なくありません。
ですが、工夫次第で楽しくお絵描きに取り組むことができます。
ここでは、触覚過敏に配慮した画材選びと環境づくりのポイントをご紹介します。
🎨 触覚過敏の子どもにおすすめの画材触覚過敏に配慮したおすすめ画材
クレヨン
✅ 三菱鉛筆「かきかたクレヨン」
サラサラとした触感でべたつかない設計✨
三角形で握りやすく、筆圧が弱い子にもおすすめ✨
✅ プラントベースクレヨン「きっずいろ」
100%植物性素材で、肌にやさしく安全。
ナチュラル志向のご家庭にも◎
手に優しいテクスチャ(質感・感触)が特徴です。
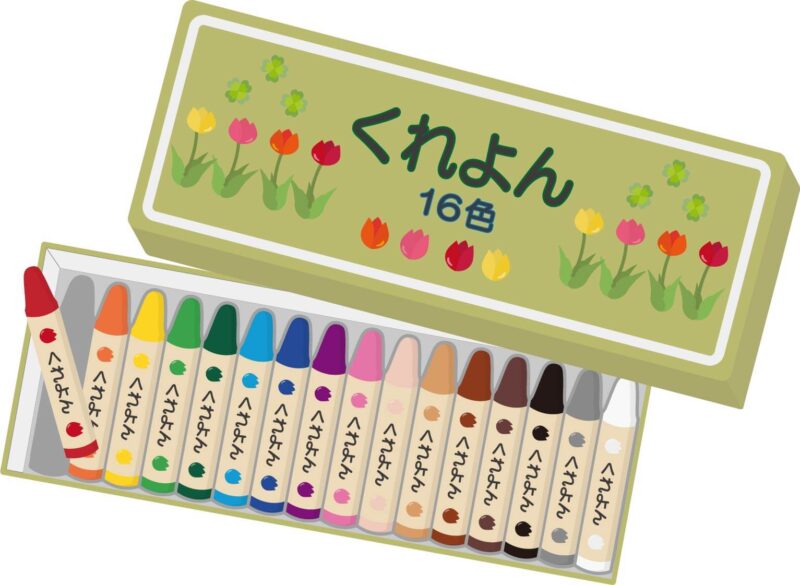
色鉛筆
✅ ファーバーカステル「グリップ鉛筆」
三角形+滑りにくいドット加工で、力を入れずに描けます✏️
軽い力で握れる設計✨
✅ ステッドラー「トライプラス色鉛筆」
柔らかい芯でスルスルと滑らかな描き心地✏️
軽い力でしっかり色が出ます🌈
タッチペン(デジタル画材)
✅ Wacom Intuos(ワコム・インテュオス)
タブレットを使えば、紙やクレヨンの感触が苦手な子どもでも、ストレスなくお絵描きを楽しめます💻✨
Wacom Intuosは、サラサラとした描き心地で操作もしやすく、初めてのデジタル画材にもおすすめです。
🖊️ 感圧機能とは?
→ ペンの押す強さによって線の太さや濃さが変わる仕組みのこと。
この機能により、鉛筆や筆で描くような自然な表現ができ、子どもの感覚遊びや創造力を引き出します🎨
また、指先で直接描く操作に比べて、タッチペンは手が汚れないので、触覚過敏がある子にもぴったりです👌
🧸 画材選びの注意ポイント
✅ アレルゲンや耐水性もチェック
肌トラブルを防ぐために、低刺激・アレルゲンフリーの製品を選ぶと安心。
✅ 握りやすさに注目
太め・三角形の持ち手は、不器用さがある子にもおすすめです。
✅ 紙以外の素材も選択肢に
チョークボード、砂遊び、LEDお絵描きボードなど、感触に負担の少ないツールも活用できます。
🏡 環境の工夫で安心感UP!
🏡 安心できる空間を整える
座り心地の良い場所やリラックスできる空間でお絵描きができるようにします。
クッションを使ったり、床に座って自由に描ける場所を用意することで、ストレスなく取り組めます。

🖌️「自由に描いていいよ」の一言を大切に
細かい指示をなるべく避け、自由に描かせることでストレスを減らす。
何を描くかを考える過程を楽しむために、子どもが自分で決める時間も大切にしましょう。

触覚過敏の子どもも、合う画材と安心できる環境があれば、のびのびと表現を楽しむことができます。
ぜひ、親子でお絵描きタイムを楽しんでみてくださいね😊💕
4. 子どもの発達を支える親の観察力と環境づくり👀💡
子どもの発達を支えるうえで、親の「気づく力」と「整える力」はとても大切です。
毎日の中で、「あれ?ちょっと気になるかも?」という発達のサインに気づけるだけでも、早期のサポートにつながります。

🔍お絵描きを通じて見える発達のサイン
✏️ 線がぎこちない・筆圧が弱い
→ 手指の筋力や協調運動が発達段階にある可能性
🖼️ 同じ絵ばかり描く
→ 発想の幅や表現力の広がりに課題がある場合も
表現の幅を広げる工夫を取り入れる
🎨 特定の色しか使わない・色に強いこだわり
→ 感覚特性やこだわり傾向の可能性も。
無理に変えず、見守りながら観察を!
🏠 発達を促すお絵描き環境づくりのヒント
🪑 快適な姿勢を保てる椅子・机を選ぶ
→ 足が床につく高さで安定感を。集中力がUP!
🖌️ 表現の自由を尊重する雰囲気を作る
→ 「うまい・へた」ではなく、描くことそのものを楽しむ雰囲気を作る。
「うまく描けた?」より、「楽しめたね!」が大事😊
🎯 興味を広げるためにテーマや季節感を決めるのも◎
(例:「今日はかき氷を描こう!」「海の生き物しりとりお絵描き」)
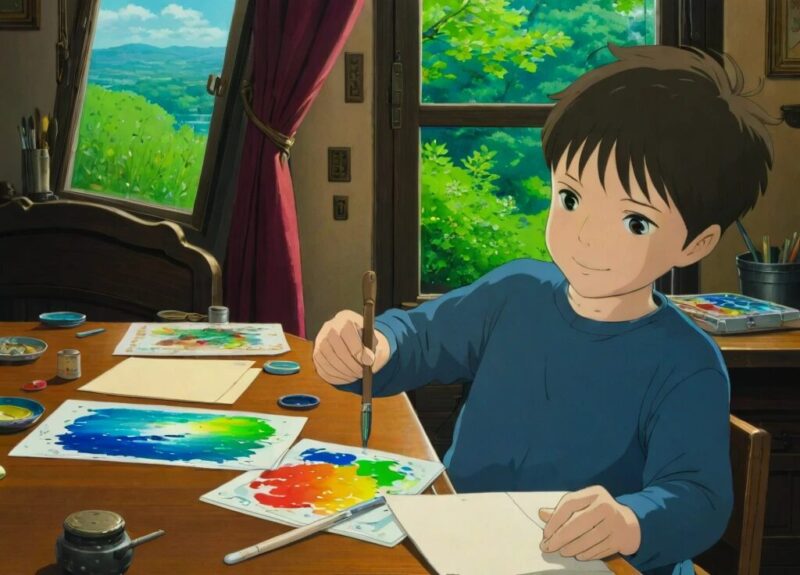
お絵描きは、ただ上手に描くことが目的ではありません。
「表現してもいい」「描いてもいい」と感じられる場を整えることで、
子どもは自分の世界を安心して広げていけるようになります🌱
🌈関連ページ:
👉 [【感覚過敏の子ども向け】家庭でできる環境づくりとおすすめ支援グッズ]
👉 [指先トレーニング9選|3歳から始める家庭での遊びで脳を育てる]
5. よくある質問(Q&A)
お絵描きは子どものどのような発達を促しますか?
お絵描きは、手と目の協調性、集中力、感覚統合、創造力など、多方面の発達を促します。
子どもがクレヨンのべたつきを嫌がる場合、どう対処すれば良いですか?
べたつかないクレヨンやタッチペンなど、子どもが快適に使える画材を選ぶと良いでしょう。
お絵描きの発達段階は年齢ごとにどのように変化しますか?
1歳半頃から線を引き始め、2歳頃に丸を描き、3歳半頃に顔らしき絵を描くなど、段階的に発達します。
子どもが同じ絵ばかり描くのは問題ですか?
同じ絵を繰り返し描くことは、特定の興味や安心感を示す場合がありますが、多様な表現を促す工夫も大切です。
触覚過敏の子どもに適した画材は何ですか?
べたつかないクレヨンや滑らかな色鉛筆、デジタル画材(タッチペンなど)が適しています。
お絵描きを通じて子どもの発達をサポートする方法は?
子どもが楽しめる環境を整え、適切な画材を提供し、自由な表現を尊重することが重要です。
子どもが絵を描かない場合、どうすれば良いですか?
無理に描かせるのではなく、興味を引き出す環境や活動を提供し、自然な関心を育てることが大切です。
お絵描きと他の遊びとのバランスはどう取れば良いですか?
お絵描き以外の遊びや活動ともバランスを取り、多様な経験を通じて総合的な発達を促すことが望ましいです。
親が子どもの絵に対してどのようにフィードバックすれば良いですか?
具体的な部分を褒めたり、感想を伝えたりすることで、子どもの自信と意欲を高めることができます。
お絵描きを通じて子どもの感情を理解する方法はありますか?
子どもの描く内容や色使い、テーマなどから感情や興味を読み取り、コミュニケーションのきっかけにすることができます。
まとめ
お絵描きは、ただの遊びではありません。
子どもの成長を後押しし、親子の絆を深める貴重な時間です💖
🧠 手元をじっと見る力
🎨 色や形を使った表現力
✋ 指先の器用さと集中力
お絵描きを通じて育つこれらの力は、幼児期の発達にとってとても大切です。
ただし、触覚過敏や不器用さがある子どもにとっては、画材の感触や動作の難しさが壁になることも…。
そんなときは――
🌟 子どもに合った画材を選ぶ
🌟 安心して描ける環境を整える
この2つを意識するだけで、子どもは自分らしく表現する楽しさを少しずつ取り戻していきます✨
また、子どもの絵には「発達のサイン」がたくさん隠れています。
「なんとなく気になるな?」と感じたら、その変化を観察することが発達支援の第一歩になります💡
「できない」ではなく、「どうすれば楽しめるか」に目を向けて、
お子さんと一緒に、お絵描きの時間を大切に過ごしてみてくださいね😊

🔜次回予告
模倣行動には、ことば・身体・社会性などの発達を促すヒントがたっぷり!
次回もお楽しみに✨






