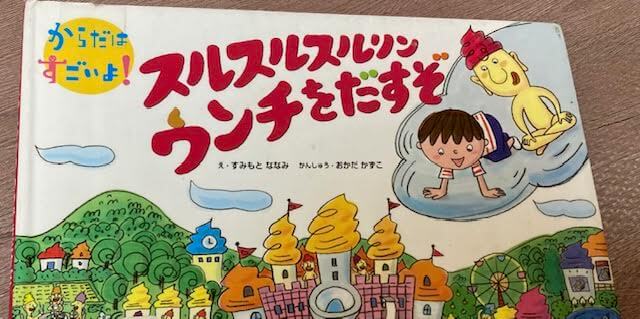はじめに
子どもが「うんち出ない…」とトイレで困っている姿、見たことはありませんか?💦
そんな時にぴったりなのが、
絵本『スルスルリンうんちをだすぞ』(あかね書房/「からだはすごいよ!」シリーズ)。
ウンチというテーマを、楽しく・科学的に・優しく伝えてくれる一冊です。
「スルリン」と出る健康なウンチの大切さを学べるこの絵本は、
親子での読み聞かせやトイレトレーニングにも最適。
今回は、実際に読んで感じた魅力や、家庭での活用法を紹介します✨
✅ 目次
はじめに
- 『スルスルリンウンチをだすぞ』とは?
└「からだはすごいよ!」シリーズの紹介
└ あらすじと登場キャラクター - この絵本が優れている3つの理由
- わが家の体験談|「スルスルリンうんちをだすぞ」が変えた日常
- 親子での読み聞かせ効果
- 家庭での活用法|トイレ・食育・生活習慣
- いいウンチを出すために家庭でできること
- よくある質問(Q&A)
- まとめ|「スルスルリン!」が合言葉になる絵本
1.『スルスルリンウンチをだすぞ』とは?

シリーズ概要:「からだはすごいよ!」ってどんな本?
『スルスルリンウンチをだすぞ』は、子どもの身体の仕組みをわかりやすく伝える「からだはすごいよ!」シリーズの1冊。
シリーズでは他にも「ちいさなけが」「くしゃみとせき」など、
生活に密着したテーマが扱われています。
どの作品も、子どもたちが「自分のからだってすごいんだ!」と感じられる構成になっていて、
保育園や小学校低学年でも人気です。
あらすじ
主人公は、ウンチの精「チャント・ウンチ」。
彼が登場して、「食べたものがどうやってウンチになるのか」を、
楽しい物語とイラストで教えてくれます。
バナナのような「スルスルリンうんち」が理想的であること、
我慢すると体に悪いことなど、子どもにも理解しやすい内容。
「うんち=おもしろい」だけでなく、「うんちはからだからの大事なメッセージなんだ」と学べるのが特徴です。
2. この絵本が優れている理由

①「ふざけていない」うんち絵本
「うんち」というテーマは笑いを誘いがちですが、この絵本は教育的でまじめ。
でもまじめすぎない。
子どもたちが笑いながらも、しっかり体の仕組みを理解できるよう作られています。
② 体の仕組みを自然に学べる
食べたごはんがどのように消化され、腸を通ってウンチになるのか。
難しい説明はなく、イラストとセリフで感覚的に理解できる構成です。
保育園や低学年の「生活科」「食育」にもぴったりです。
③「いいウンチとは?」が分かる
バナナのような形の「スルスルリンうんち」が理想✨
コロコロ・ベチョベチョなど、さまざまなウンチの状態を紹介しながら、
健康のサインを子ども自身が見分けられるようになります。
3. わが家の場合|「スルスルリンウンチをだすぞ」が変えてくれたこと🌸

わが家には、5歳と3歳の兄弟がいます。
どちらも小さいころから便秘ぎみで、ころころうんちが続く日も多く、病院で薬を処方してもらっていました💊
お薬のおかげで今は落ち着いていますが、それでもたまに「でない…」「おしりがいたい」と言う日があります。
そんなときに出会ったのが、この絵本『スルスルリンうんちをだすぞ』でした📖✨
💡「ママが言うより、絵本のほうが素直に聞ける」
この絵本には、するするうんちを出すコツがわかりやすく書かれています。
「うんちの精・チャントウンチ」が登場して、
「どんなうんちがいいのか」「どうすればスルリンと出るのか」を楽しく教えてくれるんです。
私が「野菜食べようね」と言ってもなかなか聞いてくれなかったのに、
絵本に書いてあるとスッと受け入れてくれるんです🥦
「野菜を食べるとスルスルリンうんちが出るんだよ!絵本にも書いてあったでしょ?」
と声をかけると、「あ、そうだったね!」と素直にパクパク✨
やっぱり「ママの言葉」より、
「絵本からの学び」の方が耳👂に届くこともあるんだなと感じました。
🧡絵本は「心に残るおまじない」みたい
子どもって、ママが言葉で注意すると反発したりスルーしたりしがちですが、
絵本を通すと、物語として自然に心に残るようです。
「スルスルリン!」という言葉もリズムが楽しくて、
我が家ではトイレの合言葉になっています🚽🎵
ちょっと出にくそうな日も、
「チャント・ウンチさん呼ぼうか?」と言うと笑いながらトイレに向かうようになりました。
🌼「伝える」じゃなく「一緒に感じる」
この絵本を読んで感じたのは、
「正しい知識を教える」だけじゃなく、親子で一緒に体を考える時間になるということ。
うんちの話って、つい「ちゃんと出さなきゃダメだよ」と言いがちですが、
実は「からだの仕組み」まではなかなか説明できないものですよね。
でも『スルスルリンうんちをだすぞ』を読んでからは、
「からだってすごいね✨」「うんちはがんばってる証拠だね💪」
と、子どもと一緒に「体の中で起きていること」を前向きに話せるようになりました。
✨まとめ
『スルスルリンうんちをだすぞ』は、
子どもがうんちが「自分の体の合図」として前向きに捉えられるようになる絵本です。
便秘やトイレトレーニングで悩んでいるご家庭にもおすすめ。
なにより、親子で笑いながら「体のこと」を考えられるのがうれしいポイントです🌈
絵本の力って本当にすごい。
「スルスルリン」の魔法の言葉が、今日もわが家のトイレで聞こえています😊
4. 読者からの声・実際の活用例
🌟「トイレが苦手だった子が、絵本を読んだ後から「スルリン出たよ!」と笑顔に」
🌟「保育園で読み聞かせしたら、大爆笑しながらも真剣に聞いてくれました」
🌟「便秘気味の娘が、「いいウンチ出すぞ!」と前向きになった」
保育現場でも、「うんち=恥ずかしい」から「うんちは大事」に意識が変わる絵本として、
取り入れられています。
5. 家庭での読み聞かせポイント
💡おすすめのタイミング
- 朝ごはん後やトイレ前後など、「うんち」を意識しやすい時間に読む
- 食育・体の話をする流れで読む
💬子どもに投げかけたい質問
- 「今日のうんちはどんな形だった?」
- 「チャント・ウンチさん、元気かな?」
- 「スルスルリンうんち出すには何食べたらいいかな?」
こうした声かけで、絵本が「ただ読むだけ」から「体を学ぶ教材」に変わります。
6. いいウンチを出すために家庭でできること
🍚 食事と水分
野菜・果物・発酵食品・水分をしっかり摂ることで、腸の動きを助けます。
「うんちが出る食べ物」を絵本の世界とつなげて話すと理解が深まります。
🏃♀️ 適度な運動
身体を動かすことで腸の蠕動運動が活発になります。
「スルスルリン体操」など、親子で楽しく動くのもおすすめ。
🚽 トイレのリズムを整える
我慢せず、毎日同じ時間にトイレに行く習慣を。
絵本のキャラクターをきっかけに「行こうか」と声かけするとスムーズです。
7.【よくある質問(Q&A)】💬
『スルスルリンうんちをだすぞ』は何歳からおすすめですか?
3歳ごろから小学校低学年まで楽しめます。
トイレトレーニングを始める時期にもぴったりです。この絵本はどんな内容ですか?
うんちの精・チャントウンチが登場し、
食べたものが体の中を通って「スルスルリンうんち」になるまでを楽しく説明してくれます。ふざけた内容ではないですか?
いいえ。笑いながらも体の仕組みをきちんと学べる教育的な絵本です。
保育園や学校でも読み聞かせに使われています。便秘の子に効果はありますか?
医療効果はありませんが、子どもが「うんち=体に大切」と理解するきっかけになります。
便秘への意識づけには効果的です。トイレトレーニング中でも使えますか?
はい!「スルスルリン!」というリズムが楽しく、トイレに行くきっかけ作りになります。
男の子・女の子どちらにも向いていますか?
性別問わず楽しめます。
うんちの仕組みをテーマにしているため、すべての子どもが学べる内容です。絵がリアルで怖くないですか?
イラストはカラフルでかわいらしいタッチ。
子どもが抵抗なく受け入れられる優しい表現です。「からだはすごいよ!」シリーズの他の本もおすすめ?
ぜひ!「ちいさなけが」「くしゃみとせき」など、
体の仕組みを楽しく学べる絵本が揃っています。読み聞かせのタイミングは?
朝ごはん後やお風呂上がりなど、リラックスした時間が◎。
トイレ前後にも効果的です。どこで購入できますか?
書店やオンラインショップ(Amazon・楽天ブックスなど)で購入できます。
まとめ 🌿
『スルスルリンうんちをだすぞ』は、
子どもが自分の体と向き合い、「うんち=健康のバロメーター」だと気づける貴重な一冊。
💡ただの「うんち絵本」ではなく、
身体の理解・生活習慣づくり・トイレトレーニングにもつながります。
お子さんが「うんち」や「体」に興味を持ち始めたら、ぜひ親子で読んでみてください📚✨
「スルスルリン!」の言葉が、家庭に笑いと健康を運んでくれます。
📢次回予告
「カスタムクレヨン×センサリートイがすごい!」
お楽しみに!
📎関連記事
- 「おこりたくなるのはどんなとき?」絵本レビュー|怒りの気持ちとやさしく向き合う
- 会話が苦手な幼児・子どもにおすすめ絵本『絵でわかる なぜなぜ会話ルールブック
- 1歳から5歳の子どもにおすすめの絵本10選:年齢別の絵本選びのポイント
- こころを育てる七田式えほん:年齢別に学ぶ心の成長
- 子育てママにおすすめの偉人や有名人の格言:育児に役立つ言葉たち
- 【4歳向け絵本おすすめ12選】想像力と社会性が育つ!現役ママ厳選
- 【保存版】3歳の子どもに本当に読んでよかった絵本12選
- 【保存版】2歳児におすすめの絵本11選|知育・言葉・しかけ絵本を厳選
- 【実体験】5歳児におすすめの絵本13選|知育・感情教育にも◎
- 宮西達也の恐竜絵本|おすすめランキング&全作品あらすじ【泣ける】
- 『わくわく!たのしい まいにちのつくりかた』絵本レビュー|子どもの自己肯定感を育む