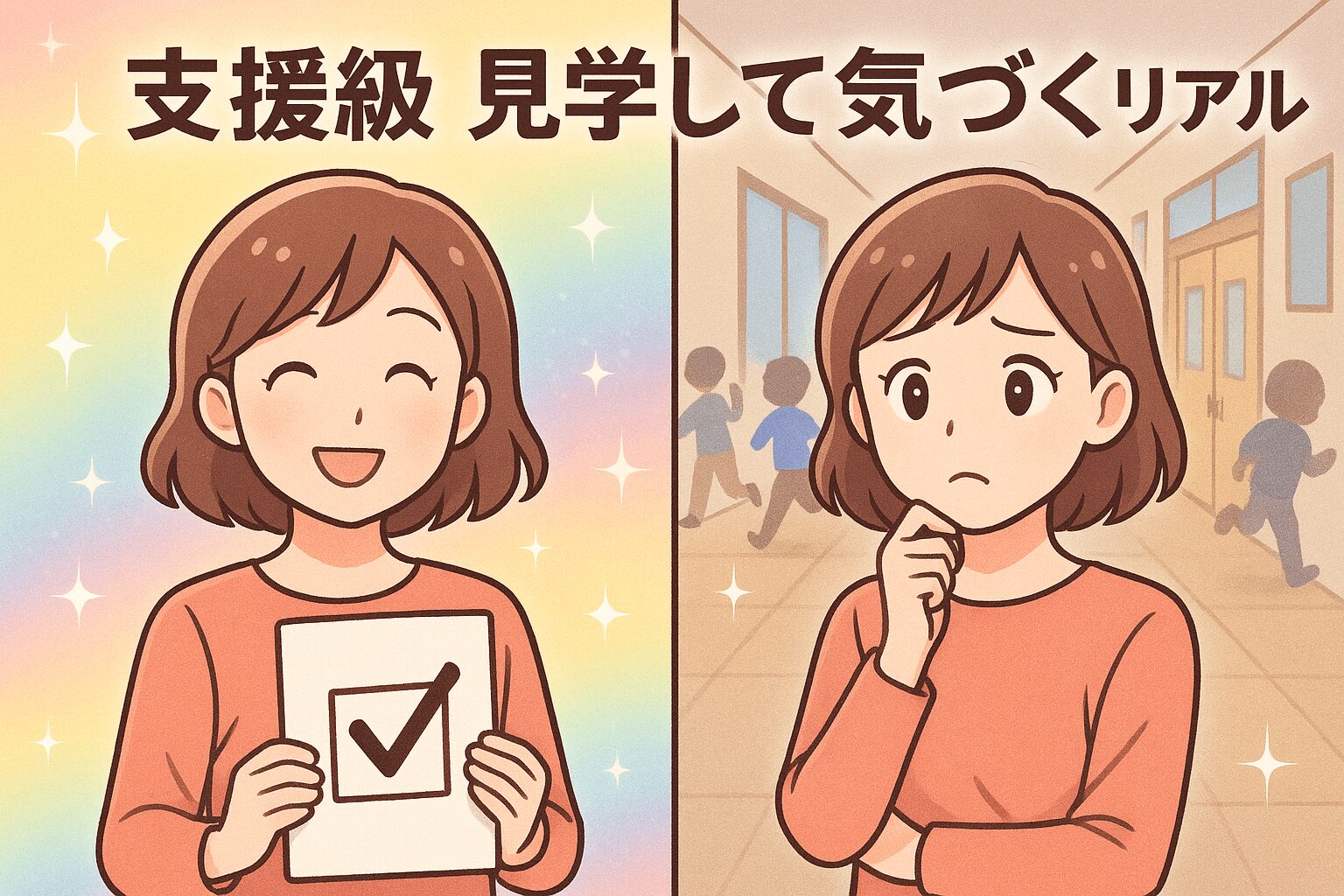はじめに|支援級の見学は「実際に見ること」が一番大切
支援級に通うかどうかは、子どもにとってとても大切な選択。
だからこそ、私は実際に学校へ見学(2校目)に行ってきました。
周りのママたちからは
「ここの支援級はすごく良いよ!」
と聞いていたので期待していたのですが、実際に自分の目で見てみると、口コミとは少し違う印象を受けました。
子どもの特性は一人ひとり違うので、合う学校も違います。
だからこそ、見学で「親の直感」を大切にしていいと思います。
やっぱり、どれだけ評判がよくても 自分の子どもが過ごす環境は「自分の目で見ること」が一番大事 だと感じました。

目次
はじめに|支援級の見学は「実際に見ること」が大切
- 支援級の見学で感じたリアルな印象
・学校全体の雰囲気
・指導のトーン
・先生同士の連携
・クールダウンスペースの状態
・支援員さんの人数
・支援級の良かった点 - 支援級の見学でチェックすべきポイント(ママ視点まとめ)
- 見学して感じたこと|口コミよりも「自分の感覚」が大事
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|子どもに合う環境を見つけるために
1. 支援級の見学で感じたリアルな印象
① 学校全体の雰囲気はとてもにぎやか
全校生徒は約800人。
情緒級4クラス、知的級2クラスの合計6クラスがあり、規模の大きい学校です。
休み時間になると廊下にたくさんの児童があふれ、
わしゃわしゃとしたにぎやかな雰囲気に少し圧倒されました。
特に高学年の子どもたちは体格もしっかりしていて、
チャイム後に勢いよく走って戻ってくる姿もあり、不安を感じる場面も。
「うちの子、この環境で大丈夫かな?」
という気持ちが正直芽生えました。
② 高学年への強い口調の指導に驚いた
見学中、廊下で高学年の子に対して
「静かにしろ!黙って静かに待つって言っただろう!」
と強い口調で叱っている先生がいて、その場の空気がピリッとするほど。
私は少し怖く感じてしまいました。
もちろん状況や指導方針は学校によって違いますが、
子どもに対する声かけのトーンは毎日の安心感に直結する部分
なので、見学でしっかりチェックして良かったと思いました。
③ 先生同士が緊張感のある雰囲気
見学中、先生同士のやり取りが少し「緊張感のある雰囲気」に見える場面があり、
チームとしての連携がどのように取られているのか、ふと気になるところでした。
これも実際に見学しないと気付けないポイントだと思います。
④ クールダウンスペースは使い込まれている印象
支援級のクールダウンスペースを見せてもらいましたが、
思っていたよりも「使い込まれている」印象がありました。
落ち着きたい時に使う場所だからこそ、
どれだけ安心して過ごせる空間になっているか 、
環境の整い具合は大事なチェックポイント です。
⑤ 支援員さんの人数は不足気味らしい
学校側の説明では、
「支援員さんが不足していて、もう少し必要な状況」とのこと。
支援員の人数は、子どもの安全や日常のサポートに直結するため、ここも重要なポイントです。
⑥ ただし、支援級の「良さ」も感じた
不安に感じる部分があった一方で、良いところも分かりました。
- 子どもの 特性や相性に合わせて クラスを変更できる柔軟性
- 本人の安心感を大切にした環境調整
- 無理に通常級へ行かせない配慮
「この子にはこちらのクラスのほうが合いそうですね」と先生方が話してくれたのは、
支援級だからこその安心ポイントでした。
2. 支援級見学でチェックすべきポイント

ここは読者に役立つポイントとしてしっかりまとめました。
✔ 学校全体の雰囲気(にぎやかさ・安全性)
✔ 先生の声かけ・表情・指導のトーン
✔ 先生同士の連携の雰囲気
✔ 支援級の教室環境・クールダウンスペース
✔ 支援員さんの人数と役割
✔ 通常級との行き来の柔軟さ
✔ IEP(個別支援計画)の作り方
✔ 友達トラブル・パニック時の対応方法
✔ 1日の流れや学習スタイル
✔ 子どもが安心して過ごせるかどうかの「肌感覚」
実際に見て、子どもの特性と学校が合うかどうかを見極めることが大切です。
3. 支援級の選び方|深掘りガイド
1. 通える学校の仕組みをまず知る(地域差が大きい)
支援級は「どこでも自由に選べる」わけではなく、
自治体の方針によって選択肢がかなり違う という点を最初に理解する必要があります。
自治体によっては:
・学区内に支援級が複数ある ⇒ 選べる可能性が高い
・学区外も調整でOKになる場合がある ⇒ 環境を優先できる
・支援級が1校しかない ⇒ その学校を中心に考える
・通級と支援級の組み合わせが柔軟 ⇒ 子どもの特性に合わせて選択できる
まずは市区町村の教育相談や学校に問い合わせ、
実際に選べる範囲を知ること が最初のステップです。
2. 見学は「数」よりも「見方」が大事
選べる学校が1校でも4校でも、
大事なのは「どこを見るか」 です。
特に見ておきたいポイント:
- 教室の環境(視覚刺激の多さ・落ち着ける空間設計)
- 先生の声かけのトーン
- 支援員さんの人数・動き方
- 通常級との距離や行き来のスムーズさ
- 他児童の雰囲気(にぎやかさ、ぶつかる危険性など)
- クールダウンスペースの使い方
- 1日の流れの柔軟さ
- パニックやトラブル時の対応
これらは 口コミだけでは絶対に分からない部分 です。
3. 「先生との相性」は支援級選びで最重要ポイント
支援級は少人数で、先生との接触時間が長いため、
担任や支援員さんの人柄・声かけのトーンは特に重要。
チェックポイント:
- 子どもを見る視線が優しいか
- 困っている子への対応が丁寧か
- 叱る時の声の大きさ
- 相談したときの受け止め方
- 保護者とのコミュニケーションの姿勢
実際、多くのママたちが「先生が決め手だった」と話します。
4. 「安全性」と「安心感」は最優先していい
発達特性のある子は、
環境が合わないだけでストレスが大きく増える傾向があります。
特に大切なのは:
- 廊下・昇降口が混雑しすぎていないか
- 高学年との接触で危険がないか
- 逃走対策(鍵の位置、見守り体制)があるか
- 校内の導線が整理されているか
「安心して通わせられるか」
これは保護者が大切にしていい視点です。
5. 子どもの特性と「学校のタイプ」が合っているかを見る
支援級にも学校によってカラー🎨があります。
例:
- 学習重視タイプ(ゆっくりだけど学習の積み上げを大切にする)
- 生活・情緒ケア重視タイプ(安心感最優先、無理させない)
- 通常級との行き来が多いタイプ
- 個別支援が充実しているタイプ
子どもの特性に合わせるとミスマッチが減ります。
6. 1校しか選べないときは「ここを重点的に見る」
- 先生の声かけ
- クラスの雰囲気
- 教室の刺激量
- クールダウンスペース
- 支援員さんの人数
- 行事や通常級との距離感
選択肢がなくても、
「この学校はこういうタイプなんだ」と理解できると親も安心しやすくなります。
7. 見学して感じたこと|口コミは参考程度に。口コミよりも「自分の感覚」が大事
口コミは大切だけれど、
保護者や子どもによって感じ方・相性が全く違います。
見学に行く前は、
「すごくいい学校らしいよ!」
という周りの口コミを信じて、私もワクワクしていました。
でも実際に見に行ってみると、
「ん…?想像と違うな」
と感じる部分も。
口コミはあくまで口コミ。
最終的な判断は、自分の目で見るのが一番。
これは、今回の見学で一番強く実感したことでした。
支援級を選ぶときに大切な7つの視点(まとめ)
- 自治体の仕組みを知って、選べる学校の範囲を把握する
- 見学は「数より質」。見るポイントを明確にする
- 先生との相性は最重要ポイント
- 安全性と安心感は優先していい
- 子どもの特性と学校のタイプが合うかを見る
- 選択肢が少ない場合は1校を深く理解する
- 口コミよりも最終的には「親の直感」を信じる
4. よくある質問(FAQ)
支援級の見学は何校くらい行くべき?
実際には、住んでいる地域によって通える学校がある程度決まっています。
そのため、候補が1〜2校しかないケースも多いです。
ただし、その範囲の中でも 可能であれば2〜3校を見比べると、
雰囲気や支援体制の違いがより分かりやすくなります。- 学区内に複数校がある地域
- 特別支援学級の調整で学区外も選べる自治体
- 通級や支援級での融通が効く地域
などでは「比較できる場合」もあります。
逆に、「決められた学校しか選べない」地域の場合は、
複数校の比較よりも「1校をじっくり見て納得する」ことが大切です。
どちらの場合でも、「実際の環境を自分の目で見る」ことが最も大きな判断材料になります。見学時に質問していい内容は?
支援員の人数、1日の流れ、通常級との行き来、個別支援計画(IEP)の作り方などは遠慮なく聞いてOKです。
口コミと実際の差が大きいときはどうすれば?
口コミはあくまで他の子の体験。自分の子どもに合うかどうかを優先して判断します。
支援級の「良い学校」って何で判断する?
先生の声かけ、教室の環境、安心して過ごせる雰囲気、柔軟な対応、支援体制がポイントです。
クールダウンスペースは重要?
とても重要です。
安心して1人になれる場所があるかどうかで、学校生活のストレスが大きく変わります。見学時、子どもを連れて行った方がいい?
可能なら連れて行くと、本人がどう感じるかが分かりやすくなります。難しい場合は事前に相談を。
見学では何をメモすればいい?
良い点・不安な点・先生の雰囲気・支援体制・安全面など、あとで比較しやすくメモすると便利です。
見学で嫌な場面を見てしまった場合は?
一度の場面だけで判断せず、複数校を見て比較するのがおすすめです。
支援級の先生の指導のトーンは気にすべき?
はい。子どもの安心感に直結するため、日常的な声かけの様子は重要な判断ポイントです。
見学後、学校へ断っても大丈夫?
もちろんOKです。
後から「合わなかったので違う学校を検討します」と伝えて問題ありません。
まとめ|子どもに合う環境を見つけるために
支援級といっても、学校の雰囲気・先生の関わり方・支援体制は本当にさまざま。
口コミだけでは分からない部分を、実際の見学でしっかり確認できてよかったと思っています。
今回の見学で感じたことを踏まえて、
子どもが安心して過ごせる環境を見つけられるよう、引き続き複数校を見ていく予定です。
同じように悩んでいるママ・パパの参考になれば嬉しいです。
📢次回予告
お楽しみに!
関連記事
- 年長の子どもの成長は突然やってくる⁉ 急にできるようになったこと体験談
- 年長児の就学前学習|ひらがな・数・図形の目安と家庭でできる対策
- ヨコミネ式で伸びる子・伸びにくい子|【体験談あり】
- 就学前チェックリスト(年長向け)|小学校入学までに必要な力と家庭での練習法
- 【就学相談の流れ】年長ママ体験談|聞かれること&後悔しない準備
- 【体験談】発達検査WISC(ウィスク)の流れと結果|就学判断・診断の参考に
- 就学判定の結果が届いたらどうする?|特別支援学級と通級の違い・家庭での準備
- 【体験談あり】就学前検診の所要時間と当日の流れ|持ち物・服装・注意点
- 【就学準備】立って靴を履く練習|小学校入学前に身につけたい身辺自立スキル