はじめに|なぜ「立って靴を履く」が大切?
入学準備の中でも、意外と見落とされがちなのが「靴の着脱」です。
園では座って靴を履くことが一般的ですが、小学校では立ったまま履く場面が急増します。
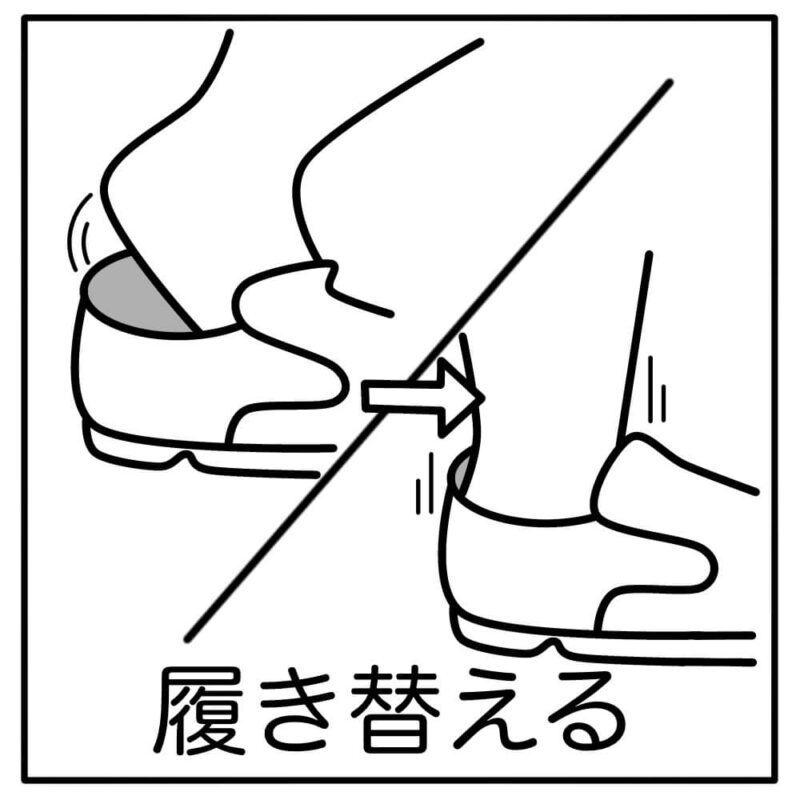
うちの園でも、年長からは立って履くことを推奨しており、
バランスをとりながら自分で靴を履ける力は、就学に向けた大切な生活スキルとされています。
小学校に入ると、外遊びや体育、下校準備などで「立ったまま靴を履く」場面が増えます。
座って履く時間や場所がないこともあり、バランスをとりながら自分で靴を履けることは、
就学に向けた大切な生活スキルです。
また、立って靴を履くことは、
- 体幹の安定
- バランス感覚
- 手先と足の協調動作
などの発達にもつながります。
目次
はじめに|なぜ「立って靴を履く」が大切?
- 立って靴を履くのに必要な力とは?
- 練習を始める前にチェックしたい準備
- ステップ別!立って靴を履く練習方法
- よくあるつまずきポイントとサポート法
- 家庭での声かけ・工夫のコツ
- 片足立ちが苦手な子におすすめの遊び
- 靴選びのポイント
- よくある質問と答え(Q&A)
- まとめ|楽しく体幹を育てて「できた!」を増やそう
🧠 1. 立って靴を履くのに必要な力とは?
立って靴を履くには、いくつかのスキルが関わります。
- 🦵 体幹の安定:片足立ちをキープできる力
- ✋ 手足の協調:手で靴を持ちながら足を動かす力
- 👀 空間認知:靴の向きを理解して合わせる力
- 🧠 動作の順序理解:「靴を開く→足を入れる→かかとを合わせる→マジックを閉める」などの順序を覚える力
発達性協調運動症(DCD)やASD傾向のあるお子さんは、これらの複合動作に苦手さを感じることがあります。

👟 2. 練習を始める前にチェックしたい準備
まずは成功体験を増やすことが大切です。
以下を準備しましょう。
- ✅ 安定した靴(マジックテープで履きやすい)
- ✅ すべりにくい床(フローリングよりマットの上が安心)
- ✅ 姿勢を支える場所(壁や手すりの近く)
- ✅ しっかりした体幹・バランス練習(片足立ち、ケンケン、平均台など)
🪜 3. ステップ別!立って靴を履く練習方法
🔹ステップ1:座って正しい順序を覚える
まずは座った姿勢で「靴の前後・左右」を確認する練習から。
💡ポイント:「マーク」や「シール」で左右を区別すると◎
🔹ステップ2:壁に手をついて、片足で履く練習
壁や棚に手をついて安定させながら、片足立ちで靴を履いてみましょう。
このとき、片足立ちの時間を少しずつ伸ばすのがコツ。
🔹ステップ3:支えなしでトライ!
床が安定している場所で、両手を使って履く練習をします。
💬声かけ例:「バランスとって〜」「かかとトントン!」
🔹ステップ4:朝の準備や外出前に実践
実際の生活場面で「立って履く」練習を組み込みましょう。
毎日少しずつ取り入れることで、習慣化が進みます。
💡 4. よくあるつまずきポイントとサポート法
| つまずきポイント | サポート法 |
|---|---|
| 片足立ちでふらつく | 壁や手すりを使って支える/片足立ちゲームで練習 |
| 靴の向きがわからない | 左右マーク・動物シールを貼る |
| 順序がわからない | 絵カードや写真で手順を可視化 |
| 焦ってしまう | 時間を区切らず、ゆっくり取り組む |
🏠 5. 家庭での声かけ・工夫のコツ
- 「おっとっと〜バランス〜✨」と遊び感覚で楽しく
- 「上手にトントンできたね!」とできた部分を具体的に褒める
- 朝の時間に余裕を持たせ、成功体験を優先
6.🧍♂️片足立ちが苦手な子におすすめ!
遊びながらバランス力を育てる方法
立って靴を履くには、片足立ちでバランスを保つ力が欠かせません。
この力は、体幹・足首・股関節などの筋肉の発達と深く関係しています。
特に、発達性協調運動症(DCD)やASD傾向のあるお子さんは、
- 体幹がぐらつく
- 片足で立つと不安定
- すぐに転びそうになる
などの様子が見られることも。
でも大丈夫✨
「遊びながら」「楽しく」練習することで、自然とバランス感覚が育ちます!

🦶① ケンケンパ
昔ながらの「ケンケンパ」は最強のバランス遊び!
- 片足立ち+ジャンプでバランス感覚UP
- 室内ではマットやカラーテープを使うと◎
💡ステップアップ:ケンケンの回数を増やしてチャレンジ!
🐸② カエルジャンプ・ウサギジャンプ
しゃがんでジャンプする動きは、足の筋力や体幹を鍛えます。
「カエルみたいにピョン!」「ウサギになって3回ジャンプ!」など、動物なりきり遊びでモチベーションUP。
🎈③ 風船バランスキャッチ
風船を片手でポーンと投げて、キャッチする瞬間に片足立ちポーズ!
遊びながらバランスと集中力を育てられます。
💡床が滑らないように注意!
🧘④ 片足バランスチャレンジ
「どっちの足で長く立てるかな?」と競争形式にすると楽しい✨
タイマーを使って「5秒」「10秒」「15秒」と少しずつ時間を延ばします。
🐧⑤ ペンギン歩きゲーム
足の間にタオルやぬいぐるみを挟んで歩く遊び。
自然とバランス感覚と体幹が育ち、歩行姿勢も安定します。
💬「ペンギンさん、落とさないように歩けるかな〜?」と声かけ。
練習を楽しく続ける工夫と声かけ
- 「どっちの足が上手かな?」とゲーム感覚にする
- 「すごい!5秒立てたね!」とできた瞬間を具体的に褒める
- 失敗しても「もう一回チャレンジしてみよう!」とポジティブな声かけ
👉 できた喜びを積み重ねることで、自信と体幹力がぐんぐん育ちます。
7. 立って靴を履きやすくする「靴選びのポイント」👟
バランスが安定しない原因の1つに「靴の合わなさ」もあります。
以下のポイントをチェックして選びましょう。

✅ サイズ
- つま先に5〜10mmの余裕がある
- かかとがしっかりフィットして脱げにくい
✅ ソール(底)
- 柔らかすぎず、安定感のあるもの
- すべり止め加工付きで安全
✅ 留め具
- マジックテープ(ベルクロ)で調整可能なタイプ
- 紐靴はまだ難しい子には不向き
✅ 素材・形
- 軽量で通気性がよい
- 足首を適度に支えるデザインが◎
💡「瞬足」「ムーンスター」「IFME」などのブランドは、発達支援の現場でも人気です。
8. よくある質問と答え(Q&A)
立って靴を履く練習は何歳から始めるのがいいですか?
4〜5歳頃が目安です。
体幹が安定してきて、座っての着脱に慣れた頃に始めましょう。片足立ちが苦手で、すぐ転びます。どうすればいい?
壁に手をついたり、手すりの近くで練習しましょう。
遊びの中で体幹を育てることも効果的です。ASD・DCDの子でもできるようになりますか?
はい。段階的にサポートすれば、多くの子ができるようになります。
「順序理解」と「バランス練習」が鍵です。練習時間の目安は?
1回5分以内でOK。
毎日少しずつ、遊び感覚で続けるのがコツです。靴はどんなものを選ぶといいですか?
かかとがフィットして、マジックテープで調整できる靴がおすすめです。
左右をよく間違えるのですが?
左右の靴にシールやマークを貼りましょう。
動物の顔など、合わせると分かるデザインが◎片足立ちのバランスを鍛える遊びは?
ケンケンパ、風船キャッチ、ペンギン歩きなど、ゲーム感覚で楽しく取り組めます。
朝の準備で時間がないときはどうすれば?
平日の朝はサポート多めにして、休日にじっくり練習するのがおすすめです。
練習が嫌になったら?
無理せず中断OK。
「できた」体験を優先して、できた瞬間を具体的に褒めましょう。どのくらいで自分で履けるようになりますか?
個人差はありますが、1〜3か月の継続で「支えあり」→「自立」に進む子が多いです。
🌸 まとめ|楽しく体幹を育てて「できた!」を増やそう
「立って靴を履く」には、体幹とバランスの力が欠かせません。
遊びながらバランス感覚を育て、合った靴を選ぶことで、
子どもが「自分でできた!」という成功体験を積み重ねられます✨
焦らず、毎日少しずつ取り組んで、就学準備を楽しく進めていきましょう👟🌈
立って靴を履くのは、就学前に身につけたい大切なステップ。
焦らず、「できた!」を少しずつ積み重ねることが、子どもの自信につながります。
「毎日の生活の中で、少しずつ練習」していきましょう👟✨
📢次回予告
「『もったいないばあさん てんごくとじごくのはなし』感想|3歳・5歳兄弟が笑って学んだ「分け合う心」」
お楽しみに✨






