はじめに
ヨコミネ式教育法は、幼児期の「やる気スイッチ」を引き出す教育法として注目されています。
「できることは楽しい」「楽しいから練習する」「練習すると上手になる」という好循環を通して、子どもが自ら学ぶ力を育てることが目的です。
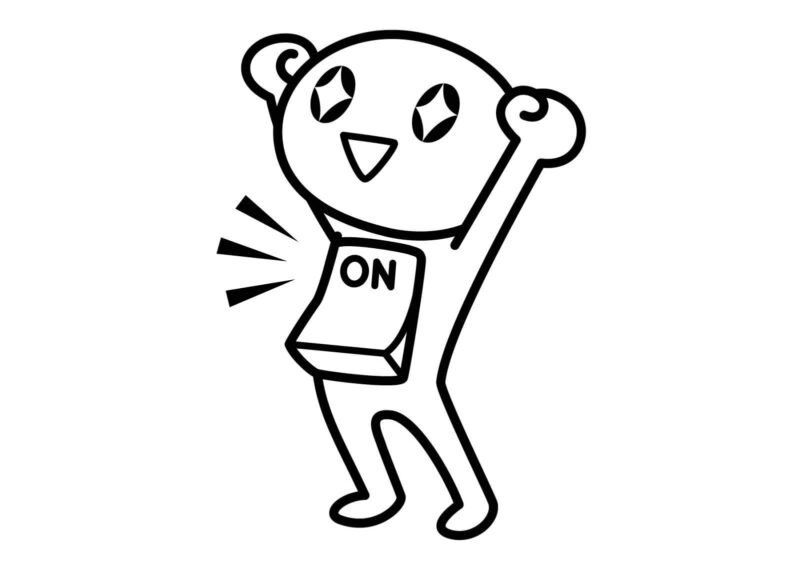
ヨコミネ式を家庭に取り入れることで、子どもの自主性や学ぶ力を伸ばせますが、
すべての子どもに同じ効果があるわけではありません。
性格や興味によって、伸びやすい子・伸びにくい子がいます。
この記事では、家庭でヨコミネ式教育を活かす方法と注意点を、具体例や体験談を交えて解説します。
目次
- はじめに
- ヨコミネ式教育とは?家庭で取り入れる前に知っておきたい基礎知識
- ヨコミネ式で伸びる子・伸びにくい子の特徴
- 家庭でできるヨコミネ式の活かし方
- ヨコミネ式教育のメリットと注意点
- ヨコミネ式で成功した子どもの事例
- ヨコミネ式の「95音」とは?【体験談】
- FAQ(よくある質問)
- まとめ|ヨコミネ式は子どもに合うかがカギ
1. ヨコミネ式教育とは?家庭で取り入れる前に知っておきたい基礎知識
ヨコミネ式教育は、女子プロゴルファー横峯さくらさんの伯父、教育者の横峯吉文氏が考案した幼児教育法です。
その理念は「子どもは自ら学ぶ力を持っている」という考え方に基づき、
無理やり教えるのではなく、子どものやる気を引き出す環境づくりを大切にしています。
ヨコミネ式の4つの柱
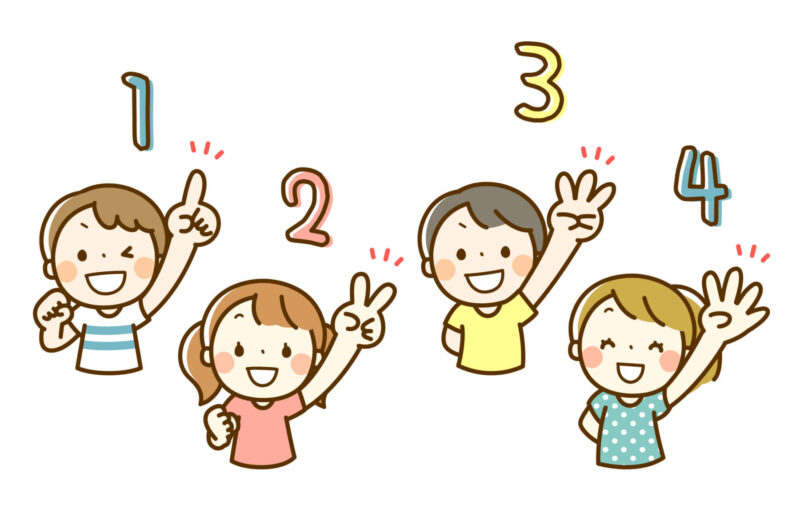
- 学ぶ力:読み書きや計算などの基礎学力を習得
- 体の力:体操や遊びで体力やバランス感覚を養う
- 心の力:挑戦や努力を「楽しい」と感じる気持ちを育てる
- 音楽の力:音楽を楽しむことで集中力や表現力を伸ばす
この4つの力がバランスよく育つことで、子どもの自立心と学ぶ意欲が高まります。
2. ヨコミネ式で「伸びる子」「伸びにくい子」の特徴🌟
ヨコミネ式の効果は、子どもの性格や取り組み方によって大きく変わります。
以下の表にまとめるとイメージしやすいです。
| 特徴 | 伸びる子 | 伸びにくい子 |
|---|---|---|
| 挑戦する気持ち | 新しいことにワクワクして取り組む | 失敗を恐れてやりたがらない |
| 反復練習 | コツコツ繰り返すのが苦にならない | 飽きやすく、続けるのが苦手 |
| 達成感の積み重ね | 「できた!」を楽しみ、次の挑戦へつなげる | うまくいかないと諦めやすい |
| 自己肯定感 | 褒められるとさらにやる気がアップ | できない自分に落ち込みやすい |
| 親の関わり方 | 見守りながらサポートし、達成を一緒に喜ぶ | できないことを責めてしまいがち |
3. 家庭でできるヨコミネ式の活かし方
子どもに合った課題を選ぶ
- 学習・運動・音楽など、子どもの興味や得意分野を優先
- 「少し難しいけどできそう」な課題で挑戦心を刺激
小さな成功体験を積み重ねる
- できたことを褒めて自己肯定感を育む
- 成功体験は次の挑戦への原動力になります
競争よりも自己成長を重視
- 兄弟や友達との比較ではなく、昨日より上手になったことを褒める
- 自分の成長にフォーカスすることで、競争が苦手な子も伸びやすくなる
習慣化と短時間集中の工夫
- 学習は20分以内に区切り、集中力を維持
- 運動や掃除、片付けも生活に取り入れ、自然に習慣化
楽しさを原動力に学ぶ
- 「できる → 面白い → 練習する → 上手になる → 大好きになる」の好循環を意識
- 無理に押し付けず、楽しさを原動力に学習を広げる
4. ヨコミネ式教育のメリットと注意点
メリット
- 自主性や学ぶ力が育つ
- 習慣化や集中力が身につく
- 小学校以降の学習や生活にも活かせる
注意点(デメリット)
- 競争や反復練習がストレスになる場合がある
- 体力や性格に合わない場合は負担に感じることも
ポイント💡
メリット・デメリットは子どもの特性次第。
無理なく楽しめる範囲で取り入れることが大切です。
5. ヨコミネ式で成功した子どもの事例
- 横峯さくら選手
幼少期にヨコミネ式教育を経験し、挑戦心や努力を楽しむ心を育む - 紀平梨花選手(フィギュアスケート)
基礎体力や集中力を幼児期に養い、競技力向上に繋がった
→ 共通しているのは「挑戦を楽しめる」「小さな成功体験を積み重ねられる」ことです。
6. ヨコミネ式の「95音」とは?
ヨコミネ式教育の特徴のひとつに 「95音」 という独自の文字習得ステップがあります。
これは「50音表」のように音を網羅するものではなく、子どもが書きやすい順に並べ替えた95文字です。
目的は「読み書きの入口でつまずかせない」こと。
無理なく書ける順に学ぶことで、子どものやる気を引き出します。
95音の基本ポイント
- 直線 → 角ばった字 → 曲線の多い字 の順に配列
- ひらがな・カタカナ・一部の漢数字が混ざっている
- 「一・|・十・二」など直線だけの字からスタート
- 「あ・む」など曲線が多い字は最後に出てくる
例:先頭は「一|十二エノイテナハフラヨリ」
最後は「あ・む」など曲線系。
95音を使った練習の流れ

- なぞり書き → 2. 見写し → 3. 思い出し書き の3段階
- 1日20分以内を目安に、飽きる前に切り上げる
- 書けたら大げさに褒めることで「またやりたい!」を引き出す
よくある誤解
- 「50音+濁音+拗音=95音」ではない
→ 書く難易度で並んでいるため、カタカナとひらがなが混ざっている。 - 読みを教える表ではない
→ 読みは絵本やカードで。
95音は「書き」のための順序。
95音のねらい
- 「できた!」が続きやすいように直線から始める
- 運筆の発達順に合っている(曲線・交差は後半)
- 「あ」から始めて挫折する子でも、直線文字からなら成功体験を積める
体験談:95音で「苦手な字」も覚えやすくなった
うちの息子は4歳の頃、お絵描きで口のニッコリが描けず、いつも一本線。
「まねしてごらん」と声をかけても上手くできず、もちろんひらがなも書けなくて、親としてとても心配していました。
年中になると幼稚園でお手紙ごっこが流行り、いよいよひらがなの練習に本格的に取り組み始めました。
ところが、普通の50音順で進めると「できない!」と机に向かうのを嫌がり、なかなか前に進めません。💦
特に曲線の多い「あ」「お」「め」「ぬ」はどうしても難しく、とても書けそうにありませんでした。

そんなとき、ヨコミネ式の95音表を知り、直線だけの文字から始めてみることに。
すると「書けた!」という達成感を味わえるようになり、
少しずつ難しい字にも自分から挑戦する姿勢が見られるようになりました。
公式・準公式の参考資料(無料PDFあり)
- 配列が一望できるPDF(一覧/書き込み用)
👉 ヨコミネ式公式:95音表ダウンロード(yokomine.ifep.jp) - 同趣旨の練習シートPDF
👉 ワールド幼児教育センター:95音練習シート(wne.jp)
家庭で取り入れるときは、このような公式配布のプリントを活用するとスムーズに練習が進められます。
最初は「一」「十」といった直線だけの字をノートいっぱいに書いて楽しんでいましたが、
数か月後には、あれほど苦手だった「あ」や「め」も自然に書けるようになったのです。

→ 「できることから始める」仕組みがあるからこそ、子どもは無理なく前に進め、親も安心して見守れました。
7. よくある質問と答え(10個)
何歳からヨコミネ式を始められますか?
3歳頃からが目安で、6歳までに習慣化すると効果的です。
家庭だけでも実践できますか?
はい。読み書き、体操、掃除、片付けなど家庭で取り入れやすい内容があります。
競争が苦手な子も効果がありますか?
小さな成功体験や自己成長に焦点を当てることで、競争が苦手でも伸びます。
ヨコミネ式はどのくらいの時間取り組むべきですか?
学習は1日20分以内、運動や遊びは子どもの体力に合わせて調整してください。
メリットは何ですか?
自主性、習慣化、集中力、学ぶ意欲の向上などが期待できます。
デメリットはありますか?
競争や反復練習が苦手な子には負担になる場合があります。
親の関わり方はどうすればいいですか?
無理に教えず、子どもが楽しめる環境を作り、達成を褒めることが大切です。
どんな子が伸びやすいですか?
挑戦を楽しめる、習慣化が得意、自己肯定感が高い子です。
どんな子が伸びにくいですか?
マイペースで競争が苦手、反復練習やプレッシャーが苦手な子です。
成功例はありますか?
横峯さくら選手や紀平梨花選手など、幼児期に基礎を身につけた子がいます。
まとめ|ヨコミネ式は子どもに合うかがカギ
ヨコミネ式教育は、伸びる子・伸びにくい子が存在する教育法です。
家庭での取り入れ方のポイントは以下の5つです:
- 興味や得意に合わせた課題を選ぶ
- 小さな成功体験を積み重ねる
- 競争よりも自己成長に目を向ける
- 短時間で習慣化を工夫する
- 楽しさを原動力にする
結論
ヨコミネ式は「無理に伸ばす」のではなく、子どもの個性に寄り添いながら伸ばす教育法です。
家庭でこれらを意識することで、子どもの「学びたい気持ち」をしっかり育てられます。
📢次回予告
次回は、「インクルーシブ保育とは?実体験を交えたブログでわかりやすく解説」です。
お楽しみに。
👉 関連記事:
「家庭でできる幼児教育法5選|モンテッソーリ・リトミック」
「【家庭でできる】簡単で楽しいリトミック遊び10選|0歳からOK!」
「着替え・身支度が苦手な理由とサポート法|視覚支援×遊び」
「家庭でできるリトミック遊び10選|0歳から楽しめる発達サポート」
「【保存版】家庭でできるモンテッソーリ|初心者におすすめの実践法」
「【保存版】ヨコミネ式とは?取り入れる方法とメリット・デメリット」






