はじめに
発達検査(WISCなど)の結果や、日々の息子の様子を振り返ってみると、
幼稚園生活で「つまずきやすい場面」が少しずつ見えてきました。

親としては「大丈夫かな?」「どうやって支えたらいいのかな?」と不安になることも多いですが、
同じように悩んでいる方も少なくないのではないでしょうか。
今回は、息子の特性の傾向やこれまでのエピソードをもとに、
幼稚園で起こりやすい困りごとと、そのサポートの工夫についてまとめてみました。
目次
- ルールのある遊びが難しい
- 集団行動が苦手(先生の指示が通りにくい)
- お友達との距離感が近すぎる
- 順番や待つのが苦手
- 力のコントロールが難しい
- 忘れ物や片付けができない
- ダンスや体操が苦手
- 先生に自分から話しかけられない
- 幼稚園での困りごとを支える工夫
- よくある質問(FAQ)|幼稚園生活での困りごととサポート
- まとめ
1. ルールのある遊びが難しい
鬼ごっこや椅子取りゲームなど、ルールを覚えて遊ぶ活動は苦手です。
一度に覚えることが多いと混乱したり、自分のやりたいようにしてしまったり…。
(WISCの流動性推理〈FRI〉の「ルール理解」の弱さが影響している可能性)
🔹工夫
- 絵やカードでルールを「見える化」して伝える
- 家で少人数で練習してから園で挑戦する
2. 集団行動が苦手(先生の指示が通りにくい)
「次はみんなで〇〇するよ」と言われても、自分の好きなことを続けてしまうことがあります。
また、一度に複数の指示を出されると、混乱して動けなくなってしまうことも。
(ASDやADHDの特性により、注意の切り替えや理解が難しいことがある)
🔹工夫
- 「次は何するの?」と本人に質問させて確認する
- 先生に「一つずつ具体的に伝えてください」とお願いする
3. お友達との距離感が近すぎる
遊んでいる時に急に抱きついたり、顔を近づけすぎたりしてしまうことも。
逆に誘われると恥ずかしくなって逃げてしまうこともあります。
(ASD特性として、対人距離の理解が難しい場合がある)
🔹工夫
- ロールプレイで「お友達とのちょうどいい距離」を練習する
- 「これくらいの距離が安心だよ」と具体的に声をかける
4. 順番や待つのが苦手
おもちゃや遊具を使う順番を待てずに横入りしてしまったり、みんなが終わる前に動いてしまうことがあります。
(WISCの視空間〈VSI〉・流動性推理〈FRI〉の弱さや、ADHDの衝動性が影響している可能性)
🔹工夫
- 番号カードを見せながら「次は自分の番だね」と伝える
- 砂時計やタイマーで「待つ時間」を見える化する
5. 力のコントロールが難しい
ふざけているつもりが、強く押したりパンチしてしまうことも…。
鬼ごっこでは捕まえるときに力が入りすぎて相手が転んでしまうこともあります。
(発達性協調運動症〈DCD〉の傾向から、運動の調整が難しいことがある)
🔹工夫
- ぬいぐるみで「やさしいタッチ」を練習する
- 力加減をゲーム感覚で身につける
6. 忘れ物や片付けができない
持ち物をどこに置いたか分からなくなったり、遊んだ後に片付けられないことが多いです。
(WISCの視空間認知〈VSI〉やASD・ADHDの特性が影響している可能性)
🔹工夫
- 「帰る前にチェックリストを見る」習慣をつける
- 片付けの手順をカードで示し、視覚的に分かりやすくする
7. ダンスや体操が苦手
運動会や発表会などで、みんなと同じ動きを覚えるのはハードルが高いです。
振り付けやフォーメーションが覚えられず、周りと違う動きをしてしまうことも。
(WISCの視空間認知〈VSI〉が弱い特性と関連する可能性)
🔹工夫
- 動画を見ながら1ステップずつ練習する
- 動きを分けて繰り返し、少しずつ定着させる
8. 先生に自分から話しかけられない
困っていても「どう言えばいいか分からない」ため、黙ってしまうことがあります。
(ASD特性として、対人コミュニケーションの始め方が難しい場合がある)
🔹工夫
- 「困った時に言うセリフ」を練習
(例:「先生、分かりません」「手伝ってください」) - カードや合図を用意して、声に出しづらいときに使えるようにする
9. 幼稚園での困りごとを支える工夫
息子の場合、
- 視覚的にルールや手順を示す
- ロールプレイで練習する
- チェックリストやカードで確認する
- 先生や周りの大人に協力してもらう
といった工夫が、安心材料になりやすいと感じています。

10. よくある質問(FAQ)|幼稚園生活での困りごととサポート
発達障害やグレーゾーンの子は、幼稚園でどんなことで困りやすいですか?
ルールのある遊び、集団行動、順番を待つこと、
お友達との距離感、ダンスや体操などの模倣活動が苦手になることが多いです。
また、忘れ物や片付け、先生に助けを求めることも難しいケースがあります。WISCの結果と幼稚園での困りごとは関係ありますか?
はい。
例えば「ワーキングメモリー」が弱いと指示を覚えにくい、
「処理速度」が低いと作業が遅れるなど、
検査結果が日常の困難さに直結することがあります。
検査結果を知ることで、支援の方向性が見えやすくなります。幼稚園で「ルールを守れない」と言われたらどうすればいいですか?
まずは家庭で少人数でルール遊びを練習したり、
絵カードやチェックリストでルールを「視覚化」すると効果的です。
園の先生に協力をお願いし、遊びに参加できるようサポートしてもらうと安心です。集団行動が苦手な子に家庭でできる練習はありますか?
「お片付けの歌で一緒に片付ける」など、
小さな集団行動を家庭で取り入れることが有効です。
遊びの中で「次は〇〇するよ」と予告し、
一つずつ行動を促す練習を重ねると幼稚園でも取り組みやすくなります。お友達との距離感が近すぎてトラブルになります。どうしたらいいですか?
ロールプレイが効果的です。
ぬいぐるみを使って「ここまで近づくと安心だよ」と練習したり、
実際に親子で立って「適切な距離」を体感するのもおすすめです。順番を待てずにトラブルになるときの工夫は?
砂時計やタイマーで「待つ時間」を可視化したり、
「〇番目だよ」とカードで示すと理解しやすくなります。
待つ間にできる「小さなタスク」を用意しておくのも効果的です。幼稚園での忘れ物や片付けが多い場合、家庭でできることは?
「持ち物チェックリスト」を用意し、毎日一緒に確認する習慣をつけるとよいです。
また、片付ける場所を固定し、色やマークで分かりやすくすると成功体験につながります。ダンスや体操が覚えられない子にどう接すればいいですか?
「完璧に同じ動きをすること」を求めず、楽しむことを優先しましょう。
動画を見ながら1ステップずつ練習すると負担が減ります。
先生にも「できる部分を褒めてほしい」と伝えると安心です。先生に助けを求められない子にどう声かけをすればいいですか?
家で「困った時に言うセリフ」を一緒に練習するのが効果的です。
カードに「先生、分かりません」と書いて持たせる方法もあります。
徐々に「カード → 声」でステップアップできると安心です。幼稚園での困りごとは、小学校でも続きますか?
すぐに解決することは少なく、特性として小学校以降も続くことがあります。
ただし、支援や工夫を積み重ねることで「できること」が増えていく子も多いです。
早めにサポートを始めることが、将来の安心につながります。
まとめ
幼稚園生活では、
- ルールを守ること
- 順番や待つこと
- お友達との距離感
- 集団での模倣(体操・ダンス)
- 先生に助けを求めるスキル
などが特に難しくなりやすいです。
でも「できない」ではなく、
👉 「工夫すれば少しずつできるようになる」
👉 「サポート次第で安心して過ごせる」

という視点を持つことが大切だなと感じています。
そして何より、親だけで抱え込まなくて大丈夫。
園の先生や支援機関に相談しながら、一緒に工夫していけば良いのです。
同じように悩む親御さんが「一人じゃない」と感じられるきっかけになれば嬉しいです😊✨
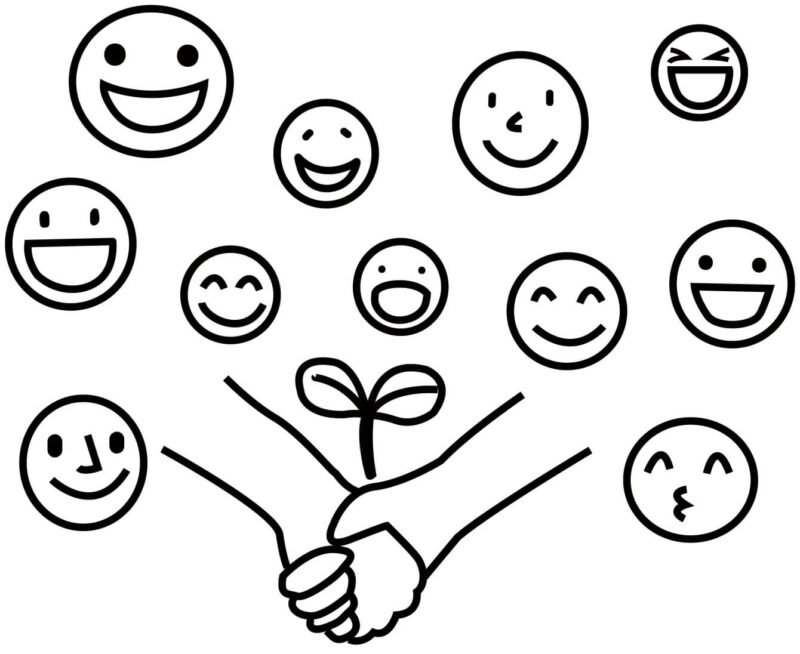
📢次回予告
次回は、「就学前チェックリスト(年長向け)|小学校入学までに必要な力と家庭での練習法」をお届けします。
お楽しみに!






