はじめに専門的な個別支援がある児童発達支援施設を選んだ理由🧒✨
息子が児童発達支援施設に通い始めて、気づけば1年が経ちました。
数ある施設の中から今の場所を選んだ一番の決め手は、言語聴覚士(ST)や理学療法士(PT)といった専門職が常駐しており、
集団活動に加えて、毎回個別トレーニングがしっかり受けられる点でした。

家庭でもサポートを続けながら、息子は少しずつ言葉や体の使い方に変化が見られるように🌱
毎日の積み重ねが、着実な成長につながっていると実感しています。
この記事では、
- 児童発達支援施設と幼稚園の違いは?
- ST・PTによる個別支援の具体的な内容とは?
- 子どもだけでなく親にも与える安心感とは?
といった視点から、わが家のリアルな体験をお伝えしていきます。
これから児童発達支援を検討されている方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです😊
目次
- 【児童発達支援と幼稚園の違い】行き渋りが改善した理由とは
- 【授業参観で実感】児童発達支援と幼稚園の手厚いサポートの違い
- クラス規模と支援体制の違い
- 参観で感じた幼稚園と児童発達支援の違い
- 【感想まとめ】児童発達支援は「安心できる環境+専門的な支援」が魅力
- 【ST/PTの専門支援】息子の発達に寄り添うプロのサポート
- 言語聴覚士(ST)による言葉とコミュニケーション支援
- 理学療法士(PT)による体の使い方・姿勢の改善支援
- 【多彩な支援プログラム】楽しみながら成長する毎日
- 実際の活動内容(一部)
- 【児童発達支援の成果】息子の前向きな変化と成長
- 【親としての想い】息子の成長を支える環境に出会えたことへの感謝
- 【長期休暇の過ごし方】発達支援施設の活用で親子に笑顔を
- よくある質問
- まとめ
1. 【児童発達支援と幼稚園の違い】行き渋りが改善した理由とは?🚌💨
以前は、息子が幼稚園に行くことを嫌がり、毎朝「行きたくないよ」涙ぐむ日が続いていました。
ところが、この施設では通い始めて間もない頃から、息子は笑顔で「行ってくるね!」と元気に出発できるように✨
あまりの違いに驚き、スタッフの方に理由をたずねると、こんな答えが返ってきました。
「私たちは一人ひとりに合わせて、活動内容を丁寧に説明する時間を設けているんです。それが子どもたちの安心感につながっているんですよ😊」
確かに息子は、「今日は何するの?」が分かっていると安心するタイプ。
この施設では、事前にスケジュールを伝える「予告」や、やさしい声かけを大切にしてくれているため、不安が減り、通うことが楽しみになったようです。

2. 【授業参観で実感】児童発達支援と幼稚園の手厚いサポートの違い👀📚
👦クラス規模と支援体制の違い
| 項目 | 幼稚園 | 児童発達支援施設 |
|---|---|---|
| クラス規模 | 3歳:15名以下 4・5歳:25名以下(2024年基準) | 利用者10名以下にスタッフ2名以上 (10名を超える場合は5名増ごとに1名追加) |
| スタッフ体制 | 1クラスに担任1名 | 少人数での個別対応が可能 |
👀参観で感じた幼稚園と児童発達支援の違い

- 参観の頻度
幼稚園では学期ごとに1回、発表会や運動会などのイベント時にも参観の機会があります。
一方、児童発達支援施設では、希望者に向けて毎月の参観が実施されており、私は3か月に1度ほど参加しています。 - 幼稚園の参観では…
- 1人の先生が多くの生徒をまとめるため、対応が大変そうに見えました。
- それでも先生方が一生懸命に取り組む姿や、多人数をまとめるスキルには感心しました。
- 1人の先生が多くの子どもをまとめており、全体指示が中心。
- 息子は先生の声かけ(集団指示)を聞き逃して戸惑う場面もありました。
- 緊張しながらもがんばる姿に成長を感じる一方で、「もう少しサポートがあれば…」と思う場面もありました。
- 児童発達支援施設の参観では…
- 先生が子ども一人ひとりに合わせて声かけし、活動のサポートをしてくれます✨
- 息子も安心して発言したり、のびのびと遊びに参加できている様子が見られました。
- スタッフが子ども一人ひとりに声をかけ、「できたね!」「もう一回やってみよう」など肯定的なサポートが充実✨
- ただの遊びに見える活動にも、発達支援のねらい(支援目標)がしっかりと組み込まれている点が印象的でした。
🎮「遊び」×「支援目標」で楽しみながらスキルアップ!
例えば「お買い物ゲーム」では、こんなスキルが自然に育まれていました👇
- 🧠記憶力:買うものを覚える
- 📋手順理解:順番を守って行動する
- 🤝社会的スキル:距離感・順番待ち
- 🗣コミュニケーション:店員役との会話
- 🔢数の概念:お金を払う
- 🏆達成感:最後までやりきる喜びを味わう
遊びの中に「支援の目的」が自然と組み込まれていることに、専門性の高さを感じました🎯
✅【感想まとめ】児童発達支援は「安心できる環境+専門的な支援」が魅力🌱
幼稚園では1人の先生が多くの子どもたちをまとめる必要があり、とても大変そうでした。
それでも、先生方の努力と工夫には感謝の気持ちでいっぱいです👏
一方で、児童発達支援施設では——
- 少人数制&手厚いスタッフ配置
- 特性に合わせた個別対応
- 遊びの中に支援目標が組み込まれたプログラム
このような支援体制が整っていることで、息子の小さな変化や困りごとにもすぐに気づいて対応してもらえる安心感があります。
また、活動はすべて支援目標に基づいて設計されており、子どもの発達段階や特性に合わせた丁寧な声かけが日常的に行われています。
その結果、息子は安心して自分らしく過ごせるようになり、自信を持って活動に取り組む姿が増えてきました。
「この施設を選んで本当によかった」──そう実感できるのは、息子が笑顔で成長している今の姿があるからです🍀
3. 【ST/PTの専門支援】息子の発達に寄り添うプロのサポート
施設には、言語聴覚士(ST)や理学療法士(PT)が在籍し、息子の発達をサポートしてくれています。
言語聴覚士(ST)による言葉とコミュニケーション支援🗣️
施設には言語聴覚士(ST)が在籍しており、言葉の発達に関する専門的な支援を行ってくれています。
具体的な支援内容:
- 吹きゴマ遊びや絵本の読み聞かせ
- 言葉あそびによる語彙力・表現力の向上
- 吃音への理解と個別相談の機会の提供
- 遊びを通じたコミュニケーションスキルの向上

息子はこれらの活動を通じて、言葉の使い方やコミュニケーションスキルを少しずつ身につけています。
吃音を抱える息子にとって、「困ったときにすぐ相談できる場所がある」ことは、私自身にとっても大きな安心材料です。
理学療法士(PT)による体の使い方・姿勢の改善支援🏃♂️
理学療法士(PT)によるサポートでは、体幹や姿勢の強化に向けた運動を取り入れています。
プログラム例:
- バランスボールやジャンプを使った体幹トレーニング
- 姿勢改善を目指したダンス・運動遊び
- 日常生活に役立つ「からだの使い方」を学ぶ動き遊び

これらを通して、息子は姿勢の安定やバランス感覚の向上に少しずつ取り組めるようになりました。
専門家のサポートがあるからこそ、「ここまで来られた」と思える場面が増えてきました。

4. 【多彩な支援プログラム】楽しみながら成長する毎日🌈
この児童発達支援施設では、子どもたちが「遊びの中で自然に学べる」よう工夫された活動が数多く用意されています。
実際の活動内容(一部):
- 製作活動・知育あそび・ルール遊び
- ごっこ遊び・クッキング・椅子とりゲーム
- リトミック・ビジョントレーニング・おくちことば遊び
- 季節行事(夏祭り・ハロウィン・クリスマスなど)

息子はこれらの活動を通じて、「できた!」「楽しい!」という成功体験を積み重ねています😊
5. 【児童発達支援の成果】息子の前向きな変化と成長
児童発達支援施設での丁寧な関わりや声かけの積み重ねにより、息子には少しずつ前向きな変化が見られるようになってきました。
以前は…
- 「できない」「難しい」といったネガティブな発言が多かった
- 自分に自信が持てず、新しいことに挑戦するのが苦手だった
私自身、「どう声をかければ前向きになれるんだろう」と悩んだ日もあります。
でも今では、驚くほど成長を感じる場面が増えてきました🌱
今では…
✅ 「やってみる!」と、自信をもって活動に取り組めるように
✅ 距離感を保ちながら、落ち着いて友達と関われるように
✅ 手先も少しずつ器用になり、集中力もアップ
✅ ダンスや運動も楽しめるようになり、姿勢も改善中
✅ 吃音が出ても「大丈夫」と安心できる環境がある
✅スタッフから「リラックスして楽しんでいる様子」が伝えられることも増えた
ある日、家で息子が笑顔で児童発達支援で行っている「朝の会」のダンスを見せてくれたんです🕺
かつては避けていた活動を、今では笑顔で披露してくれる——その姿に、胸がいっぱいになりました😊

支援の力で、「苦手」が「楽しい!」に変わる。
そんな小さな一歩一歩が、親としてうれしく、支援の大きな力を感じています😊
6. 【親としての想い】息子の成長を支える環境に出会えたことへの感謝🍀
息子が日々前向きに成長しているのは、児童発達支援という環境の力が大きいと感じています。
「できない」が「やってみよう」に変わり、
「不安」が「安心」に変わった今、
親としても心からこの場所に感謝しています。
これからも一歩ずつ、新しい挑戦を楽しみながら、息子らしい成長を見守っていきたいと思います🌸
7. 【長期休暇の過ごし方】発達支援施設の活用で親子に笑顔を😊
夏休みや冬休みなどの長期休暇、
家で過ごす時間が増えると、子どもも退屈したり、親の負担が大きくなったりしますよね。
そんな時、児童発達支援施設の活用が、わが家にとって心強い味方になっています。
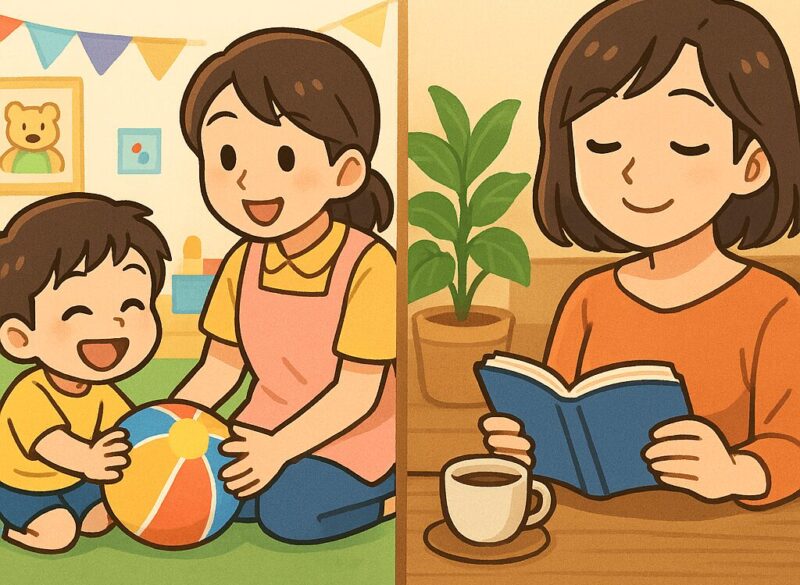
🌈 子どもにとってのメリット
- 安心できる環境で、楽しい活動に参加できる
- 規則正しい生活リズムをキープできる
- お友達やスタッフとの関わりから社会性を育める
🌱 親にとってのメリット
- 「安心して預けられる場所がある」ことの心のゆとり
- 家事や仕事、自分のリフレッシュ時間が持てる
- 兄弟児との時間や、自分自身のケアにもつながる
私自身、息子が施設で楽しく過ごしてくれているおかげで、
「今日は1人でゆっくりできた」「少し気持ちに余裕ができた」と感じる日が増えました。
🧡 家族みんなが笑顔になれる時間
長期休暇中も、無理に予定を詰めることなく、
支援の力を借りながら穏やかに過ごすことができる——これが、わが家の大きな安心です。
親子それぞれが「自分の時間」を持てることが、
家族の心と体の健康を守るカギ🔑になっています。
8. よくある質問
児童発達支援施設とは何ですか?
発達に課題のあるお子さんを対象にした専門的な支援を行う施設です。
言語聴覚士(ST)と理学療法士(PT)の役割は何ですか?
STは言語能力やコミュニケーションの支援を、PTは身体能力や姿勢改善をサポートします。
児童発達支援と幼稚園の違いは何ですか?
個別対応が手厚く、専門的なプログラムが組まれている点が大きな違いです。
費用はいくらくらいですか?
収入に応じて自治体が助成を行うため、実質負担額は家庭により異なります。
また、一定の条件を満たすと無償化の対象となります。
詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。専門家の支援はどのように受けられますか?
定期的な個別トレーニングや相談の場を通じて受けられます。
施設利用にあたり条件はありますか?
児童相談所や医師の診断が必要な場合があります。
ただし、一部の施設では診断が不要で、相談ベースで利用できる場合もあります。
具体的には、地域や施設の方針により異なるため、事前の問い合わせをおすすめします。どのくらいの頻度で通えますか?
施設により異なりますが、週1~5回程度が一般的です。
最大23日間/月 利用できる場合もあります。
詳細は施設との相談で調整可能です。保護者へのサポートはありますか?
親向けの勉強会やカウンセリングが行われることが多いです。
施設利用で子どもはどんな成長が見られますか?
言語、身体、社会性の向上など、多方面での成長が期待されます。
通所にはどのような準備が必要ですか?
通所前に必要な書類や持ち物は施設から案内されます。
具体的には以下のようなものが挙げられます。- 必要書類:健康診断書、自治体からの利用決定通知など
- 持ち物:お子さんの日常的な用品(おむつ、着替え、タオルなど)
また、保護者の事前相談では、以下の内容を話し合います。
- 子どもの困りごとや支援の目標
- 家庭での様子や希望するサポート内容
この相談が、より適切な支援プランを作成する基礎になります。
まとめ児童発達支援で親子が得られた安心と成長🌈
この1年を振り返ると、専門職による質の高いプログラムを受けられたことは、
息子の発達だけでなく、私自身の「安心感」と「信頼感」にもつながったと感じています。
「今日は何するのかな?」と毎回ワクワクしながら通う息子の姿を見ると、
親としても本当に嬉しく、心からこの施設を選んでよかったと思えます🌟
これからも、息子の成長を温かく見守りながら、
私自身も一緒に成長していけたら——そんな気持ちで日々を過ごしています。
👩👦児童発達支援の利用を考えている方へ
まずは見学や相談から始めてみると、自分の子に合った支援の形が見えてくるかもしれません。
🔜次回予告
「【体験談】1時間(短時間集中型)の児童発達支援施設で息子が得た成長」もお楽しみに!






