はじめに
幼稚園や保育園では、毎日子ども同士の関わりが生まれます。
その中で「お友達とトラブルになった」「先生から連絡があった」という経験は、多くの親が直面する悩みです。

この記事では、私の息子が園で起こしたトラブルの体験をもとに、
子どもの心理や発達特性を踏まえた考え方、家庭でできる具体的なサポート方法を紹介します。
目次
- 園で起こる「お友達トラブル」とは?よくあるケース
- 【体験談】息子が鬼ごっこ中に友達を叩いてしまった出来事
なぜその場から逃げるの?子どもの心理と発達特性
どうして理由を話せないの?言葉と感情の整理の難しさ
不器用さが関係する?バランス・力加減の課題
本当にわざとじゃなかった?子どもの気持ちの理解
友達との距離感や勝ち負けの気持ちとの関係 - 今回の出来事から私自身が学んだこと(親目線)
- 園でのトラブルを減らすために家庭でできる具体的な工夫
- 先生や園との連携で大切なポイント
- 幼稚園・保育園でのお友達トラブル【よくある質問Q&A】
- まとめ|「トラブルも学びの一歩」
1. 園でよくある「お友達トラブル」とは?
園生活で起きやすいトラブル例:
- 鬼ごっこや遊び中に押す・叩くなどの接触
- おもちゃや席の取り合い
- ルールを守れず喧嘩になる
- 謝れない・言い訳ばかりしてしまう
小さなすれ違いでも、子どもにとっては大きな出来事。
繰り返すと「うちの子、大丈夫かな?」と心配になりますよね。

2. 【体験談】息子が鬼ごっこ中に友達を叩いてしまった出来事
ある日、幼稚園の園庭で鬼ごっこをしていた息子が、突然お友達の顔を叩いてしまう出来事がありました😨。
先生からの電話を受けて園に駆けつけると、
息子は「してない」と言い訳…。
先生が「さっき謝ったよね?」と聞いても黙り込んでしまい、私は戸惑いました。
先生によると――
- 先生は目撃はしていなかったが、周りや当事者の話を聞くと…
- 遊んでいた途中、滑り台付近で突然お友達を叩いてしまった
- そのまま逃げてしまったが、別のお友達に連れられて先生のもとへ
- 「どうしてそんなことをしたの?」と聞いても答えられなかった
- 最終的に謝り、お友達とも一応仲直りできた
とのことでした。
その後、私はお相手の保護者の方に謝罪🙏。
息子も叱りましたが、その夜になってようやく
「実はこけそうになって当たっちゃっただけなんだ」
「一瞬謝ったけど、大きな声で泣いたからビックリして逃げたの」
「わざとはしてないんだよ」と教えてくれたのです。
そのとき私の頭に浮かんだ疑問💭
- どうしてその場から逃げるの?
- なぜ理由を話せないの?
- 不器用さが関係しているのかな?
- 本当にわざとじゃなかったのかな?
- 負けたくない気持ちや、友達との距離感の問題なのかな?
なぜその場から逃げるの?子どもの心理と発達特性

子どもはトラブルが起きると「どうしたらいいか分からない!」とパニックになりやすいです。
特に発達特性のある子は、突発的な出来事への対応が難しいことも。

よくある反応
- 想定外の出来事にフリーズ or 逃げてしまう
- 「怒られる!」と不安になり本能的に逃走行動をとる
- 瞬時に「正しい対応」を選べず、逃げるのがラクな選択肢になる
✨ 対策
- 「ぶつかったら『ごめんね』と言う」というシンプルなルールを決めておく
- ロールプレイ(ぬいぐるみ遊びなど)で繰り返し練習する
どうして理由を話せないの?言葉と感情の整理の難しさ
息子がその場で説明できなかったのは、「気持ちと言葉を整理する力」が追いつかなかったからだと感じます。

考えられる理由
- 混乱して言葉が出ない
- 「順序立てて説明する」ことが難しい
- 責められていると感じて頭が真っ白になる
✨ 対策
- 「わざとじゃない、ごめんね」と言えるフレーズを用意しておく
- 親や先生は「こけそうになったの?」などYes/Noで答えやすい質問をする
不器用さが影響?バランスや力加減の課題
「こけそうになって当たっただけ」という息子の言葉から、不器用さも関係していたと思います。
実際に後々、DCD(発達性協調運動障害)の診断を受けることに。
バランスや力加減が苦手さもトラブルに影響しました。

考えられる背景
- バランスを崩しやすい(協調運動が苦手)
- 力加減が難しく、とっさの動きが強く出てしまう
✨ 対策
- バランスボール・平均台・トランポリンなどで体幹を鍛える
- 力加減を学べる遊び(風船キャッチ・紙をやさしくちぎる・スライムを潰さず触る)
関連記事もチェック
DCD(発達性協調運動障害)と発達障害へのアプローチ事例
子どもの不器用さが気になる?発達性協調運動症(DCD)の基礎知識
【体験談】発達検査WISC(ウィスク)の流れと結果|就学判断・診断の参考に
本当にわざとじゃなかったのかな?子どもの気持ちをどう見る?
「わざと叩いたのでは?」と親はどうしても不安になりますよね😔。
でも、子どもの行動には「本当にわざと」か「偶然」かを見極めにくいケースが多いです。
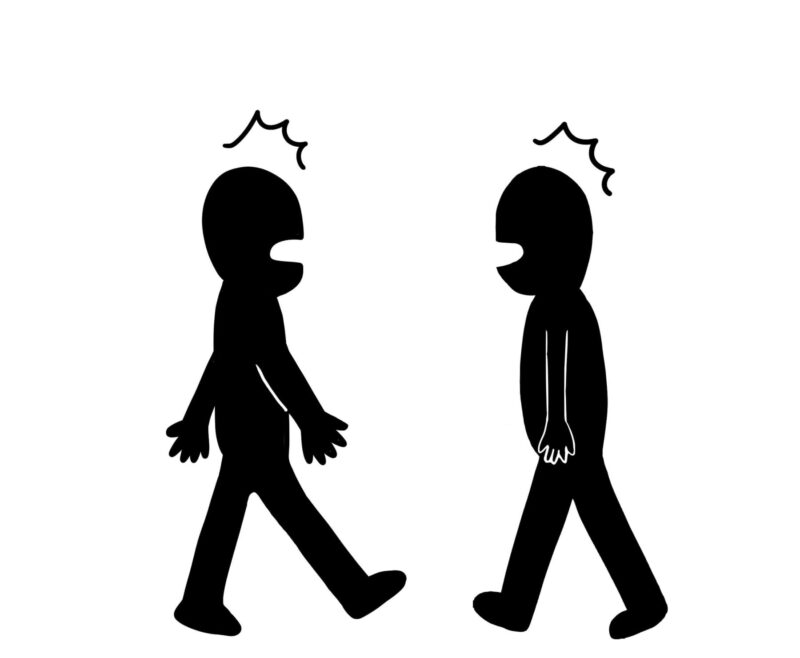
考えられる背景
- 転びそうになってとっさに手が出ただけ
- 遊びの延長で「力加減」ができずに強くなってしまった
- 自分でも何が起きたのか整理できていない
✨ 対策
- 「次からどうすればよかったかな?」と未来につながる声かけをする
- 「叩いた=悪い子」と決めつけず、状況や気持ちを一緒に振り返る
- 言葉にできないときは、絵やジェスチャーを使って表現してもOKにする
👉 「わざとじゃないこともある」けれど、「どうすればよかったかを学ぶこと」が一番大事です。
負けたくない気持ちや友達との距離感の問題なのかな?
園でのトラブルには、「負けたくない!」」「もっと遊びたい!」という気持ちが影響していることもあります💦。

また、友達との距離感が近すぎて、思わず手が出てしまうケースも珍しくありません。

考えられる背景
- 勝ち負けにこだわって感情が爆発する
- 「もっと一緒に遊びたい!」気持ちが強すぎてコントロールできない
- 相手との適切な距離感がまだつかめない
✨ 対策
- 勝ち負け以外の楽しみ方(協力プレイの遊びなど)を経験させる
- 「近すぎると相手は嫌がる」というソーシャルスキルを少しずつ教える
- 先生や親が「遊びの切り替え」をサポートする
👉 友達トラブルも「社会性を学ぶ大切な過程」。
焦らず少しずつ練習していけば、子どもは関わり方を身につけていけます🌱。
🌸 まとめ:お友達トラブルから学べること
息子の「鬼ごっこ中に友達を叩いてしまった」体験から学ぶ、
5つの疑問と対策、保護者として大切にしたいこと💡
1️⃣ なぜその場から逃げるの?
👉 想定外の出来事にパニック → 「怒られる!」と感じて逃げてしまう
✨ 対策:シンプルなルール作り & ロールプレイで練習
2️⃣ なぜ理由を話せないの?
👉 感情と言葉の整理が追いつかない → 責められると頭が真っ白に
✨ 対策:「ごめんね」の定型フレーズ準備 & Yes/No質問でフォロー
3️⃣ どうしてそんなに不器用なの?
👉 バランス・力加減が苦手で、予想外に強く当たってしまう
✨ 対策:風船キャッチ・バランスボール・力加減遊びで練習
4️⃣ 本当にわざとじゃなかったのかな?
👉 「転んで当たった」など偶然の可能性も。大切なのは「次にどうするか」
✨ 対策:状況を一緒に振り返り、未来につながる声かけを意識
5️⃣ 負けたくない気持ちや友達との距離感が原因?
👉 勝ち負けにこだわったり、距離感が近すぎて手が出てしまうことも
✨ 対策:協力遊びで楽しむ経験・ソーシャルスキル練習・遊びの切り替えサポート
✅ ここでの学び・保護者として大切にしたいこと
- トラブル=悪いことではなく「学びのチャンス」
- 「叩いた=悪い子」と決めつけず、状況を一緒に振り返る
- 先生と連携しながら、情報を共有し子どもの成長を支える

👉 子どもはまだ「社会のルール」を学んでいる途中。
繰り返し経験しながら「こうすればよかった!」を少しずつ身につけていきます。
焦らず、あたたかく見守りながらサポートしていきたいですね🌱✨
3. 今回の出来事から私自身が学んだこと(親目線)
今回の「園でのお友達トラブル」を通して、
子どもだけでなく、「親である私自身」もたくさんの学びがありました。

👩👦 子どもへの気持ちと反省
正直、最初は「なんでそんなことをしたの!」と頭ごなしに叱ってしまいました💦。

でも夜になって息子から事情を聞いたとき、「本当にわざとじゃなかったのかもしれない」と思えたのです。
もっと寄り添って、「どうしたの?」「なにがあったの?」と気持ちを聞いてあげればよかったと反省しました。
さらに、「もっとできてほしい」「どうして普通にできないの?」と強く思いすぎると、
結局は息子も私自身も苦しくなってしまいます。
だからこそ今は、「この子はこの子なりに一生懸命がんばっている」と受け止め、認めてあげることにしました🌱。
保護者への謝り方:トラブル時に伝える3つのポイントと会話例🤝
子ども同士のトラブルが起きたとき、相手の保護者への対応はとても悩ましいものです。
「うちの子も…」と弁解したくなることもありますが、
謝罪の場面では相手の安心感を最優先に考えることが大切だと学びました。
私が意識しているのはこの3点です👇

1. 事実をそのまま伝える
感情や推測を交えず、「何が起きたのか」を事実ベースで伝えます。
例:
- 「今日の公園遊びで、息子がボールを投げてしまい、〇〇君に当たってしまいました。」
- 「おやつの時間に、うちの子が〇〇君のおやつを取ってしまいました。」
→ 事実を整理して伝えることで、相手は状況を冷静に理解できます。
2. 子どもの弁解をせず、謝意を伝える
「悪気はなかった」と説明したくなる気持ちはありますが、謝罪はシンプルに。
例:
- 「ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。」
- 「〇〇君に嫌な思いをさせてしまい、すみません。」
→ 弁解が入ると相手は不安やモヤモヤを感じることがあります。
3. 今後のサポートや対応を一言添える
謝罪のあとに、「同じことが起きないようにどう対応するか」を簡単に伝えると安心感が増します。
例:
- 「今後は遊ぶ前にルールを一緒に確認するようにします。」
- 「家でも危ない場面がないか声かけしていきます。」
- 「ケンカになったらすぐに仲介するよう声かけします。」
→ 相手は「ちゃんと配慮してくれている」と感じ、トラブル後も関係がスムーズになります。
✅ 謝罪ポイントまとめ
- 事実を淡々と伝える
- 弁解せず、誠意を込めて謝る
- 今後の対応やサポートを簡単に伝える
→ この3つを心がけるだけで、相手も少し安心してくださると感じました。
謝罪は「すみません」と言うだけではなく、状況整理と今後の対応を添えることで、相手も安心できます。
🏫 幼稚園との関わりから学んだこと
先生からのお話は「100%息子が悪い」というニュアンスに聞こえてしまい、正直ショックを受けました。
どこか「レッテルを貼られているのでは?」と感じてしまったのです。
でも一方で、先生方は毎日たくさんの子どもを見守り、いつも親切に接してトラブルをフォローしてくださっています。
だからこそ、
私自身が「もっとこうしてほしい」と無意識のうちに求めすぎていたのだと気づかされました。
園に求めるものは療育先での専門的な支援とはまったくの別物 だということを改めて認識。
その結果、園の対応については、
「園に過度な期待をしすぎないこと」「でも感謝の気持ちは忘れないこと」
― そういうバランスが大切なのだと気付かされました。
🌟 まとめ:感謝とこれから
園でのトラブルは、親にとっても大きな心の揺れを伴います。
でも「叱る」だけでなく「寄り添う」こと、「期待」ではなく「理解」することが大切なんだと気づけました。
そして、園の先生方が支えてくださっていることにも改めて感謝しています。
👉 子どもとの関わり方も、園との付き合い方も、完璧じゃなくて大丈夫。
少しずつ「親も一緒に成長していく」気持ちで向き合っていけたらと思います😊。
4. 園でのトラブルを減らすためにできる家庭での工夫
- 家庭で「トラブル時の行動パターン」を決めて練習
- 力加減を学ぶ遊びを日常に取り入れる
- 子どもが気持ちを言いやすい環境を整える
5. 先生や園との連携で大切なポイント
家庭だけで抱え込まず、園と連携することも大切です。
- 先生に家庭での工夫を伝える
- トラブル時の対応を園と共有する
- 子どもの特性を理解してもらうことで安心につながる
6. 幼稚園・保育園でのお友達トラブル【よくある質問Q&A】
子どもがお友達を叩いてしまいました。どう対応すればいいですか?
まず相手に謝罪し、落ち着いたら家庭で振り返り。
ロールプレイで練習すると効果的です。うちの子はトラブルが起きると逃げてしまいます。
逃げる」は防衛反応。叱るより行動パターンを教えるのが効果的です。
叱るより「こういう時はこうすればいい」と行動パターンを教えることが効果的です。トラブルの理由をうまく説明できません。発達障害の可能性ですか?
可能性はゼロではありませんが、年齢や経験の少なさによることも多いです。
言葉の整理が苦手な子には、Yes/Noで答えやすい質問や短いフレーズを準備してあげましょう。力加減ができず、すぐに強く叩いてしまいます。改善できますか?
はい。
風船遊び・紙をやさしくちぎる・バランスボールなどで調整を学びましょう。先生から「またトラブルがありました」と報告されるのがつらいです。どうしたら?
落ち込む必要はありません。
先生と連携し、家庭での工夫を伝えることで「一緒にサポートしていく」姿勢が大切です。謝れない子どもにはどう教えればいいですか?
「ごめんね」を強制するより、
絵カードや人形遊びで「ぶつかったらどうする?」を体験的に教えると自然に身につきます。トラブルが多いと友達ができないのでは?
その可能性もありますが、練習とサポートで改善できます。
親や先生が「仲直りの場」を作ってあげることで、関係を築くきっかけになります。家でできる具体的な練習法はありますか?
ロールプレイ、力加減遊び、Yes/No質問練習などが有効です。
短時間でも繰り返すことがポイントです。発達障害がある子はトラブルを起こしやすいですか?
ASDやADHDなどの特性がある子は
「予測不能なこと」「感情の整理」「力加減」が苦手なことがあります。
ただし支援と環境調整で大きく改善できます。親がどこまで介入すべきですか?
基本は子ども同士の学びに任せつつ、必要な時はフォローする姿勢が大切です。
園の先生と相談し、介入のバランスを決めると安心です。
まとめ|「トラブルも学びの一歩」親子で一緒に成長していこう
園でのお友達トラブルは、子どもにとって避けられない経験です。
大切なのは「どう対応できるようになるか」を少しずつ練習していくこと。
- 逃げる → 「ごめんね」とルール化
- 話せない → 言いやすいフレーズを準備
- 不器用さ → 遊びで力加減を学ぶ
トラブルをきっかけに、子どもが「自分でも乗り越えられる」と自信を持てるようになることが、
何よりの成長につながります😊✨
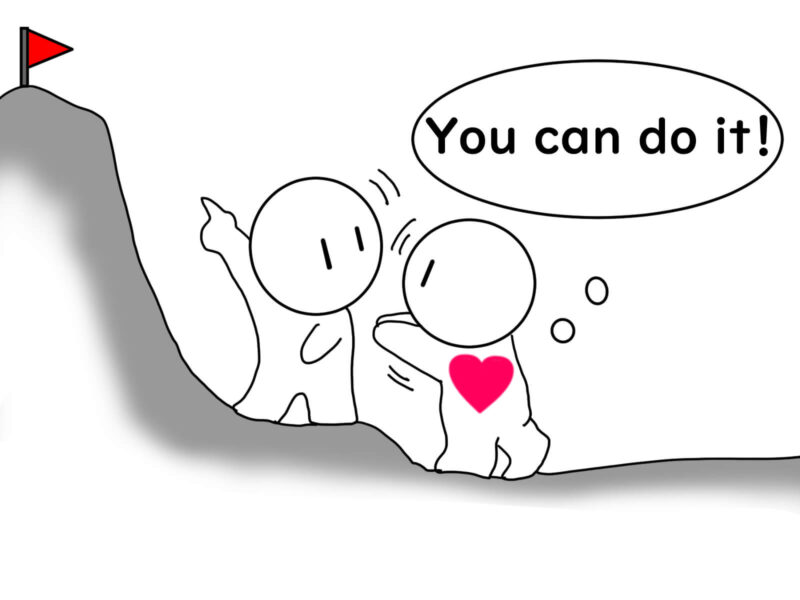
📢次回予告
「幼児が乱暴な言葉を言うときの原因と対応法|子育ての悩み解決ガイド」をご紹介予定です!
どうぞお楽しみに。
関連記事
DCD(発達性協調運動障害)と発達障害へのアプローチ事例
子どもの不器用さが気になる?発達性協調運動症(DCD)の基礎知識
【体験談】発達検査WISC(ウィスク)の流れと結果|就学判断・診断の参考に
【2歳〜4歳向け】七田式えほんの効果|育児ママの実体験レビュー付き
💛感情の切り替えが苦手な子どもに|自己コントロール力8選【療育にも◎】
【保存版】子どもの怒り・パニック対処法|23の感情コントロール遊び
子どもがルールを守らない!家庭でできるしつけと習慣づけの成功例5つ
育児ストレスの原因は「完璧を目指すこと」?比較しない子育てのススメ
【比較しない子育て】才能を伸ばす親の関わり方とは?実体験&4つの工夫






