はじめに
子どもが発達障害と診断されたとき、胸に抱いたのは「育てていけるだろうか?」という不安と、「この子を全力で支えたい」という親としての覚悟。
夫との価値観のズレに戸惑い、「ただ話を聞いてほしいだけなのに…」と心がすれ違う日々。
育児の本を手渡しても読んでもらえなかったり、疲れた顔で「また今度ね」と言われたり…。
「一緒に悩んで、一緒に前を向いてほしい」
そんな気持ちが通じず、孤独を感じていました。
でも、こうした葛藤は私だけではなかったのです。
発達障害のある子どもを育てる家庭では、同じような悩みを抱える人が少なくありません。
本記事では、
- 発達障害育児で親が感じるストレスの正体
- それが夫婦関係や離婚率に与える影響
- 関係修復のためにできる具体的な方法
これらを私自身の体験も交えて、リアルにお伝えします。
「うちだけじゃなかった」と、少しでも心が軽くなるきっかけになれたら嬉しいです。
目次
- 発達障害育児と親のストレス|離婚・夫婦関係悪化の4つの背景
- 子どもの発達の遅れと親の心理的ストレス
- 発達障害育児で感じる社会的孤立と孤独
- 経済的負担と家庭内トラブルの関係
- 発達障害育児と夫婦のすれ違い|コミュニケーション不足の実態
- 発達障害育児と離婚率|夫婦関係が崩れる本当の理由
- ストレスを減らし、夫婦関係を守るためにできること
- 「正しさ」より「気持ち」の共有を意識する
- 短い時間でも「対話の習慣」をつくる
- お互いの「得意」「苦手」を把握し、役割分担を明確に
- 第三者の力を借りる勇気を持つ
- よくある質問
- まとめ
1. 発達障害育児で親が感じるストレス要因とは?
発達障害のあるお子さんを育てる中で、多くのご家庭が共通して感じるストレスがあります。
まずはその主な要因を見ていきましょう。

1. 子どもの発達の遅れによる心理的な負担
「ほかの子はできているのに、うちの子は…」
そんな比較がストレスの原因に。
周囲との違いに不安を感じ、「この先どうなるんだろう?」という将来への心配が常につきまといます。

2. 社会的な孤立
発達障害に対する理解が進んでいない地域では、親が孤立してしまうことも。
「誰にも相談できない」
「わかってもらえない」
その孤独感は、心に大きな負担をかけます。

3. 経済的な負担
療育や通院、福祉サービスの利用などで家計への負担が増えることもあります。
仕事をセーブせざるを得ないケースもあり、家族全体の生活に影響を及ぼすことも…。
💡 経済的支援の例:
- 幼児教育・保育の無償化制度(対象:3〜5歳児)
- 児童発達支援の無償化(満3歳後の4月から)
🔗厚生労働省:無償化の詳細
また、療育手帳や特別児童扶養手当などの支援も自治体によって異なります。
「〇〇市 発達障害 支援」で検索して、お住まいの自治体の制度をチェックしてみてください。

4. 夫婦間のコミュニケーション不足
育児の方針や負担の分担をめぐり、夫婦の間にすれ違いが生まれやすくなります。
「なんでわかってくれないの?」「自分ばかり頑張っている」——
そんな感情が積み重なると、会話が減り、信頼関係にも影響を及ぼします。

2. 発達障害育児と離婚率の関係|データが示す現実

発達障害のある子どもを育てる家庭では、夫婦関係に悩みを抱えるケースが非常に多く見られます。
実際、研究データでも以下のような結果が出ています。
発達障害育児の離婚率は一般より高い?
- ウィスコンシン大学(2010年)
発達障害児を育てる家庭の離婚率:約23%
一般家庭の離婚率:約14%
➡ ストレスや孤立感が、夫婦関係に大きく影響していることがわかります。
- 日本の調査でも同様の傾向が指摘
障害児家庭の離婚率が、健常児家庭の約6倍というデータも。
👉 出典:弁護士LINE|障害児の育児と離婚
👉 JIL労働政策研究・研修機構
これらの結果からも、発達障害の育児は夫婦関係に大きな影響を及ぼす可能性があるといえます。

私の体験談|すれ違いと向き合った日々
私自身も、夫と育児に対する考え方の違いで何度もぶつかりました。
「どうして気持ちをわかってくれないの?」「私は一人で頑張ってるのに…」
そんな思いが言葉にならず、涙を流した日もあります。
小さなすれ違いが積もり積もって、気づけば会話が減り、「このままではダメかもしれない」と思ったことも…。
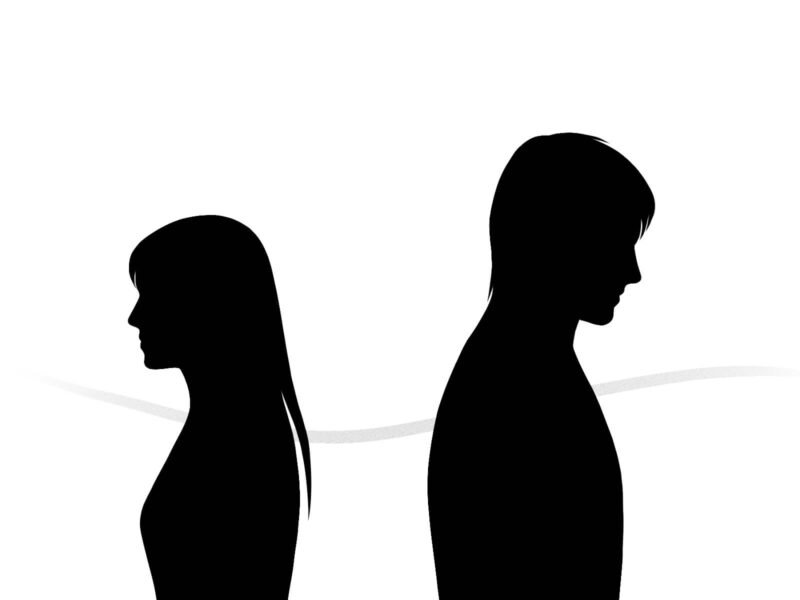
でも今振り返ると、あのとき必要だったのは「話し合う時間」と「お互いを理解する努力」だったのかもしれません。
3. ストレスを減らし、夫婦関係を守るためにできること
発達障害育児において、夫婦が同じ方向を向くことはとても難しい。
でも不可能ではありません。
私自身が取り組んできたこと、支援者の方々から学んだことを踏まえて、少しでも関係をよくするためのヒントをお伝えします。

①「正しさ」より「気持ち」の共有を意識する
夫婦で話し合うとき、「どちらが正しいか」ではなく、「どう感じているか」を伝えることが大切です。
NG例:
「あなたが協力してくれないから、私ばかり大変なんだよ」
OK例:
「最近ちょっとしんどくて…少し話を聞いてもらえると嬉しいな」
責められると人は心を閉じてしまいます。
「伝えたいことをどう伝えるか」は、夫婦関係を大きく左右します。
② 短い時間でも「対話の習慣」をつくる
忙しくても、「1日5分だけ話す時間」をつくるだけで、関係性は変わってきます。
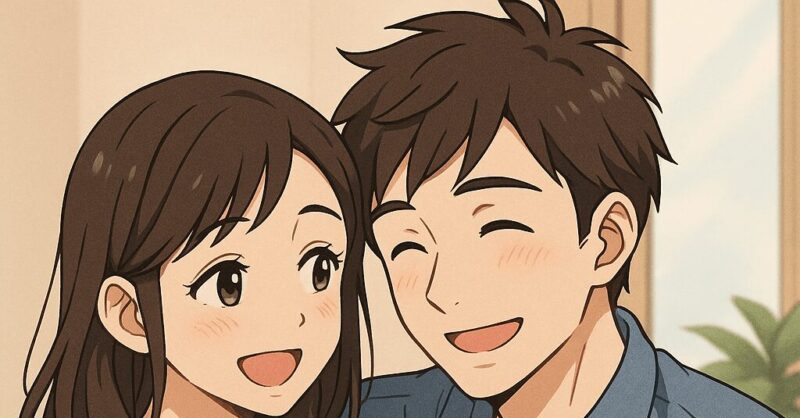
たとえば、
- 寝る前の「おやすみ」の一言を丁寧に
- 子どものいない時間に10分だけお茶を飲む
- 今日よかったことを1つだけ話す
ほんの小さな時間が、「私は一人じゃない」という安心感につながります。
③ お互いの「得意」「苦手」を把握し、役割分担を明確に
夫婦間でのストレスの多くは、「期待と現実のギャップ」から生まれます。
最初から完璧な分担を目指すのではなく、「できることを、できる方がやる」という柔軟な視点を持ってみましょう。
💡 わが家の一例:
| 家事・育児の内容 | 担当 |
|---|---|
| 朝の送り出し準備 | 私(ママ) |
| ゴミ出し・風呂掃除 | 夫(パパ) |
| 曜日ごとの療育対応チェック | 夫婦でシェアしたGoogleカレンダーで管理 |
| 保育園・幼稚園の行事把握 | 私(ママ) |
相手に「期待しすぎず」「できたら感謝する」——これが、長続きのコツでした。
④ 第三者の力を借りる勇気を持つ
どうしても二人だけで解決できないときは、無理せず「第三者」に頼ることも大切です。
- カウンセリング
⇒ 夫婦関係や育児のストレスについて冷静に見つめ直す時間に。 - 家族支援センター・育児相談窓口
⇒ 地域の支援情報や制度の案内もしてくれる心強い存在。 - ピアサポートグループ(同じ立場のママ・パパ)
⇒「うちだけじゃなかった」と感じられるだけで救われることがあります。
4. よくある質問
発達障害の育児で夫婦関係が悪化する原因は?
育児の負担の偏り、理解のギャップ、コミュニケーション不足が主な原因です。
どうすれば夫婦で協力して子育てできる?
定期的な話し合い、感謝の言葉を伝える習慣を持つことが大切です。
離婚率は本当に高いの?
一部の調査では、発達障害児を育てる家庭の離婚率は高い傾向があります。
ストレス対策には何が効果的?
自己ケア・リフレッシュ時間の確保・専門機関の利用などが効果的です。
支援制度にはどんなものがある?
幼児教育の無償化、児童発達支援、特別児童扶養手当などがあります。
夫婦関係が限界のとき、どうすれば?
家族カウンセリングや第三者機関の活用をおすすめします。
子どもの障害に対する理解が夫と違う時は?
専門書を一緒に読む・支援機関の説明会に参加するなどが効果的です。
サポートグループの参加は効果ある?
同じ立場の親と悩みを共有でき、孤独感が和らぎます。
共働きで育児が大変。どう役割分担すれば?
家事育児タスクを書き出し、週ごとに役割を交替する方法があります。
発達障害児の育児に疲れた時の対処法は?
ひとりの時間を意識して確保し、休息・趣味に時間を使いましょう。
まとめ
発達障害のある子どもの子育ては、想像以上にエネルギーが必要です。
一生懸命頑張っているのに、報われないような気持ちになることもあるかもしれません。
でも大丈夫。
🌈あなたの悩みは、あなただけのものではありません。
🌱そして、少しずつでも確実に、状況を変えていくことはできます。
私自身、すべてを一人で背負っていた時期がありました。
✅でも療育センターにつながり、専門家のアドバイスを受けてからは、気持ちが軽くなり、子育てへの自信も少しずつ戻ってきました。
✅さらに、 児童発達支援を活用したことで、自分の時間もでき、家族全体が穏やかに過ごせるようになったことは、私にとって大きな変化でした。
🌟「ひとりで抱えなくていい」──
まずはその一歩を踏み出すことが、夫婦関係を守り、子育てを前向きにするきっかけになるかもしれません。
▶児童発達支援センターのサポートについて詳しく知りたい方は、【こちらのリンク】をご覧ください
🔗児童発達支援ガイドライン
📚あわせて読みたい関連記事:
・【1日型の児童発達支援で見られた息子の成長と変化【親子の実体験】】
・【【体験談】言語聴覚士・理学療法士によるトレーニングでの成長|児発の効果】
・【【体験談】1時間(短時間集中型)の児童発達支援施設で息子が得た成長】
💡次回予告
次回は、「忙しいママにおすすめ!今すぐできるストレス解消アイデア11選」をお届け予定です♪
たとえば、毎日5分でできるリラックス法や、子育ての合間にスキマ時間でできるリフレッシュ法、ぜひお楽しみに!






