はじめに
最近「インクルーシブ保育」って言葉をよく聞くけど…正直どういう意味なんだろう?🤔
私自身、息子の子育てを通して気になるようになりました。
うちの息子はASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、吃音症、そしてDCD(発達性協調運動症)と、いくつかの特性を持っています。
現在は幼稚園と療育に通っていて、
療育に参加したあとに、幼稚園に登園することや、幼稚園を中抜けして療育に参加することもあります。
将来的には支援級に進むことも視野に入れています。
そんな日々の中で、「みんなと同じが難しい場面」もあれば、
「周りの理解やちょっとした工夫があれば一緒に楽しめる場面」もたくさんあることに気づきました。
子どもたちって、本当に一人ひとり違っていて、発達のスピードも得意・不得意も、家庭や文化の背景もバラバラ。
その「違い」を否定するのではなく、認め合って安心して過ごせる環境を作る――それが「インクルーシブ保育」です🌱
この記事では、私が実際に感じたことや調べて知ったことを交えながら、
インクルーシブ保育の意味や大切な視点、具体的な実践方法までを、わかりやすく紹介していきます😊
📑目次
- インクルーシブ保育とは?
・定義と意味
・教育での4つの「受け入れ方」排除・分離・統合・包摂
・どうして「包摂」が大切なの? - インクルーシブ保育が目指す姿
- 多様な特性を持つ子どもたちへの理解
- インクルーシブ保育を実現する環境整備
- 具体的な支援方法と実践例
- インクルーシブ保育がもたらす効果
- インクルーシブ保育の課題とこれから
- インクルーシブ保育ブログ
療育や支援級見学を通して感じた親の体験談 - インクルーシブ保育に関するよくある質問(FAQ)
- まとめ
1. インクルーシブ保育とは?🌈

定義と意味
「インクルーシブ(inclusive)」って聞くと難しく感じますが、意味はとってもシンプル✨
「みんなを包み込む」「仲間はずれにしない」ということです。
インクルーシブ保育は、すべての子どもが同じ場所で過ごしながら、それぞれの違いを認め合って一緒に成長していける保育のスタイルを指します😊
教育での「受け入れ方」の4つのステップ
子どもたちを受け入れる形は、教育の世界で4段階に分けて考えられます👇
- 排除:特性を持つ子どもを受け入れない
- 分離:特別な場所に分けて支援する
- 統合:同じ場所にいるけど十分に活動に参加できない
- 包摂(インクルーシブ):違いがあっても一緒に活動できる環境を整える
インクルーシブ保育は、この「包摂(ほうせつ)」にあたります💡
どうして「包摂」が大切なの?
子ども時代から「みんな違って当たり前」と感じる経験は、将来の社会での共生につながります🌱
だから、保育現場で「違いを認めながら共に育つ体験」をすることがとっても大事なんです✨
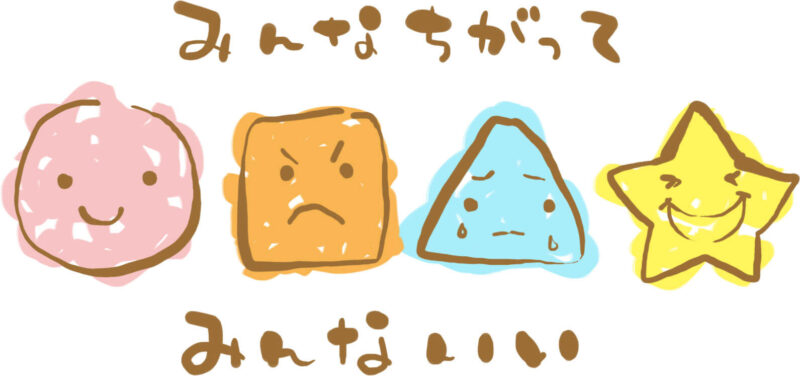
2. インクルーシブ保育が目指す姿🌟
- 誰もが安心して参加できる場
- それぞれの個性や背景を尊重する環境
- 必要に応じた合理的配慮で、無理なく活動できる工夫
ここでいう「合理的配慮」とは、特別扱いではなく、子どもが不利にならないようにちょっと調整してあげること🛠️
これを行うことで、みんなが一緒に育ち合える場が生まれます💛
3. 多様な特性を持つ子どもたちへの理解👶✨
インクルーシブ保育を考えるとき、まずは子どもたち一人ひとりの特性をよく知ることが大事です💡
例えば…
- ADHD:ちょっと集中が続かないことがある⚡
- ASD:コミュニケーションや関わり方に個性がある🗣️
- 学習障害(LD/SLD):読み書きや計算が少し苦手📚
- 知的・身体障害:発達のスピードや動作にサポートが必要🏃♂️
- ギフテッド:特定の能力が高いけど、人間関係で悩むことも🌟
- LGBTQ+や多文化背景:性や文化の多様性を理解することが大切🌏
ポイントは、「特別扱い」ではなく、「みんなの仲間」として一緒に過ごすこと💛
違いを尊重しながら関わることで、子どもたちは安心して成長できます😊
4. インクルーシブ保育を実現する環境整備🏫
子どもが安心して過ごせる環境には、ちょっとした工夫がたくさんあります✨
- 保育者・教師の役割:一人ひとりをしっかり受け止め、信頼関係を築く🤝
- 教材や遊具の工夫:絵カードや選べる遊び道具で、いろんな子に対応🖍️
- 物理的環境:段差をなくしたり、座席を自由に動かせたり🪑
- 活動プログラム:一斉活動だけでなく、子ども自身が選べる時間も⏰
ちょっとした工夫でも、子どもたちの「やってみよう!」を引き出すことができます🌱
5. 具体的な支援方法と実践例🛠️
さらに具体的に、こんな方法があります👇
- 視覚的サポート:予定を絵やカードで見せると安心📅
- 個別と集団のバランス:一人で集中する時間と、みんなで遊ぶ時間の両方⚖️
- 異年齢交流や多文化交流:自然と「違い」を学び合える🌍
- 家庭や地域とのつながり:保護者や地域と協力して子どもを支える🤗
保育者だけでなく、家庭や地域が一緒に関わることが成功のカギです🔑
6. インクルーシブ保育がもたらす効果🌟
こうした取り組みで、子どもたちには嬉しい効果がいっぱい!
- 自己肯定感が育つ💪
- 思いやりや協調性など社会性が自然と身につく💞
- 保護者や地域の理解が広がる🏘️
- 共生社会の実現に近づく🌏
小さな日常の積み重ねが、将来の大きな学びにつながります✨
7. インクルーシブ保育の課題とこれから🚀
もちろん、課題もあります💦
- 人材不足と研修:専門知識を持った先生をもっと増やす必要がある👩🏫
- 制度の整備:支援体制や予算の確保がまだまだ課題💰
- ICTやAIの活用:個別支援の新しいツールとして期待される🤖
- SDGsとのつながり:「誰一人取り残さない」という目標にも直結🌱
これからは、テクノロジーも活かしながら、みんなが安心して育てる社会を目指していきたいですね😊
8. インクルーシブ保育ブログ療育や支援級見学を通して感じた親の体験談
子育てをしていて強く感じるのは、インクルーシブ保育は「特別な子どものためだけ」ではなく、みんなのための保育だということです🌱
うちの息子はASD・ADHD・吃音症・DCDなどの特性を持っており、日々療育に通ったり、支援級の見学を検討したりと、親としても試行錯誤の連続です💦
最初は、幼稚園やお友達に「迷惑をかけちゃうんじゃ…」と不安でいっぱいでした😥
特に療育のために幼稚園をお休みしたり、登園が遅れる日があると、息子も私も緊張します。
しかし、療育や園での体験を重ねるうちに、少しずつ安心して活動できる姿が見られるようになりました😊
療育と園の連携で安心して過ごせる
例えば、療育で絵カードや視覚サポートを使うと、息子は自分で行動を選びやすくなります。
また、療育の先生と幼稚園の先生が連携し、声掛けや工夫をしてくれることで、安心して参加できる環境が整っているのを実感しています✨
園でも友達と笑い合いながら遊ぶ時間が増えました。
もちろん、申し訳なさや人目が気になる瞬間もあります💦
「あの子はできない子」と決めつけられたように感じることもありましたが、全体としては協力的で温かく見守ってくれる先生や保護者が多く、ホッとする場面もたくさんあります😊
親としての意識と社会の変化
親として、自分の意識改革もまだまだ必要だと感じます。
昔の「障害者」のイメージとは違い、今は多様性を受け入れる社会になりつつありますが、差別的な意識を持つ保護者も残っています。
そうした場面でも、穏やかに、でも強い意志を持って向き合うことが大切だと感じます。
私自身、胸を張って自信を持ち、キラキラ✨とした子育てを目指していきたいと思っています。
児童発達支援施設や放課後デイサービスも増え、子どもへのサポート環境は以前よりずっと充実しています。
支援級の見学で感じたこと
就学準備として支援級を見学した際、思ったより開けた印象でした。
交流学級制度もあり、昔のイメージとは大きく違います。
普通学級でもインクルーシブ教育は可能ですが、低学年のうちは手厚いサポートをお願いしたいため、支援級を希望する予定です。
支援級の壁は以前より低く、選択肢が広がっているのは本当にありがたいことです💡
家庭でもできる小さな積み重ね
子どもたちが互いの違いを認め合う経験は、
息子だけでなく周りの子どもたちにとっても、「思いやり」や「協調性」を育む大切な機会です💞
家庭でも、
- 「できたことを一緒に喜ぶ」
- 「失敗しても大丈夫だよ」と声をかける
などの小さな積み重ねが大切です🏡
9. インクルーシブ保育に関するよくある質問(FAQ)
インクルーシブ保育とは何ですか?
すべての子どもが同じ環境で学び合い、個性や特性を尊重しながら成長できる保育のことです。
違いを受け入れ合うことで共生社会の基盤を育みます。特別支援保育とどう違うのですか?
特別支援保育は特性のある子どもに重点的に支援を行います。
一方、インクルーシブ保育は「全員が一緒に過ごせる場」を前提に環境や配慮を整える点が特徴です。ADHDやASDの子どもがいると、他の子に迷惑になりませんか?
行動や関わり方に工夫は必要ですが、周囲の子どもも「多様性を理解する」経験を積めます。
結果的にお互いの成長につながります。合理的配慮って具体的にどんなことですか?
例として、絵カードでスケジュールを見せる、静かな場所を確保する、椅子や机の高さを調整するなどです。
特別扱いではなく「不利をなくす工夫」です。インクルーシブ保育は保育士にとって負担が大きくありませんか?
一人で抱えると負担になりますが、研修やチームでの支援、保護者や地域との連携を取り入れることで負担を軽減できます。
障害のない子どもにとってメリットはありますか?
はい。違いを自然に受け入れる力、思いやりや協調性が育ちます。
社会性や自己肯定感の向上にもつながります。保護者がインクルーシブ保育に不安を感じたらどうすればいいですか?
保護者との対話を重ね、取り組みや子どもの変化を共有することが大切です。
理解と安心感を持ってもらえるよう支援します。ICTやAIはどのように役立ちますか?
タブレットを使った視覚支援、AIによる学習データ分析、コミュニケーション支援アプリなどが有効です。
ギフテッドや多文化背景の子どもも対象ですか?
もちろんです。
インクルーシブ保育は発達特性だけでなく、文化や言語、性の多様性なども含めて支援します。インクルーシブ保育を家庭で取り入れる方法はありますか?
家庭でも「できることを一緒に楽しむ」「違いを否定しない声かけ」を心がけることで、日常的にインクルーシブな関わりができます。
まとめ
インクルーシブ保育は、すべての子どもが自分らしく安心して育ち合える教育モデルです。
違いを認め合う経験は、将来の社会における共生の力になります。
そのためには、保育者だけでなく、家庭や地域が一緒になって子どもを支える環境を整えることが大切です。
日常生活の中でも、
- 「できることを一緒に楽しむ」
- 「違いを否定せず認める声かけ」
を意識することで、家庭でもインクルーシブな関わりを実践できます。
小さな積み重ねが、子どもたちの自己肯定感を育み、未来の共生社会をつくる第一歩になりそうです🌈
📢次回予告
次回は、「3歳〜6歳の子どもが遊びに入れないときの理由と声かけ・サポート」についてご紹介します。
お楽しみに。
👉 関連記事:
「【就学相談の流れ】年長ママ体験談|聞かれること&後悔しない準備」
「太田ステージ完全ガイド|ASDの子どもの発達と家庭での支援法を紹介」
「【決定版】ASDの療育法を徹底比較|ABA・TEACCH・感覚統合の違いと家庭での活かし方」
「【体験談あり】発達障害の子どもを支える家庭療育|視覚支援・感覚統合・SSTの実例」
「発達障害の子が集団生活に馴染む5つの支援策!幼稚園・学校でできる対応」






