はじめに
👋 こんにちは。当ブログにお越しいただきありがとうございます。
今回は、「発達検査を受けるか迷ったとき、親はどう向き合うのか?」というテーマで、私たち家族のリアルな体験をお話しします。
「うちの子、ちょっと他の子と違うかも…」
「発達検査を受けさせた方がいいのかな…」
そんな不安や戸惑いを感じたことはありませんか?
私自身、息子の「吃音(ことばの詰まり)」が悪化し、3歳8か月のときに専門病院を受診したことをきっかけに、発達検査の必要性と向き合うことになりました。
当時はこんな悩みでいっぱいでした👇
- 幼稚園でお友達とうまく関われない
- 家庭でも癇癪やパニックが増えてきた
- 夫と「本当に検査が必要なのか?」と何度も話し合った

そんな私たち家族が、なぜ発達検査を受ける決断をしたのか。
その過程で得られた気づきや、迷っていた私の背中を押してくれた言葉についてもお伝えします。
🌱 この体験記が、同じように悩むパパ・ママの「判断のヒント」になれば嬉しいです。
目次
- 発達検査を受けるきっかけ
● 【吃音と発達検査】受ける決断を後押しした言葉
● 【葛藤と希望】発達検査に踏み切るまでの気持ちの揺れ
● 【幼稚園での困りごと】「もしかして発達に特性が?」と思い始めた瞬間 - 【夫にどう伝える?】発達検査の必要性を理解してもらうまでの道のり
● なぜ夫の理解が必要だったのか?
● 夫と話し合うために意識したこと
● 夫が納得したきっかけ
● 家族で納得して進むことが大切 - 【就学前に知っておきたい】
支援学級と放課後等デイサービスの利用条件をわかりやすく解説
● 支援学級・通級指導教室は、診断なしでも入れる?
● 放課後等デイサービスはどうなの?
● ママ・パパが知っておくべき「今できる準備」 - よくある質問
- まとめ
1. 発達検査を受けるきっかけ 吃音と日常の変化から見えた課題
【吃音と発達検査】受ける決断を後押しした言葉🗣️
息子に「吃音(ことばの詰まりや繰り返し)」が見られ始めたのは、2歳半ごろ。
それは「おしゃべりが大好き!」だった息子が、言葉を発するたびに辛そうな様子を見せる日々の始まりでした。
3歳半になると吃音はさらに悪化し、親としての無力感に打ちひしがれる毎日。
私たちはついに療育スタッフへ相談することにしました。
すると、吃音の専門病院を紹介され、診察を受けた際に、先生からこんな助言を受けたのです。
「吃音のあるお子さんは、言葉以外の発達にも課題を抱えていることが多いです。まずは発達検査を受けてみましょう。」
この一言が、私たちにとって大きな決断への第一歩になりました。
息子は2歳半頃から吃音が見られ、3歳半になるとさらに悪化しました。
おしゃべりが大好きだった息子が、言葉を発するたびに苦しそうな様子を見て、親としての無力感に打ちひしがれました。
療育スタッフに相談したところ、吃音の専門病院を紹介され、診察を受けることに。
その際、担当の先生よりこんな助言をいただきました。
「吃音のあるお子さんは、言葉以外の発達にも課題を抱えていることが多いです。まずは発達検査を受けてみましょう。」
この言葉は、親として非常に大きな決断を迫るものでした。
【葛藤と希望】
発達検査に踏み切るまでの気持ちの揺れ🌀
- 「本当に検査まで必要なのか?」
- 「検査の結果を知ってしまったら、息子の未来はどう変わるんだろう?」
- 「でも、検査を受ければ、もっと息子のことを理解できるかもしれない…」
不安と希望が入り混じる中、私たちは少しずつ発達検査の必要性を感じ始めました。
【幼稚園での困りごと】
「もしかして発達に特性が?」と思い始めた瞬間🏫
吃音が目立つようになると、幼稚園でもさまざまな困りごとが出てきました。
▼具体的な困りごとの例
- 登園時に泣いて嫌がる、行き渋りが続く
- お友達との距離感が近すぎてトラブルに
- 園内ではほとんど話さず、少し孤立気味
- 先生の指示が通りづらく、運動会のダンスやフォーメーションが覚えられない
そんな中、ある日先生から言われた言葉が、私の心を揺さぶります。
「療育を考えられていますか?」
すでに私たちは療育を始めていたのですが、先入観で見られることへの不安から、その事実を先生には伝えていませんでした。
けれどこの一言で、「もっと息子の状態を深く理解しなければ」という思いが強まりました。
【家庭での困りごと】育児の限界を感じた日常の変化🏠
幼稚園での様子と同じように、家庭でも困りごとが目立つように。
▼家庭で見られた困りごと
- 些細なことで癇癪を起こす
- 壁にクレヨンで落書きしてしまう
- テレビに物を投げて壊してしまう
まだ療育を始めたばかりだったこともあり、「今すぐ検査すべきかどうか」と迷う気持ちもありました。
けれど、目の前の困難を前に私は決意します。
息子の状態を正確に把握し、彼に本当に合った支援を受けることが必要だ――
こうして、私たちは発達検査を受ける決断をすることになったのです。
まずは「わが子を知ること」から始めよう👣
発達検査を受けるかどうかは、簡単な決断ではありません。
けれど、「もっと深くわが子を理解する」という視点から見ると、大きな一歩となります。
💡 「もしかしてうちの子も…」と感じたら、まずは地域の相談窓口や療育センターに問い合わせてみましょう。
🌱 同じような経験をされた方、ぜひコメント欄で体験をシェアしてください。
あなたの声が、誰かの支えになります。
🔗 関連記事はこちらもおすすめ!
2.【夫にどう伝える?】発達検査の必要性を理解してもらうまでの道のり👨👩👦
🟡なぜ夫の理解が必要だったのか?
発達検査を受けるには、家族の同意と協力が不可欠です。
特に我が家では、夫の理解を得ることが大きな壁となりました。
夫は当初、発達検査に対して否定的でした。
理由は、こんなものでした👇
- 「まだ3歳で早すぎる」
- 「発達障害だと決めつけたくない」
- 「周囲になんて説明すればいいのか…」
これらの言葉には、息子への愛情と、未来を思うがゆえの不安が込められていたのだと、今は思えます。
🟢夫と話し合うために意識したこと🗣️
否定的な姿勢にショックを受けつつも、私は夫を責めないように意識しました。
まずは感情ではなく事実ベースで話すことを心がけました。
🔍話し合いの中で伝えたこと
- 息子の困りごとの具体例(吃音・癇癪・園での孤立など)
- 将来「困る前に支援する」ことの大切さ
- 検査は診断ではなく、息子の特性を知るためのスタート地点であること
このように、「息子を守るために検査が必要」という視点で何度も話を重ねることで、夫の気持ちに少しずつ変化が生まれました。
💡夫が納得したきっかけ
ある日、夫がポツリとこう言いました。
「今のままで本当にいいのかなって、最近よく考えたんだ。何もしないままでいるより、息子のためになることがあるなら、できることをやってみるのもアリかなって思うようになったよ。」
この言葉をきっかけに、夫は発達検査に前向きになってくれました。
理解には時間がかかるもの。
でも、「子どものために」という軸を共有できたことが、大きな転機でした。

家族で納得して進むことが大切
発達検査は、「障害の有無を決めるため」ではなく
「子どもの特性を知り、支援の方法を見つけるため」の第一歩です。
パートナーに理解してもらうのは簡単ではありませんが、
「子どもを思う気持ちは同じ」という前提を忘れず、対話を続けていくことが大切です✨
📣あなたも一人で抱え込まずに…
もし、同じように「パートナーにどう伝えるか」で悩んでいたら、ぜひコメントで体験をシェアしてください📝
あなたの声が、きっと誰かの助けになります。
3. 【就学前に知っておきたい】
支援学級と放課後等デイサービスの利用条件をわかりやすく解説🏫✨

夫と何度も話し合い、ようやく「発達検査を受けよう」と決断した私たち。
でも…
なぜそこまでして検査が必要だったのか?
それは、「今の困りごとを把握するため」だけでなく、
小学校入学後の支援につながる、大切な第一歩になるからです。
実は、小学校で支援学級や放課後等デイサービスなどのサポートを受けるには、
就学前からの準備がとても重要なんです👀
ここでは、就学前に知っておきたい「支援学級」や「放課後等デイサービス」の利用条件について、ママ・パパにもわかりやすくまとめました👨👩👧👦
🟢支援学級・通級指導教室は、診断なしでも入れる?📝
▶ 結論:発達検査や診断が「なくても入れる」が、「あったほうがスムーズ」!
というより…現実的には、ないと難しい場合も多いんです💦
自治体や学校によって基準は異なりますが、主にこんな情報が判断材料になります👇
- 保護者・園からの申し出
- 就学時健康診断や教育相談での指摘
- WISCなどの発達検査結果
- 医師の意見書・診断書など
🧠診断が「絶対条件」ではありませんが、
「支援が必要です」と説明するための根拠として、発達検査はとても有効。
学校や教育委員会も、検査結果があると判断しやすくなるんです✨
🟠放課後等デイサービスはどうなの?👧🌈
▶ 結論:受給者証の取得が必要。そのためには「診断」または「発達検査による所見」が基本。
放課後等デイサービスは、放課後に療育や生活支援を受けられる福祉サービス。
利用には「受給者証」の取得が必須で、以下のような流れになります👇
- 市区町村の福祉窓口に申請
- 医師の診断書、または発達検査結果を提出
- 面談・調査を経て「受給者証」発行
- サービス利用スタート🎉
📄【提出書類の一例】
- ASD(自閉スペクトラム症)・ADHD・LDなどの診断
- 療育センター・専門機関による発達検査結果や支援計画書
【比較でわかる】支援を受けるために必要なこと
| 利用サービス | 発達検査 or 診断が必要? | 補足ポイント |
|---|---|---|
| 支援学級・通級 | ❌必須ではない | あると判断材料になり、話がスムーズに進みやすい |
| 放課後等デイサービス | ✅ 原則必要 | 受給者証の発行には、診断や検査結果の提出が必要 |
🌱ママ・パパが知っておくべき「今できる準備」
就学後のサポート体制は、就学前の準備がカギです。
「まだ小さいし、様子見でもいいかな…」と思っていても、
いざ小学校入学が近づくと、時間が足りずに後悔するケースも少なくありません。
特に発達関連の病院や検査機関は、予約が数ヶ月先まで埋まっていることもザラなんです💦
だからこそ、今のうちに動いておくことで、
後悔せずに子どもに合った選択ができるようになります🌟
📣「うちも同じ状況かも…」と感じた方へ
あなたの不安や迷いは、決して一人だけのものではありません。
私も同じように悩んで、葛藤して、少しずつ進んできました。
実は、私自身も発達検査を受けるまでに長い時間がかかりました。
すぐに決断できることではありませんし、無理にすすめたいわけではないんです。
でも、就学のタイミングが近づくと、診断や検査の話は避けて通れなくなることが多く、
「もっと早く知っていればよかった…」と焦る親御さんの声を何度も耳にしました。
だからこそ、この記事では「必要になったときに備えて、今知っておいてほしい」という想いでお伝えしています🌷
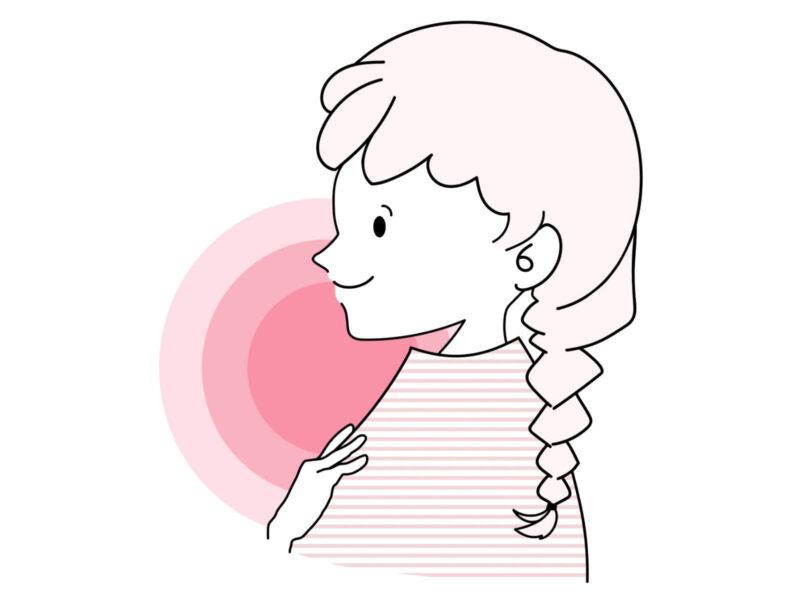
4. よくある質問
発達検査ってどんなことをするの?
知能検査や言語理解、運動能力、社会性などを多角的に評価します。
何歳から発達検査は受けられるの?
一般的には2歳半ごろから受けることができます。年齢に応じた検査項目が設定されます。
吃音があるだけで発達検査は必要?
吃音だけでなく、他の発達特性が隠れていることもあるため、検査を勧められることがあります。
検査を受けると発達障害の診断が確定するの?
発達検査は診断の一部ですが、それだけで診断が確定するわけではありません。
夫や家族が理解してくれない場合はどうしたらいい?
子どもの困りごとを具体的に伝え、検査の目的を「支援の第一歩」として話すと伝わりやすくなります。
検査を受けるデメリットはある?
一時的な不安やレッテル貼りへの懸念がありますが、正確な理解と早期支援のための一歩となります。
発達検査の費用はどれくらい?
病院や自治体によりますが、公費負担が使えるケースもあります。
療育と発達検査の違いは?
発達検査は「評価」、療育は「支援(トレーニングや関わり方)」です。
検査の結果が悪かったらどうなるの?
結果は「今の状態」を把握するもので、支援方法を決める参考になります。悪い・良いではありません。
検査を受けて良かったことは?
子どもの得意・不得意が見え、家庭や園での対応がしやすくなります。親の安心感にもつながりました。
まとめ
📌 発達検査を受ける決断は、私たち家族にとって勇気のいる選択でした。
不安や葛藤もありましたが、結果的に「息子に合った支援」を受けるための第一歩となり、今では本当に良かったと思っています。
子どもの「困り感」は、大人が想像する以上に本人にとって大きなストレスです。
だからこそ、早めに気づき、寄り添うことが大切なのだと実感しました。
もし今、迷いや不安を感じている方がいれば——
👪 ご家族でじっくり話し合いながら、一歩ずつ前に進んでみてください。
🗨️ ご質問や感想があれば、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね!
🔜次回予告
次回は「【体験談】発達検査WPPSI-IIIを受けた息子|検査の流れと親の気づき」をお届けします。
どうぞお楽しみに!
参考リンク
🔗 関連リンク(内部リンク・外部リンクの設計)
- ✅【体験談】療育を始めた理由と発達検査の決め手(準備中)
- ✅【保存版】発達障害のチェックリスト&支援先まとめ(準備中)
📚 外部参考サイト:






