はじめに
「療育 絵本 メリット」「発達 絵本 効果」などのキーワードで情報を探している方へ。
幼児期の絵本読み聞かせは、言語発達や認知力、社会性に多くの効果があることが研究でも示されています。
特に、発達障害や言葉の遅れをもつ子どもへの療育支援においても、絵本は大きな役割を果たします✨
私自身、子どもの療育や言語訓練を受ける中で、保育士さんや言語聴覚士の先生から「絵本の読み聞かせはとても大切です」と繰り返しアドバイスされてきました。
でも、ふと「なぜ絵本がそこまで重要なの?」と疑問に思い、実際に論文や育児支援の専門情報を調べてみることに。

この記事では、絵本の読み聞かせが子どもの発達に与える好影響を、専門的な視点と親としての体験談を交えてわかりやすく解説します。
📌 忙しい毎日でも取り入れやすい【読み聞かせのコツ】もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください♪
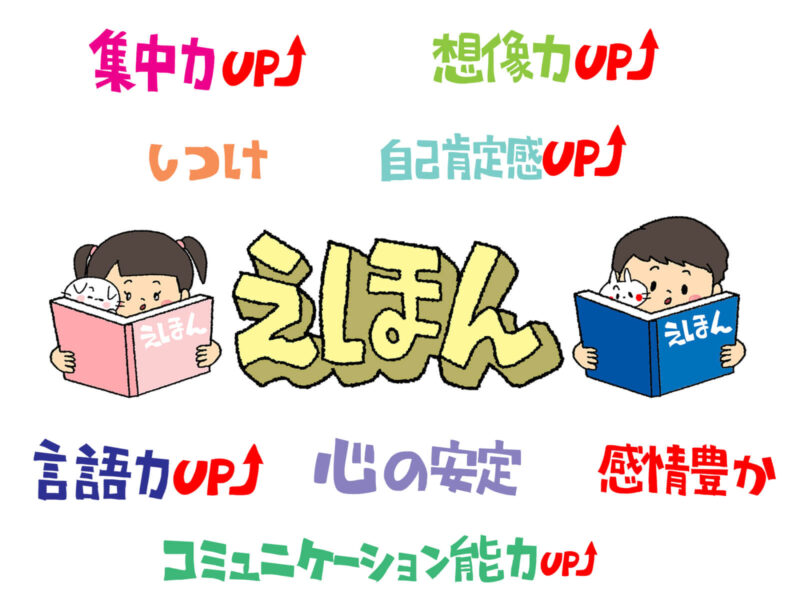
目次
■ 1. 【専門家推奨】絵本の読み聞かせが幼児教育や療育で重要な理由
① 言語発達をサポートする絵本の力
② 視覚と聴覚を刺激し、認知力を高める
③ 共感力と社会性の発達における絵本の重要性
④ 想像力と創造力を豊かにする
⑤ 親子の絆を深める時間を提供
■ 2. 脳科学から見た!絵本が幼児期の発達を後押しする理由
・言葉の学びを自然にサポート
・視覚と聴覚を同時に刺激する
・共感力と社会性を育てる
・創造力・想像力を広げる
■ 3. 療育や幼児教育での絵本の効果を最大限に引き出すには
■ 4. 絵本を読むことで得られる長期的なメリット
■ 5. よくある質問
■ 6. まとめ
1. 【専門家推奨】
絵本の読み聞かせが幼児教育や療育で重要な理由 📚
幼児期における絵本の読み聞かせは、単なる遊びではなく、脳と心の発達を支える大切な教育的アプローチです。
実際に、療育や幼児教育の現場では絵本の活用が推奨されており、専門家もその効果を認めています。
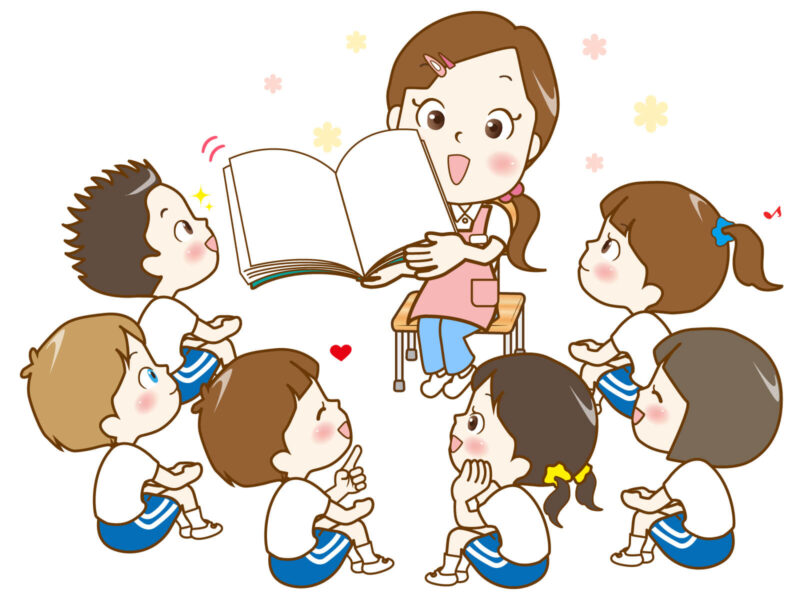
🗣 1. 言語発達を促進する
アメリカ小児科学会(AAP)は、乳幼児への絵本の読み聞かせが語彙力・文法の習得を促し、言語発達に良い影響を与えると報告しています。
🧠 2. 認知力と集中力を高める
京都府立大学の研究(2022)では、絵本を定期的に読み聞かせた幼児は、注意力・記憶力・推理力などの認知機能が高まりやすいことが示されています。
🔗出典:幼児期における絵本の読み聞かせと認知力の関連
💞 3. 社会性と共感力を育む
奈良教育大学の調査によると、物語を通じて登場人物の気持ちを想像することで、子どもたちに共感力・自己表現力・他者理解が育まれることがわかっています。
🔗出典:幼児の心情理解に及ぼす絵本の読み聞かせの効果
🗨 保育士のコメント:
「読み聞かせの時間は、子どもの心の成長を感じる貴重なひととき。安心感と学びが同時に得られる『魔法の時間』です」
🌟要点まとめ
- ✅ 言語発達:語彙・表現力の習得に貢献
- ✅ 認知力:集中力・記憶力UP
- ✅ 社会性:感情の理解や共感の基礎作り

👉 絵本の読み聞かせは、発達障害や言葉の遅れを持つ子どもへの療育支援としても高く評価されています。
➡️ [療育とは?基礎知識と支援方法を見る] 準備中
2. 脳科学から見た!絵本が幼児期の発達を後押しする理由🧠
幼児期は「脳のゴールデンタイム」と呼ばれ、言語・認知・感情など、さまざまな発達が急速に進む時期です。
この時期に絵本を読み聞かせることは、脳の発達に多方面から良い刺激を与えるといわれています。
① 言葉の学びを自然にサポート🗣
絵本のリズム・繰り返し表現・簡潔な語彙は、言語を覚える力を自然に引き出してくれます。
これは、発語の遅れや吃音に悩むお子さんにも効果的とされています。
🧑🍼 実体験より
長男は吃音が出始めた時期、『だるまさんが』シリーズのようなテンポの良い絵本に夢中になり、自然にリズムよく話すコツをつかんでいきました。
次男も発語がなかなか出なかったのですが、毎日絵本を読んでいるうちに少しずつ言葉を口にするようになってきたのです。

🗨 言語聴覚士のコメント:
「絵本は遊び感覚で言葉を学べる、非常に優れたツールです。特に吃音や遅れがあるお子さんには『無理のないアウトプットの練習』になります」
📌 豆知識
米国小児科学会(AAP)も、「乳幼児期からの絵本の読み聞かせが言語発達を促す」と推奨しています。
🔗関連記事:
吃音や発語の悩みには?
👉吃音改善や言語発達を促進!療育で使える『だるまさんが』シリーズの魅力
👉子どもの語彙力を伸ばす5つのポイント
👉親子で楽しむ!『くれよんのくろくん』と絵本療育のすすめ
👉『あかちゃんのあそびえほん』|療育的視点で徹底解説
👉子どもの語彙力を伸ばす5つのポイント
👉発語が遅い子におすすめの発語練習!動作模倣で言葉を引き出す方法
② 視覚と聴覚を同時に刺激する👀
絵本には、カラフルなイラスト・文字の形・音のリズムなど、五感を刺激する要素がたっぷり含まれています。
特に、視覚優位や聴覚優位といった子どもの特性に合わせて効果的な刺激を届けられるのが魅力です。
🧠 脳科学の視点から
- 絵を「見る」ことで視覚野を刺激
- 音を「聴く」ことで聴覚野を活性化
- さらに「話す」「まねる」ことで前頭葉が活性化
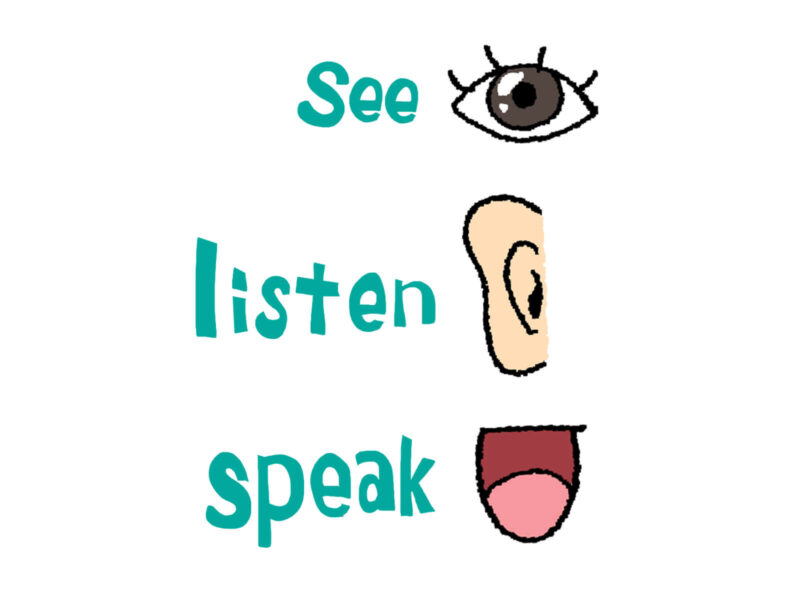
🧑🏫 わが家の実感
言語トレーニングの先生から、「息子くん、以前より集中力がついてきましたね」と言われるように✨
毎日の絵本読み聞かせが、集中力や注意力の土台づくりにつながっているのを感じています。
📌 参考研究
京都府立大学の研究では、絵本の読み聞かせが幼児の認知機能(集中力・記憶力)を高める効果があることが示されています。
🔗出典:幼児期における絵本の読み聞かせと認知力の関連
🔗関連記事:
子どもがもっと夢中になる!絵本の読み聞かせ7つのコツ
【年齢別】1歳・2歳・3歳・4歳・5歳におすすめの絵本&選び方ガイド
③ 【共感力と社会性】絵本が育てる『こころの発達』🫶
絵本に登場する多彩なキャラクターやストーリーは、子どもが他者の気持ちや立場を想像し、共感する力を育てます。
これは、社会性の発達にとって欠かせないステップです。
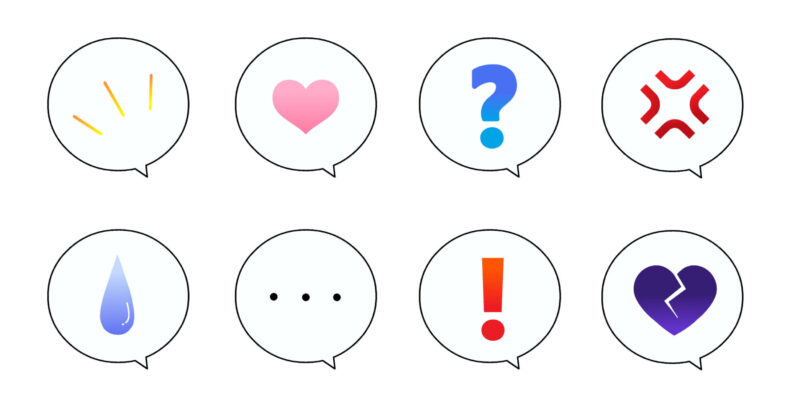
特に、自閉スペクトラム症(ASD)など社会的なやりとりが苦手なお子さんには、
絵本を通して
・他人の感情を理解する力
・「順番」「お願い」「断る」などの基本的なやりとりの型
を自然と学べる貴重なツールになります。
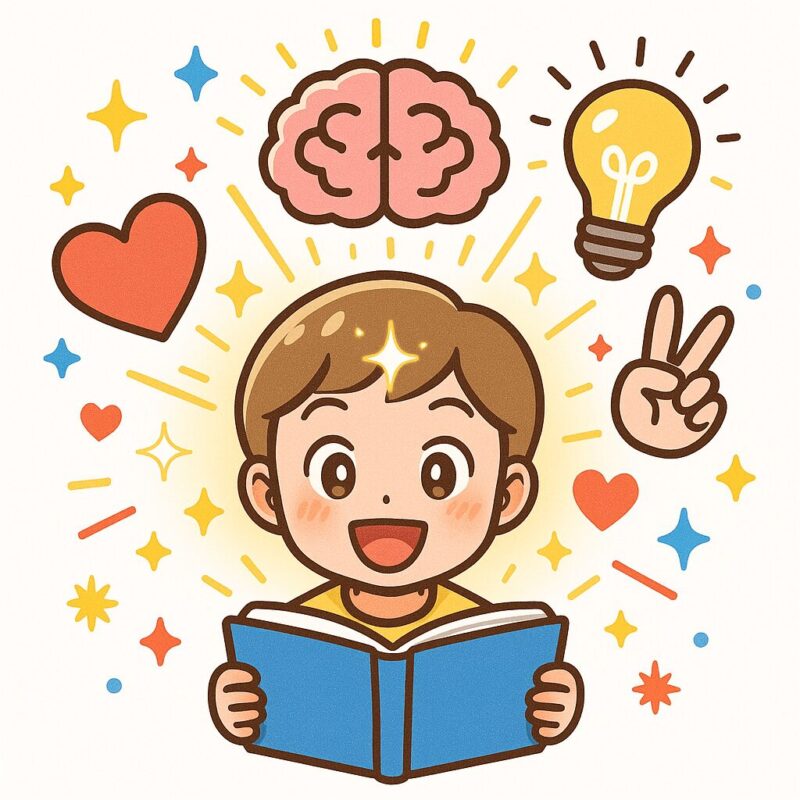
📖 わが家のエピソード
息子も、絵本の中でキャラクターが困難を乗り越える姿に触れ、「ぼくもがんばる!」と前向きな言葉を口にすることが増えました✨
療育先でも、絵本を通して気持ちを考えるカリキュラムが取り入れられています。
たとえば『かおかおどんなかお』では、表情から感情を読み取る練習をしました。
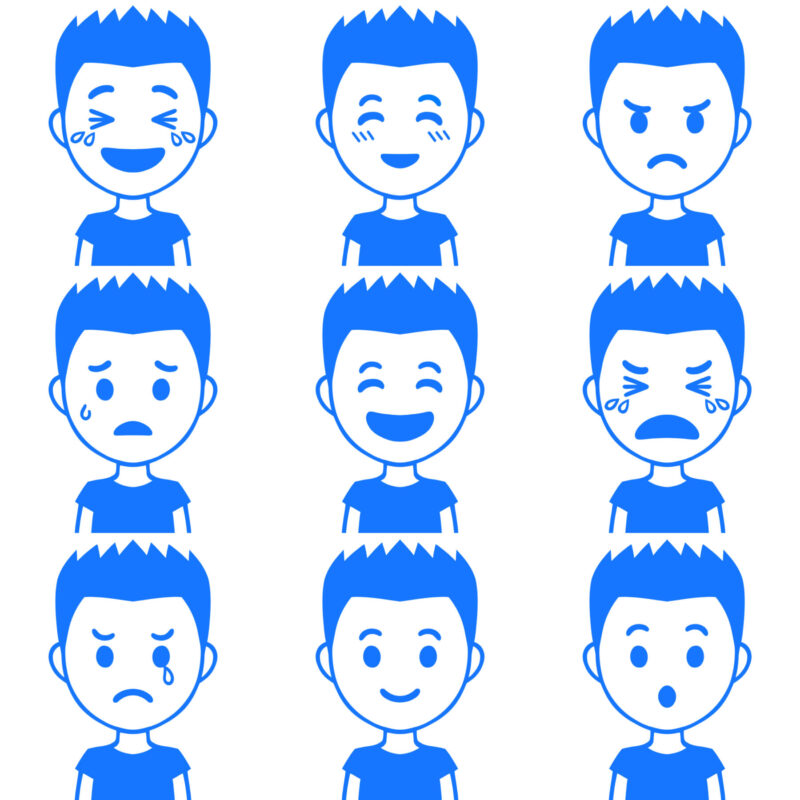
👩⚕️ 保育士のコメント
🔗「絵本は『疑似体験』の宝庫。感情を言葉にする練習にも最適です。」
関連記事:
子どもの心を育むおすすめ絵本5選:成長をサポートする読み聞かせストーリー
こころを育てる七田式えほん:年齢別に子どもが学べる心の成長エピソード
④【創造力・想像力】絵本がひらく「子どもの世界」🌈
絵本の中に広がるファンタジーや冒険の世界は、子どもの想像力と創造力を大きく育てます。
知らない世界を自由に旅する体験は、
- 発想力
- 表現力
- ストーリーを組み立てる力
といった力を自然と育むのです。
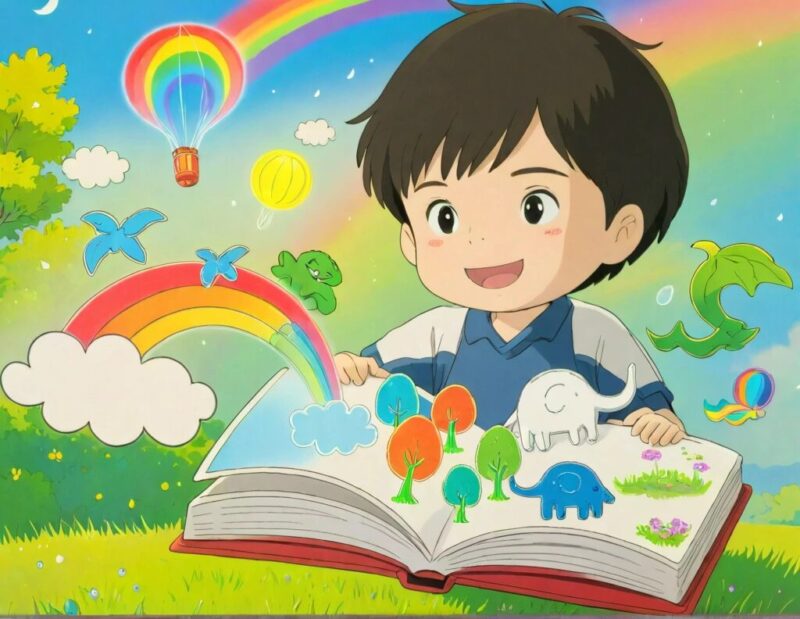
📖 体験談:息子の姿から実感
息子は、絵本のキャラクターになりきって遊ぶのが大好き。
「この子は○○を探してるの!」と自分なりのストーリーを作って楽しんでいます。
想像した世界で遊ぶ力は、彼の自己表現の土台になっています。
🗨発達支援スタッフの視点
「創造力の育成は、自己表現の土台になります。
特にことばの発達がゆっくりな子どもにとって、自分の気持ちを形にする練習にもなります。」
🔗関連記事:
【自己表現力を高める育児法】絵本・ディスカッションで思考力と発語力を伸ばそう
『ねえ、どれがいい?』― 子どもの想像力と主体性を育む絵本
⑤ 【親子の絆】絵本がつなぐ『安心と信頼』の時間👨👩👦
絵本の読み聞かせは、親子の心をつなぐかけがえのない時間です。
ぬくもりのある声で物語を共有することで、子どもは
- 安心感
- 信頼感
- 愛着形成
を育みます。
これは、心の安定や自己肯定感にも深く関わります。

👶 わが家の場合
息子は毎晩「絵本よんで〜!」とベッドに飛び込んできます。
この時間は、親子にとって『心の栄養補給』。
1日の終わりに安心して眠りにつける、特別な時間です🛏️
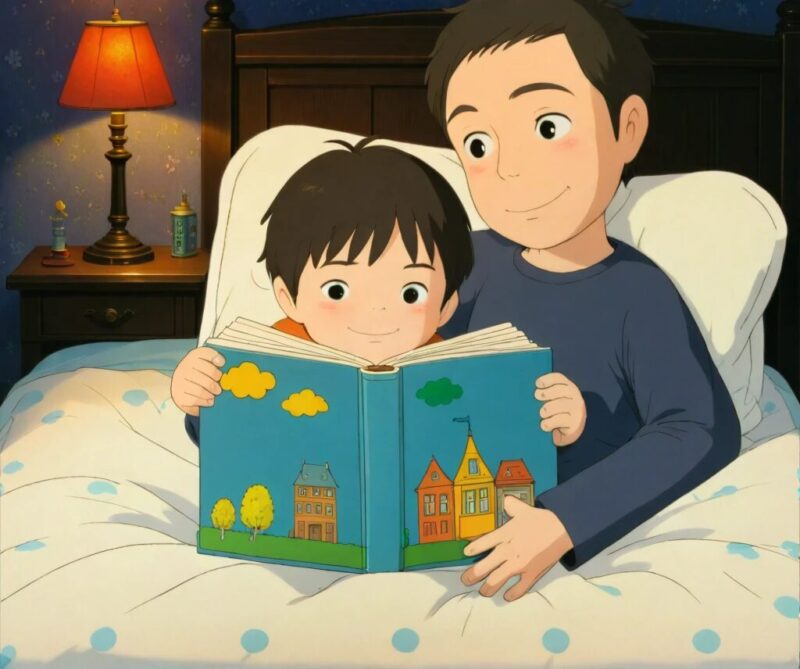
🧑⚕️ 言語聴覚士のコメント
「親の声は、子どもにとって『一番安心できる音』。読み聞かせは、信頼関係を深める最高のツールです」
📚 発達に不安があるお子さんにも
安定した親子関係が、発達の土台になります。
毎日の絵本タイム=心の安全基地にもなります。
🔗関連記事:
【2024年版】親子の絆を深める!創造力とコミュニケーションを育むおすすめおもちゃ10選
【保存版】親子で楽しむ知育遊び!賢く育つアイデア15選
親子でリラックスする方法:家庭内でストレスを管理し、心地よい空間を作る
3. 療育や幼児教育での絵本の効果を最大限に引き出すには📚✨
絵本の読み聞かせを効果的に活用するには、子どもの興味に寄り添った絵本選びと、楽しく無理なく続ける工夫が大切です。
また、療育の現場では、子どもの発達に合わせた絵本を選ぶことが効果的とされています。
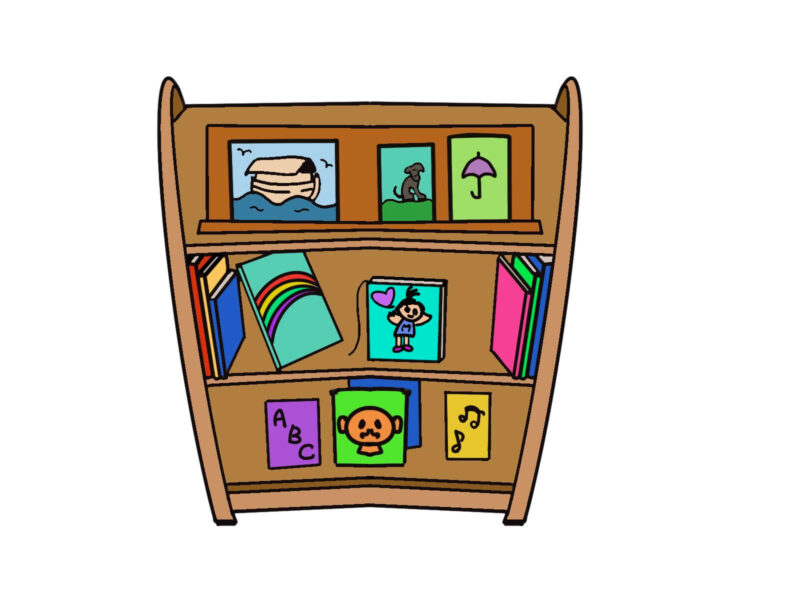
🔍 療育や幼児教育の現場でも実践されているポイント
- 言葉の発達がゆっくりな子には、繰り返し表現やリズムのある絵本
(例:『だるまさんが』シリーズ)が効果的です。 - 感情の理解が難しい子には、豊かな表情を描いたキャラクターが登場する絵本
(例:『かおかお どんなかお』)を使って、気持ちのラベリング(名前づけ)を促す方法が取り入れられています。
📖 わが家の体験談:絵本選びに『好き』を取り入れる工夫
我が家では、息子の好きな「ヒーロー」や「恐竜」が出てくる絵本を1冊、
もう1冊はあえて別ジャンル(季節行事・感情・日常生活など)の絵本を選んで、毎晩2冊読み聞かせしています。
こうすることで、息子の興味を引き出しながらも、自然と新しい語彙や感情表現に触れることができています。
👩🏫 保育士のコメント:
「子どもの『好き』は、読み聞かせへの集中力や定着力を高める最大のカギです」
4. 絵本が子どもに与える『長期的なメリット』とは?📈
絵本の読み聞かせは、その場限りの楽しさにとどまりません。
継続的に読み続けることで、以下のような長期的なメリットが期待できます。
✅ 語彙力・表現力の向上
✅ 共感力や想像力が育つ
✅ 小学校以降の学習・対人関係の土台ができる
特に療育や幼児教育を受けている子どもたちにとって、絵本は感情の調整や自己表現のサポートツールとしても非常に有効です。
📖 わが家の成長エピソード
息子は、絵本の中で覚えた言葉やセリフを日常会話で使うようになり、コミュニケーション力や社会性が少しずつ育ってきたと感じています。
以前は「気持ち」をうまく言葉にできなかったのですが、今では「うれしい!」「ちょっとこわいかも」など、自分の感情を表現する場面が増えてきました。
🧑⚕️ 言語聴覚士のコメント:
「絵本は、語彙や文脈理解だけでなく、感情表現や会話の基本を自然に学べる『ことばの教科書』です」
💡 豆知識:絵本と発達の関係は研究でも注目!
『幼児の心情理解に及ぼす絵本の読み聞かせの効果』では、絵本の読み聞かせが共感性・語彙・情緒安定に好影響を与えることが報告されています。
(🔗出典:奈良教育大学リポジトリ)

📚 ポイント絵本は『毎日の育ちの時間』に!脳の発達もサポートする最強ツール✨
絵本は、ただの「読み物」ではありません。
言葉・感情・認知発達を同時に支える、『育ちの時間』をつくるツールなのです。
なにより大切なのは、親子で毎日楽しく読み続けること。
たとえ短い時間でも、日々の習慣にすることで、絵本の効果はぐんと高まります。
🔍 絵本 × 発達のメリットまとめ
- 🎯 言語・認知・感情の発達に同時アプローチ
- 🎯 発達障害や言葉の遅れがある子にも有効
- 🎯 親子の時間が充実し、安心感・信頼感が育つ
💡たった1冊の絵本が、子どもの世界をぐっと広げてくれることも。
「遊び」としてだけではなく「育ちの時間」として、絵本を日常に取り入れてみてください😊
5. よくある質問
絵本の読み聞かせは何歳から始めるのが良い?
新生児からOK!0歳でも音やリズムを楽しむことができます。
どんな絵本を選べばいい?
年齢や興味に合わせ、シンプルなものから始めるのがおすすめ。
1日に何冊くらい読むのが理想?
1〜2冊でもOK。大切なのは「継続」と「楽しさ」。
子どもが絵本に興味を持たない時は?
興味のあるテーマ(動物・乗り物・ヒーロー)を選び、無理に読ませないこと。
療育で絵本はどう活用されるの?
言葉の発達支援や社会性の学習、感情認識のトレーニングとして使われる。
絵本を読む時間帯はいつがベスト?
寝る前・お風呂上がり・食事後など、リラックスできる時間が◎。
親が読み聞かせるのと、音声で聞かせるのでは違う?
親の声の方が安心感を与え、語彙の習得にも効果的。
絵本を読むときに気をつけることは?
子どものペースに合わせ、感情を込めて読むのがポイント。
発達が遅れている子にも効果がある?
はい。個々に合った絵本を選べば、発語や集中力の向上に役立つ。
絵本を読むと学習能力も向上する?
研究でも証明されており、言語力・記憶力・論理的思考力が向上しやすい。
まとめ絵本は「未来への投資」✨
絵本の読み聞かせは、以下のようなさまざまな面で子どもの発達を支えてくれます。
- 🗣️ 言語能力の向上(語彙・表現力)
- 🧠 認知能力の育成(集中力・記憶力)
- 💞 社会性・感情表現の発達(他者理解・共感)
- 🌈 想像力や創造性の促進
- 👪 親子の絆を深める時間の確保
療育や保育の現場でも、「絵本の読み聞かせ」は発達支援の有効な手段として広く取り入れられており、家庭でも日常のルーティンに組み込むことで、子どもの成長に継続的な良い影響を与えます。
📘 日々の暮らしに絵本という温かな習慣を取り入れ、子どもの未来を一緒に育んでいきましょう。
次回予告🔖
「【年齢別】1歳〜5歳におすすめ絵本まとめ|発語・感情・発達に合う選び方ガイド」を公開予定!
年齢や発達段階に合わせた選書のコツをわかりやすくまとめます。お楽しみに♪






