はじめに
「一緒に遊ぼう!」と「僕も入れて!」。
ほんの少しの言葉の違いですが、幼児にとっては大きなハードルになることがあります。
わが家の息子(4歳)もその一人。
お友達から「一緒に遊ぼう」と誘われれば、にこっと笑ってうなずけます。
でも、みんなが遊んでいるところに自分から入ろうとするとき、
本来なら「僕も入れて」「僕も一緒に遊びたい」と言う場面で、
息子は「僕も一緒に遊ぼう」と言ってしまい、不自然になってしまうことが多いのです。
自分から「誘う」言葉を口にできるだけでも立派なこと。
でも、親としては「もう少しスムーズに会話できたらいいのに…」と思ってしまう場面がありました。

同じ「遊びたい」という気持ちなのに、どうして言葉が変わるのか、息子には理解が難しそうでした。
私も最初は「どうして言えないんだろう?」と戸惑いました。
けれど調べてみると、それは息子の性格や努力の問題ではなく、幼児にとって「言葉のニュアンスの違い」を理解すること自体がとても難しいのだと気づいたのです。

目次
- 幼児にとって「言葉のニュアンスの違い」は難しい
- 幼児が理解しにくい理由
- 視点の切り替えが苦手
- 言葉の細かい違いを感じにくい
- 「遊びは誘われるもの」と思い込みやすい
- 経験不足でイメージできない
- 家庭でできる工夫とサポート方法
- ロールプレイで役割を交代する
- 絵カードやイラストで可視化する
- 「誘われない場面」を意図的に作る
- 実際の遊び場でチャレンジする
- 小さな一歩が大きな自信になる
- 「言葉のニュアンスの違い」を理解するメリット
- まとめ
1. 幼児が「言葉のニュアンスの違い」を理解しにくい理由
視点の切り替えが苦手
特に発達特性のある子は、「自分の視点」と「相手の視点」を切り替えることが苦手です。
「一緒に遊ぼう」は相手目線の言葉、「僕も入れて」は自分目線の言葉。
この立場の切り替えが頭の中でうまくできないことがあります。
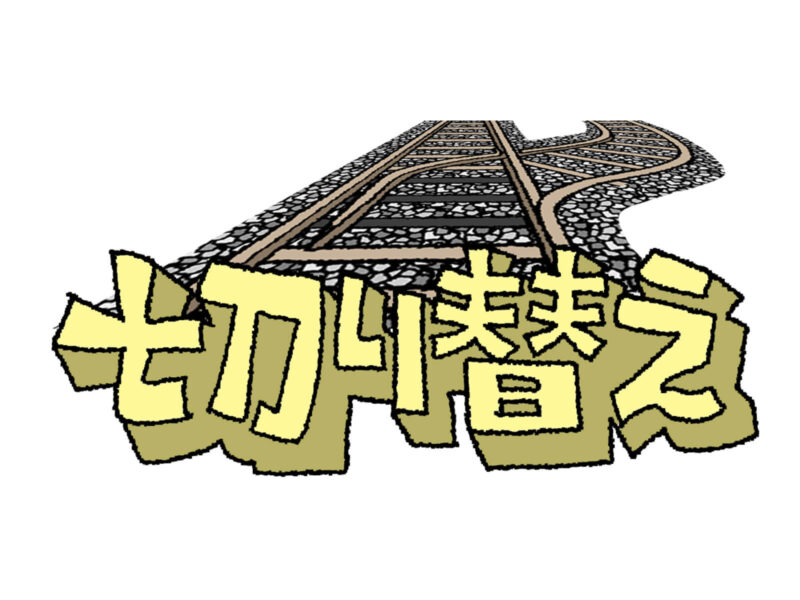
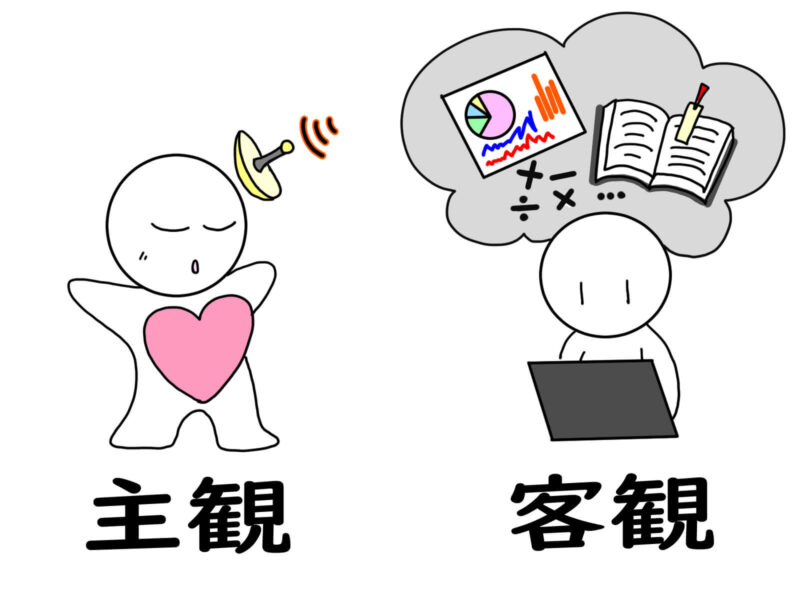
言葉の細かい違いを感じにくい
幼児にとっては、「一緒に遊ぼう」も「僕も入れて」も「遊びたい」の意味にしか聞こえません。
だから、「なんで言葉が違うの?」と感じてしまうんです。

「遊びは誘われるもの」と思い込みやすい
普段からお友達に誘ってもらうことが多い子は、「遊び=誘われて始まるもの」と思い込みがち。
そのため、自分から声をかける場面を想像しにくくなります。
経験不足でイメージできない
実際に「僕も入れて」と言う経験が少ないと、頭で分かっていても、いざという時に言葉が出てきません。

2. 家庭でできる工夫とサポート方法
私は「どうしたら息子が分かりやすいかな?」と考えて、色々試しました。
① ロールプレイで役割を交代する
ぬいぐるみを使って「お友達役」と「息子役」を交代します。
👩「くまさんが『一緒に遊ぼう!』って誘ってるよ」
👦「…うん、いいよ!」
👩「今度は○○くんの番!お友達に入りたいときはなんて言う?」
👦「…僕も入れて!」
こうして立場を交代しながら練習すると、視点の切り替えが少しずつできるようになります。

② 絵カードやイラストで可視化する
私は手作りで絵カードを作りました。
- 青いカード → 「お友達が言う言葉」=「一緒に遊ぼう」
- 赤いカード → 「自分が言う言葉」=「僕も入れて」
色やキャラクターで区別すると、「どっちが言う言葉なのか」がパッと分かるようになりました。

③ 「誘われない場面」を意図的に作って練習
ぬいぐるみ同士を遊ばせて、あえて息子を仲間に入れない状況を演出しました。

👩「くまさんとパンダさんが遊んでるよ。○○くんも遊びたいよね?このとき、なんて言う?」
👦「…僕も入れて!」
ちょっと恥ずかしそうに言ったけれど、自分から言葉を出せた瞬間、息子の顔がぱっと誇らしげになりました。
④ 実際の遊び場でチャレンジする
公園でお友達が楽しそうに遊んでいたとき。
👩「入りたい?」
👦(小さくうなずく)
👩「じゃあ『僕も入れて!』って言ってみよう」
勇気を出して小さな声で「僕も入れて」と言えた瞬間。
お友達が「いいよ!」と笑顔で迎えてくれました。
そのときの息子の輝く笑顔は、今でも忘れられません。

3. 小さな一歩が大きな自信になる
その日以来、息子は少しずつ「僕も入れて」と言えるようになりました。
もちろん、まだ毎回スムーズにはいきません。
しかし、少しずつでも自分の言葉で伝えられた経験は、幼児にとって大きな成長のきっかけになります。
子どもは、たった一度でも「自分の気持ちを伝えて受け入れられた」という体験をすると、
その感覚を記憶し、次に似た場面で自信を持って行動できるようになります。
これは言葉の習得だけでなく、「自分は人と関われるんだ」「お願いしても大丈夫」という自己肯定感にもつながるのです。
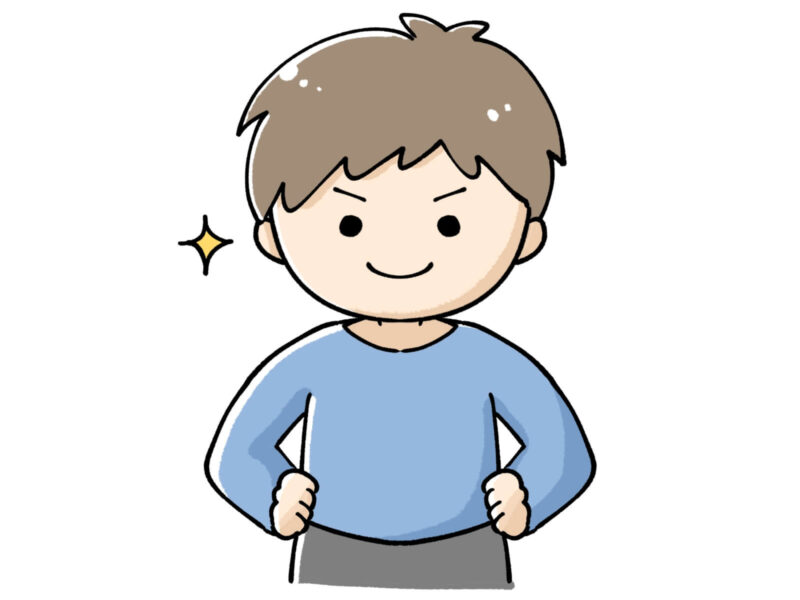
私自身も、息子が小さな声で「僕も入れて」と言った瞬間、胸がいっぱいになりました。
これまで親として何度も見守り、励ましてきた時間が、こうして成果として現れたことに感動したのを覚えています。
子どもにとっての小さな一言は、
未来への大きな一歩であり、成功体験の積み重ねが自信という形で心に刻まれるのだと実感しました。
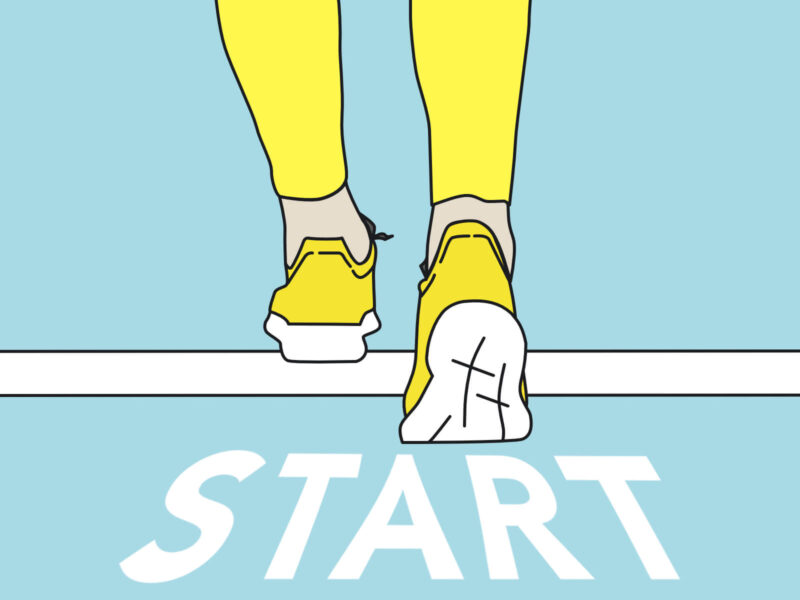
4. 「言葉のニュアンスの違い」を理解するメリット
言葉のニュアンスの違いを理解できるようになると、幼児にとってさまざまなメリットがあります。
1. お友達との遊びがスムーズになる
「一緒に遊ぼう」「僕も入れて」などの微妙な違いを理解し、
自分から適切に声をかけられるようになることで、遊びの輪に自然に入れるようになります。
2. 自分の気持ちを言葉で伝えられる
「やりたい」「参加したい」という思いを、相手に伝えられるようになることで、
欲求や感情を我慢するストレスが減ります。
3. コミュニケーション力が育つ
相手の立場を考え、自分の立場を切り替える経験は、幼児期の社会性や共感力を育てる基礎になります。
言葉のニュアンスの違いを学ぶことは、
単なる言葉の練習に留まらず、子どもが人と関わる力や自己肯定感を育むための大切なステップです。
小さな成功体験を積み重ねることで、やがて自分から主体的に関わろうとする姿勢が育っていきます。

5. よくある質問と答え(FAQ)
幼児が言葉のニュアンスの違いを理解するのは普通ですか?
はい、多くの幼児が「誘う」と「誘われる」の違いを理解するのは難しく、
特に発達特性がある子は時間がかかることがあります。どうして息子は「僕も入れて」と言えないの?
「自分視点」と「相手視点」の切り替えが難しい場合や、経験不足で状況を想像できないことが原因です。
絵カードはどう作ればいいですか?
「青カード=お友達が言う」「赤カード=自分が言う」など色分けして、キャラクターや場面のイラストを描くと理解しやすくなります。
家庭でできる簡単な練習はありますか?
ぬいぐるみを使ったロールプレイで「誘う側」「誘われる側」を交代するのがおすすめです。
公園で実際に試すときのポイントは?
最初は親が声かけの見本を見せ、子どもが小さな声でも「僕も入れて」と言えたら褒めて安心感を与えましょう。
成功体験を増やすにはどうすればいいですか?
家庭での練習+公園での実践を繰り返し、少しずつ成功体験を積み重ねることが大切です。
幼児の理解スピードはどれくらいですか?
個人差があります。
数日で理解できる子もいれば、数週間~数か月かかる子もいます。焦らず取り組むことが大切です。視覚的サポート以外に効果的な方法は?
ロールプレイや会話形式で実践的に練習すること、
親子で具体的な場面を想像して話すことも効果的です。発達障害の子もこの方法で大丈夫ですか?
はい。視覚的に整理したり、段階的に経験を積む方法は発達特性のある子にも適しています。
失敗しても大丈夫ですか?
もちろんです。失敗も学びの一部。成功体験を重ねることが自信につながります。
まとめ
幼児にとって「誘う」と「誘われる」の違いは、とても分かりにくいもの。
でも、
- ロールプレイで役割を交代して練習する
- 絵カードやイラストで整理する
- 誘われない場面を体験してみる
- 実際の遊び場でチャレンジする
こうした工夫で、少しずつ理解できるようになります。
そして何より、子どもが「言えた!」と感じた瞬間の笑顔は、親にとってかけがえのないご褒美。
焦らず寄り添いながら、一歩一歩一緒に歩んでいけたらいいですね😊
📢次回予告
「【実体験あり】発達障害の子どもの登園準備|ASD・ADHDの苦手と家庭・園でのサポート法」
どうぞお楽しみに。
関連記事
3歳〜6歳の子どもが遊びに入れないときの声かけ例|家庭でできるSST・会話アイデア
3歳〜6歳の子どもが遊びに入れないときの理由と声かけ・サポート
【2歳〜4歳向け】七田式えほんの効果|育児ママの実体験レビュー付き
💛感情の切り替えが苦手な子どもに|自己コントロール力8選【療育にも◎】
【保存版】子どもの怒り・パニック対処法|23の感情コントロール遊び
子どもがルールを守らない!家庭でできるしつけと習慣づけの成功例5つ
幼児が乱暴な言葉を言うときの原因と対応法|子育ての悩み解決ガイド
【幼児の自己肯定感を育てる】褒め言葉7選|今すぐ使える声かけ例つき
【言葉の発達に◎】幼児に効果的な日本語CDリスニング学習の始め方と選び方






