はじめに
【こんな悩みありませんか?】
指示をすぐ忘れる、話を最後まで聞けない、宿題に時間がかかる…。
そんな姿を目にして、不安や焦りを感じたことはありませんか?
この記事では、家庭でできる対策とおすすめアプリを紹介します。
💭「どうしてうちの子は、こんなに勉強が苦手なんだろう…」
宿題に何度もつまずく、先生の話がうまく聞き取れない、ちょっと前のことをすぐに忘れてしまう——。
💡実は、こうした困りごとの背景には「ワーキングメモリ(作業記憶)」の弱さが関係していることがあります。
ワーキングメモリとは、短期間の情報を一時的に記憶しながら処理する能力のこと。これは、「短期記憶」「情報処理力」「集中力」など、学習や生活に直結する大切な土台です。
発達障害(ASD・ADHDなど)や学習障害(LD)を持つ子どもにも、このワーキングメモリの弱さが見られることがあります。
私の息子も、幼稚園で集団行動が苦手だったり、先生の指示が通らなかったりと、多くの場面でつまずいていました。その背景にある「見えにくい困りごと」が、まさにワーキングメモリの弱さだったのです。
この記事では、
👉 ワーキングメモリが弱い子どもに見られる特徴
👉 家庭でできるトレーニング・アプリ
👉 学校や園との連携法
などを、実体験を交えてわかりやすく解説します。
お子さんの「苦手」の裏にある理由と、今日からできる具体的なサポートを一緒に探していきましょう🌱
目次
- ワーキングメモリとは?|短期記憶・情報処理に欠かせない力
- ワーキングメモリが弱い子どもに見られる6つの特徴
- 実際に効果を感じた!ワーキングメモリを伸ばす家庭での工夫
- 家庭で簡単にできる!ワーキングメモリを強化する3つの習慣
- 楽しく続けられる!ワーキングメモリを鍛えるおすすめアプリ&ツール
- 教育現場との連携で安心サポート!ワーキングメモリへの理解と対応
- IQが高いのに忘れっぽい?ワーキングメモリとIQの関係をやさしく解説
- 忘れっぽさにイライラしないで…ワーキングメモリが弱い子との関わり方
- よくある質問
- まとめ
1. ワーキングメモリとは?|短期記憶・情報処理に欠かせない力
「ワーキングメモリ(作業記憶)」とは、情報を一時的に覚えながら処理する能力のことです。
イメージとしては「頭の中のメモ帳🗒️」。
たとえば、
- 先生の指示を聞いて行動に移す
- 黒板の文字を覚えてノートに写す
- 文章を読んで意味を理解する
といった、日常のあらゆる場面で必要な力です。
このワーキングメモリが弱いと、
📌 短期記憶がうまくいかない
📌 情報を整理・処理するのに時間がかかる
などの困りごとが起こりやすくなります。
特に、ADHDやASDなどの発達障害や、学習障害(LD)のあるお子さんには、このワーキングメモリの弱さが背景にあることがよくあります。
2. ワーキングメモリが弱い子どもに見られる6つの特徴
ワーキングメモリの弱さは、学習面だけでなく日常生活にも影響します。
以下のような特徴が見られる場合は、サポートの視点で見てあげましょう。
① 指示をすぐ忘れてしまう
「靴を履いて、カバンを持ってきて」と2つの指示を出すと、最初の「靴を履く」はできても、「カバンを持ってくる」を忘れてしまう…そんな場面、心当たりはありませんか?
👉 2ステップ以上の指示を一度に処理するのが苦手なケースです。

② 作業中に何をしていたか分からなくなる
宿題やお絵かきをしていて、別のことに気を取られると、
「何してたんだっけ?」と元に戻れなくなることがあります。
また、話しかけられただけで、記憶がリセットされてしまうことも。
③ 読み書きが苦手・内容が頭に入らない
- 音読中に前の文の内容を忘れて、文章全体の意味が分かりにくい
- 黒板の文字を写す途中で「どこまで書いたか」分からなくなり、順番がバラバラになる
といった困りごとがよく見られます。
👉 読解力・書字力に関わる学習障害(LD)との関連も指摘されています。
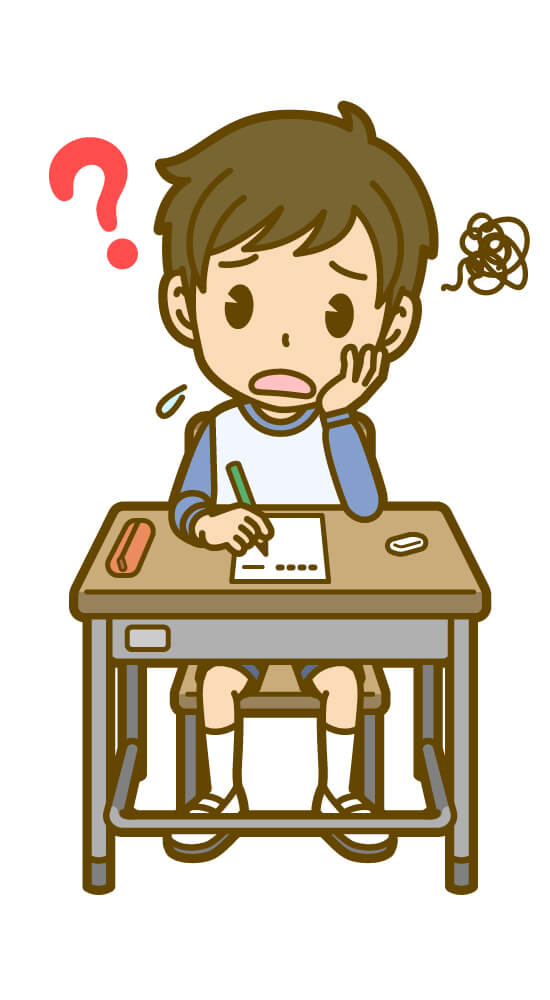
④ 計算ミスが多い・途中で混乱する
- 計算中に繰り上がりや繰り下がりを忘れる
- 長い式や文章題の手順を覚えていられない
- 一度つまずくと、どこからやり直せばいいか分からなくなる
👉 情報処理の順序や保持に負担がかかるため、学習の達成感が得にくくなります。
⑤ 話が飛ぶ・うまく説明できない
話している途中で「何を言おうとしたか分からなくなる」
言葉がつまってしまう・順序が飛ぶなど、会話力や表現の面でも困難が出やすくなります。
👉 特にASDや吃音のある子どもでは、話す順番を整理するワーキングメモリの負担が大きくなる傾向も。

⑥ マルチタスクが苦手
「ランドセルに連絡帳と水筒を入れて、帽子をかぶってね」
…このように複数の指示があると、途中で何をすべきか混乱してしまうケースも多いです。
👉 朝の準備・学校生活など、複数タスクをこなす場面でつまずきが見られることがあります。

このような困りごとが複数見られる場合は、
「うっかり」ではなく「特性」かもしれません。
お子さんの困りごとの背景に「ワーキングメモリの弱さ」があると気づけると、
イライラや叱責が減り、サポートの方向性も明確になります😊
📚関連記事はこちら👇
- ▶ 発達が気になる子どもの身支度サポート!視覚支援と遊びで楽しく解決
- ▶ 発達障害の子に効く!ワーキングメモリを伸ばす遊び&家庭トレーニング4選【実践例つき】
- ▶ 【体験談】発達検査WPPSI-IIIを受けた息子|検査の流れと親の気づき
- ▶ 【体験談】発達検査の結果で見えた支援の方向性|発達障害の子どもへの家庭での工夫とは?
3. 実際に効果を感じた!ワーキングメモリを伸ばす家庭での工夫🛠️
ワーキングメモリの弱さは、「うっかり」ではなく脳の特性によるもの。
我が家では、息子の困りごとを少しでも減らそうと、家庭でできるトレーニングや声かけの工夫を試してきました。
実際に効果を感じた方法をご紹介します👇
① シンプルに伝える工夫で記憶の負担を軽減🗣️
例:「靴を履いて、カバンを持ってきて」ではなく、
➡「まず靴を履いてね。終わったらカバンを持ってきてね」と一つずつ区切って伝えるようにしました。
さらに、「今から2つお願いがあるよ」と最初に予告すると、子どもの集中力が高まりやすくなります。
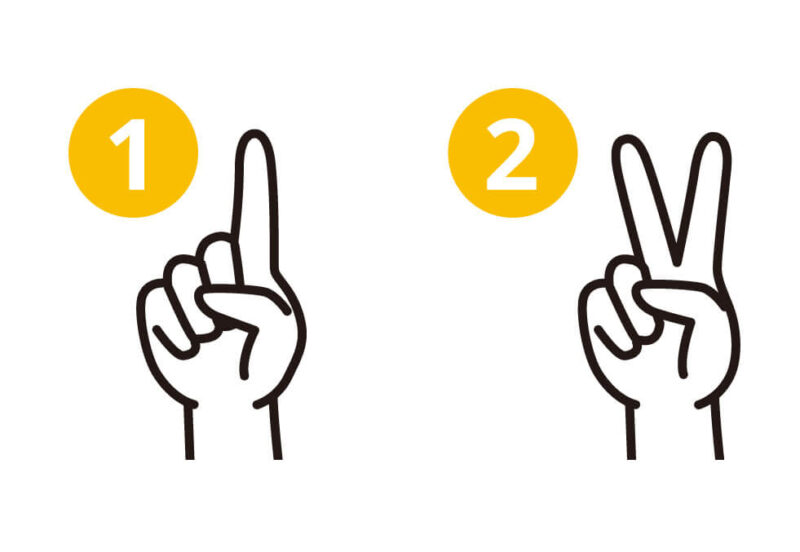
📌 我が家では、この工夫を1週間続けると、「聞き返す回数」がぐっと減りました!
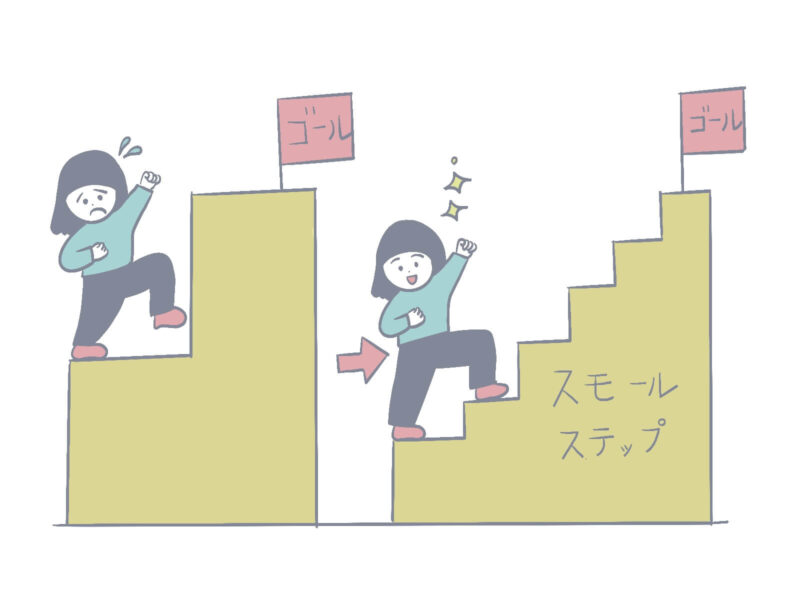
② 視覚的サポートをフル活用👀
言葉だけでは忘れてしまいがちな子どもには、視覚的な手がかりがとても有効です。
例:
- 朝の支度カード(顔を洗う → 歯を磨く → 着替える)
- お片づけ手順カード(おもちゃを箱にしまう → 絵本を棚に戻す)

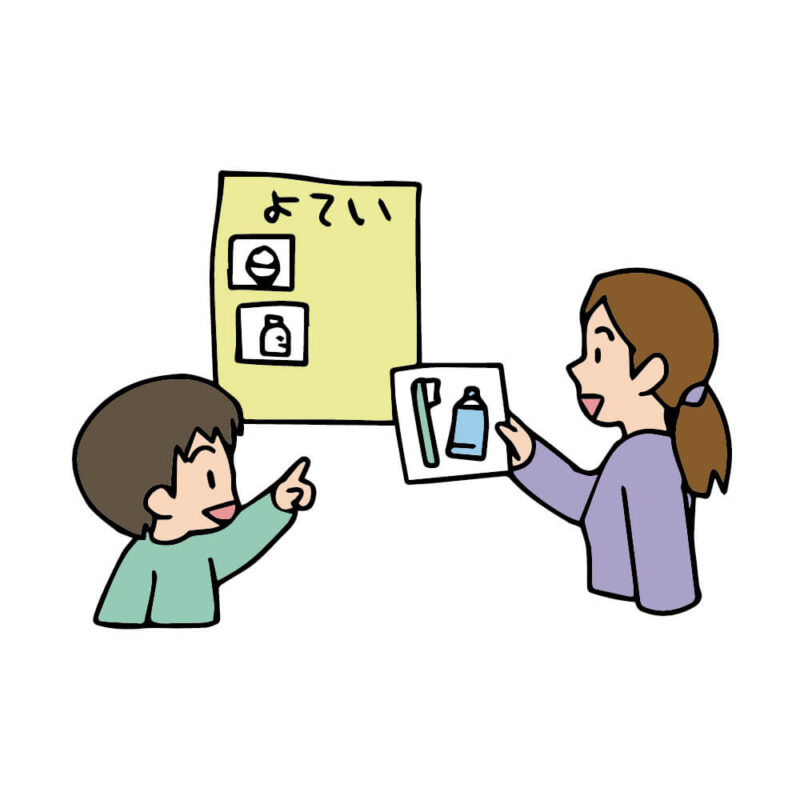
📌このように視覚的に見せることで、記憶の補助になります。
視覚支援を取り入れてからは、「次なにするの?」と聞かれることが減り、自分から動ける回数が増えました✨
関連記事はこちら👇
▶ 【実例17選】家庭でできるTEACCHプログラム|ASDの支援方法をわかりやすく解説
▶ 【決定版】ASDの療育法を徹底比較|ABA・TEACCH・感覚統合の違いと家庭での活かし方
▶ 【実例あり】家庭でできるABAとペアレントトレーニング|発達障害の子どもに変化が見えた関わり方
③ 遊び感覚でできる記憶トレーニング🎮🃏
楽しみながら取り組める、記憶力アップのゲームもおすすめです。
- 神経衰弱:カードの位置や絵柄を覚えることで、視覚的な短期記憶が刺激されます
- 記憶系アプリ(LumosityやPeakなど):子ども向けの記憶トレーニングゲームで、飽きずに続けられます


📌 息子は「遊びならやる!」と毎日5〜10分、自然とワーキングメモリを使う習慣がつきました。
4. 家庭で簡単にできる!ワーキングメモリを強化する3つの習慣📘
ここでは、ASD・ADHDの傾向がある子どもにも効果的だった「家庭でできるトレーニング方法」を3つご紹介します。
① 音読を段階的にステップアップ📚
短い文から始めて、少しずつ長文へ進む「段階的音読」は、短期記憶・理解力の両方を刺激します。
これにより、文章全体を把握し、記憶する力が向上します。
例:
2〜3行の短い詩 → 1段落の物語文 → 会話文を交えた文章
読み終わったら、内容について話し合うことで、理解力も深まります。
「どんな話だった?」「どう思った?」など会話を通じて記憶の定着を促すことも大切です💬

📌 2週間ほど続けると、内容を思い出して話す力が少しずつ育ちました。
② 計算や問題解決に「視覚的補助」を取り入れる✏️
ワーキングメモリが弱いと、計算の途中でつまずくことがよくあります。
そんなときは、以下の工夫が有効です👇
- 図やイラストで数のイメージを見える化
- 繰り上がり・繰り下がりの補助カード
- 計算手順を紙に書きながら進める習慣

📌 書き出すことで、息子は「やることが見える」と安心感を持てるようになりました😊
③ タスクを細かく区切って「達成感」を得る🧩
「部屋を片付けよう」ではなく、
➡「おもちゃ箱をしまおう」→「絵本を棚に戻そう」→「机を拭こう」と小さなステップに分けて伝えるのがポイントです。
1つずつクリアしていくことで、
👉「できた!」という体験が増え、自己肯定感にもつながります💡
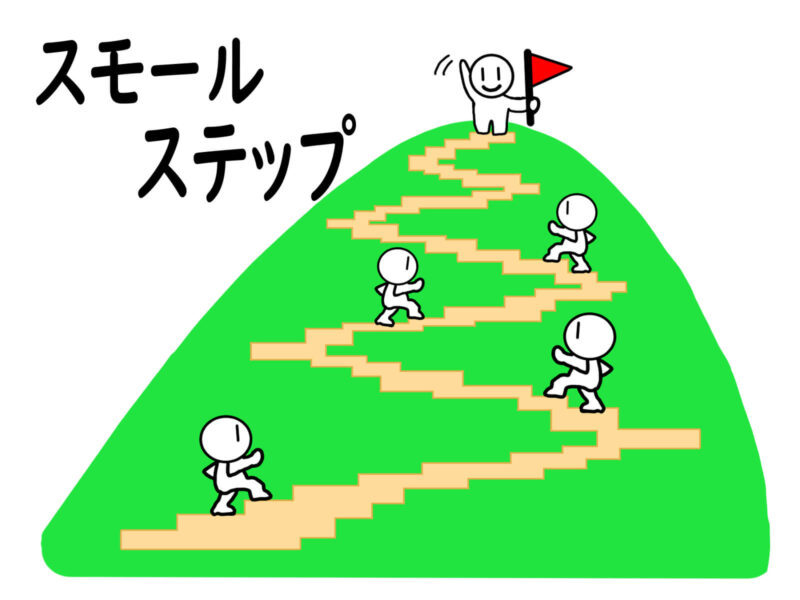
🌱保護者のあなたへ|焦らなくて大丈夫🍀
ワーキングメモリの弱さはすぐには改善しませんが、毎日のちょっとした工夫が積み重なっていきます。
「今日も1つできたね」「ちゃんと覚えてたね!」と今できていることを認めてあげることが、何よりの支えになります。

📚関連記事はこちら👇
▶ 発達障害の子に効く!ワーキングメモリを伸ばす遊び&家庭トレーニング4選【実践例つき】
▶ 家庭でできる!モンテッソーリ教育の基本と実践方法【初心者向け】
▶ つみき遊びの効果がすごい!集中力&空間認識力UPの理由と遊び方
▶ 子どもの空間認知能力を高める6つの遊び|簡単にできるビジョントレーニング&ジャグリング
5. 楽しく続けられる!ワーキングメモリを鍛えるおすすめアプリ&ツール📱
「机に向かうのが苦手」「集中が続かない」そんなお子さんでも取り組みやすいのが、ゲーム感覚で記憶力を鍛えられるツールやアプリです🧠✨
ここでは、我が家でも使って効果を感じた、ワーキングメモリを伸ばすおすすめアプリをご紹介します。

🎮Cogmed(コグメッド)|本格的な記憶力トレーニング
- 医療や教育機関でも導入されているプログラムで、科学的根拠に基づいた内容。
- ゲーム形式で、子どものレベルに合わせて課題が変化。
- 集中力・短期記憶の向上が期待できます。
📌 我が家では、週3回・1日15分で取り組み、2か月後には指示の聞き返しが少なくなりました!
🧠Lumosity(ルモシティ)|認知力を総合的に育てるゲームが豊富
- 記憶力・情報処理・柔軟な思考をバランスよく鍛えるミニゲームが充実。
- 色使いや効果音が楽しく、子どもも飽きずに取り組めます。
- ワーキングメモリに特化したゲームもあり。
🕹️Peak(ピーク)|スキマ時間に取り組める脳トレアプリ
- 1ゲーム約3分でOK!毎日の習慣にしやすい✨
- 「ワーキングメモリ」「注意力」「言語理解」など目的別に選べます。
- 学習障害やADHD傾向のあるお子さんにも無理なく継続しやすい設計。
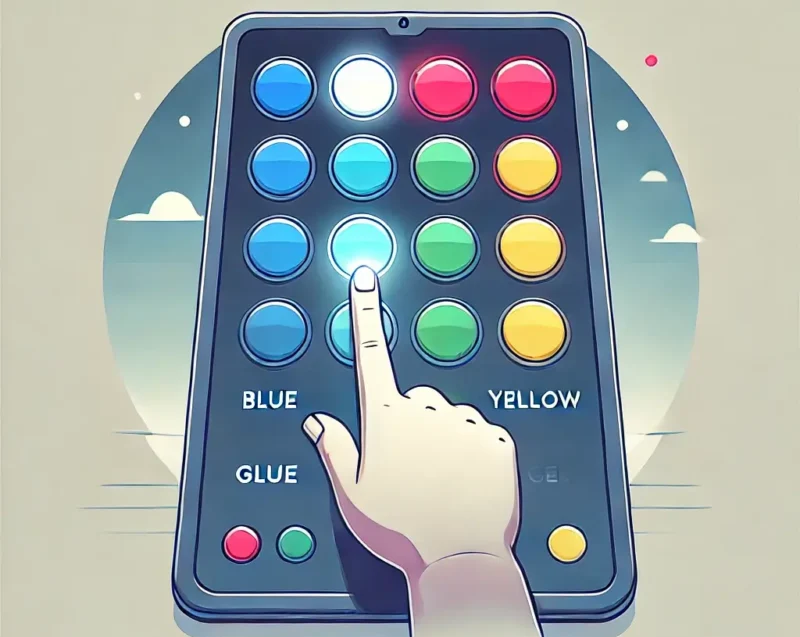
📎関連記事はこちら👇
▶ 【簡単&楽しい】親子でできる知育遊び15選!成長をサポートするアイデア集
▶ 【家庭学習】子どもが楽しく学べる教育ツール&アイデア集
6. 教育現場との連携で安心サポート!ワーキングメモリへの理解と対応🏫
家庭での工夫と同じくらい大切なのが、学校や幼稚園との連携です。
ワーキングメモリが弱い子どもは、情報処理や集団活動に苦手さを感じやすいため、教育現場での理解と配慮が欠かせません。

🧾 IEP(個別教育支援計画)を活用しよう
IEPとは、学習や生活に特別な配慮が必要な子どものために、
学校が一人ひとりに合わせて作成する「個別支援計画」です。
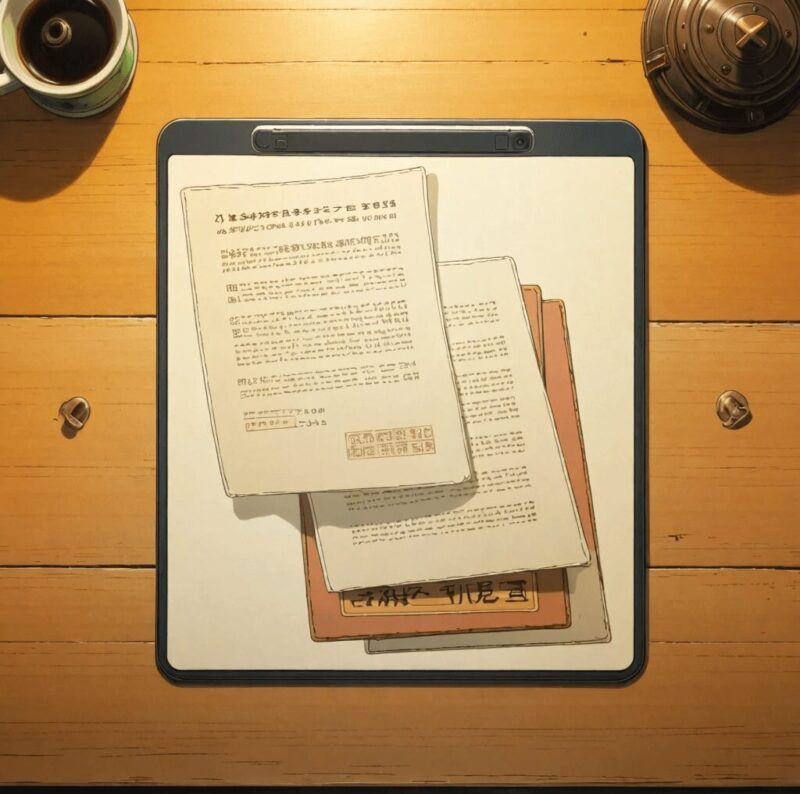
📌 内容には、「どんな場面で困りやすいか」「どんな配慮が有効か」などが盛り込まれ、保護者と教師が共有できます。
✨教育現場でお願いしたい具体的な配慮例
- 視覚支援の活用:イラスト・図表・ホワイトボードの活用など
- 段階的な指示:一度に複数伝えず、1ステップずつ明確に
- メモや手順表の活用:やることを見える化して、不安を減らす

📌 担任の先生だけでなく、「特別支援教育コーディネーター」に相談することで、校内での支援体制がより整いやすくなります。
🤝家庭と学校が連携すると、子どもは安心して伸びていく
我が家では、園の先生に特性を伝えたことで、
「今から〇〇するよ」と事前に声かけしてもらえるようになり、集団活動の不安が激減しました🌈
お子さんのワーキングメモリ特性に合わせた対応を、家庭と教育現場の両方で整えることが、学習のつまずきを減らすカギになります。
📎関連記事はこちら👇
▶ 発達障害の子どもを支える!療育と家庭でできるサポート実践例
▶ 【体験談】療育の効果を実感したのはいつ?1年4か月のリアルな変化
7. IQが高いのに忘れっぽい?ワーキングメモリとIQの関係をやさしく解説🧠
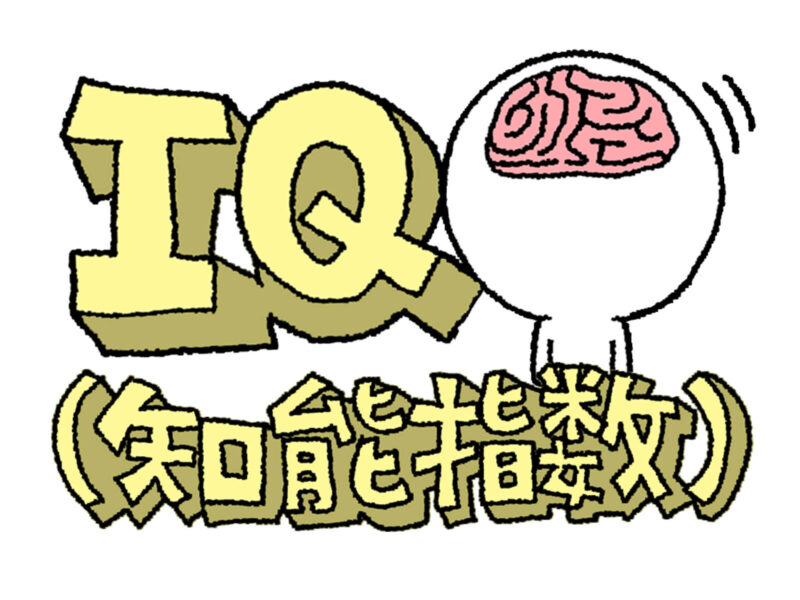
「話は理解しているのに、なんで指示が通らないの?」
「IQが高いのに、どうして忘れっぽいの?」
「テストの点は悪くないけど、日常生活がグダグダ…💦」
そんな風に感じたことはありませんか?
実はIQ(知能指数)とワーキングメモリ(短期記憶・情報処理)は密接に関係しつつも、必ずしも比例するとは限りません。
ここでは、ASD・ADHD傾向や学習障害があるお子さんに多く見られる「IQとワーキングメモリのアンバランスさ」について、わかりやすくご紹介します。
🧠ワーキングメモリ(WM)とは?
一時的に情報を保持しながら処理する力のこと。
例えば、「先生の話を聞いて黒板の内容をノートに書く」といった複数の処理に関わります。
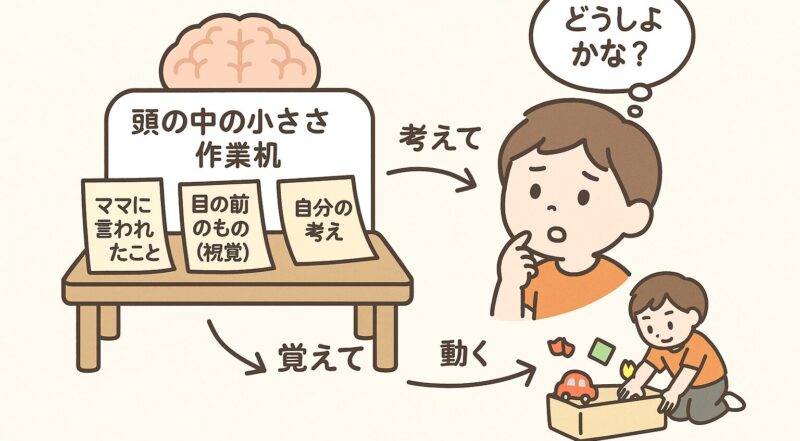
📊IQ(知能指数)とは?
IQ(知能指数)は、人の知的能力を数値化した指標で、100が平均とされます。
以下のような水準の目安があります:
- 高IQ(130以上):非常に優れている
- 平均IQ(90〜109):年齢相応の知的発達
- グレーゾーンIQ(70〜84):発達に少し配慮が必要な可能性あり
- 知的障害の可能性(69以下):日常生活に支援が必要な水準

さらに、IQは以下の4つの指標(指標IQ)に分かれています
(検査例:WPPSI〈幼児〉・WISC〈児童〉・WAIS〈成人〉など)
✔ 言語理解(VCI):言葉の意味理解・語彙・表現力
✔ 知覚推理(PRI):図形・空間認識・パズル的思考力
✔ ワーキングメモリ(WMI):頭の中での一時的な記憶力・情報操作力
✔ 処理速度(PSI):情報を素早く正確に処理する力
🎯ワーキングメモリとIQの関係性とは?
IQの一部にワーキングメモリは含まれますが、IQが高い=ワーキングメモリが高いとは限りません。
✔ ワーキングメモリが低いとIQ全体のスコアに影響することがある
✔ただし、 IQが普通〜高めでも、ワーキングメモリだけが低いことはよくある
具体的なパターン

① IQもWM(ワーキングメモリ)も低いパターン
→ 全体的に認知機能が低めで、情報処理や学習や思考のスピードがゆっくり
→ 例えば
📌 話の流れについていくのが難しい、繰り返し説明が必要
② IQは普通だけどWM(ワーキングメモリ)が低い(非常によくある!)
→ 知識はあるが「処理しきれない」ためミスが増える
→ 「話を理解する力や知識はあるけど、複数の情報を同時に処理するのが苦手」
→ 例えば
📌 一度に複数の指示を聞くと忘れてしまう
📌 順番通りに作業するのが難しい
📌 段取りに時間がかかる
📌 計算はできるのに、暗算が苦手
📌 読み書きはできるのに、文章をまとめるのが苦手
③ IQが高いのにWM(ワーキングメモリ)が低い(発達特性のある子に多い)
→ 「頭は良いのに生活が不器用」に見えることが多い
→ 「考える力はあるけど、記憶の持続が難しい」
→ 例えば
📌 難しい質問には答えられるのに、簡単な指示を忘れる
📌 知識はあるけど、テストの時間内に解けない
📌 頭が良いのに、持ち物を忘れる・日常の段取りが苦手
まとめ
💡 ワーキングメモリはIQの一部だけど、IQ全体のスコアを決めるものではない
💡 IQが高くてもワーキングメモリが低いことはよくある
💡 ワーキングメモリが低いと「困りごと」は多くなるが、知的能力とは別
🔑サポートのヒント
- ✔ 指示は短く区切って伝える
- ✔ やることリストやイラスト、スケジュール表を使う
- ✔ 「できたこと」に注目して自信を育てる
💡 IQや知的能力が高くても、「うっかり・忘れやすい」は本人のせいではありません。
記憶の扱い方に合わせて環境を整えることで、お子さんの力はしっかり発揮されていきます🌱
📎関連記事はこちら👇
▶ 発達障害の子に効く!ワーキングメモリを伸ばす遊び&家庭トレーニング4選【実践例つき】
▶ 【完全版】3歳児向け知育アイデア20選!家庭&外遊びで楽しく学ぶ
▶ 【2024年最新版】2歳児向け知育玩具おすすめランキングTOP10|人気&口コミ付き
▶ 【最新版】未就学児におすすめの知育おもちゃ15選|2〜6歳に買ってよかった実体験つき
8. 忘れっぽさにイライラしないで…ワーキングメモリが弱い子との関わり方💕
ワーキングメモリが弱いと、日常のちょっとしたことでもつまずくことが多くなります。
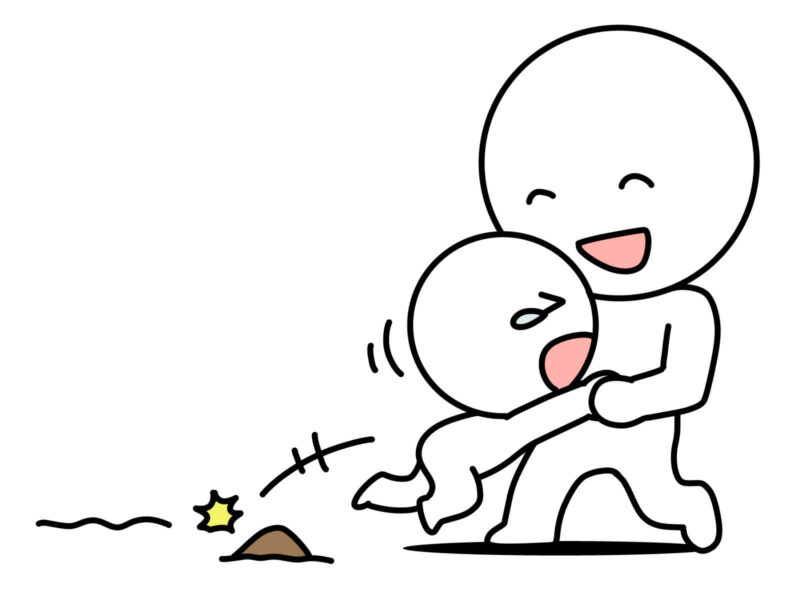
「さっきも言ったよね!」「また忘れてる!」
こんな風に、毎日同じことを繰り返していると、つい感情的になってしまうこともありますよね…。
でも、ワーキングメモリが弱い子にとって、「覚え続けること」自体がとても大変なことなんです。
ここでは、日々の声かけで私が意識している3つの関わり方をご紹介します🌼
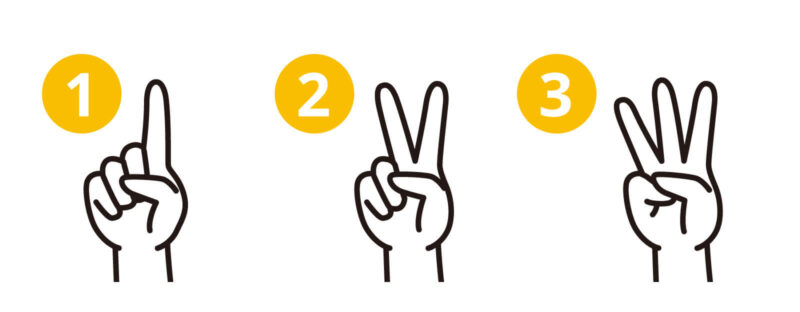
1️⃣ 怒らず、繰り返し伝える
忘れたり、途中で抜けたり、同じ失敗が続いても、「なんでできないの!」「前も言ったでしょ!」でと怒らずに、
「もう一度やってみようね」「もう一回一緒にやろうね😊」と落ち着いて繰り返し関わることで、安心感が育ちます。
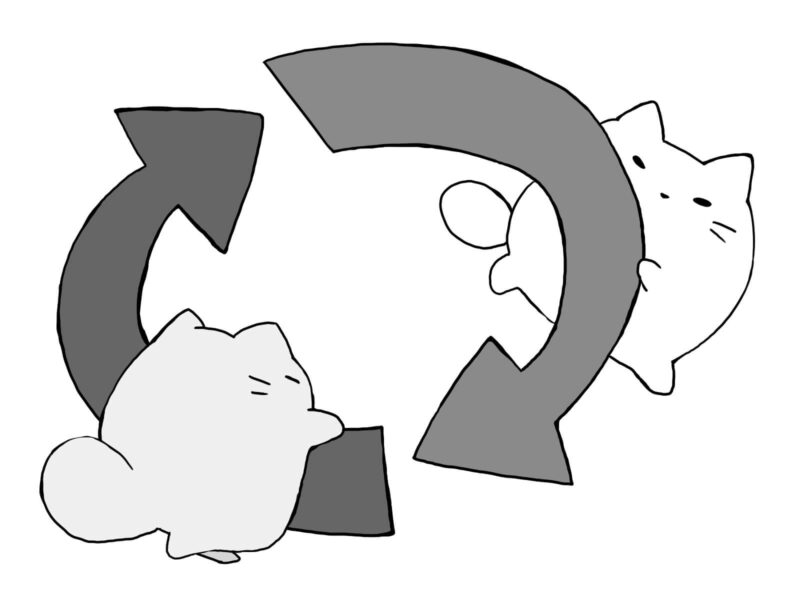
2️⃣ 短く・具体的に伝える
長い説明や抽象的な言葉は理解しにくいため、「〇〇をしたら、次に〇〇しようね」とシンプルに伝える。
「早く支度して!」よりも
「くつをはいて→カバンを持って→玄関に行こう」と段階を分けて伝えるのが効果的です✨
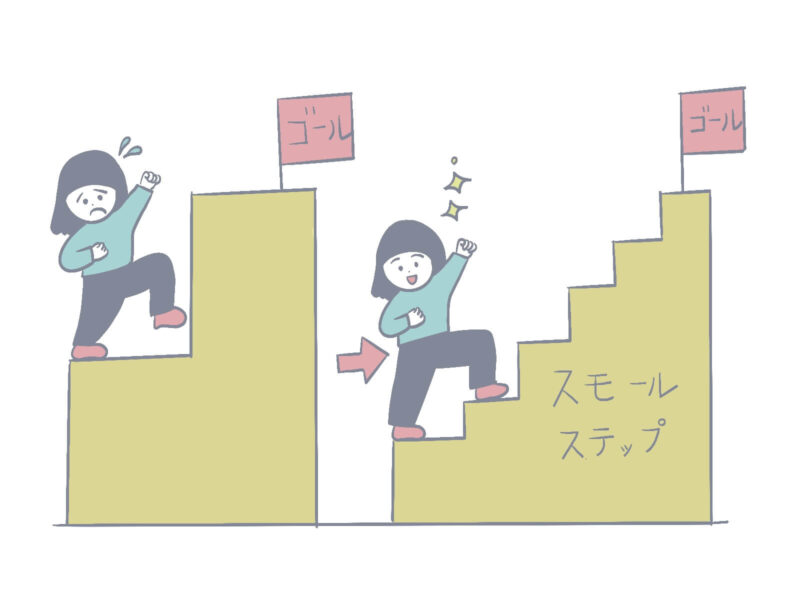
3️⃣ 一つできたら思いきり褒める🎉
「ちゃんと覚えてたね!」「今、自分でできたね!」など、小さな達成を大げさなくらいに褒めることで、成功体験が積み重なります。

💬【わが家の体験】
「今日は自分で準備できたね!」と毎日声をかけ続け、
さらに口頭だけでなく、絵カードを使って順番に並べる遊びを取り入れることで、楽しみながら取り組めるようになりました✨
最初は何度言ってもできなかったことが、視覚的な支援と声かけの工夫によって少しずつ身につき、
数週間後には「ママ、今日は全部自分でできたよ!」と自信たっぷりに報告してくれるまでに成長しました☺️
🌈まとめ|「できない」のではなく「今はむずかしい」だけ
ワーキングメモリが弱い子どもは、「わざと忘れてる」「やる気がない」わけではありません。
私たち大人がサポートの視点を変えることで、子どもたちは少しずつ、でも確実にできることを増やしていきます。
💌あなたも、十分がんばっています
「うまくいかない日もあるけれど、それでも関わり続ける」
その姿勢こそが、子どもにとって何よりの安心材料です🌷
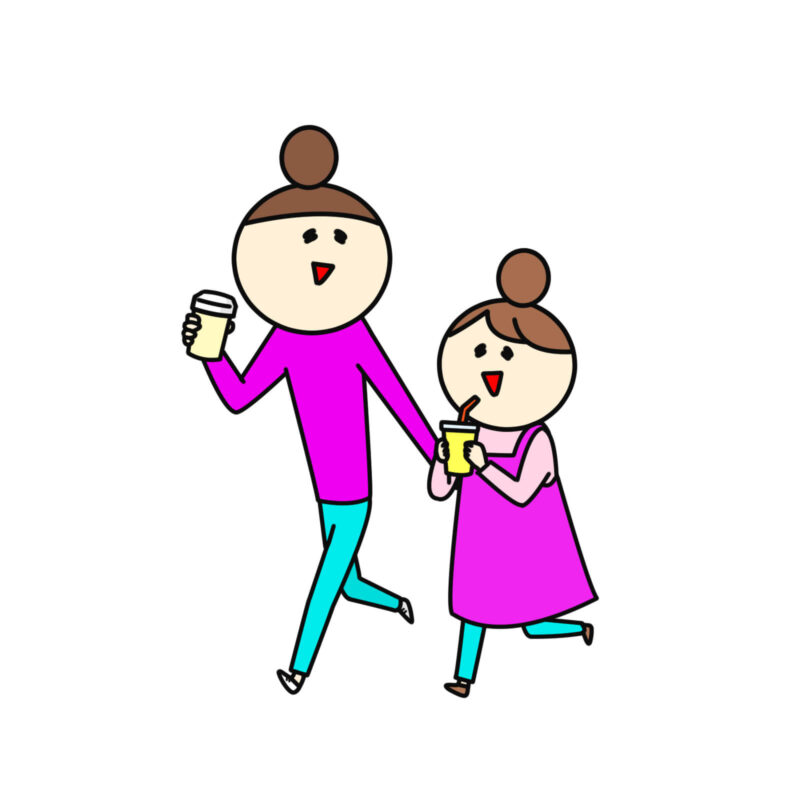
📎関連記事はこちら👇
▶ 療育×声かけ|成功するポジティブコミュニケーションのコツと実例
▶ 挑戦できない子どもへの対応法|親の声かけ実例と自信の育て方
▶ 💛感情の切り替えが苦手な子どもに|遊びで身につく自己コントロール力8選【療育にも◎】
9. よくある質問
ワーキングメモリとは何ですか?
短期間の記憶を保持しながら情報を処理する能力のことです。
学習や日常生活で重要な役割を果たします。ワーキングメモリが弱いとどんな影響がありますか?
読み書きの苦手さ、計算の困難、複数の指示を覚えられない、注意散漫などの問題が起こることがあります。
ワーキングメモリは鍛えられますか?
一定のトレーニングで向上が期待できます。音読やゲーム、視覚的なサポートなどが効果的です。
学習障害のある子どもにどんなサポートができますか?
タスクの分割、視覚的な補助、音読の工夫、計算の補助などが役立ちます。
アプリを使うとワーキングメモリが鍛えられますか?
「Cogmed」「Lumosity」「Peak」などのアプリは、ゲーム感覚で記憶力を向上させるのに役立ちます。
学校で先生に相談するときのポイントは?
具体的な困りごとを伝え、視覚的補助や個別対応の提案をすることが大切です。
幼稚園児でもワーキングメモリの問題はありますか?
はい。指示を覚えられない、集団行動が苦手、話が長くなると混乱するなどの兆候が見られることがあります。
ADHDの子どもはワーキングメモリが弱いですか?
ADHDの子どもはワーキングメモリの問題を抱えていることが多いですが、個人差があります。
家庭でできるワーキングメモリ強化の遊びは?
神経衰弱、しりとり、ストーリー作り、積み木遊びなどが効果的です。
どのくらいの期間でワーキングメモリは改善しますか?
個人差がありますが、継続的なサポートを行うことで徐々に改善が期待できます。
まとめ
ワーキングメモリが弱い子どもにとって、日常や学習は想像以上に大きなハードルです。
私も息子の「できないこと」ばかりに目が向き、「どうして?」と悩む日々が続いていました。
でも、それは本人の努力不足ではなく、脳の特性によるもの。
そのことに気づいてから、私たちは「責める」から「支える」関わりへと、少しずつ変わっていきました。
たとえば…
📖 読み聞かせ中に「次はどうなると思う?」と問いかけて記憶を促す
🎴 神経衰弱やアプリで遊びながら記憶力を高める
🗂 タスクをカードで「見える化」し、次の行動を分かりやすくする
小さな工夫の積み重ねで、息子にも少しずつ「できた!」の経験が増えてきました😊
完璧を目指さなくて大丈夫です。
「今、できていること」に目を向けて、お子さんと一緒に少しずつ前へ進んでいきましょう。
🌼親であるあなた自身も、十分にがんばっています。どうかご自身のことも、大切にしてくださいね。
📌 今回のまとめ
- ワーキングメモリは「短期記憶と処理」を担う大切な力
- 弱さがあると、勉強・生活のあらゆる場面で困りごとが生じやすい
- 家庭でも、視覚支援・声かけ・遊び・アプリなどでサポートが可能
- 子どもの特性に合った関わり方が、自信と笑顔につながる
関連記事はこちら👇
📝次回予告
👉「空間認知能力を高める6つの遊び|ジャグリングやビジョントレーニングも紹介」です。
お楽しみに!






