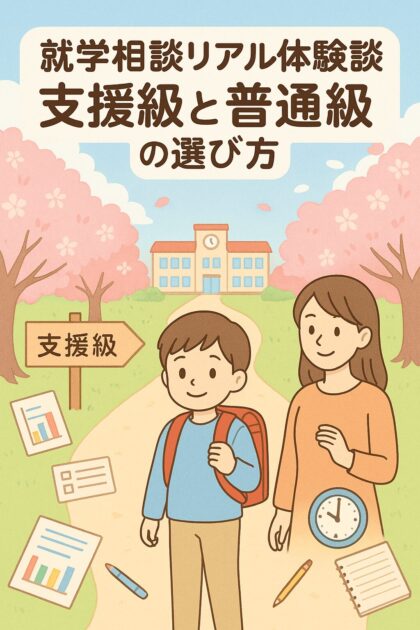目次
- はじめに:就学相談とは?なぜ必要?
- 就学相談の流れとスケジュール(年長秋〜入学前)
- 【就学相談】親だけ参加?
- 就学相談で聞かれること
- 後悔しないための就学相談準備ポイント
- 支援級か普通級か…迷ったときの考え方
- 就学相談でよくある不安とその対策
- 私の就学相談リアル体験談まとめ
- 周りの保護者の就学相談体験談タイプ別まとめ
- 就学相談でよくある質問
- まとめ
1. はじめに:就学相談って何?なぜ必要?
「就学相談」とは、小学校入学前に教育委員会や学校の先生と話し合い、子どもに合った学びの環境を一緒に考える場です。
発達特性や学習面・生活面に不安がある場合、特別支援学級や通級などの選択肢を含めて検討する大切な機会になります。
私も、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD・DCDと吃音のある息子の就学相談を経験しました。
今回は、流れ・準備・聞かれること・後悔しないコツを、リアル体験談としてまとめます。
2. 就学相談の流れとスケジュール(年長秋〜入学前)
一般的な就学相談の流れは以下の通りです。
自治体によって細かい時期や手順は異なります。

1. 申し込み(6〜7月)
教育委員会や市区町村の就学相談窓口に申し込みます。
2. 発達検査(必要に応じて)
WISC-VやKABC-II,新型K式,田中ビネーなどが多く、診断や支援方針の参考にします。
3. 面談(就学相談本番)
保護者・子ども・担当者で、日常の様子や支援の必要性を話し合います。
4. 書類の提出
①~③の書類を教育委員会に提出
①教育支援個人票(保護者記入用)
②教育支援委員会協議のための基礎資料(保育園・幼稚園作成)
③検査結果(WISC-VやKABC-II,新型K式,田中ビネー等)
5. 対象児童の把握
保護者の了解を得て、教育委員会が保育園・幼稚園を訪問し、子どもの様子を確認
6. 教育委員会開催
推奨する就学の場を判定
7. 就学先の決定(判定と通知)(12月〜1月)
保護者の同意を得て、教育委員会から就学先の案内が届きます。(決定通知)
私の場合は、発達検査の予約が混んでいて、申し込みから実施まで約3カ月待ちでした。
早めの動きが安心につながります。
3. 【就学相談】親だけ参加?
「就学相談は親だけで参加してもいいのか?」という点ですが、結論から言うと 多くの自治体では可能 です。
ただし、状況や目的によってメリット・デメリットがあります。

就学相談 親だけ参加する場合
メリット
- 子どもにとって負担や緊張が少ない
- 保護者が落ち着いて話を聞き、質問できる
- 園での様子や発達検査の結果など、資料だけで説明できる場合もある
デメリット
- 実際の子どもの様子を担当者が直接見られない
- 行動面やコミュニケーションの印象が伝わりにくい
- その場で簡易な観察ややりとりができないため、判断材料が限られる
就学相談 子どもも一緒に参加する場合
- 担当者が直接、表情・話し方・反応・集中の様子などを見られる
- その場で簡単なテストや質問遊びができる
- 「資料だけでは分からない部分」が評価に加わる
就学相談 実際の流れ
- 1回目は親だけで話を聞く
- 2回目以降に子ども同伴で観察・やりとりをする
という2段階方式をとる自治体も多いです。
💡 ポイント
「子どもが不安がる」「スケジュールが合わない」という場合は、親だけでも相談可能です。
ただし、その場合は 園での様子を詳細に記録した資料や動画 を持参すると、判断がスムーズになります。
4. 就学相談で聞かれること
面談では、主に以下のような質問を受けました。
- 成育歴(生まれた時の状況~現在に至るまで)
- 家庭での生活リズム(就寝・起床時間)
- 集団活動での様子(園での行動、友達との関わり方)
- 学習面(ひらがな・数字・簡単な計算の理解度)
- 感情のコントロール(嫌なこと・困ったときの対応)
- 身辺自立(トイレ、着替え、持ち物管理)
- 医療や療育の利用状況
準備として、家庭と園での様子をメモにまとめ、記録を持参するとスムーズでした。
5. 後悔しないための就学相談準備ポイント
就学相談を終えて振り返ると、「これはやっておいて本当によかった」と思う準備が3つありました。
これらをしておくことで、当日の不安や後悔をかなり減らせます。

① 学校の見学は「百聞は一見にしかず」
ネットやパンフレットでは分からないのが、教室の雰囲気や先生の関わり方、子どもたちの様子です。
支援級と普通級の両方を見学すると、クラスの人数やサポート体制、授業中の雰囲気の違いがよく分かります。
「支援級=閉ざされた空間」という固定観念が変わったのも、見学のおかげでした。


② 質問リストの作成で聞き逃し防止
就学相談では、緊張しているうちに時間が終わってしまうこともあります。
事前に「授業中に立ち歩きがあった場合の対応」「加配の先生が入る条件」など、気になる点をリスト化しておくと安心です。
私はスマホのメモに書き出して、その場でチェックしながら質問しました。

③ 子どもと一緒に通学路の練習
実際に歩くと、信号の位置や車通りの多さ、坂道の有無など、想像と違う発見があります。
登下校の所要時間や危険箇所を把握できるので、防犯や体力面の不安も減ります。

6. 支援級か普通級か…迷ったときの考え方

「普通級にしたら支援が受けられない?」という誤解
就学相談でよく聞く声のひとつが、
「普通級を選んだら、もう支援は何も受けられないんですよね?」
という不安です。
という不安です。
結論から言えば、普通級でもさまざまな支援を受けられる可能性があります。
ただし、制度の内容や利用条件は自治体や学校によって異なるため、確認は必須です。
1. 普通級でも受けられる主な支援制度
通級指導教室(通級)
普通級で学びながら、週に数時間だけ別室または、別の学校で、個別または小集団の指導を受けられる制度です。
例:国語の作文が苦手なら作文指導、音読のサポートなど、課題に合わせた支援が可能。
加配の先生(加配教員)
学級担任をサポートするために追加配置される教員です。
授業中の補助や休み時間の見守り、行事のサポートなど、日常的に関わってくれます。
個別の学習支援
授業の一部を別室で行う、放課後補習を行うなど、本人のペースに合わせた学びが可能です。
2. 柔軟な学び方「交流学習」制度
普通級と支援級の両方を活用する方法もあります。
例えば…
- 国語と算数は支援級で少人数指導を受け、
- 図工や体育、音楽は普通級でクラスの友達と一緒に学ぶ
このような「交流学級制度」を導入している学校も多く、子どもの特性や得意分野に応じた柔軟な学び方が可能です。
3. ポイントは「自治体と学校の確認」
支援の内容や条件は、同じ県内でも自治体・学校によって差があります。
私の地域では普通級でも通級や加配が利用しやすい一方、
友人の地域では申請条件が厳しく、支援を受けられるまで時間がかかることもありました。
就学相談の際は、次のような質問をしておくと安心です。
- 普通級を選んだ場合、どんな支援が受けられますか?
- 交流学習は可能ですか?
- 加配の先生はどんな条件で配置されますか?
まとめ
「普通級と支援級のどちらが正解か?」ではなく、
「今のわが子が安心して学べる環境はどこか」という視点が大切です。

- 支援級 → 少人数で手厚いサポート。集団が苦手な子にも安心
- 普通級 → 同年代と同じカリキュラムで学び、友だちとも関わりやすい
- 通級 → 普通級をベースに、必要な時間だけ支援を受けられる
実際に見学してみると、事前のイメージと違うことも多く、希望が変わる場合もあります。
私は見学を通して「この環境なら息子が安心して過ごせそう」と感じた支援学級を第一希望にしました。
また、支援級に在籍する先輩ママからの具体的なアドバイスも大きな参考になりました。

🔹普通級を選んだからといって、支援の道が閉ざされるわけではありません。
通級や加配など、多様な制度を活用しながら、お子さんに合った学びの形を作ることができます。
🔹また、支援級を選んだ場合でも「交流学級制度」がある学校では、
支援級に在籍しながら、「普通級」にも籍を置き、図工や体育、音楽など一部の授業を普通級で過ごすことが可能です。
大切なのは、制度の内容を知ることと、利用できる支援を早めに確認することです。
知識があることで、進路の幅や安心感が大きく変わります。

7. 就学相談でよくある不安とその対策
ショックな判定を受けたら…
就学相談の判定は、あくまで「今の状態」をもとにした提案です。
子どもの成長や状況に応じて変更の申し立てもできます。
「支援級にすると将来が限られる?」という不安
支援級に在籍しながら、学年が上がるタイミングで普通級へ移る事例もあります。
実際のところ、多くはないようですが、珍しくもないようです。
転籍には教育委員会の承認が必要ですが、可能性は閉ざされません。
交流学級とは?
交流学級とは、支援学級に在籍している児童が、普通級の授業や学校生活に一部参加する制度です。
これは、子どもの得意分野や成長段階に合わせて、少しずつ集団活動や普通級のカリキュラムに慣れていくことを目的としています。
たとえば…
- 国語や算数など集中が必要な科目は支援級で少人数指導
- 図工、体育、音楽、生活科などは普通級の友達と一緒に参加
交流学級を活用することで、
- 普通級の友達とのつながりを保てる
- 得意分野を伸ばしやすい
- 将来的な普通級への移行がスムーズになる
などのメリットがあります。
ただし、交流学級の取り組み内容や回数は学校・自治体によって異なります。
見学や就学相談の際に、「どの科目で交流できますか?」「頻度はどのくらいですか?」と確認しておくと安心です。
8. 私の就学相談リアル体験談まとめ
幼稚園の先生、療育先のスタッフ、就学相談の担当者、診断を受けた病院の先生――
実は、誰もが一方的に「支援級がいい」と断言するわけではありません。
だからこそ、親としては迷う場面が多いのです。
さらに感じたのは、就学相談や支援級には地域格差があるということ。
市町村によって、支援級のサポート内容や雰囲気は大きく異なります。
私の地区では「支援級希望者が増えていて、希望しても必ず入れるとは限らない」という状況でしたが、
実際に見学してみると明るく開けた印象で、ネガティブな印象は受けませんでした。
一方で、友人の地域では支援級が「閉ざされた環境」に感じられることもあり、ハードルが高いと感じる親御さんもいます。
中には、希望の支援級に通わせるために学区を変えたり引っ越しを決断する家庭もあります。

私は、息子の特性に気づいたのが3歳児健診のときでした。
それ以来、「普通級に入学すること」を一つの目標に、日々の療育や家庭でのサポートに力を入れてきました。
しかし、WISC検査によって発達特性が明確になり、その結果を踏まえて支援級を希望する決断をしました。
正直、普通級を想定していた分、検査結果はショックでした。

それでも、支援方法が具体的に分かったことで、就学先を選ぶための重要な判断材料になったと感じています。
就学前に発達検査を受けれて良かったと思います。

小学校には、いくつかの選び方があります。
普通級で集団生活に慣れていく方法もあれば、支援級で困り感を減らし、安心してスタートする方法もあります。
また、支援級に在籍しながら必要に応じて普通級の授業に参加する「交流学習」を取り入れている学校も多く、
私の住む地区は「交流学習」が主流でした。
我が家では、支援級に在籍しつつ、小学校3〜4年生頃には完全普通級への移行を目標にサポートしていく予定です。

選択肢は一つではありません。
就学相談は、お子さんに合った学びの環境を探すための「入り口」です。
「支援級」か「普通級」かを一度決めたら変えられないわけではなく、子どもの成長や状況に応じて見直すことができます。
私自身、迷いながらも行動を起こしたことで、必要な情報が集まり、不安が少しずつ軽くなりました。
最終的に感じたのは、親が安心して送り出せる準備こそ、子どもにとって最高のスタートサポートになるということです。

9. 私の周りの就学相談リアル体験談まとめ
就学相談を経験した保護者さんを見ていると、立場や考え方によっていくつかのパターンに分かれます。
ここでは、実際に聞いた声をもとにタイプ別の特徴と流れを整理しました。
タイプ①:
支援級に決めているタイプ
「最初から支援級が安心」と考えているケース。
流れとしては、判定の説明を聞き、必要書類を受け取って終了というスムーズな進行が多いです。
タイプ②:
支援学級か普通級かで迷っているタイプ
就学相談では普通級を勧められるケースが多め。
普通級で入学し、1学期を過ごしてから必要に応じて支援級へ移るパターンもあります。
ただし、支援級への移籍は教育委員会での会議や手続きが必要なため、実際に利用できるのは3学期からになることもあります。
タイプ③:
準備不足で迷いが深まるタイプ
最新の発達検査結果がない、または情報整理が不十分なまま相談に臨むケース。
必要な資料が揃っていないと、普通級を勧められることが多いようです。
判定が後回しになることもあります。
タイプ④:
知的障害があるタイプ
生活や学習において明確な支援が必要なため、支援学級または支援学校を勧められることが多いです。
タイプ⑤:
知的発達は平均〜グレーで、診断あり生活面の困り感が少ないタイプ
日常生活ではほぼ困らないため、普通級を勧められる傾向があります。
ただし、学習面や集団活動でつまずく可能性もあるため、入学後のフォローが重要です。
タイプ⑥:
支援学級か支援学校かで迷っているタイプ
支援学校は障害の程度が比較的重いお子さんが多く通うため、環境やカリキュラムの違いをしっかり比較検討する必要があります。
タイプ⑦:
加配や通級も含めて検討するタイプ
「普通級に在籍しつつ、必要な時間だけ通級や加配を利用する」という中間型の支援を希望するケース。
学校によっては受け入れ体制が異なるため、事前確認が必須です。
タイプ⑧:
ADHD(注意欠如・多動症)が主な特性の場合
「ADHDだけでは支援級に入れない」というのは一部本当で、一部誤解があります。
ADHDは知的発達に遅れがない場合が多く、この場合は通常級が基本です。
ただし、集中力や衝動性により授業参加が難しい場合は、通級指導教室(情緒級)や加配支援が検討されます。
また、自治体によっては支援級(情緒)での受け入れもあり、判断はお子さんの困り感と地域の支援体制によります。
インクルーシブ教育の視点から

インクルーシブ教育とは、障害の有無にかかわらず、すべての子どもが共に学び、成長できる教育のこと。

就学相談でも、この理念に基づき「普通級で可能な限りサポートする」方向性が重視されることがあります。
一方で、サポート体制が不十分な場合は、支援級や支援学校の方が本人に合う場合もあります。
重要なのは、「制度」よりも「本人にとって安心して学べる環境」を第一に考えることです。
親の考え方によるタイプ分け
- Aタイプ:就学相談で「普通級で大丈夫」と言ってほしい
- Bタイプ:支援級に入れるための形式的な相談と考えている
- Cタイプ:情報不足で判断材料が少ないまま悩んでいる
- Dタイプ:障害はあるが、普通級に入れたい意思が強い
- Eタイプ:障害はあるが困り感が少なく、普通級でいいか確認したい
- Fタイプ:困り感はあるが、支援級に行かせたくない。普通級で対応してほしい
まとめ
就学相談は、家庭の考えやお子さんの特性によってゴールが大きく変わります。
事前に自分のタイプを把握し、必要な情報や質問を整理して臨むことで、後悔のない選択がしやすくなります。

10. 就学相談でよくある質問
発達検査は必須?
自治体や学校によって異なりますが、多くの場合は就学相談前後で発達検査を受けるよう求められます。
予約に数か月かかることもあるため、早めの申し込みが安心です。普通級希望でも支援級を勧められたら?
あくまで「提案」であり、最終的な決定権は保護者にあります。
見学や体験を経て、納得して選択することが大切です。申込は誰にすればいい?
市区町村の教育委員会または通っている園(幼稚園・保育園)を通して申し込みます。
園が間に入ってくれるケースも多いです。途中で進路変更できる?
一度決めても、成長や状況に応じて普通級⇔支援級の変更は可能です。
ただし手続きや教育委員会の承認が必要な場合があります。相談当日の持ち物は?
母子手帳、健康診断票、発達検査の結果、園での様子をまとめた資料などがあるとスムーズです。
親だけ参加でもいい?
私の地区は親だけで可能でした。
地域によっては子どもと一緒に行うケースもあります。発達グレーでも受けられる?
受けられます。
診断の有無にかかわらず「学校生活に不安がある場合」は就学相談の対象です。ショックを受けたらどう立ち直る?
まずは時間をかけて受け止め、情報収集をしながら次の行動を考えましょう。
信頼できる人や支援者に話すことで、気持ちが整理されやすくなります。就学相談後、入学式までにやることは?
園や家庭で生活習慣を整える、必要な物品の準備、通学ルートの確認などを進めます。
支援が必要な場合は、事前に学校側へ情報共有しておきます。他の自治体の学校は選べる?
基本は学区内の学校ですが、特別な事情や支援ニーズによっては越境入学が認められることもあります。
自治体の規定を確認しましょう。
まとめ 🌸
就学相談は、単なる「進学の手続き」ではなく、わが子に合った学びの環境を見つける大切な入り口です。
💡 ポイントは3つ
- 情報を集める(見学・制度確認・体験談)
- 準備する(質問リスト・発達検査・資料整理)
- 柔軟に考える(支援級⇔普通級の移行や交流学級の活用)
支援級でも普通級でも、子どもの特性に合った環境なら成長のチャンスは広がります。
そして、一度決めた進路も、成長に応じて見直すことは可能です。
私自身も迷いながら準備を進めましたが、行動したことで情報が集まり、不安が減っていきました。
親が安心して送り出せる準備こそ、子どもにとって最高のスタートサポートだと感じます。
あなたの就学相談が、お子さんの未来への大きな一歩になりますように🍀
📢次回予告
「 発達検査WISC(ウィスク)とは?対象年齢・費用・結果の見方をわかりやすく解説」
お楽しみに!
関連記事
- 就学に向けて 年長 リアル体験談|ASD・吃音の息子と歩む支援級か普通級かの選び方と入学準備
- 【発達が気になる子に】着替え・身支度が苦手な理由とサポート法|視覚支援×遊び
- 発達障害の理解とサポート:子どもの特性に寄り添う親の心構え
- 発達検査とは?息子の体験と親としての気づき
- 【体験談】発達検査の結果で見えた支援の方向性」
- 【体験談】発達検査WPPSI-IIIを受けた息子|検査の流れと親の気づき
- 就学に向けて 年長 リアル体験談|支援級か普通級かの選び方と入学準備
- 【体験談】発達検査WISC(ウィスク)の流れと結果|就学判断・診断の参考に
- 発達検査WISC(ウィスク)とは?対象年齢・費用・結果の見方をわかりやすく解説
- 発達検査WISCでわかるFRI(流動性推理)|家庭・学校での支援法と体験談
- 【発達検査WISC-Ⅴ】VSI(視空間指標)とは?サポート法と体験談
- 【発達検査WISC-Ⅴ】VCI(言語理解)とは?サポート法と体験談