はじめに
WISC(ウィスク)検査の結果に出てくる「PSI(処理速度指標)」。
数字を見て「うちの子は遅いのかな?」「将来に影響するの?」と不安になる親御さんも多いのではないでしょうか。
PSIは、子どもが「どれだけスムーズに情報を処理できるか」を見る指標です。
たとえば「黒板の字をノートに写す」「たくさんの図の中から同じものを探す」など、生活や学習で欠かせない力を評価します。
この記事では、
- PSIがどんな意味を持つのか
- 数値が低い/高いときに見られる特徴
- 家庭や学校でのサポート方法
- 実際に検査を受けた親の体験談
を、研究データと体験談を交えてわかりやすくご紹介します。
目次
はじめに
- WISC検査とPSI(処理速度)の基礎知識
- WISC検査とは?5つの認知指標の概要
- PSIの役割と測定内容
- 符号・記号探しなどの下位検査 - WISC-PSI(処理速度)の数値からわかること
- PSIが高い子の特徴
- PSIが低い子の特徴
- 他の指標との関係性 - PSI(処理速度)が低い場合に見られる困りごと
- 学校生活での影響
- 家庭での困難さ
- ADHDやASDとの関連 - PSIを活かした教育・対応への応用
- 学校でできる配慮
- 家庭でのサポート
- 療育やトレーニング - 【体験談】我が子のWISC-PSI結果と支援の工夫
- よくある質問(Q&A)
- まとめ|WISC-PSIは「処理の速さ」を理解する手がかり
1. WISC(ウィスク)検査とPSI(処理速度)の基礎知識
WISC検査とは?5つの認知指標の概要
WISC(ウィスク)検査は、5歳~16歳を対象とした知能検査で、日本でも学校や医療機関で広く使われています。
子どもの発達を「一つのIQ」ではなく、複数の能力のバランスでとらえられるのが特徴です。
5つの指標は以下の通りです:
- VCI(言語理解指標):言葉を理解したり説明したりする力
- VSI(視空間指標):形や位置関係を見分ける力
- FRI(流動性推理指標):新しい課題を考える力・推理力
- WMI(ワーキングメモリ指標):覚えながら考える力
- PSI(処理速度指標):素早く正確に処理する力
PSI(処理速度指標)の役割と測定内容
PSI(処理速度)は、「視覚で見た情報をどのくらい速く、正確に処理できるか」を測定します。
例えば、
- 板書のスピード
- 計算プリントの処理
- パズルやコピー作業の速さ
など、日常で必要な「作業の速さ」と深く関係しています。
符号・記号探しなどの下位検査について
PSI(処理速度)は主に次の課題で評価されます。
- 符号:見本の記号を、できるだけ速く書き写す
- 記号探し:いくつかの図の中から、同じものを探す
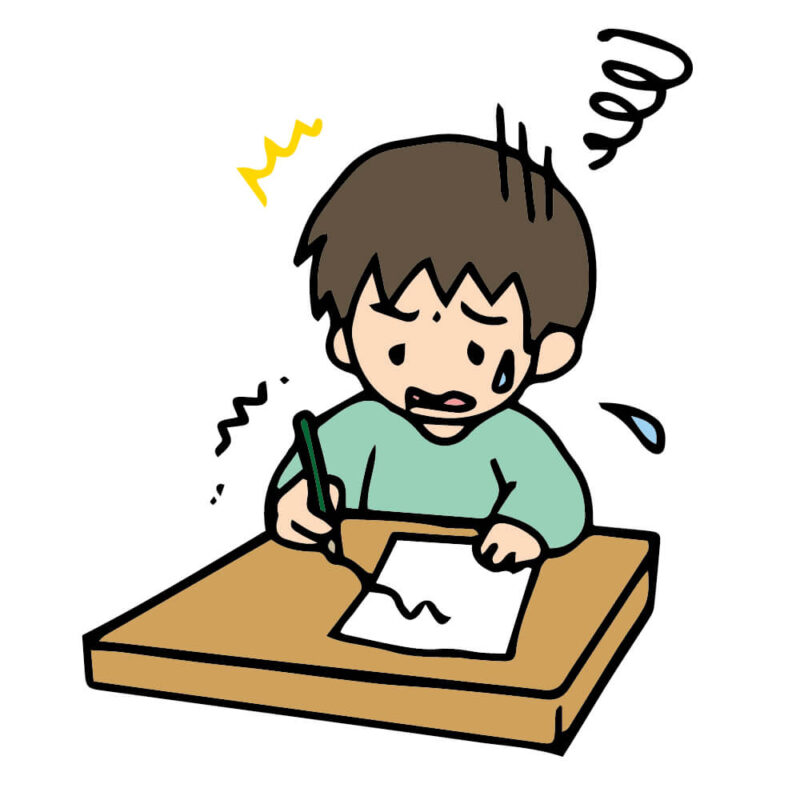
👉 これらは「集中力・注意力・手先の器用さ」も関わるため、PSIの数値=知能そのものというわけではありません。
2. WISC-PSI(処理速度)の数値からわかること
PSI(処理速度)が高い子どもの特徴
- 板書やプリントの処理が速い
- 作業を効率よくこなせる
- 細かい作業をストレスなく進めやすい
PSI(処理速度)が低い子どもの特徴(作業の遅さ・不注意など)
- 板書やテストで「間に合わない」と言われやすい
- 宿題に時間がかかる
- うっかりミスや集中の切れやすさがある
PSI(処理速度)と他の指標との関係性
- Wechsler(2014) の標準化研究では、ADHD児ではPSIが平均より低く出やすい傾向があると報告されています。
ただし、言語理解(VCI)や推理力(FRI)が高ければ、
「考える力はあるのにスピードが追いつかない」ケースも少なくありません。 - Jacobson et al. (2011) の研究によると、処理速度が低い子どもは学業成績に直接影響を及ぼすという結果が示されています。
- 日本LD学会(2019) でも、「処理速度が低い子は実力を発揮しにくく、支援が必要」と提言されています。
👉 だからこそ「総合IQ」よりも「指標ごとのバランス」で見ることが大切です。
3. WISC-PSI(処理速度)が低い場合に見られる困りごと
学校生活での影響
- 板書が終わらないうちに先生が消してしまう
- テスト時間が足りず、実力を発揮できない
- 周囲から「怠けている」と誤解される
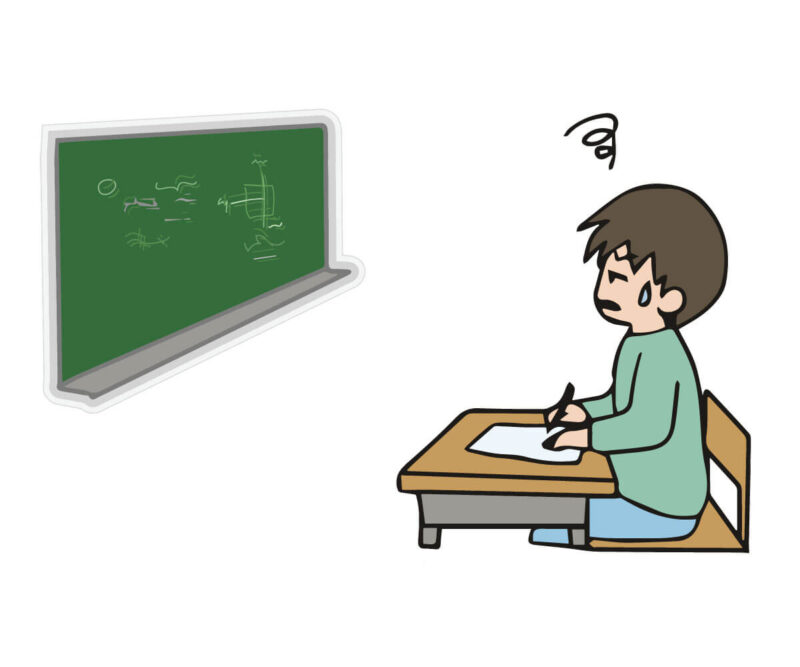
家庭での困難さ
- 朝の準備や着替えがなかなか進まない
- 宿題に取りかかるまでが遅い
- 片付けや整理に時間がかかる
ADHDやASDとの関連は?
PSIが低いこと自体は診断名につながりませんが、
ASDの不器用さやADHDの不注意傾向と一緒に現れることもあります。
4. PSI(処理速度)を活かした教育・対応への応用
学校でできる配慮
- 板書をプリントで配布してもらう
- テストの時間を延長する
- タブレットやPC入力を活用する
家庭でのサポート
- タイマーで時間を「見える化」する
- 手順カードやイラストで流れを提示する
- 片付けの場所を固定して迷わないようにする
療育やトレーニング
- ビジョントレーニング(視覚認知を育てる練習)
- パズルやレゴなど手先を使う遊び
- 集中力を少しずつ伸ばす取り組み
5.【体験談】我が子のWISC-PSI結果と支援の工夫
体験談:年長で受けた息子のケース
息子は年長の春にWISCを受け、処理速度指標(PSI)が平均よりやや低めという結果でした。
普段から「着替えに時間がかかる」療育先で「板書が苦手」と言われていたので、検査結果を見て納得しました。
家庭では次のような工夫をしています:
- 朝の支度を絵カードで「順番に見える化」
- 宿題はタイマーで区切る
- 片付けはラベル付きボックスで「置き場所が一目でわかる」ようにする
👉 数値が見えたことで、「ただ遅い子」ではなく「自分のペースでできる子」と前向きにとらえられるようになりました。
体験談B:小3で受けた友人のお子さんのケース
友人の娘さんは、小3でWISCを受けました。
授業では発言力があるのに、宿題やプリントが遅いと先生に指摘されることが多く、心配だったそうです。
結果を見ると、言語理解や推理力は高いのにPSIが低め。
「理解できているのに作業が追いつかない」タイプだとわかりました。
学校に相談し、板書プリントの配布や宿題量の調整を受けるようになってから、安心して取り組めるようになりました。
6. よくある質問(Q&A)
WISC-PSIって何ですか?
処理速度指標のこと。目で見た情報をどれだけ速く正確に処理できるかを測ります。
PSIが低いと知能が低いのですか?
いいえ。処理の速さの指標であり、理解力や推理力とは別です。
PSIが高い子の特徴は?
板書や作業をスムーズにこなせる、手先の作業が得意などが多いです。
PSIが低い子の特徴は?
作業が遅い、集中が途切れやすい、宿題や板書に時間がかかるなどです。
PSIとADHDやASDは関係ありますか?
PSIが低く出る子にADHDの不注意傾向やASDの不器用さが重なることがありますが、
低いからといって診断ではありません。PSIは年齢とともに変わりますか?
個人差がありますが、成長や経験で少しずつ改善する場合もあります。
PSIを上げるトレーニングはありますか?
急激な改善は難しいですが、ビジョントレーニングや手先の遊びで生活のしやすさは改善できます。
学校でどんな配慮が必要ですか?
板書プリントの配布、テスト時間延長、PCやタブレットの活用などが有効です。
家庭でできるサポートは?
タイマーや手順カードを使った見える化、片付けの環境整備などで日常生活がスムーズになります。
PSIの結果は将来に影響しますか?
数値は特性の一部です。
支援や環境調整次第で、学びや生活のしやすさは大きく変わります。
7. まとめ|WISC-PSIは「処理の速さ」を理解する手がかり
PSI(処理速度)は、子どもの特性を理解するためのヒントです。
数値が低くても「考える力」「理解する力」がしっかりある場合も多く、サポート次第で安心して学びを続けられます。

大切なのは、数字だけにとらわれず、お子さんの得意・苦手を理解して支援を組み立てること。
家庭・学校・療育の力を合わせることで、子どもは自分のペースで力を発揮していけます。

📢次回予告
次回は、「【発達検査WISC-Ⅴ】FSIQ(知能指数)とは?サポート法と体験談」をお伝え予定です。
お楽しみに!
📌関連記事
- 検査結果がもたらした生活の変化と新たなサポート方法
- 発達検査を受けるきっかけとその意義 | 家族の葛藤と決断
- 発達障害の理解とサポート:子どもの特性に寄り添う親の心構え
- 診断名はお子さんを理解する手がかり:正確に聞き取るためのポイント
- 【体験談】発達検査WPPSI-IIIを受けた息子|検査の流れと親の気づき
- 【就学相談の流れ】年長ママ体験談|聞かれること&後悔しない準備
- 就学に向けて 年長 リアル体験談|支援級か普通級かの選び方と入学準備
- 【体験談】発達検査WISC(ウィスク)の流れと結果|就学判断・診断の参考に
- 発達検査WISC(ウィスク)とは?対象年齢・費用・結果の見方をわかりやすく解説
- 発達検査WISCでわかるFRI(流動性推理)|家庭・学校での支援法と体験談
- 【発達検査WISC-Ⅴ】VSI(視空間指標)とは?サポート法と体験談
- 【発達検査WISC-Ⅴ】VCI(言語理解)とは?サポート法と体験談






